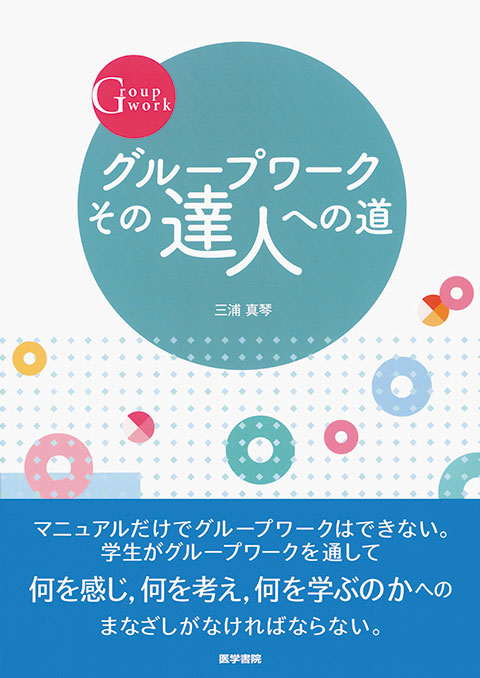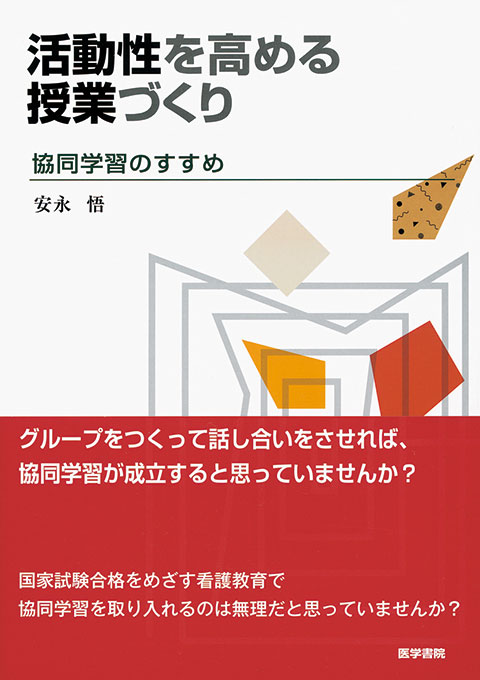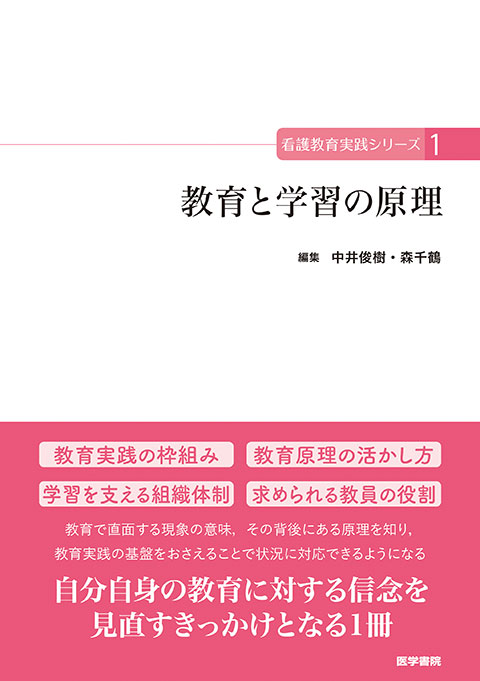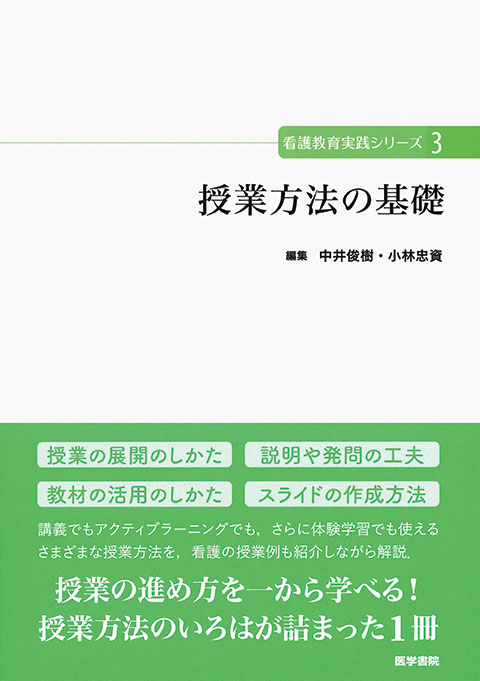教えるを学ぶエッセンス
[第9回] グループワークをワーク(機能)させるには
連載 杉森公一
2022.12.12 週刊医学界新聞(看護号):第3497号より
今回のポイント
✓ グループワークを成功させるには,問いの質や学習プロセスの評価と省察が重要となる。
✓ グループワークにおける教師の役割は,局面によって変化することに留意する。
人が集まって,ある目的に向かって何かを生み出そうとする時,しばしばその場が「意味ある場」に感じられないことがある。グループワークがワーク(機能)しない時,三田地は,その場は目標(ゴール)を見失った「放牧型」になっているのではないかと言う1)。一方で,一糸乱れずに同じ道を歩む「線路型」では,参加者がやらされていると感じるだろう。
活動性を高め,かつその場の目的・目標も明確にする場づくりのために,グループワークにおいて教師がどのような役割を担えばよいのだろうか。参加者の相互作用を大きく高めていくにはどうすればよいのだろうか。
学びにおける責任の主体を学生に移行する
グループワークを通して学生の学びを促すためには,知識獲得の3つのスタイル(後述の①~③)を把握しておくことが重要だ。知識獲得を促す問いを教師が提示し,教師が転移した知識を記憶させるような直接指導の方法は,個人が獲得する知識の量を優先する①「勉強モデル」に分類される2)。このモデルと対比される協同的・協調的な学習には,学生が教師から提示された問題や課題(problem)に取り組む学習形態として,調査に基づいた学習(IBL)や問題に基づいた学習(PBL)などが用いられる。他にも知識獲得のスタイルとして,グループのメンバーと協力しながら正解にたどり着く中で協同性や葛藤によって知識の獲得や思考の幅を広げる②「学習モデル」,課題そのものを学習者一人ひとりが設定し,メンバーと共に問いを掘り下げ,協調のための相互理解を深めていく③「学問モデル」が挙げられる。一般に,グループワークは小グループに分かれることが多いため「グループ学習」と呼ばれ3),問いの質や学習プロセスの評価と省察が成功の鍵となる。
教育学のフィッシャーらは,グループで行う活動を「協働学習」と位置づけた上で,学びにおける責任の主体が教師から学生へ移行していく「学びの責任移行モデル」を提案している(図1)4)。一斉授業に当たる「焦点を絞った指導」「教師がガイドする指導」では,教師の責任の比重が高い(教師が行う)。「協働学習」では探究プロセスに重きを置き,課題の発見や解決に取り組むことで多くの失敗も経験し,成果物だけではなく学習プロセスそのものからも学ぶ(学生が共に行う)。本連載第2回(3471号)で触れたアクティブラーニング型授業における教師の役割としてファシリテーターが求められるのは,この領域だろう。協働学習...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。