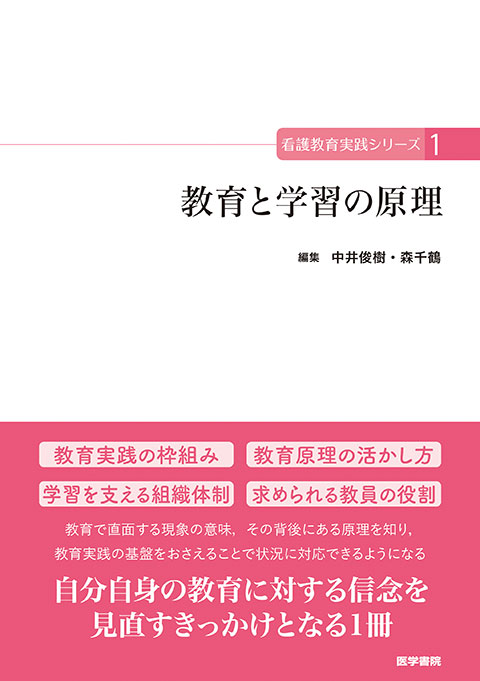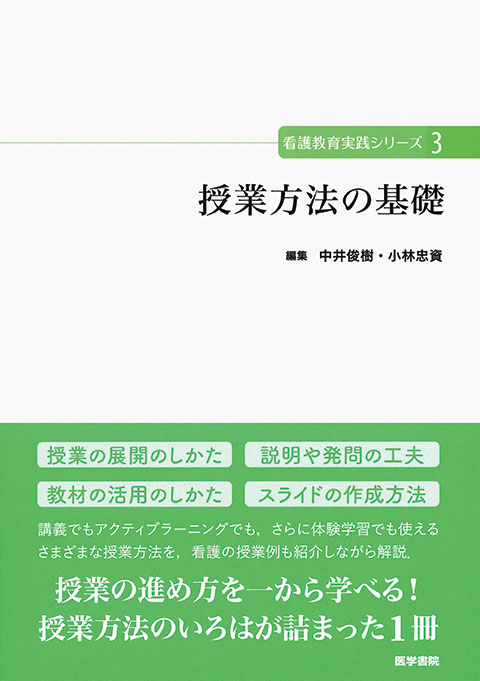教えるを学ぶエッセンス
[第8回] 教育評価に潜む誤解とパフォーマンス評価の有用性
連載 杉森公一
2022.11.28 週刊医学界新聞(看護号):第3495号より
今回のポイント
✓ 学生の学習を促す評価を行うには,教育評価に3つの主体・機能があることに留意する。
✓ 評価方法を選ぶ際は信頼性,客観性/比較可能性,妥当性,効率性を意識する。
✓ パフォーマンス評価ではルーブリックを用いることが推奨される。
評価という訳語には,計測(Measurement)と教育評価(Evaluation)の2つが混在している。私たちはしばしば,「結果をテストすること」と「結果を受けてフィードバックすること」を同じとみなし,間違えてしまう。前者は審査・格付け・選抜であり,後者は支援・教育・学習に当たる。
150年前に登場した多肢選択式の客観テストは,口頭試問を一斉テストに置き換え,学校教育を産業化社会の担い手を生み出す工場のような装置に転換してしまった。経営学のセンゲは,自動機械のようにベルトコンベア上に生産され続ける学校教育への警鐘を鳴らした一人である1)。全ての子どもが同じ様式で学び,画一的な評価を受けることが正しいとされる無自覚な仮定が問題となる。
歴史学のミュラーは,「問題は測定でなく,過剰な測定や不適切な測定だ。測定基準ではなく,測定基準への執着なのだ」と指摘している2)。では,測定基準への執着を乗り越え,学習を促す評価としてのアセスメントへ転換するために,私たち教育者はどうすればよいのだろうか。
定期試験が学習プロセスに与える影響は限定的
教育評価とは,教育がうまくいっているかを把握するために学生のデータを収集し,「目標として設定した知識や能力が身についているか?」という観点をもとに教育方法や内容,学習目標を問い直し,改善に結びつけるプロセスとされる3)。学生に学修を促す評価をするには,教育評価の中に3つの主体があることを意識したい。教師は,本連載第3回(3475号)で示した学習目標について,学生の理解度確認,フィードバック,動機づけ,授業の改善を行い,評定(成績づけ)を行う。組織(養成校)は,教育の質保証や説明責任を目的とし,授業を受けた学生の成績分布も参考にカリキュラム改善を行う。学生は,自己評価・相互評価を問わず,到達度の把握や今後の学習の調整を行う。教師・組織・学生の3つの主体はそれぞれ異なる目的を持っており,成績づけはその中の一部であることに留意する必要がある。
また,「適切な成績づけを行いさえすれば学習を促せる・学習したとみなせる」との誤解もしばしばみられる。教育評価には3つのタイミング(機能)がある。学習の開始前に行われる「診断的評価」は,前提状態(既有の知識・能力・関心・経験)を把握するために行われ,クラス編成や授業設計の修正・改善に有効な情報となる。入学選抜試験やプレースメントテストが該当するだろう。学習の途中で行われる「形成的評価」は,学習の過程で実施される。学生の活動の様子や,小テスト・アンケートなどに...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。