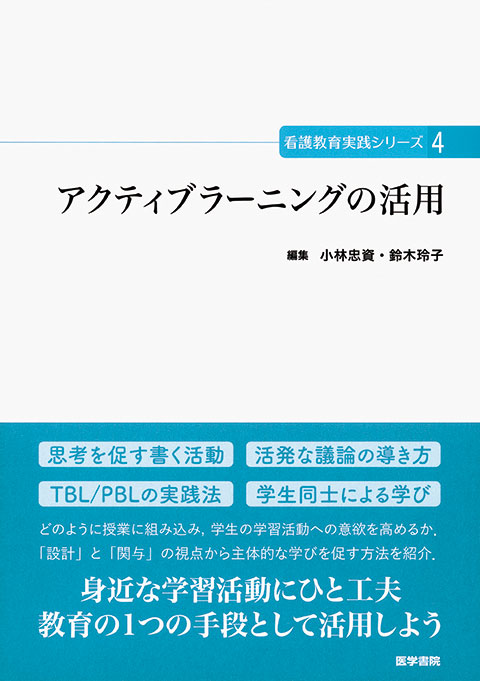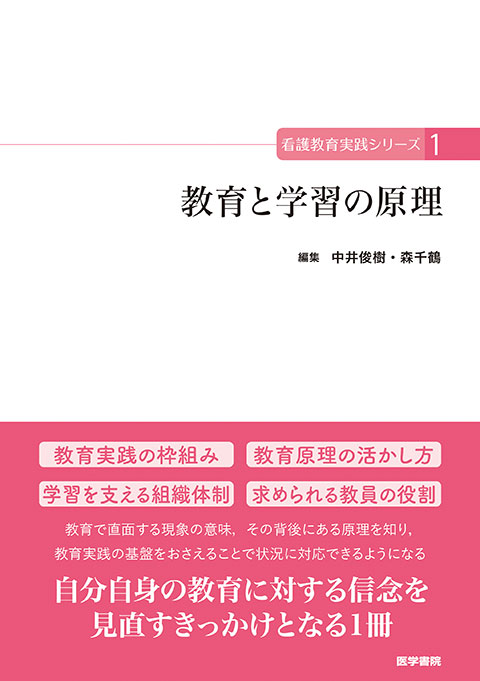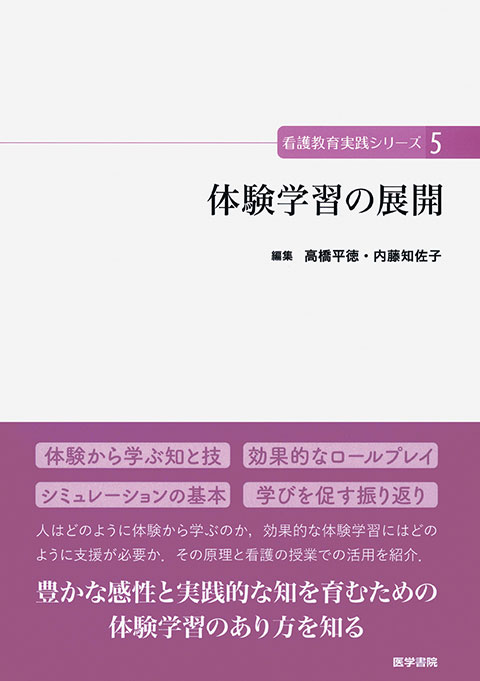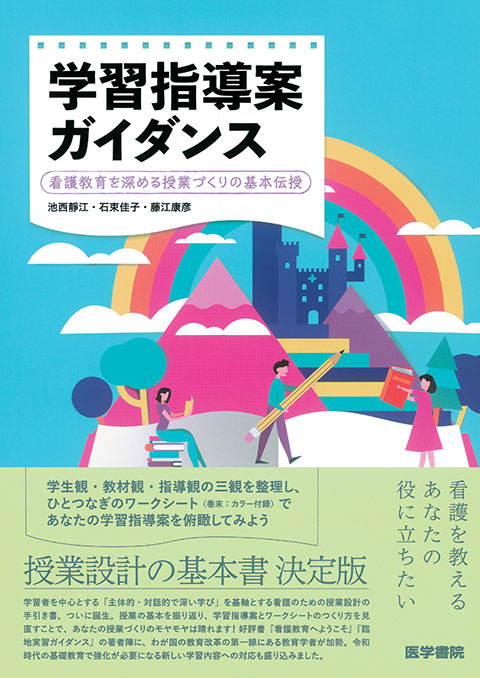教えるを学ぶエッセンス
[第2回]アクティブラーニングにおける教師の役割
連載 杉森 公一
2022.05.30 週刊医学界新聞(看護号):第3471号より
今回のポイント
✓ 学生の多様化を受け,教育者による一方的な教授から学習者の能動的な学びへと,パラダイム転換が求められている。
✓ アクティブラーニングは単にグループワークを行えばよいものではない。実施には教育者側の意図と工夫が問われる。
近年,看護教育ではアクティブラーニング(Active Learning : AL)の手法を用いることが増えている。ALと聞くと,グループワークのような授業を連想する読者も多いかもしれない。筆者は「『教師が何を伝えたか?』から『学生が何を身につけたか?』への学習の価値転換を図る運動」がALであるととらえている1)。
「教える」から「学ぶ」へのパラダイム転換が起きている
高等教育機関への進学率上昇による学生の学力や学習意欲などの多様化を背景に,「教える」から「学ぶ」への転回(パラダイム転換)が日本の教育現場に求められている。そのため,学ぶ/学習(者)を中心とするパラダイムを志向して,ALなどさまざまな教育改善の取り組みが実践されてきた。文科省の中央教育審議会による答申2)で用いられた用語集では,「アクティブ・ラーニング」(施策用語には「・」が入る)を以下のように定義している。
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり,学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって,認知的,倫理的,社会的能力,教養,知識,経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習,問題解決学習,体験学習,調査学習等が含まれるが,教室内でのグループ・ディスカッション,ディベート,グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。
教育学者・青年心理学者の溝上慎一氏は,ALを「一方向的な知識伝達型講義を聴くという(受動的)学習を乗り越える意味での,あらゆる能動的な学習のこと。能動的な学習には,書く・話す・発表するなどの活動への関与と,そこで生じる認知プロセスの外化を伴う」と定義する3)(註)。また溝上氏は,能動的な学修を取り入れALを効果的に促す学修活動(予習・復習を含む)が適切に設計された授業を「AL型授業」としている3)。同氏の言う「AL型授業」は技法の転換を定めており,ただ単位が取れれば良いような「浅い学習」の対語に当たる「深い学習」へ向かうための技法として示されている。つまり,表面的な方略や技法のみの採用は本質的ではない。教育者側が学習目標を明確にし,学習成果を獲得するために十分に意図された授業設計が重要になる。
教える/教授(者)を中心としたパラダイムでは,知識は学生の向こう側(外側)にあるもので,教師がその固まりを分割してわかりやすく伝達するものであった。学習者を中心にした教育への移行4)は ,古くは臨床心理学者カール・ロジャーズ氏の「患者中心のアプローチ」5)の中で提唱された“student-centered educatio...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.03
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。