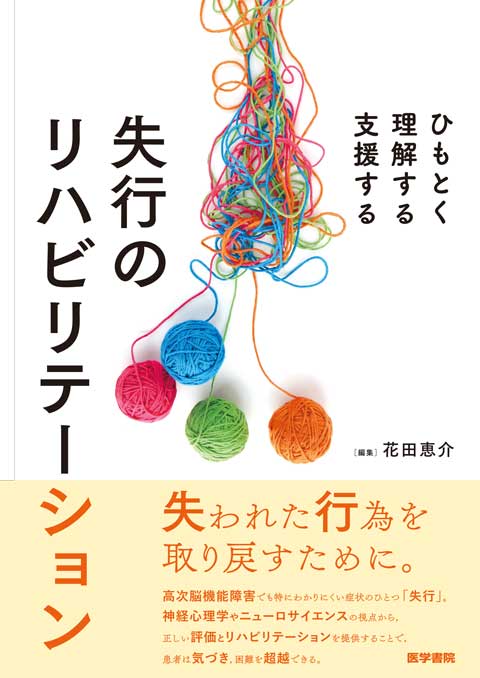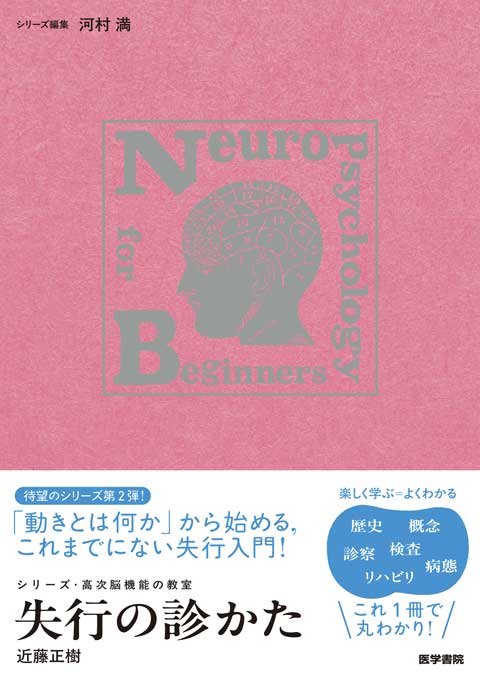FAQ
失行のリハビリテーション 障害の性質と介入のポイント
寄稿 花田 恵介
2025.11.11 医学界新聞:第3579号より
手に力は入るのに,その手を「どう動かすか」がわからない……。その手で「道具をどう使ったらよいか」がわからない……。それが「失行(apraxia)」という症候です。運動麻痺は筋そのものが動かないのに対し,失行は運動機能そのものには問題がないのにもかかわらず,自身の手指をどう動かし,道具をどう扱うかがわからなくなった状態を指します。
FAQ 1
失行とは何ですか?
失行とは,「運動執行器官に異常がないのに,目的に沿って運動を遂行できない状態」を指します1)。大脳損傷,とりわけ左半球の頭頂葉や前頭葉の損傷が原因で起こる,高次脳機能障害の一種です。失行は脳卒中のほかに,アルツハイマー病などの神経変性疾患でも出現することがあります。
失行を初めて体系的に概念化したのは,20世紀初頭のドイツの神経学者Liepmannでした。彼は「運動の観念」と「運動の実行」の分離に注目し,①道具をうまく使えない観念性失行,②身振り(ジェスチャー)がうまく行えない観念運動性失行,③手指動作が拙劣になる肢節運動失行の三類型を提唱しました。
しかしその後,研究者ごとに定義や分類が異なり,混乱が生じたため,現在では「limb apraxia」という包括的用語が使われるようになりました。失行は単一道具の使用障害だけではなく,行為を成立させる複数の過程(知覚・記憶・意味・動作計画)が破綻した状態として理解されています。
道具をうまく使えなくなる観念性失行(図)2)が生じると,食事,整容,着替え,家事など日常生活のあらゆる場面で支障が出ます。特に「順序がある行為」や「複数の対象を扱う動作」が苦手になりやすいです。

道具と物品(この場合,かなづちや釘)において生じる観念性失行の誤りの質のうち,1つは道具と対象の位置関係や方向が合わない誤り(a),もう1つは道具に適した対象物を選べない誤り(b)である。
Answer
失行は運動機能に問題がないにもかかわらず,目的に沿った運動ができなくなったり,道具をうまく扱えなくなったりする高次脳機能障害の一種です。
FAQ 2
適切な介入方針を立てるために,失行症状をどのように評価・理解するとよいですか?
失行症状を評価する際の前提として,左半球損傷を負った右利きの患者では,失行とともに失語を合併することが多いことを押さえておきましょう。したがって臨床では,「指示を理解できないからできない」のか,「理解しているのに動作が組み立てられない」のかを慎重に見極める必要があります。
評価に当たっては,患者にさまざまな日用道具を実際に使用してもらい,その様子を観察します。櫛や歯ブラシ,うちわなど自らの身体に向けて使う道具,金槌やホッチキス,ドライバー(ねじ回し)のように対象物に働きかける道具,さらにスマートフォンや家電ボタンなど電子機器を操作する動作など,評価対象は多岐にわたります。生活場面の観察や患者の訴えに応じて,観察すべき使用動作をピックアップします。
観察の要点は「どのような場面で,どんなエラーが生じるか」です。手順の間違い,姿勢や持ち方の誤り,対象の方向づけの不一致など,動作エラーの質的分析が重要です。近年は失行が単なる運動の失敗ではなく,「道具の意味的知識(semantic knowledge)」や「道具の機械的知識(mechanical knowledge)」の障害に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
花田 恵介(はなだ・けいすけ)氏 四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 教授
2005年広島大医学部保健学科卒。大学病院などで約18年間,作業療法士として従事。臨床の傍ら,社会人大学院生として大阪府立大(当時)にて修士(保健学),山形県立保健医療大にて博士(作業療法学)を修了。大阪公立大大学院総合リハビリテーション学研究科客員研究員を経て,23 年より現職。専門は身体障害作業療法学,高次脳機能障害学,神経心理学。編書に『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。