MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2026.02.10 医学界新聞:第3582号より
《評者》 加藤 庸子 藤田医大ばんたね病院教授・統括副院長・脳神経外科
術者の手技と思考過程をリアルに追体験できる実践書
神経内視鏡手術の発展は,近年の脳神経外科領域における最も顕著な進化の一つです。従来の顕微鏡手術では到達が困難であった深部病変や狭小な術野に対して,内視鏡がもたらす鮮明な視界と最小限の侵襲は,診断・治療の新たな可能性を切り開いてまいりました。その進歩の裏には,先人の不断の努力と,確かな教育体系の構築があったことを忘れてはなりません。本書『神経内視鏡手術ハンドブック』は,まさにその歩みを総括し,次世代へと継承するための優れた実践書です。
本書は,神経内視鏡手術の理論と実践を包括的にまとめた全248頁の大冊であり,編者の永谷哲也先生,村井尚之先生,西山健一先生を中心に,第一線で活躍されているエキスパートの先生方が執筆陣として名を連ねています。総論では,脳室・傍鞍部領域を中心に,術野の理解に不可欠な解剖学・生理学的知見を平易に解説され,手技選択の理論的基盤を明確に示しています。
単なる手技書にとどまらず,「なぜこのアプローチを選ぶのか」「どのような判断過程で術中対応を行うのか」といった思考の流れが重視されており,読者は術者の思考過程を追体験するように学ぶことができます。
各論では26の代表的症例が取り上げられ,術中の実際に基づく詳細な解説が展開されています。術中のピットフォールや想定外の局面をいかに乗り越えるか,またその際にどのような工夫が有効であったかなど,経験豊富な術者ならではのリアルな知見が随所にちりばめられております。こうした記述は,これから内視鏡手術を志す若手医師にとって,机上の知識を超えた「臨床の英知」に触れる貴重な機会となることでしょう。
さらに注目すべきは,本書全体に通底する「教育の精神」です。難しいことを難しく書くのではなく,理論と実践をバランスよく配置し,若手の先生方にも理解しやすい構成に仕上げられています。豊富な写真,シェーマ,イラストはいずれも高精度で,読者が実際の手術手順を明確にイメージできるよう工夫され,教育現場での教材としても極めて有用です。
内視鏡手術が単なる“技術”ではなく,“判断力”と“解剖への洞察”に支えられた思考の医学であることを,本書は明確に示しています。読者はページを進めるごとに,術者としての考え方,視点の置き方,そしてリスクへの構え方を自然と学んでいくことができます。この構成こそが,永谷先生らが本書で示された「論理と証拠に基づく外科思考」の神髄であると感じます。
神経内視鏡手術は今後,AI支援ナビゲーションやロボット技術との融合により,さらなる発展を遂げることが予想されます。そのような時代においても,確かな基礎と判断力を備えた術者の育成こそが最も重要な課題です。本書は,その礎を築く「未来の教科書」として,多くの若手医師の学びを導くものとなるに違いありません。
本書を通じて,神経内視鏡手術が持つ奥深さと美しさ,そして何より「患者に優しい外科医療」という原点をあらためて感じさせられました。本書の刊行に携わられた全ての先生方に心より敬意を表するとともに,本書が今後の神経内視鏡教育の新たな礎となることを心より期待申し上げます。
《評者》 上田 剛士 洛和会丸太町病院副院長/救急・総合診療科
全ての臨床医のための感染症診療の羅針盤
待望の改訂となった本書を手に取りました。初版から21年,前作から数えても12年の月日が流れましたが,本書が放つ「臨床の熱量」は微塵も衰えておりません。
◆変わらぬ「根幹」と,深化する「アート」
感染症診療の世界は,この20年で劇的に変化しました。質量分析器が普及し,細菌の分類がいくつも変更となり,COVID-19が世界を揺るがしました。しかし,編者の藤本卓司氏が序文で断言するように,診療の「根幹」は微塵も揺るぎません。
詳細な病歴聴取,徹底した身体診察,そして自ら行うグラム染色。この泥臭くも論理的なプロセスこそが,感染症診療の本質であり「アート」なのです。本書は,最新のエビデンスという「サイエンス」を,この不変のアートに融合させる手法を提示しています。
◆「単著」の魂を継承した「知の集合体」
第3版の最大の転換点は,藤本氏の単著から,伊東直哉氏,寺田教彦氏を加えたチーム体制へと進化したことでしょう。通常,多人数執筆は記述の方向性や熱量が分散しがちですが,本書はその懸念を見事に裏切ります。
本書を特徴付けるのは,多人数執筆でありながら驚くほどの統一感を備えている点です。藤本氏が原稿の一字一句にまで目を通し,計18回もの議論を重ねたことで,読者はあたかも一人の医師と対話しているかのような感覚を得ます。そしてこの統一感は,実際に“共に患者を診て,共に検体を染めた”仲間たちが執筆に参加したことで,机上の説明ではなく,臨床現場の湿度を帯びた文章へと結実しています。ESBL産生菌の地域差など,現場で意思決定に迷う論点にも踏み込み,情報の質を格段に高めています。
さらに本書の中心にあるのは,問診・診察・グラム染色という,普遍にして揺るぎない「三種の神器」です。刷新されたグラム染色アトラスは,顕微鏡越しの微小な世界を“美しい”と感じられるほどの解像度と迫力をもち,身体診察ではlate inspiratory crackleなどの所見を共通言語として扱う意義が丁寧に語られます。それらは,検査数値に寄りかかりすぎた日常の診療姿勢を心地よく揺さぶります。
そして,本文に彩りを添えるMemoは前版の2倍に拡充され,先人から継承された知識や物語が凝縮されています。読み進めるうちに,単なる補足情報以上の“息遣いのある臨床知”として胸に響いてきます。
◆次世代のジェネラリストへ
「All physicians should be general(全ての医師はジェネラルであるべきだ)」。この言葉通り,本書は感染症専門医をめざす者だけでなく,全ての臨床医にとっての羅針盤となるであろうものです。
薬剤耐性菌の脅威が増す現代において,可能な限り「狭域スペクトラム」を選択する本書のスタンスは,かつてないほど重要性を増しています。効率化の名の下に身体診察やグラム染色が軽視されがちな今こそ,本書をポケットに忍ばせ,ベッドサイドへ向かってほしいと思います。そこには,最新のサイエンスによって裏打ちされた,決して古びることのない臨床のアートが息づいているはずです。
《評者》 高山 哲治 徳島大大学院教授・消化器内科学/腫瘍内科学
日々進化するがん医療を支える臨床家の力強い味方
『がん診療レジデントマニュアル』が改訂され,第10版が出版された。本書は,レジデントのみならず,初期研修医,中堅医師,さらには指導医に至るまで,がん診療にかかわるあらゆる層の医師にとって有用な実践書である。各がん種について,疫学,診断,治療,予後などの要点が簡潔に整理され,白衣のポケットに収まるコンパクトなサイズで携帯性にも優れる。およそ3年ごとに改訂が重ねられ,その都度,標準治療・ガイドライン・疫学データが最新情報に更新されてきた点も大きな特徴である。
私自身,消化器がんの診療を中心に従事しているが,診療中にステージ分類や一次・二次治療の確認,薬剤投与量の再確認などを行う際,本書の簡潔な構成が極めて役立つ。各がん種の章末には最新のステージ別5年生存率が掲載され,治療方針を考える上でも参考になる。また,免疫チェックポイント阻害薬の普及を背景に,免疫関連有害事象(irAE)の特徴・診断・対応についてもわかりやすくまとめられており,近年の臨床現場の需要に即している。
さらに,本書の優れた点は,構成が臓器別の腫瘍のみならず,「がん性胸膜炎・がん性腹膜炎・がん性髄膜炎・がん性心膜炎」「感染症対策」「がん疼痛の治療と緩和ケア」「腫瘍随伴症候群」,そして「がんゲノム医療」などの章が設けられていることである。がん診療の現場でしばしば遭遇する事象に対して,具体的な初期対応や管理法が簡潔に記載されている点は非常に実用的である。
本マニュアルは,臨床腫瘍学や腫瘍内科学の体系書ではないが,日常診療で即座に知識を確認できる“ポケットリファレンス”として完成度が高い。特に日本臨床腫瘍学会が実施する「がん薬物療法専門医」試験の受験者にとっては,知識整理と確認のための最適なツールといえる。
がん診療の高度化が進み,チーム医療が不可欠となる現在,本書は医師だけでなく,薬剤師や看護師など多職種の医療者にとっても価値ある一冊である。第10版の刊行は,日々進化するがん医療を支える臨床家の力強い味方となるだろう。
《評者》 小原 英幹 香川大教授・消化器・神経内科学
教科書にない“リアル内視鏡診療”を読んで真の名医に
一言でいうと「実地の本音が詰まった玉稿」である。
読み進めていくと,教科書にはない,“そうそう”と頷く内容の連続。“良い医者ってこういうことだ”という想いが伝わってくる。“技術だけでなく人間力を磨いて,真のエキスパートをめざせ!”という熱いメッセージだ。
著者の平澤欣吾(きんちゃん)先生は,私と1997(平成9)年卒の同期で,公私ともに旧知の親友である。彼との初めての出会いでは,見ためから近寄りがたく,声をかけるのも躊躇したのを覚えている。しかし,いざ話し込んでいくと,フランクで親しみやすく,同じ空気感を共有できた。
とにかくトータルバランスが優れた人物である。われわれのラボに彼を招聘した折,彼の内視鏡技術の高さを目の当たりにした。常に綺麗な視野でブレないメスさばきは,もはや達人の域で,感銘を受けた。そして何より,自分が抱いた疑問やアイデアあるいは技術を,必ず学術論文という形にして世界に発信している点が超一流である。それはこの本の中で,ただ自分の思想を述べているのではなく,自分が世に出したエビデンスを基に語っていることからもうかがい知れる。つまり彼は,患者・病気を深く洞察できる臨床医であると同時に,医学研究者でもある,真の「Scientific Physician」なのである。そして何より思いやりが深い。「お前,大丈夫か,ごめんな,ありがとうな」など誰にでも気遣いができる。これは,できそうで簡単でない。だから,きんちゃん先生の周りにはたくさんの部下や外科医が集い,信頼し合えるチームができる。この素養こそが,患者目線の医療や,安全かつ信頼性のある高度治療につながっていることが本書からもうかがえる。
おそらくこの本は,ESDに慣れてきてエキスパートをめざす中級医が,主な対象であろう。でも,エキスパートも,ビギナーも読んで損はない。“技術だけでなく人間力,つまり心技体”を持つ医師をめざすための,きんちゃん先生の思いが詰まった一冊といえよう。
この本を読めば「『安心して身を任せたい』と思う患者が集まる医師にきっとなれる」と信じてやまない。
《評者》 田口 敦子 慶大教授・看護医療学
教育・実践・研究を架橋する知として読み継ぐべき書
Lawrence W. Green博士のPRECEDE-PROCEEDモデルのテキストは,健康行動科学・ヘルスプロモーション分野において,長年にわたり国際的な標準書として位置付けられてきた。本書はその最新版の翻訳であり,エビデンスに基づく保健活動を,企画・実装・評価という一連のプロセスとして体系的にとらえ直すための,実践的かつ理論的完成度の高い一冊である。
大学生であった私は,オタワ憲章で示されたヘルスプロモーションの理念や,Green博士らが理論的に発展させてきたヘルスプロモーションの考え方に初めて触れ,公衆衛生という学問の奥深さと,理論が実践と結び付く面白さに強い衝撃を受けた。住民の健康行動や地域の変化は偶然に生じるものではなく,理論とエビデンスに基づき意図的に設計された介入によって生み出され得るという視点は,保健師として実践に携わる際の思考の基盤となり,研究者として活動する現在の私にとっても原点であり続けている。本書は,その原点を現在の社会的文脈に引き寄せて再確認させてくれた。
本書の大きな特長は,保健プログラムを「計画して終わり」にせず,実装の過程や評価までを含めた循環的なプロセスとしてとらえている点にある。また,PRECEDE-PROCEEDモデルという理論的枠組みと,評価を目的としたロジックモデルとが,それぞれ異なる役割を担いながら相互に補完し合う関係にあることも示されている。いずれも事業の目的や成果を可視化する点で有益であり,理論的な検討と実践的な評価とをつなぐ架け橋として位置付けられている点は理解しやすい。本書は,事業内容を関係者間で共有し,日々の保健師活動を「説明可能な実践」として整理する上で,大きな助けとなるだろう。
また,本書の視点は,近年日本でも注目されている実装研究(implementation research)とも親和性が高い。介入がなぜ機能したのか,あるいは機能しなかったのかを,個人要因のみに還元せず,組織や環境,政策といった多層的な文脈の中でとらえる視点は,地域で活動する保健師の実感とも重なるものである。
そして本書は,公衆衛生看護学を学ぶ学生にとっては,地域診断や事業計画が単なる課題ではなく,住民の健康を支えるための戦略的思考であることを理解する手掛かりとなるだろう。また,現職保健師や自治体関係者にとっては,自らの実践を振り返り,改善と評価につなげるための理論的支柱となるだろう。
本書は,丁寧に選ばれた訳語と一貫した語り口により,原著の理論的厳密さを損なうことなく,日本の保健師や学生が自らの実践に引き寄せて理解できる形で提示している。これは,神馬征峰先生が原著の意義を深く理解し,「この知を日本の公衆衛生実践に届けたい」という思いをもって翻訳に取り組まれたことによる。その橋渡しの営みに深い敬意を表したい。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。



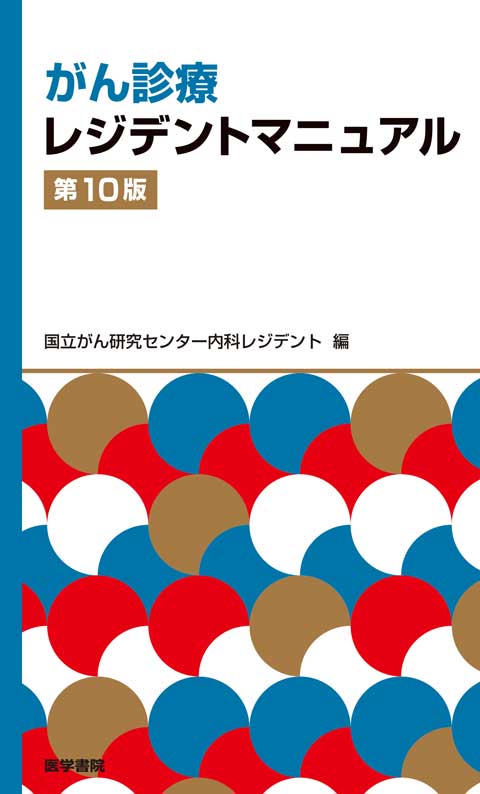
![Dr. 平澤欣吾の「こだわらない」EMR・ESD[Web動画付]ESD時代のEMR論とナイフ別ESD攻略法](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2417/5997/8124/115187.jpg)
