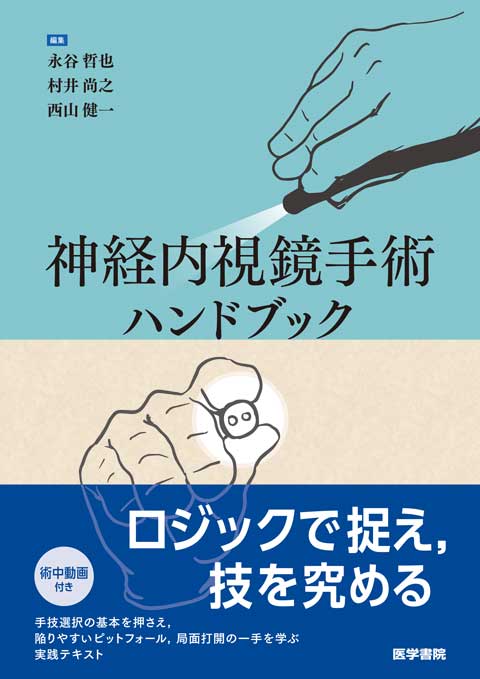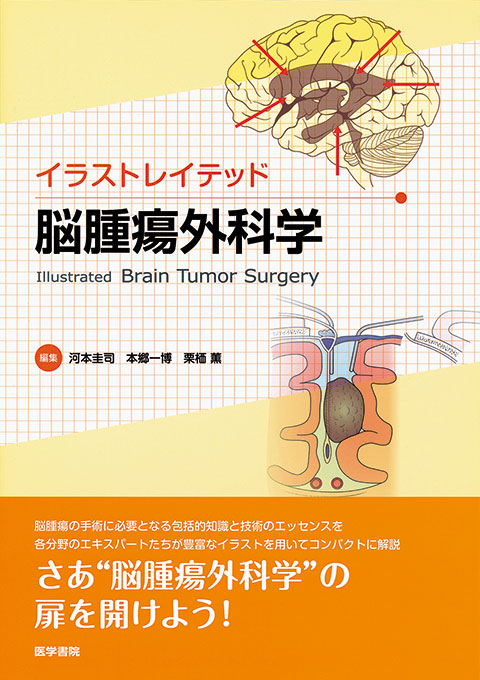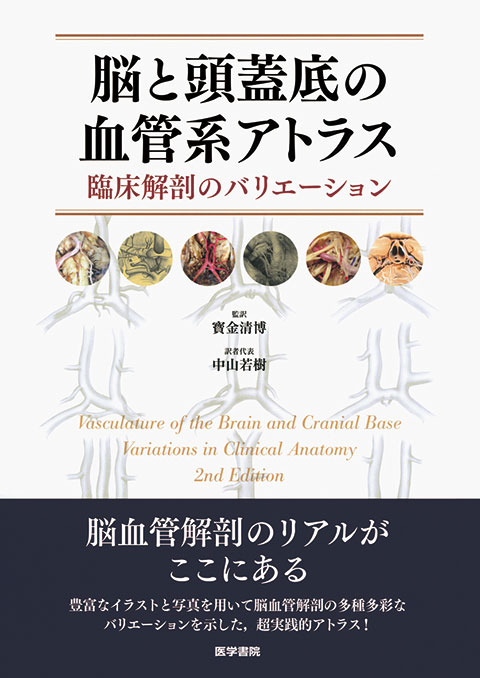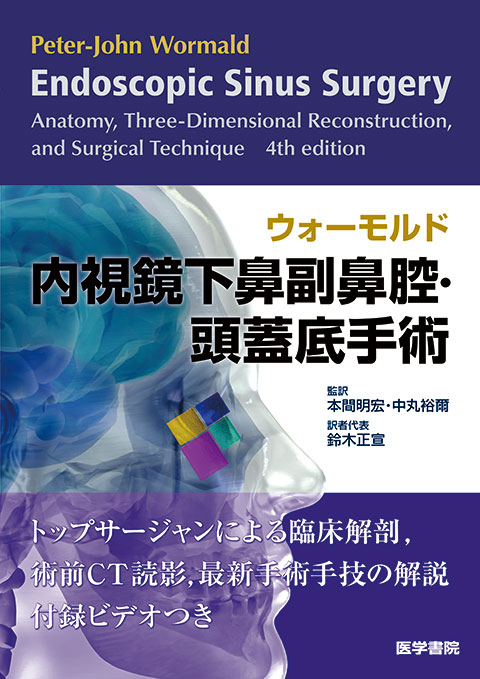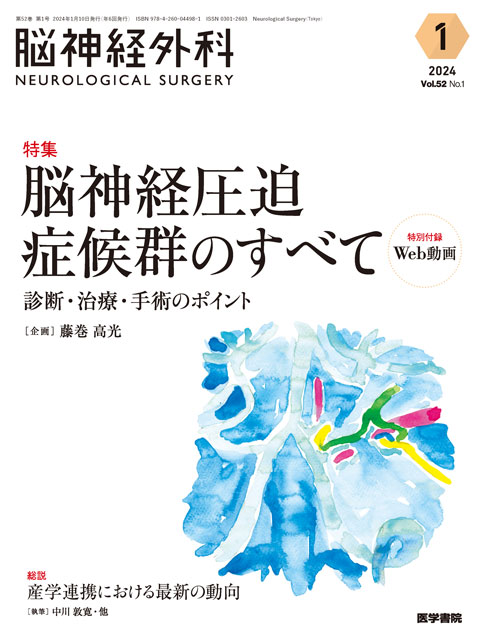神経内視鏡手術ハンドブック
神経内視鏡手術の理と技を磨く。手技選択の基本と局面打開の一手を学ぶ実践テキスト。
もっと見る
神経内視鏡手術の理論と実践を体系的に学べる実践テキスト。脳室内・傍鞍部病変を中心に解剖学・生理学の知見を踏まえ、手技選択の基礎を培う。各論の26症例をもとに、ピットフォールへの対応や局面を打開する工夫を解説。論理と証拠から手術を捉え、適切な判断と正確な操作を可能にする「思考と技術のプロセス」を提示する。神経内視鏡をサブスペシャルティとして目指す若手脳神経外科医、教育を担う指導医の指針となる一冊。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
内視鏡の特性を考えた場合,理想的な適応は管腔臓器病変であることは自明であろう。歴史的にも神経内視鏡手術は水頭症,脳室内病変の観察,処置から始まっていることからもうなずける事実である。ただし,脳神経外科領域では管腔臓器と呼べる組織構造は限られ,永く神経内視鏡手術の守備範囲は,水頭症関連疾患と鼻・副鼻腔を経由する下垂体病変に限られていた。
過去20年の本邦の神経内視鏡手術の変化に目を向けると,各術式の段階的な保険収載に加え2006年には日本神経内視鏡学会によって神経内視鏡技術認定制度が整備され,神経内視鏡術者の人口は順当に増加傾向を示している。また,内視鏡の高精細化,手術機器の多様化など,周辺技術の進歩を背景にして,一般的な脳神経外科医の神経内視鏡手術に対する認識は明らかに変化してきたと考えられる。さらに,外視鏡の出現は脳神経外科手術に「鏡視下手術」という新たな概念をもたらし,いわゆる Heads-up surgeryが脳神経外科手術の1つの常識となってきた。同じ Heads-up surgeryである神経内視鏡手術は外視鏡と併用が容易であるという利点を有し,今後さらに裾野の広がりが期待される。
本書はこうした本邦の現状をふまえ,これから内視鏡手術に取り組みたいと考える若手脳神経外科医から後進の育成に携わる脳神経外科医まで,幅広い読者を想定し企画した。神経内視鏡手術は道具に依存する部分が大きく,術式に応じた特有の道具がまず手元にあることが必要である。またその先には,狭い術野での手術機器と内視鏡との干渉やレンズ面の汚れに悩まされ,機器の配置や助手との位置関係に苦心するといった現実がある。こうした点が従来の顕微鏡手術とは大きく異なり,一見顕微鏡手術の常識が通用しない世界が存在する。しかし,これは単にモダリティの違いによる結果と捉えるべきであり,両者とも手術の目的に対して理にかなったアプローチを選択する姿勢が重要である点に違いはないのである。
本書の編集方針の柱は,読者に対して①読みやすいこと,②使える情報であること,③普遍的な内容であることの3点である。全体の構成は「総論」と「各論」の2部とした。
「総論」では,脳室内病変と傍鞍部病変の神経内視鏡手術において必要な知識を基礎と臨床の両面から解説する。細分化と多様化が日々進む神経内視鏡手術の現状にあえて逆らうようだが,この2つが神経内視鏡手術の大きな柱であるとの理由からである。
「各論」では総論で得た背景知識をふまえ,実践の場で使える情報を記載した。ここでは単なる症例提示ではなく,一見簡単そうに見える病変に潜むピットフォール,内視鏡の特性を配慮したアプローチの方法,手詰まりになりそうな局面を打開する工夫,そのような場面をピックアップして読者のもつ引き出しを少しでも増やせるよう構成を工夫した。さらに教育的側面も重視し,卓上でのトレーニング用に自作できる模型や練習法など,ユニークな試みも紹介している。
物には順序があるように,神経内視鏡手術もステップを踏んでこそ新たな道が見えるものである。物事をロジックと知識で捉え,適切な判断を下し正確な操作を行うことの重要性を読者にお伝えできれば編者として本望である。
2025年10月
永谷 哲也
目次
開く
第I章 脳室病変に対する神経内視鏡手術
1 総説
脳室病変に対する神経内視鏡手術──歴史的背景と現状
2 解剖生理学の基礎知識
A 髄液の生理学──組成と人工髄液の可能性
B 脳室と髄液動態
C 水頭症と脳室──正常構造からの変化
3 手技のスキルアップをはかる
A ETV,嚢胞開窓のすべて
B 脳室内生検術
コラム① ハンズオンセミナーをどう実施するか
──目的と意義(自身で考案したモデルの活用例とIFNEでのコラボレーション)
C 硬性鏡を究める──シリンダー手術へのステップアップ
1 硬性鏡シリンダー手術に慣れよう
2 シリンダー手術の限界を知る
3 手術適応をどう考えるか
4 シリンダー手術の可能性を考える
D 軟性鏡を究める
コラム② 脳室病変と脳実質病変──身近な材料でできるモデル紹介
第II章 傍鞍部病変に対する神経内視鏡手術
1 総説
傍鞍部病変に対する神経内視鏡手術──歴史的背景と現状
2 解剖生理学の基礎知識
A 下垂体外科に必要な内分泌学と神経眼科学
B 下垂体近傍病変の鑑別診断
C 知っておくべき間脳下垂体腫瘍の病理
3 手技のスキルアップをはかる
A 解剖と生理に基づくトルコ鞍へのアプローチ
B トルコ鞍内操作のすべて──拡大法に向けて
コラム③ 傍鞍部病変──卵モデルの開発とトレーニングの実際
C 合併症回避と術後管理のポイント
第III章 神経内視鏡手術 術野別 Up to date
1 脳室内手術(15例)
A 穿頭位置,穿孔部位の選択(軟性鏡手術)
[症例1] ETV(中脳水道狭窄症,脳室拡大が顕著な例)
[症例2] ETV(水頭症シャント不全時におけるシャント離脱目的)
[症例3] ETV(非交通性水頭症を伴う松果体部腫瘍例)
B 脳室内手術の基本手技
[症例4] 腫瘍生検術(脳室拡大あり)
[症例5] 腫瘍生検術(脳室拡大なし)
[症例6] 嚢胞開窓術
[症例7] 嚢胞開窓術(後角穿刺)
C 鉗子類と外套の選択(硬性鏡手術)
[症例8] 生検術(側脳室前角)
[症例9] 生検術(側脳室体部)
[症例10] 腫瘍摘出術(Monro 孔近傍腫瘍)
[症例11] 腫瘍摘出術(視床~第三脳室)
D 止血テクニック(軟性鏡,硬性鏡)
[症例12] 静脈性出血(軟性鏡)
[症例13] 動脈性出血(軟性鏡)
[症例14] 静脈性出血(硬性鏡)
[症例15] 動脈性出血(硬性鏡)
2 経鼻手術(11例)
A 鼻腔・副鼻腔操作
[症例1] 初回手術,鼻中隔彎曲なし
[症例2] 初回手術,先端巨大症
[症例3] 再手術(アプローチの選択)
B トルコ鞍内・鞍上部操作
[症例4] 非機能性腫瘍 grade C(被膜外摘出)
[症例5] 非機能性腫瘍 grade D(被膜下摘出)
[症例6] 機能性腫瘍 grade E(海綿静脈洞アプローチ)
[症例7] 巨大下垂体腫瘍(術式選択)
[症例8] 微小腫瘍(Cushing病)
C 鞍底再建
▪ 鞍底再建の選択について
[症例9] 術中に髄液が漏れていない場合の再建
[症例10] 術中に髄液が漏れている場合の再建
[症例11] 再手術,鞍底形成
第IV章 資料集
1 内視鏡所見アトラス
A 脳室内内視鏡所見
B 傍鞍部の正常解剖
2 日本で使用できる主なモデル一覧
索引
書評
開く
内視鏡術者の「知りたい」が凝縮された一冊
書評者:谷口 理章(大阪脳神経外科病院病院長)
本書は,神経内視鏡手術の各分野において第一線で活躍する名だたるエキスパートが共同執筆した,まさに待望の一冊である。これまでもアトラスや総説書は刊行されてきたが,本分野は現在も日進月歩で技術革新が続いており,知見のアップデートが強く求められていた。そのような状況下で本書が刊行された意義は大きく,これから神経内視鏡手術に取り組もうとする医師のみならず,すでに日常診療で本手技を実践している医師にとっても,極めて有益な内容となっている。構成は,前半に基本的事項,後半に豊富な症例提示を配し,前半で習得した知識を実臨床に即して深化させることができるよう工夫されている。内視鏡機器の取り扱い上の注意点,手術室のレイアウト,手技の基本から実践的なコツに至るまで,豊富な画像や手術動画と共に丁寧に解説されており,全体として非常に読みやすい構成となっている。
単なる知識の羅列にとどまらず,日常臨床ですぐに役立つ「使える情報」が随所に盛り込まれ,また特定の術者の考え方に偏ることなく,本分野に共通する基本的原則が整理されている点も,本書の大きな魅力の一つである。
さらに,発生・解剖・病理といった基礎的事項に加え,歴史的背景にまで踏み込んで網羅されており,日常臨床のハンドブックとしてのみならず,「この一冊で全てが完結するバイブル」と呼ぶにふさわしい内容である。
中でも,本邦における神経内視鏡手術黎明期から本分野をけん引してきた諸先生による総説は,あらためて深い感慨を覚えさせられる。「髄液循環」を巡る議論が現在もなおホットトピックであることを実感し,今後の発展に大きな期待を抱かせる。また,実習モデル作製にまつわる苦労話からは,後進教育に注がれてきた並々ならぬ情熱が伝わり,深い敬意を抱かずにはいられない。
本分野にはいまだ議論の余地が残る課題も少なくないが,それらを正しく認識した上での考え方や,合併症への具体的な対処法が示されている点は,数多くの臨床経験と試行錯誤を重ねてきたエキスパートから直接学ぶことのできる,極めて貴重なエッセンスである。各章を通じて,単に「どのように行うか」だけでなく,「なぜその判断に至るのか」の思考プロセス,さらには技術習得に至る過程が丁寧に示されている点は,本書の大きな特徴であり,読者に深い理解をもたらす。まさに内視鏡術者の「知りたい」が凝縮された一冊であり,今後の神経内視鏡手術の発展に大きく寄与することは疑いない。
今回は基本的事項を重視した構成とされたため,難治例や希少疾患はあえて除外されたと述べられているが,これらを含めたアドバンス編の第2巻を期待してしまうのは,読者のわがままであろうか。
最後に,本書を執筆された諸先生方の多大なるご尽力に,心より敬意と感謝を表したい。
術者の手技と思考過程をリアルに追体験できる実践書
書評者:加藤 庸子(藤田医科大学ばんたね病院教授・統括副院長・脳神経外科学)
神経内視鏡手術の発展は,近年の脳神経外科領域における最も顕著な進化のひとつです。従来の顕微鏡手術では到達が困難であった深部病変や狭小な術野に対して,内視鏡がもたらす鮮明な視界と最小限の侵襲は,診断・治療の新たな可能性を切り開いてまいりました。その進歩の裏には,先人の不断の努力と,確かな教育体系の構築があったことを忘れてはなりません。本書『神経内視鏡手術ハンドブック』は,まさにその歩みを総括し,次世代へと継承するための優れた実践書です。
本書は,神経内視鏡手術の理論と実践を包括的にまとめた全217頁の大冊であり,編者の永谷哲也先生,村井尚之先生,西山健一先生を中心に,第一線で活躍されているエキスパートの先生方が執筆陣として名を連ねています。総論では,脳室・傍鞍部領域を中心に,術野の理解に不可欠な解剖学・生理学的知見を平易が解説され,手技選択の理論的基盤を明確に示しています。
単なる手技書にとどまらず,「なぜこのアプローチを選ぶのか」「どのような判断過程で術中対応を行うのか」といった思考の流れが重視されており,読者は術者の思考過程を追体験するように学ぶことができます。
各論では26の代表的症例が取り上げられ,術中の実際に基づく詳細な解説が展開されています。術中のピットフォールや想定外の局面をいかに乗り越えるか,またその際にどのような工夫が有効であったかなど,経験豊富な術者ならではのリアルな知見が随所に散りばめられております。こうした記述は,これから内視鏡手術を志す若手医師にとって,机上の知識を超えた「臨床の叡智」に触れる貴重な機会となることでしょう。
さらに注目すべきは,本書全体に通底する「教育の精神」です。難しいことを難しく書くのではなく,理論と実践をバランスよく配置し,若手の先生方にも理解しやすい構成に仕上げられています。豊富な写真,シェーマ,イラストはいずれも高精度で,読者が実際の手術手順を明確にイメージできるよう工夫され,教育現場での教材としても極めて有用です。
内視鏡手術が単なる“技術”ではなく,“判断力”と“解剖への洞察”に支えられた思考の医学であることを,本書は明確に示しています。読者はページを進めるごとに,術者としての考え方,視点の置き方,そしてリスクへの構え方を自然と学んでいくことができます。この構成こそが,永谷先生らが本書で示された「論理と証拠に基づく外科思考」の真髄であると感じます。
神経内視鏡手術は今後,AI支援ナビゲーションやロボット技術との融合により,さらなる発展を遂げることが予想されます。そのような時代においても,確かな基礎と判断力を備えた術者の育成こそが最も重要な課題です。本書は,その礎を築く「未来の教科書」として,多くの若手医師の学びを導くものとなるに違いありません。
本書を通じて,神経内視鏡手術が持つ奥深さと美しさ,そして何より「患者にやさしい外科医療」という原点をあらためて感じさせられました。本書の刊行に携わられた全ての先生方に心より敬意を表するとともに,本書が今後の神経内視鏡教育の新たな礎となることを心より期待申し上げます。