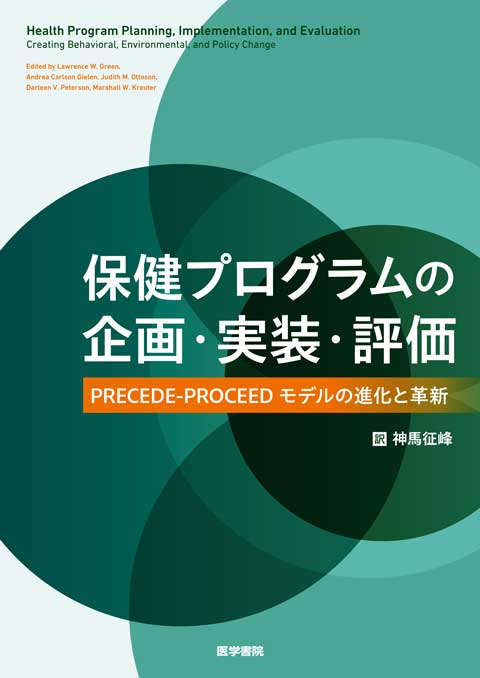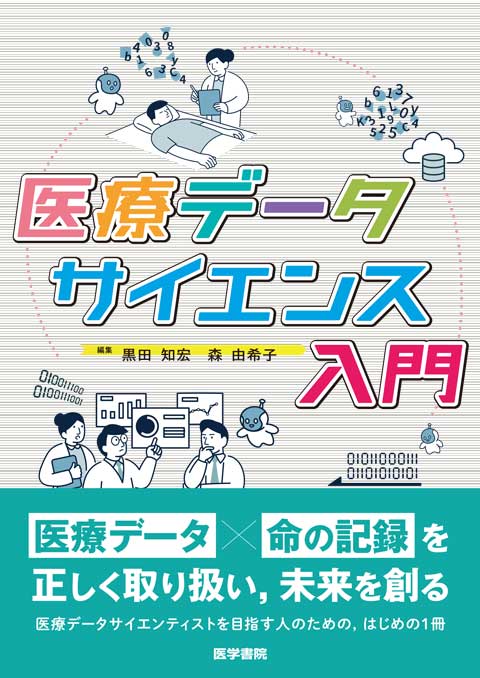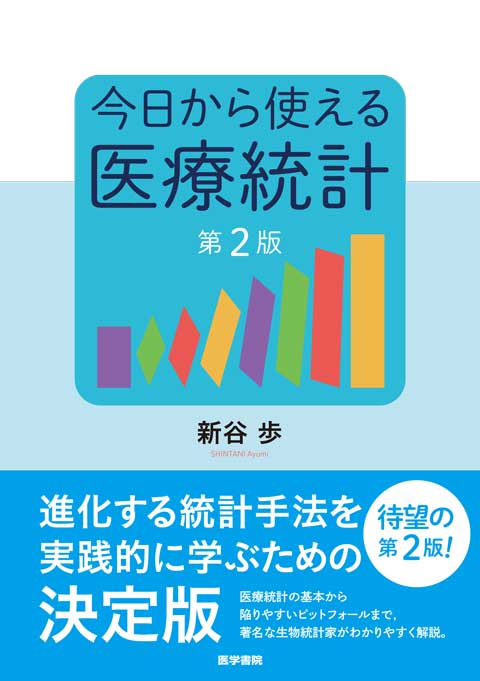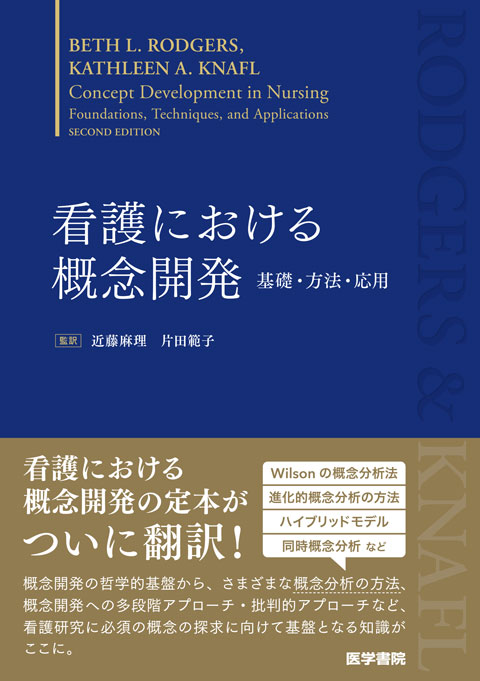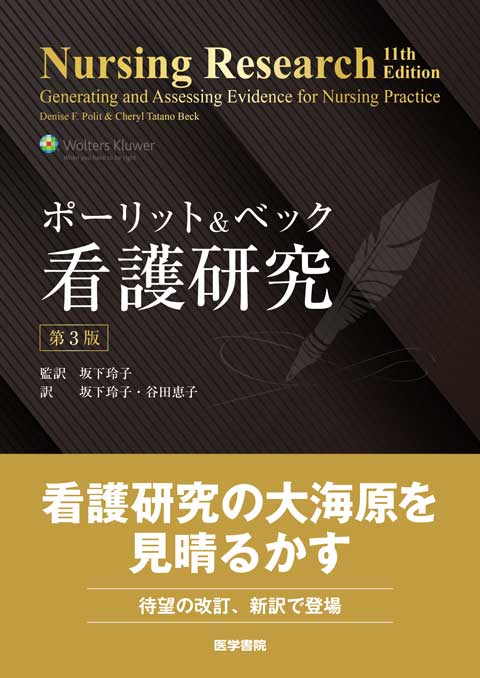保健プログラムの企画・実装・評価
PRECEDE-PROCEEDモデルの進化と革新
幅広い健康問題に取り組むための保健プログラムの標準テキスト
もっと見る
40年以上、幅広い健康問題に取り組むために世界中で有効に適用されてきたPRECEDE-PROCEEDモデルの変化と、新たな適応についてを述べた原著の翻訳。複雑な公衆衛生の課題を解決するための保健プログラムの戦略を、計画・実装・評価の面から、体系的にまた具体的に明記している。ヘルスプロモーションにとどまらず、集団の健康課題の解決を実践する公衆衛生関係者とその領域にかかわる学生にとって必携の1冊。
| 原書編集 | ローレンス W. グリーン / アンドレア カールソン ギーレン / ジュディス M. オットソン / ダーリーン V. ピーターソン / マーシャル W. クロイター |
|---|---|
| 訳 | 神馬 征峰 |
| 発行 | 2025年10月判型:B5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-05355-6 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
訳者序文/日本語版に向けて
訳者序文
本書はLawrence W. Green, Andrea Carlson Gielen, Judith M. Ottoson, Darleen V. Peterson, Marshall W. Kreuter編「Health Program Planning, Implementation, and Evaluation: Creating Behavioral, Environmental, and Policy Change」(Johns Hopkins University Press, 2022)の翻訳書である。原著は全14章からなり,前半の第1~9章は総論,第10~14章は各論である。本書では総論の第1~9章に加えて,各論としてPRECEDE-PROCEEDモデルとコミュニケーション技術を取り扱っている第14章を訳した。また,今回新たに加えられたFAQと評価指標に関する表を巻末に掲載した。PRECEDE-PROCEEDモデルにすでに慣れている読者は,まずはFAQから読んでいただき,長年の疑問点への回答を得ていただいてもよいかもしれない。
タイトルの翻訳にあたり,主タイトルはそのまま日本語訳とし,副題として「PRECEDEPROCEEDモデル」は残すべく,最終的に「保健プログラムの企画・実装・評価:PRECEDE-PROCEEDモデルの進化と革新」とした。
では何が進化したのか。原著の主タイトルの移りかわりをみると,「Health Education Planning」(1980),「Health Promotion Planning」(1991&1999),「Health Program Planning」(2005),「Health Program Planning, Implementation, and Evaluation」(2022)となっている。第1の進化は,単なるPRECEDEモデルから,評価を重視したPRECEDE-PROCEEDモデルへの進化であり,これは第2版(1991)で達成されている。第2は,健康教育からヘルスプロモーションへ,そして保健プログラムへという進化であり,PRECEDE-PROCEEDモデルの適用範囲が2005年の時点でヘルスプロモーションをこえている。第4版の翻訳(「実践ヘルスプロモーション」[2005])の際は,日本語タイトルに「ヘルスプロモーション」を残したものの,今回は原著に合わせて,ヘルスプロモーションの枠をこえるようにした。
次に革新とは何か。この原著第5版では「実装」強化という点が時代の動きに見合った第1の革新である。上にも示したように,第4版の主タイトルが「Health Program Planning」(2005)であったのに対し,今回はImplementation(実装)とEvaluation(評価)が加わっている。評価については第4版でも強調されていたが,今回の大きな焦点は「実装」であり,それに関する記述は大きく書きかえられている。日本でも実装科学が注目されてきているなか,本書はヘルスプロモーションのみならず,保健プログラム全般における実装科学推進のよき導き手となるであろう。
第2の革新は,PRECEDE-PROCEEDモデルのフレームワークにおける各アセスメント間の関係が一方通行ではないことを強調すべく,モデルに円環上の枠が付け加わったことである。また第4段階の具体的な内容として介入戦略,実装戦略,評価戦略が明記され,第5段階以降の活動がこれまでにもまして実施しやすくなった。
最後の革新は,このモデルがデジタル技術と強くリンクしてきているということである。PRECEDE-PROCEEDモデルのためのデータ収集にデジタル技術が用いられているというだけではない。保健プログラムに用いるアプリ開発を行う際,PRECEDE-PROCEEDモデルにおける準備要因,実現要因,強化要因という分類が用いられているのである。
このように進化をとげ革新を続けてきたPRECEDE-PROCEEDモデルのテキストは50年あまりの歴史がある。文化の壁をこえ世界各国で読まれ,活用されている。日本の保健プログラムに特化したテキストでこれだけ長い歴史をもつものが他にあるだろうか。その意味で本テキストはヘルスプロモーションの古典であり,保健プログラム実施のための古典ともなってきている。理論だけではない。それをいかに実践にいかすべきか,問題解決の書としての価値が本書にはある。
50年余りの経験をもとに,保健プログラムを実施する際,覚えておくべきスローガンが,Green博士のウェブサイト(http://www.lgreen.net)に大きく示されている。
「もし私たちがエビデンスに基づく実践をより多く求めるのであれば,より多くの実践に基づくエビデンスが必要である(If we want more evidence-based practice, we need more practice-based evidence.)。」
筆頭編者のGreen博士をはじめとする5人の編者は論文を書くだけではなく,コミュニティや国レベルでの保健プログラム実施に多くの経験を有している。たとえばGreen博士はバングラデシュの家族計画プログラムにもかかわっていたことがある。
いわゆるRCTをもとにしたエビデンスだけでは複雑な公衆衛生課題は解決しがたい。それを現場であてはめて,齟齬を謙虚に認め,実践に基づいて,解決への道を探っていこうという気概が本書には満ち溢れている(12ページの事例を見てほしい)。既存のエビデンスにふりまわされることなく,現場経験をもとに新たなエビデンスをつくりあげていこうというこのスローガンは,今後もその価値を失うことはないであろう。
最後にGreen博士とOttoson博士との出会いについて一言触れておきたい。COVID-19の嵐がおさまりつつあった2021年10月,デンバーで開催された米国公衆衛生学会にて二人と会う機会があった。そこでこの第5版がほぼ完成しているとの情報を得て,ぜひこの新版を,原文に忠実でありながらも私自身の「ライフワーク」のひとつとして,できるだけ自分の言葉で翻訳したいと思った。そして,医学書院編集部と相談し,発刊への準備が整えられた。その後,翻訳には2年余りを要してしまった。この間に,本文中のいくつかのリンクが使えなくなっており,今後もこの傾向は続くはずである。キーワードなどをもとに,新たなリンクを各自探しあてて欲しい。
前回同様,医学書院の皆さんには大変お世話になった。とくに編集部のご担当の方は,きわめて多忙のなか,一語一語,一行一行,綿密に私の翻訳内容を,AIを駆使しながら確認し,修正してくれた。また本文の内容を十分理解していただいたうえで,原書にあった内容の誤りまで指摘してくれ,原著者(Green博士とGielen博士)の了解のもとその誤りを修正し,日本語訳を完成することができた。
たった1人で翻訳したつもりでいても,実際はそうではない。ふり返ってみれば,この翻訳という仕事においても,本書の序(p.xi)にでてくるアフリカのことわざがどれほど真実か,その言葉を若干言いかえて,この2年間お世話になった多くの人に感謝したい。
Yes, it took a village.
2025年8月 神馬征峰
日本語版に向けて
国際的な経験と英知の蓄積によって,PRECEDE-PROCEEDモデルは50年以上にもわたって発展し,代表的なモデルとなることができた。このモデルがこうして今でも用いられているのは,世界各国で,コミュニティで,またさまざまな人口集団を対象に,学生や実践家がさまざまなプログラムの企画・実装・評価にこのモデルを活用してくれてきたからである。ただし,このモデルを使ってみて,そこから得られた教訓は,自らの経験として論文や書籍として他者に伝えられなければならない。実際にウェブサイト(http://www.lgreen.net)を訪れてもらえれば,このモデルの活用事例として論文化された多くのエビデンスを見つけることができる。
このPRECEDE-PROCEEDモデルを日本語に翻訳し,またアジアの専門家のためにもこのモデルを広める役割を果たしてくれている神馬征峰教授に深く感謝したい。
ローレンス W. グリーン
目次
開く
第I部 PRECEDE-PROCEED モデルの顕著な特徴(ホールマーク)
第1章 ポピュレーションヘルスのための企画・実装・評価モデル
1 PRECEDE-PROCEEDモデルにおいて鍵となるコンセプト
①プログラム企画における,「ポピュレーションヘルス」の視点
②プログラム企画における生態学的アプローチと教育的アプローチ
③エビデンスに基づく実践の適応における人々とそのコンテキストへの配慮
2 PRECEDE-PROCEEDモデル
①ポピュレーションヘルスの企画におけるPRECEDE-PROCEEDモデルのアプローチの諸段階
②PRECEDE-PROCEEDモデルはどのように機能するのか?
・ 第1段階:社会的アセスメント
・ 第2段階:疫学的アセスメント
・ 第3段階:教育的・生態学的アセスメント
・ 第4段階:保健プログラムと政策開発(介入調整,運営・政策アセスメント,実装)
3 顕著な特徴(ホールマーク)
①柔軟性
②エビデンスに基づいた過程と評価可能なフレームワーク
③参加
④エビデンスに基づく実践と実践に基づくエビデンス
4 要約
5 演習
第2章 企画のための参加とコミュニティ・エンゲージメント(地域貢献)
1 生態学的なコンテキストと諸課題:コミュニティの最初の関心事
2 相互関係にある社会と健康
3 究極の価値ではなく手段としての健康
4 コミュニティの関心事を引きだすための主観的アセスメント
5 生態学的アプローチと環境アプローチの重要性
6 参加の原理とプロセス
7 参加の形態
8 優先度の設定と参加
9 一般住民の認識と専門家による診断:共通の土俵
10 実行能力の形成(capacity-building)と持続可能性:参加の事例
11 アセスメントの諸段階の詳細
① 機能的な企画の段階
② 技術支援
③ PRECEDEの諸段階に共通なタスク
④ 公的機関レベルでの機能
⑤ 実装と評価
⑥ 実行能力の形成,自律(機能),持続可能性のサイクル
⑦ 評価,デモンストレーション,波及効果
12 参加とパートナーシップについて銘記すべきこと
13 要約:参加とコミュニティ・エンゲージメント
14 演習
第II部 PRECEDE-PROCEEDモデルの諸段階:企画・実装・評価
第3章 社会的アセスメント:生活の質(QOL)
1 はじめに
2 究極の価値の1つの表現としてのQOL
3 個人レベルでのQOLの測定
4 コミュニティや集団レベルでのQOLの測定
5 QOLデータの限界
6 社会的アセスメントのための方法と戦略
7 データ入手後の次の作業
8 諸段階の省略,結合,入念な調整
9 要約
10 演習
第4章 疫学的アセスメントI:ポピュレーションヘルス
1 はじめに
2 途中から始めるために:実践家がかかえている現実
3 企画者がモデルの全体像を知っておかなければならない3つの理由
4 相互性,社会的決定要因,参加
5 疫学
6 健康問題の指標
7 率
8 特殊調整率
9 罹患率と有病率
10 理解を深めるための比較アプローチ
11 保健プログラムの優先事項と目的の設定
12 健康目的の明示
13 演習
第5章 疫学的アセスメントII:行動要因と環境要因
1 はじめに
2 行動の3つのレベルあるいはカテゴリー
3 遺伝と行動との相互作用
4 行動アセスメントにおける5つのステップ
①ステップ1:健康問題と関係があると思われる行動リスクのリストアップ
②ステップ2:重要性に応じた行動のランクづけ
③ステップ3:かわりやすさに応じた行動のランクづけ
④ステップ4:行動目的の選択
⑤ステップ5:行動目的の明示
5 環境アセスメントにおける5つのステップ
①ステップ1:環境要因の特定
②ステップ2:重要性に応じた環境要因のランクづけ
③ステップ3:かわりやすさに応じた環境要因のランクづけ
④ステップ4:環境目的の選択
⑤ステップ5:環境目的の明示
6 演習
第6章 教育的・生態学的アセスメント:準備要因,実現要因,強化要因
1 はじめに
2 理論的基盤
3 準備要因
①知識
②信念,価値観,態度
③行動意図,認知された規範,合理的行動理論
4 実現要因
○スキル
5 強化要因
6 行動変容および環境変化の決定要因の選択
①ステップ1:各要因の特定と分類
②ステップ2:3つのカテゴリー間での優先順位の決定
③ステップ3:各カテゴリー内での優先順位の決定
7 学習目的と資源獲得目的の記載
8 要約
9 演習
第7章 保健プログラムと政策開発I:介入戦略
1 はじめに
2 包括的なプログラムの企画における介入戦略の調整,マッチング,パッチング,ブレンディング
①調整1:介入戦略と優先決定要因との関係:マッチングによる介入戦略と優先度の高い準備要因,強化要因,実現要因との調整
②調整2:組織やコミュニティがおかれたコンテキストに介入戦略を「適合(フィット)」させるための調整
③調整3:ギャップ解消のためのパッチング:介入戦略をつくりあげ,ベストプラクティス実践のための「ハウ・ツー」ステップを見いだす方法
④調整4:包括的なプログラムのために行う介入戦略のプーリングとブレンディング
3 プログラム全体の最終調整:組織とコミュニティへの介入戦略・適合具合の確認
4 要約
第8章 保健プログラムと政策開発II:実装戦略
1 はじめに
2 実装
3 実装の諸段階
・ 探索と採用
・ プログラムの導入
・ 初期実装
・ フル稼働
・ イノベーションまたは調整
・ 持続可能性
4 運営アセスメント
①ステップ1:必要な資源は何か
・ 時間
・ 人的資源
・ 予算
②ステップ2:利用可能な資源のアセスメント
・ 人件費
・ 旅費
・ 器材費
・ その他の諸経費
・ 間接経費
・ 予算関連の説明あるいは正当化
③ステップ3:プログラムの実装に影響を及ぼす要因のアセスメント
・ 組織要因
・ プログラムの目標設定
・ 変化の程度
・ スペース
・ 人材確保
・ スタッフのコミットメントと態度
・ 手慣れた方法かどうか
・ 複雑性
・ 政治的要因
・ コミュニティ要因
5 実装ツールの開発
・ ロジックモデル
・ 実装マニュアル
・ タイムライン
・ 作業計画書
6 質の確保,トレーニング,監督指導
7 プログラム・モニタリング
8 実装アウトカム
9 実装科学
10 エビデンスに基づく実践から実践に基づくエビデンスへの「パイプライン」
11 実装研究の利点
12 実践に基づくエビデンス
13 要約
14 演習
第9章 保健プログラムと政策開発III:評価戦略
1 はじめに
2 プログラム評価とは何か
3 プログラム評価の基準
4 プログラム評価をするのはなぜか
5 PRECEDE-PROCEEDモデルとCDC評価フレームワークとの統合
6 評価のステップ1:ステークホルダー・エンゲージメント
7 評価のステップ2:プログラムの記述
8 評価のステップ3:デザインへのフォーカス
①評価のための質問
②価値づけ:関心の対象と容認基準
③評価デザイン
④サンプリング
⑤複合研究法または混合研究法
9 評価のステップ4:信用できるエビデンスの収集
10 評価のステップ5:結論の正当化
①分析方法
②提言
11 評価のステップ6:教訓の確実な利用と共有
12 要約
13 演習
第III部 PRECEDE-PROCEEDモデルの新領域での応用
第10章 コミュニケーション技術への適用
1 はじめに
2 どのようなコンテキストのなかでPRECEDE-PROCEEDモデル適用のために技術を役だてられるか
3 2つのケーススタディ:技術をもとにした(あるいは関連した)介入策の開発のためのPRECEDE-PROCEEDモデルの活用
4 ケーススタディ:若者のメンタルヘルスのためのコミュニティ意識向上キャンペーン「COMPASS戦略」の開発と評価
5 若年男性の健康的なライフスタイル向上プログラムの実現性についての調査
6 2つのケーススタディ:mHealthのアプリの類型化のための分類方法構築におけるPRECEDE-PROCEEDモデルの活用
①そのためのアプリがここにある:有料の健康・フィットネスアプリの内容分析
②晩年における疾患予防と管理のためのモバイルアプリ分析のための分類スキーム
③COVID-19に対して用いられた技術についてのケーススタディ
7 要約
付録 評価基準チェックリスト
PRECEDE-PROCEEDモデルについてのFAQ
索引
書評
開く
PRECEDE-PROCEEDモデルの実践にも自己学習にも活用できる待望の改訂版
書評者:磯 博康(国立健康危機管理研究機構グローバルヘルス政策研究センターセンター長)
本書は,保健プログラムの企画・実装・評価に関して,長年の経験と実績のあるローレスW. グリーン名誉教授(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)が主編集者として,各方面の教授陣らの執筆の下に編さんした成書であり,その理論モデル,地域貢献,企画・実装・評価,モデルの新領域での応用と広範で,実用に役立つ構成となっている。私にとっても,日本において生活習慣病の予防プログラムを45年にわたり地域で実践,評価してきた経験から,ふに落ちる記述が多く,わが国において保健プログラムを新たに展開したいと考えている若手の研究者,そのための人材育成を行っている教育者にとって大いに参考となる成書と言える。
PRECEDE-PROCEEDモデルは,1997年に本書の第2版「ヘルスプロモーション」が翻訳されて以来,主に保健所医師や保健師によって活用されてきた。PRECEDEは「教育的・生態学的診断と評価のための準備要因・強化要因・実現要因,保健プログラムのための先行段階としてのアセスメント」,PROCEEDは「教育的,環境発展のための政策,法規,組織的コンストラクト」と訳される。その本質は,これまで国内外で実施されてきた,いわゆる「地域ぐるみの予防対策」の推進要素を体系化したモデルと位置付けられ,疫学,生態学,教育学などに立脚し,PDCAサイクル,ロジックモデルなどを含む包括的なモデルと言えよう。
本書の活用方法として,第I部の「PRECEDE-PROCEEDモデルの顕著な特徴」を概観し,第III部の「PRECEDE-PROCEEDモデルの新領域での応用」を見て,自身の研究の参考となる事例を見出して,その上で第II部の「PRECEDE-PROCEEDモデルの諸段階:企画・実践・評価」に戻り,必要な箇所を精読するか,繰り返し参照することを勧めたい。なぜなら,最初から順番に読み進めると人によってはその広範な記述から,実践を伴わない理論の理解に終始してしまう懸念があるからである。
また,本書では各章においてさまざまな演習が提示されており,自己学習や教材資料として活用できることから,保健にかかわる多様な分野の学部学生,大学院生,若手の研究者にとって多くの示唆を与えるとともに,教育者にとっても有用な構成となっている。
最後に,本書(第5版)の日本語訳は,神馬征峰氏がお一人で行われており,そのため日本語の記載が統一されており理解しやすいものとなっている。氏の精緻な翻訳作業に敬意を表したい。