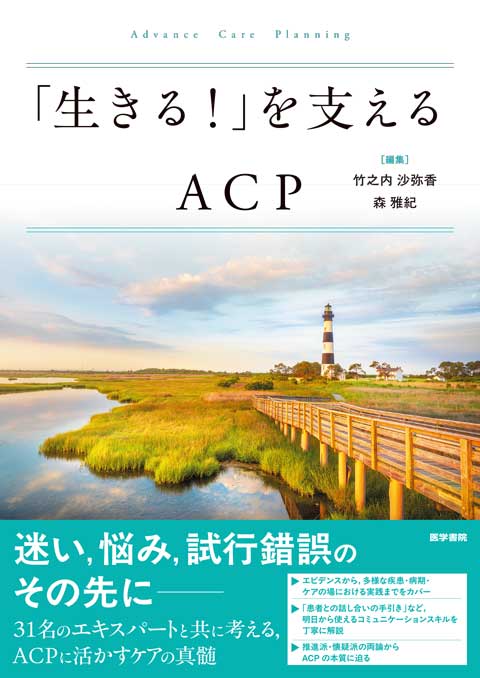MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.10.14 医学界新聞:第3578号より
《評者》 福田 正人 群馬大 名誉教授
「素朴な心因論」に基づく当たり前の精神科臨床
精神疾患について,「発達メガネ」や「トラウマメガネ」をかけて,「生活のなかで困っていること」への「反応性と考える」。そうした「素朴な心因論」に基づき,「ねぎらうことの大切さ」を心掛けて「やわらかく治す」。そのような精神科診療を,数多くの症例に基づいて身近に学べる本である。
「何かの出来事が原因のように見えても(中略)本質的には脳の失調,脳に主な原因がある」と若いころに教えられた世代にとっては,精神疾患の見方に根本転換を求められることになる。しかしそれは古き心因論の復権ではなく,精神医学の進歩を踏まえたより精緻な心因論である。そこでのキーワードは,発達症とトラウマの相互作用「発達⇄トラウマ」である。
「素朴な心因論」を示すのは,印象的なキーワードである。病状の特徴として,「スポンと抜ける」「入院反応」「一過性の発達障害」という指摘がある。医療者の心掛けとして,「『よい子』『普通の子』の奥に潜む過剰適応に気づく」「ニコニコしている人の孤立に気づく」が挙げられている。その背景として,「個人的な資質や生活史,生活環境などの面において,不利な条件が多い人」「生活圏の狭まりが精神症状を引き起こす確率を高める」「生きていくための戦略の1つとして回避,解離がある」ことへの気付きが必要とされる。
心因論を踏まえた「やわらかく治す」の基本は,「体系立った狭義の精神療法ではなく『(中略)今一生懸命に生きている,その人を支える』という支持的精神療法」「症状や原因に迫る鋭く深い精神療法ではなく,応急手当を繰り返しながら自然治癒力の発動を待つような,鈍く浅い精神療法」「いくらか温かみのある,あっさり,さっぱりとした関わり」であるという。
具体的な心掛けとして挙げられているのは,「『傾聴』が不安を招いてはいないか」に気をつけ,「サラサラと流れるように診察」「退室まで視線や気持ちを,患者さんから逸らせない」よう心掛け,「ほんのりと温かい生活支援」「注意を内(身体)から外(環境)に向ける」「解離には解離で」に努めることである。
「素朴な心因論」に基づき「やわらかく治す」ことの総論である冒頭の4章と末尾の3章の間に,診断ごとの6章がある。そこにほとんどの精神疾患が挙げられ,高齢者まで含まれていることが,「鈍く浅い精神療法」の真価を示している。
持って生まれた資質(発達症)と育った環境での出来事(トラウマ)を背景に,生活での困り事への反応として精神的な変調が生じるという理解は,改めて考えれば当たり前である。精神機能も脳機能も,暮らし生きるために進化を重ねたものだからである。それをまとめた前著『大人の発達障害を診るということ』『大人のトラウマを診るということ』(ともに医学書院)を,「素朴な心因論」へと発展させたのが本書である。
「心理も脳機能も自然な流れに沿った『当たり前』感覚の診療は,お互いに無理のない理想の姿である」と評者は書いたことがある1)。本書を穏やかで安心した気持ちで読めるのは,素朴な心因論の「当たり前」によるものだろう。そうした臨床が精神科診療の当たり前となり,日々の治療や支援が変わっていくことを期待したい。
●参考文献
1)福田正人.「未来のあたりまえ」と三百昔.こころの科学.2017;195:1.
《評者》 小倉 真治 朝日大保健医療学部学部長 / 救急救命学科長
Web付録も追加されて正常進化した第3版
郡山一明先生による『救急救命士によるファーストコンタクト 第3版』がこのたび刊行されました。2006年に初版が出て名著の評判を得,2012年の第2版,そして今回の第3版と,正常進化を遂げています。救急救命士に必須の手技についての書籍は多数ありますが,その背後にある病態生理学的な裏付けを教えてくれるのは,本書以外は寡聞にして聞いたことがありません。
今回,新たに第3版を読み込んで再び感動するとともに,「これは救急救命士をめざす学生や若手の救急救命士にはとても勉強になる内容だ」と思いました。著者の郡山先生と評者は同じ年でその付き合いは30年近くに及びます。郡山先生の発想の面白さにはいつも目を見開かされており,本書にもその「郡山イズム」がしっかり表現されています。例えば,マヨネーズで心拍出量を(pp.26-8),回転寿司でOxygen deliveryを(pp.65-7),山手線で心不全を(pp.104-6)説明するところなどです(興味を持った方はぜひ該当箇所をご覧ください)。
また第3版から追加されたWeb動画(本文に掲載の二次元コードからアクセス)はそのまま授業に使えるくらいのクオリティです。帯の「伝説の講義REBORN!」というキャッチコピーは全く大げさではありません。本書の読者はその郡山先生の講義を自分の都合のいい時間にスマホで,タブレットで,パソコンで見ることができます。ともすれば書籍を軽んじ,YouTubeなどの動画を中心に学習を進めることが流行となっていますが,「書籍と動画の複合体」の教材に勝るものはないと実感しました。
評者は昨年(2024年)に岐阜大医学部救急・災害医学分野を退職した後,現在は朝日大保健医療学部で同学部長および救急救命学科長として,本年(2025年)4月に開設された救急救命学科の一期生を迎え入れたところです。本学の学生にかかわらず,救急救命士をめざして勉強をしている全国の学生たち,そして病院前救護に日々奮闘している若手の救急救命士の皆さんに自信を持って本書を薦めます。それくらい価値のある内容です。
《評者》 明智 龍男 名市大大学院教授・精神・認知・行動医学
自己決定を超えて「生」を支える対話へ
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という言葉が,日本の医療現場でも否応なく広がっている。しかしその導入は,単に欧米の医療実践にとどまらず,日本文化や人間関係の深層にまで及ぶ営みであることを,われわれはどこまで自覚できているだろうか。
本書は,31人の臨床家・研究者が執筆し,ACPの理論的基盤,現場での工夫,課題や展望を多面的に描いている。編者の竹之内沙弥香氏と森雅紀氏の思いが込められたタイトルの通り,本書はACPを単なる輸入型の医療実践としてではなく,「生を支える対話の営み」としてとらえ直そうとする真摯な姿勢に貫かれている。
特に森氏の「ACPにおける課題と展望」,竹之内氏の「『生きる』力を...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

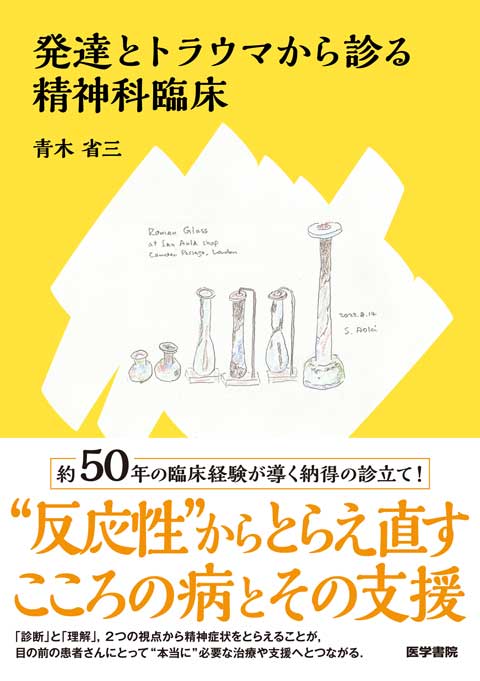
![救急救命士によるファーストコンタクト[Web動画付]第3版 病院前救護の観察トレーニング](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6017/4848/1092/113689.jpg)