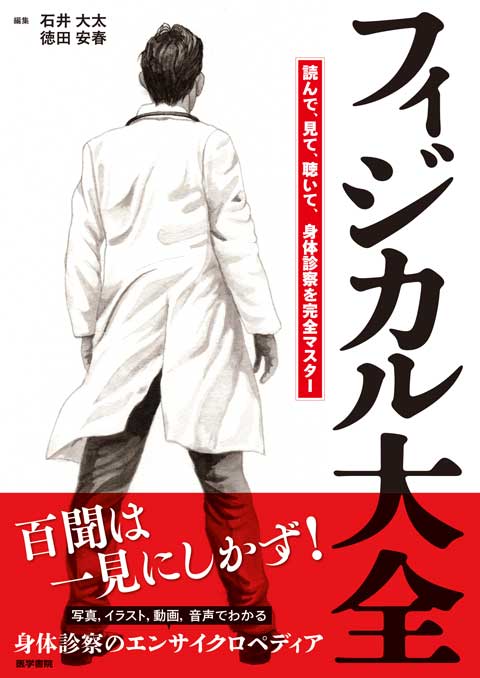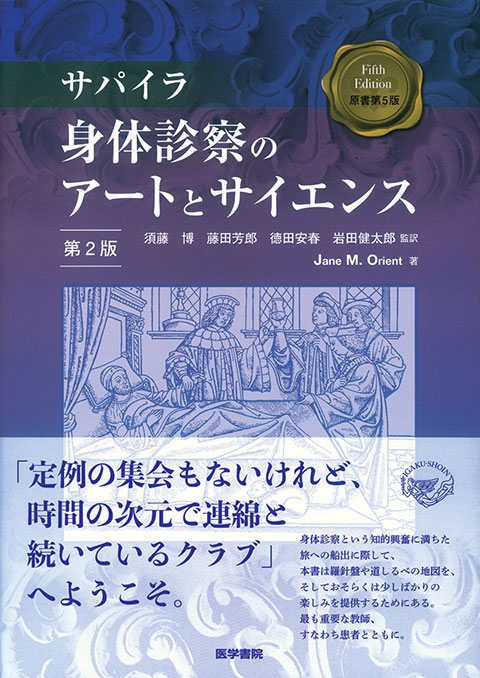病歴と視診で築く診断の確かな基盤
対談・座談会 徳田 安春,西垂水 和隆
2025.10.14 医学界新聞:第3578号より

CT・MRIといったモダリティの進化はめざましく,診断に至るまでの情報収集手段として欠かせない存在です。しかし,モダリティに依存した診療スタイルが広がる一方で,診断の基本と言うべき病歴聴取や視診が疎かにされているのではないかとの指摘もしばしば聞かれます。近年のAI時代にあっても,検査の価値を最大化するためには,適切な検査選択と結果解釈の土台をつくる「病歴と視診」が要になります。トップジェネラリストであり,書籍『総合内科診断メソッド――病歴と視診で捉える』(医学書院)を上梓した西垂水氏と,総合診療のパイオニア的存在で,総合診療医育成に尽力する徳田氏の対話を通じて,病歴と視診の意義や,日常診療で確かな手がかりを拾い上げるコツを探りました。
西垂水 徳田先生に初めてお会いしたのは医師になって6年目の頃で,県立宮古病院から先生のいらっしゃる沖縄県立中部病院に赴任した時のことです。先生の評判はとにかく高く,お会いできるのが楽しみだったことを覚えています。同じ病院で勤務したのは1年間でしたが,本当にさまざまなことを経験させてもらいました。ちなみに,今日は徳田先生にお会いできると思ったので,かりゆしウェアでそろえてきました。
徳田 本当ですね(笑)。当時の西垂水先生は,若手ナンバーワン内科医と院内で噂されていました。県立宮古病院ではどんな患者も診ますという心意気で,内科のコンサルトケースは全部診ると公言されていたとか。中規模病院で働く卒後5年目にしてこの心意気はすごいことですよ。県立中部病院に移られてきて初めてお会いしてからすぐに意気投合し,総合内科を立ち上げるに至りましたね。
西垂水 ええ。あの1年で先生は私のロールモデルとなり,その後もずっと背中を追いかける存在です。
病歴と視診を総合的に捉える
徳田 日常診療においてAIを活用することはありふれた状況になりました。しかし丁寧な病歴聴取などの患者さんとのやり取りから情報をくみ取っていくことは,AIが担うことが難しい,医師に残された人間ならではのアートな部分だと私は思います。言葉として文字化された情報だけでなく非言語的な情報も含めて総合的に判断することは,人間だからこそできる技能なはずです。このたび西垂水先生が執筆された『総合内科診断メソッド――病歴と視診で捉える』は,まさにAI時代に求められる総合内科医の技術をまとめた書籍だと言えると思います。本日は,同書籍のメインテーマであり,診断の基本である病歴聴取と視診について考えていきたいと思います。西垂水先生は診療の中で病歴聴取や視診をどのように位置づけていますか。
西垂水 診断に直結するヒントの多くは患者さんの言葉に含まれており,診断を行う上で病歴聴取は大きな役割を担うと考えています。ただ,実際にその情報を引き出すのは容易ではなく,聞き手である医師が適切に情報をくみ取れなければ,診断には結びつきません。AI技術が発展する中で人間がやるべきことは,ベッドサイドで重要な情報を引き出すことなのでしょう。また視診においては,患者さんの全身状態,表情,姿勢,雰囲気など,相手からにじみ出てくる情報を捉えることが大切です。これらの情報には言葉で表現しにくいものもありますが,うまく拾い上げられれば診断につながる手がかりとなりやすいためです。
徳田 病歴聴取から得られた情報は診断につながる情報の7割を占めるともよく言われますし,非言語的な情報を瞬時につかみ取れる視診から得た情報を病歴と組み合わせることで,診断の精度は格段に高まります。一方で,モダリティの進化に伴い診断にたどり着くための選択肢が増加したことで検査偏重の傾向がみられる近年,若手医師や研修医に「病歴と視診を統合的に捉えて診断に生かす」という視点が強調されにくくなっているのではと感じます。
西垂水 とはいえ病歴聴取や視診の重要性に着目され始めている兆しもありますよね。特に多くの人がマスクをつけるようになったコロナ禍を経て,視診の重要性に気づかされた医師も多いのではないでしょうか。目の周辺からだけでも多くの情報が得られるものの,やはりマスクを外すようになると口元から読み取れる情報がより大事だと改めて実感します。コロナ禍ではこうした非言語的な情報を得る機会が少なかったため,診察スキルに自信が持てないと不安を口にする研修医もいたようです。
徳田 確かにそうですね。顔の一部が覆われていた時期を経たからこそ,顔全体を観察することの意味を改めて認識できたと思います。コロナ禍以前の研究ではありますが,スウェーデンのカロリンスカ研究所で,エンドトキシンを注射した被験者の表情を分析したところ,病的な状態では目だけでなく,唇の色や形などにも変化が見られたとの報告があります1)。つまり,視診で得られるのは単なる印象ではなく,病態を反映した客観的な変化でもあるのです。非言語的な情報を見落とさずに捉える姿勢を,若手医師にもぜひ大切にしてほしいと感じます。
いつの時代もブレない診療の軸
徳田 先ほど挙げたマスクの問題などをきっかけに,コロナ禍を経て病歴と視診の重要性を理解し始めている若手もいます。しかし近年CT,MRIなどのモダリティが発展している中で病歴をさっと聴取した後に「とりあえずCT検査だけしておけばいいだろう」と判断してしまう傾向は根強くありますよね。
西垂水 われわれが研修医の頃は,主訴の情報を丁寧に聴取し,症状の経過も全て把握した上で,ようやく血液検査や画像検査をオーダーする流れでした。そのため「なぜオーダーするに至ったか」という理由が明確で,症例プレゼンを聞いても内容がスーッと頭に入ってくるんですよね。けれども今は「患者さんの細かな病歴や視診の結果の話はいいから」とばかりに,とにかく全身のCT検査をオーダーしがちで,なぜオーダーしたかわからないケースが増加しています。CT検査が今ほど主流ではなかった昔と今とでは状況が全く異なるとは思いますが,検査をオーダーする前の情報収集も大事にしてほしいです。
徳田 私が沖縄県立中部病院で研修をしていた1990年頃は,「1年目の研修医はCT検査をオーダーできない」というルールがありました。1年目に問診と診察のスキルを徹底的にたたき込むためです。同ルールは問診と診...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

徳田 安春(とくだ・やすはる)氏 群星沖縄臨床研修センター長
1988年琉球大医学部卒。沖縄県立中部病院にて研修後,沖縄県立八重山病院内科,沖縄県立中部病院総合内科,聖路加国際病院一般内科,筑波大水戸地域医療教育センター総合診療科教授,地域医療機能推進機構本部顧問などを経て,2017年より現職。『病歴と身体所見の診断学――検査なしでここまでわかる』『こんなときオスラー』(いずれも医学書院)など著書多数。

西垂水 和隆(にしたるみず・かずたか)氏 今村総合病院救急・総合内科 臨床研修部長
1992年鹿児島大卒。沖縄県立中部病院での研修を経て,沖縄県立宮古病院に勤務。2001年今村病院分院(当時)にて365日24時間体制の総合内科である救急・総合内科を立ち上げる。その後,手稲渓仁会病院,JA北海道厚生連倶知安厚生連病院に勤務し,07年より現職。著書に『総合内科診断メソッド――病歴と視診で捉える』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。