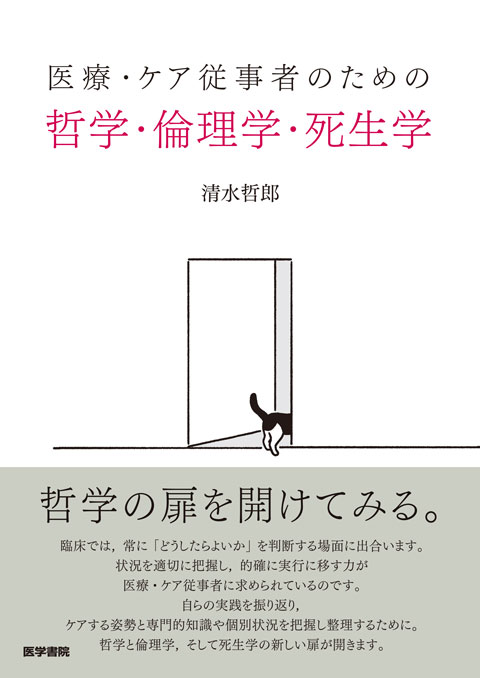応用倫理学入門
[第4回] 生殖医療の倫理(1)――体外受精,着床前診断,代理出産
連載 澤井努
2024.11.12 医学界新聞(通常号):第3567号より
1978年,世界初の体外受精(in vitro fertilization:IVF)児であるルイーズ・ブラウンが誕生し,生殖医療に革命が起きました。この技術は自然妊娠が難しいカップルにとって希望の光となり,不妊治療の選択肢を大きく広げました。しかし,IVF技術を開発したロバート・エドワーズがノーベル生理学・医学賞を受賞した際に,ローマ・カトリック教会が否定的な反応を示したことは広く知られています。IVFは現在,代表的な生殖補助技術の一つとなっていますが,その健康リスクについてはいまだ完全には解明されていません。また,問題は健康リスクにとどまりません。今回は,比較的歴史の長い生殖補助技術の中でも,IVF,着床前診断(preimplantation genetic diagnosis:PGD),代理出産に焦点を当て,それらに伴う倫理的課題を論じていきます。
体外受精で生じた胚の取り扱いの問題
IVFのプロセスでは複数の胚を作るため,使用されなかった胚(余剰胚)が発生します。次のような架空の事例を考えてみましょう。
不妊治療を受けているAさん夫妻は,体外で卵子と精子を受精させ,5つの胚を作製しました。1つを移植し,無事に妊娠しましたが,将来的にもう一人子どもを持つことを考慮し,残りの胚を凍結保存します。数年後,夫妻は子どもを持たない決断をしますが,保存コストが増す中で,これまで凍結保温してきた胚をどうするか悩んでいます。選択肢としては,廃棄,不妊治療中のカップルへの提供,研究への提供,凍結保存の継続の4つがあります。
どの選択をするにしても,まずはAさん夫妻の自律性を尊重することが重要です〔インフォームド・コンセント(informed consent:IC)については連載第3回を参照〕。そのためにも医療従事者は,患者に必要十分な情報を提供するとともに,患者が時間をかけて判断し,自分自身の決定に責任を持てるような状況を整える必要があります。一方で患者は,各選択の利点と併せて,凍結保存のコストや各選択に伴う心理的負担を含めた情報を正しく理解する必要があります。
ただし,ICに基づく患者の自己決定だけで全てが解決するわけではありません。重要な課題として,胚の道徳的地位に関する問題が残ります(連載第2回を参照)。国によっては余剰胚の研究利用が倫理的にも法的にも認められていますが,そうした行為が一切禁止されている国もあります。不妊治療中のカップルへの提供,研究利用が認められていない国では,個人の選択肢がさらに制限されるのです。
胚の道徳的地位に関する考え方は,社会の価値観や宗教的信念に大きく左右されます。胚がどの段階で道徳的地位を獲得するのかという問題は簡単に解決できません。しかし,倫理が普遍的なものではないとするならば,社会的対話を通じて多様な意見を反映した規範を策定し,その結果をもとに余剰胚の扱いを決定することが求められるでしょう(倫理的構成主義については連載第1回を参照)。
着床前診断は社会に何をもたらすのか
PGDは,胚を子宮に戻す前に遺伝的異常の有無を診断する技術です。この技術には,習慣性流産の予防や遺伝性疾患の早期発見という大きな利点があります。しかし一方で,診断結果に基づく遺伝的選別は,障害を持つ人々に対する差別を助長する可能性が懸念されています。
PGDの使用によって,多くのカップルが「健康な」胚のみを選ぶ社会が到来するとしましょう。そのような社会では,遺伝性疾患を持って生まれる子どもはまれとなり,障害を持つ人々はさらに孤立するかもしれません。障害を持つ子どもを授かった家庭は,なぜPGDを利用し...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。