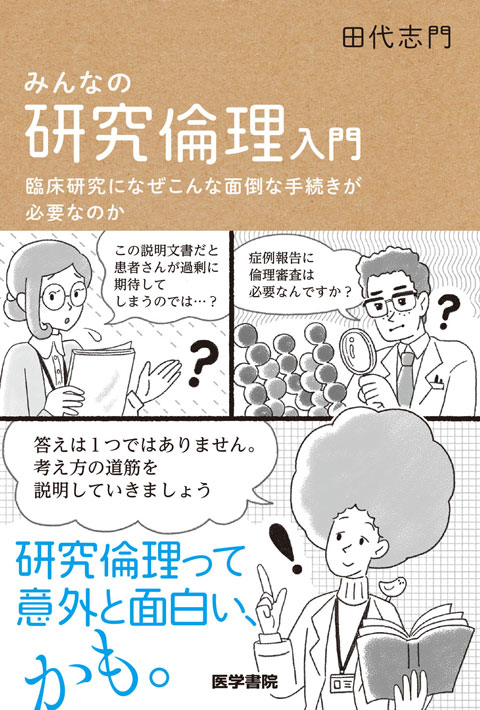応用倫理学入門 科学技術に伴う諸問題を考える
[第3回] 研究倫理におけるインフォームド・コンセントの重要性
連載 澤井努
2024.10.08 医学界新聞(通常号):第3566号より
生物医学研究は,生命現象の理解,新たな治療法の開発,疾病の予防など,人類の健康と福祉の向上に多大な貢献をしてきました。しかし,この進歩の陰には,研究対象となった人々,特に「社会的に弱い立場にある人々(socially vulnerable)」が不当に扱われてきた歴史も存在します。本稿では,ヒトを対象とした研究における研究倫理の中心的概念である「インフォームド・コンセント(informed consent:IC)」の重要性について,歴史的背景から最新の課題まで幅広く解説します。
被験者の尊厳と権利を守る
ICとは,「十分な説明に基づく同意」を意味します。これは,研究に参加する人(以下,被験者)が研究の目的,方法,予想されるリスクと利益,そして自身の権利について十分に理解し,自主的に参加を決定するプロセスです。
例えば,新薬の臨床試験において,被験者は医師から投薬に伴う安全性(副作用)や有効性(薬の効果)について詳細な説明を受けます。重要なのは,被験者がこの説明を一方的に聞くだけでなく,疑問や不安を自由に表明し,それに対して丁寧な回答が得られることです。また,研究者は試験開始前にICを取得しますが,試験の進行に伴い新たな情報が得られた場合,それを速やかに被験者に伝え,継続参加の意思を確認しなければなりません。また,社会的に弱い立場にある人々が被験者になる場合は,より積極的な支援が必要となります。このプロセスは,被験者の尊厳や権利を守ることにつながるのです。
ここで注意すべきは,例えば認知症の治療薬の臨床試験において,十分な同意能力を持たないからという理由で認知症患者を研究から除外すると,研究の信頼性が低下する可能性があるという点です。この場合,認知症患者を研究から除外するには科学的・倫理的に正当な理由が求められます。ICは,多様な人々に適切に研究へ参加してもらうための大切なステップであると同時に,研究結果の信頼性を高めるためにも必要なプロセスなのです。
被験者保護の歴史とICの確立
ICの重要性が認識されるようになった背景には,過去の倫理的に問題のある研究の存在があります。
第二次世界大戦中,ナチス・ドイツが強制収容所に収容されたユダヤ人を対象に行った非人道的な人体実験は,医学研究における倫理性の欠如を示す代表例として広く知られています。これらの痛ましい歴史は,被験者の権利保護の必要性を強く示しています。
これらの反省から1947年に「ニュルンベルク綱領」が策定され,被験者の自発的な同意の必要性が国際的に明文化されました。さらに,1964年には世界医師会によって「ヘルシンキ宣言」が採択され,医学研究における倫理指針が国際的に確立されました。この宣言はその後も改訂が重ねられ(最新版は2013年),現在も医学研究における倫理原則を示した基本文書として重要な役割を果たしています。
また,1932~72年にかけてアメリカ政府が主導した「タスキギー梅毒研究」も,重大な倫理違反として知られています。この研究では,アフリカ系アメリカ人男性を対象に梅毒の自然経過が観察されましたが,被験者には研究の目的や自身が梅毒に感染していることすら知らされませんでした。さらに,抗菌薬(ペニシリン)により治療が可能になった後も,研究のために適切な治療は提供されませんでした。この研究は,当時,全米で広がっていた人種差別反対運動とも相まって,生物医学研究における被験者保護と倫理原則の必要性が強く認識される契機となりました。
倫理原則との関係性
ICは,「自律性の尊重(respect for autonomy)」「善行(beneficence)」「無危害(non-maleficence)」「正義(justice)」という「医療倫理の四原則」のうち,直接的には自律性の尊重に依拠しています。しかし,善行,無危害,正義との関係性にも積...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。