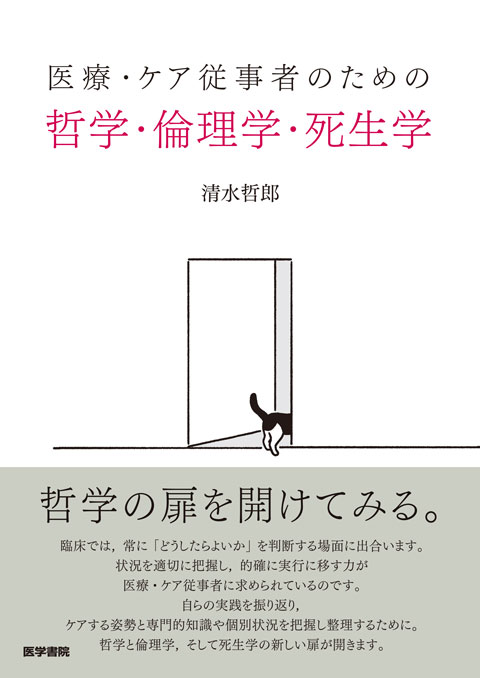応用倫理学入門
[第5回] 生殖医療の倫理(2)――先端技術が拓く生殖の未来
連載 澤井努
2024.12.10 医学界新聞:第3568号より
近年,生殖医療を巡る倫理的議論の中心には,iPS細胞(人工多能性幹細胞)などを用いた体外配偶子形成(in vitro gametogenesis:IVG),ゲノム編集による胚(受精卵)の遺伝子操作,人工子宮の技術があります。これらの技術は,不妊治療を含む生殖医療の可能性を飛躍的に拡大させる一方で,「家族とは何か」「親子のつながりはどのような意味を持つのか」という根本的な問いを私たちに投げかけています。
こうした先端技術を用いた生殖は,現在,多くの国で法的に認められていません。しかし,これらの技術が実現・普及した未来では,深刻な倫理的課題が生じる可能性があります。今回は,これらの技術がもたらす潜在的な影響と課題を取り上げ,私たちがそれらにどう向き合うべきかを論じていきます。
誰もが子どもを持てる未来
2006年にマウス,2007年にヒトで,iPS細胞が開発されました。この細胞は,皮膚や血液などの体細胞に特定の遺伝子を導入して胚のような初期状態に戻したもので,体内のあらゆる細胞へ分化する能力を持っています。そのため,生殖細胞(精子・卵子)を直接作り出すことも理論的に可能であり,2010年代にはIVG技術を用いてマウスで個体を生み出すことに成功しました。
将来,IVG技術がヒトに応用されるとすれば,現在不妊に苦しむカップルに新たな選択肢を提供する画期的な技術となるでしょう。しかし,その実用化に向けては慎重な検討が必要です。特に,安全性の問題は軽視できません。例えば,IVG技術で作られた生殖細胞から生まれたマウスでは,一部の細胞に異常が見られたことが報告されています。これらの異常は健康に悪影響を及ぼす可能性があり,ヒトへの応用を進める上で解決すべき重要な課題です。
さらに,IVG技術の普及は,私たちの家族観や親子関係に根本的な変革をもたらすかもしれません。例えば,若くして卵巣がんを患った女性が, 治療前に保存した体細胞からIVG技術を用いて卵子を作り出し,治療後に子どもを出産するケースが想定されます。また,同性カップルや単身者がこの技術を利用して,遺伝的につながりのある子どもを持つことも考えられます。現在でも人工授精などの技術で同性カップルや単身者が子どもを持つ例は存在するため,生殖や家族形成の場面で科学技術を用いること自体は突飛な発想ではありません。しかし,IVG技術は生殖細胞を「作る」という点でこれまでの技術とは異なるため,社会全体の家族観や生命観に大きな変化をもたらす可能性があります。
遺伝子をデザインする未来
ゲノム編集技術は急速に進展しており,特に2020年にノーベル化学賞を受賞した「CRISPR-Cas9」の登場により,遺伝性疾患の治療や予防が現実のものとなりつつあります。この技術は,特定の遺伝子を正確に修正,削除,挿入することを可能にし,生物学や医学の分野で革命的な変化をもたらしています。
ある遺伝性疾患を持つ夫妻のケースを考えてみましょう。夫妻は,自分たちが抱える疾患が子どもに遺伝する可能性を深く憂慮しています。そのため,ゲノム編集技術を利用して,受精卵の段階で問題となる遺伝子を修正し,子どもが疾患を発症するリスクを低減することを望んでいます。このような利用が実現すれば,ゲノム編集は家族に新たな希望をもたらす有力な手段となるかもしれません。
しかし,この技術の応用は病気の治療にとどまらず,さらなる倫理的課題を生じさせます。例えば,容姿や知能といった非病理的な特性への遺伝的介入が認められるようになれば,それを受けられる人と受けられない人の間で...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。