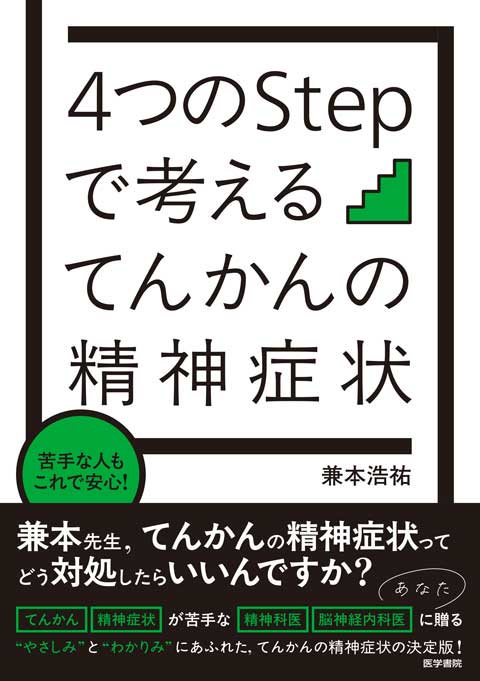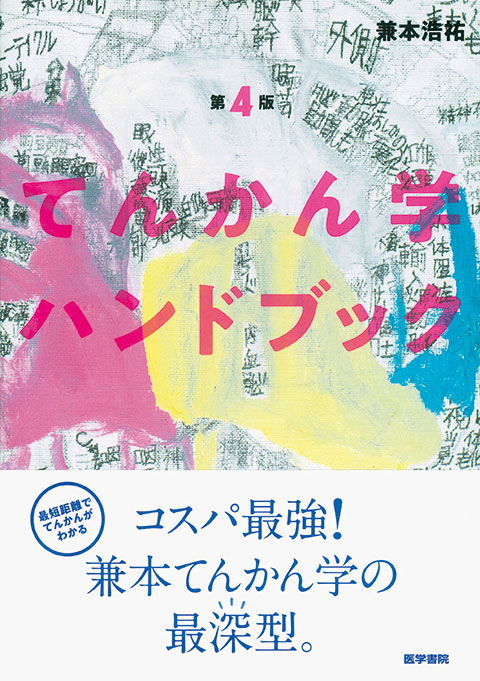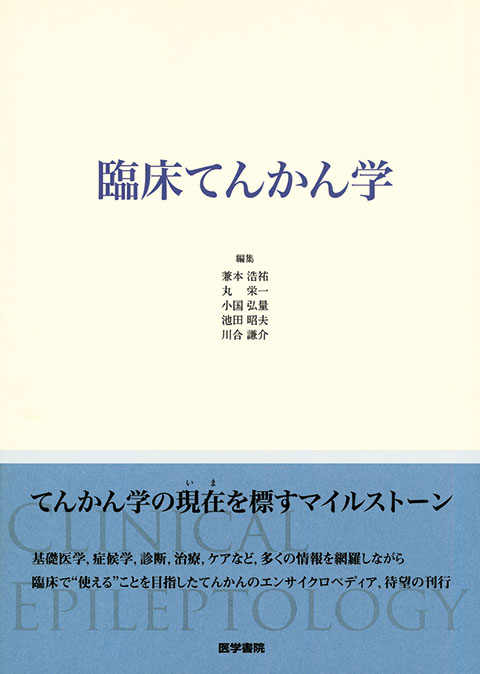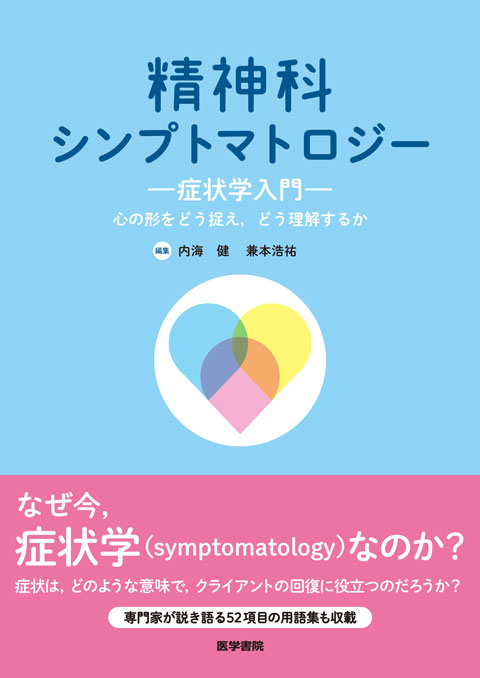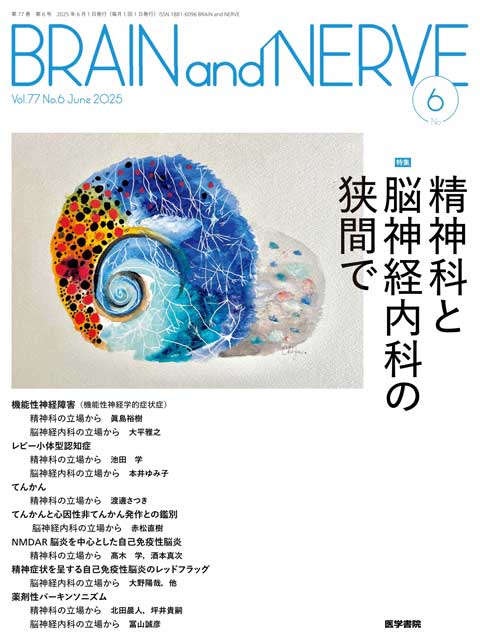- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第4回]精神的問題が心理社会的変化に起因する場合
医学界新聞プラス
[第4回]精神的問題が心理社会的変化に起因する場合
『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』より
連載 兼本 浩祐
2025.08.27
苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状
てんかんのケアに携わっているものの,てんかんに伴う精神科的問題の対応に困っている脳神経内科・脳神経外科の先生方,そして,てんかんに伴う精神科的なケアを頼まれているけれども,てんかんのことがわからな くて困っている精神科の先生方に向けて執筆された書籍『苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状』。
「医学界新聞プラス」では,本書の核となるてんかん診療に重要な4Stepの紹介とともに,具体的に4Stepをどう診療に生かしていくかを,全5回にわたってお届けします。
本節では,てんかんがもたらす心理社会的変化の結果として生じる代表的な3つの問題を示します。すなわち, 不当な扱いによるスティグマ(enacted stigma)から生じる社会的孤立, 予期によるスティグマ(felt stigma)から生じる心理的引きこもりあるいは精神症状の惹起,児童から成人への移行期における逸脱行為,についてです。
A 不当な扱いによるスティグマ
不当な扱いによるスティグマは地理的,世代的な条件により内容が異なり,それにさらされることで生活の質や自尊心を低下させます158)。おおよそ30年前ですが,次のような事例が日本でも実際にありました。
Case 30
初診時30歳前後の青年。起床時に両肩に発作性のけいれんが起こるようになったのは中学生の頃であったが,本人は学校生活が楽しく,地区大会で優勝するなどテニスに打ち込んでいたため,まったく気にしていなかった。最初の強直間代発作は17歳のときに学校で起こり,それが彼の人生を変えた。両親は彼の将来を悲観し,家族に「てんかん持ち」がいることを恥じ,青年の外出を禁じた。この青年は高校を中退し,家に引きこもることを余儀なくされた。彼は10年以上もほぼ自宅軟禁の状態で,毎週のように ,起床時には強直間代発作を起こしていた。
私たちが行った市民向けの講演会の新聞広告が,たまたま親戚の家に滞在していた両親の目にとまり,聴講することになった。講演後の個別相談で,息子のてんかんが若年ミオクロニーてんかんである可能性が高いこと,大抵はバルプロ酸という薬剤で容易にコントロール可能であり,知的障害に至ることはないと知って両親は驚愕した。住んでいるところが当院から遠く離れていたので,入院してバルプロ酸を開始すると,青年の発作はたちまち消失した。
青年は,長い間社会から隔離されていたため,入院当初は人見知りで,引っ込み思案であった。しかし,2~3ヵ月の入院で,他のてんかんを持つ同輩と共同生活を送り,比較的速やかに持ち前の社交性を取り戻していった。それから2年後,彼は高校を通信講座で卒業し,大検を受けて大学に進学し,現在は福祉関係の仕事をしている。
B 予期によるスティグマ
不当な扱いによるスティグマと予期によるスティグマは不可分に結びついています。実際の不当な扱いによる目に見えるスティグマだけがスティグマなのではなく,不当な扱いを受けるのではないかという恐れによって生ずるスティグマもあり,少なからず,スティグマの問題を意識して考えたことがない人には気づかれにくいと報告されています157)。表面的には自分には心理社会的な問題はないかのように気丈に振る舞っていても,内心では深く傷つき,自分がてんかんを持っていることを暴露されることを恐れている人たちもいます60)。その結果,目に見える精神症状が出てしまう人もいますが,目に見える症状をきたすことなく1人で葛藤している人もいます。Case 31は,全身の強直間代発作の後,深刻な 社交恐怖症に陥った人です。対照的に,Case 32は,DSMのような精神症状のカタログに載っている診断には当てはまりませんが,根深い葛藤に苦しんでいた人の例です。Case 33は,予期によるスティグマが症状の過剰な評価につながり,それが医師による過剰な治療を引き起こす悪循環をきたした例です。
Case 31
成績優秀で将来有望な大学院生が,24歳のときに強直間代発作を起こした。当時,一流企業での研究職への就職がすでに決まっていた。2回目の強直間代発作後,この若者は当科に紹介され,脳波で3~4 c/sの全般性棘徐波を示す特発性全般てんかんと診断された。バルプロ酸が1日600 mg処方され,発作はいったん止まり,翌年,企業の研究者としての新たな生活が始まった。しかし不運なことに,おそらくは睡眠不足と激務のため,3回目の発作が職場で起こった。会社はきわめて協力的で発作があっても受傷しないように職場環境を整備することを約束してくれたが,また発作が人前で起こってしまうのではないかという不安から,この男性は職場に行けなくなってしまった。
バルプロ酸の血中濃度が治療域の下限(55μg/mL)であったため,1日量を800 mgに増量したところ,血中濃度は80μg/mLとなった。しかし,彼はまた職場で発作が起こるのではないかという強い不安感に耐えられず,職場に復帰することができなかった。家族やよく知っている人以外とは交流ができなくなり,最終的には解雇されるに至った。SSRIを含む投薬はまったく無効であった。買い物や祖父母を訪ねるための小旅行,通院などの日常的な雑事を行うのはまったく問題はないが,家族以外との交流はない。25歳の3回目の発作以降,発作の再来はない。
Case 32 119)
20代後半の女性。両親と10代の妹との4人暮らし。中学生のときに強直間代発作が出現し,1ヵ月後には短時間の意識消失発作も出現した。若年欠神てんかんと診断され,バルプロ酸とエトスクシミドが開始された。その後,2年間発作のない状態が続いたが,本例に関わった臨床心理士を初めて受診する1年前に服薬を中止したため,1年ぶりに強直間代発作が再発した。
他の人からみれば,この女性は特に目立ったところなく周囲の環境にうまく適応していた。登校拒否もなく,親しい友人もいて,典型的なティーンエイジャーとこれといって変わったところはなかった。てんかんを持つ人のためにルーチンで行われていた臨床心理士による面接でも,当初,彼女は学校や家庭での問題を否定していた。しかし,何度か面接を繰り返すうちに,次第に悩みを打ち明けるようになった。「私がてんかんを持っていることが家族の負担になっていることは分かっています。そのことにいつも罪悪感があります。てんかんのせいで,友達と自由に外出できない。それはすごく嫌だけど,迷惑も掛けていると思うから,ぐっと飲みこんで家族に本当に言いたいことが言えない。なぜ,てんかん発作が誰か他の人ではなく,妹でもなく,自分に起こったのか納得ができない。もちろん,妹が何か悪いわけじゃないのは分かっています。でも本音を言ってしまうと,そんなことを思っても仕方がないのは分かっているけど,自分がてんかんとともに生きなければならないのは,とても不公平だと感じています。」
高校卒業後の就職では,教師や両親はてんかんのことは言わないほうがよいと強く勧めた。彼女は,この病気はやっぱり隠しておかなければいけない恥ずかしいものだと一層思うようになった。間の悪いことに,たまたまその頃,妹の前で強直間代発作が起こった。両親は娘を傷つけまいと発作については何も触れず,何事もなかったかのように振る舞おうとして,妹にもほとんど何も説明しなかった。何の説明もないまま,発作時の歪んだ顔と恐ろしい叫び声を目の当たりにした妹は,姉に「何だったの,あれ,気味悪いんだけど」と言ってしまった。女性は深く傷つき,てんかんは家族にも見せてはならない恥ずかしいものだという思いをますます強くした。
結局,てんかんのことを隠して,この女性は就労することになった。仕事そのものは大変気に入っていたが,てんかん発作が起こり,自分の恐ろしい秘密が暴露され,破局が訪れるのではないかという思いは彼女にいつも付きまとっていた。家族にもそんなそぶりは見せなかったが,彼女はいつもびくびくしながら過ごしていた。
就職して1年後,恐れていた強直間代発作が間の悪いことに職場で再発した。しかし,驚いたことに,彼女が恐れていたようなことは何も起こらなかった。彼女は解雇もされず,職場の人たちの彼女に対する態度も変わらず,しかも,しばらくすると,彼女は昇進し,いくつかの仕事ではリーダーを任され,信頼できる同僚として扱われていることを実感できるようになった。次第に彼女は自信を持つようになり,てんかんは他の病気と同じただの病気なんだと思えるようになっていった。「本当の自分を隠さなければ,友人,知人,同僚,家族とも関係がだめになるとずっと感じていました。長い間,自分の秘密を周囲に知られないように仮面をかぶることに慣れすぎて,仮面と素顔の違いが自分でも分からなくなっていました。素顔の自分をどうやって出していけばいいのか,練習中なんです。」
C 予期によるスティグマと関連する過剰診療
Case 31は,不安が心理社会的な問題だということを当事者も医療側も理解していたのに,それが解消できなかった事例でした。一方で,予期によるスティグマが原因であるのに,当事者も医療側もてんかんの治療が不十分なために問題が起こっているのではないかと誤認し,過剰な医療的介入によってその問題を解決しようとして,悪循環に陥ってしまう事例があります。
Case 33は,英語版には掲載していなかったモデル事例ですが,頻度もそれほど低くなく,また,介入によって問題が解決する場合があるので日本語版に追加しておくことにしました。
Case 33
30歳男性。1~2年前から,数秒~十数秒の耳鳴りが時々起こるのに気づいていたが,あまり気にとめていなかった。当科初診の4年前に耳鳴りがしてから強直間代発作が起こり,このため総合病院の脳神経内科を受診した。MRI上も脳波上も特に所見はなかったが,レベチラセタム1,000 mgの投与が開始された。しかし,2ヵ月後に同様の強直間代発作が出現。さらに立て続けに1週間の間隔を空けて3回目が出現したため,レベチラセタムは2,000 mgに増量となった。以降,当科受診まで強直間代発作は出現していない。しかし,耳鳴りの前兆は,数ヵ月に1度出現し,また,起こり始めると1日に何回か群発することもあった。耳鳴りが起こるたびに,また発作になるのではないかという強い不安感が起こり,どうして良くならないのかと担当医にきつい口調で詰め寄るため,ラコサミド,トピラマート,ペランパネルなどが試されたが,いずれも初期用量の投与でかえって耳鳴りが増えた気がするという訴えのため中止になっている。レベチラセタムを3,000 mgまで増量したが,耳鳴りはそれ以上にはまったく改善せず,定期受診以外の受診回数も次第に増え,「てんかんを良くしてほしい」と強く主張する一方で新たな投薬の試みには抵抗するため,困り果てた主治医が当科に紹介した。紹介状にはASD傾向もあるのではないかと書かれていた。ここ3週間ほどは,気分が優れず,不眠気味で,それによって発作が誘発されるのではないかとの心配もあり,休職した状態での来院であった。
訴えを詳細に聞くと,「てんかんを良くしてほしい」という訴えが具体的には,次のことであるのが分かった。耳鳴りがけいれんを伴う意識消失発作の再発につながり,人前でまたけいれんするのではないかという連想からくる強い不安があること。さらに2年前から許可されている自動車の運転が,発作が起こってまた制限されるのではないかという現実的な不安を抱えていること。そして,このようなさまざまな不安がないまぜになり,ともかくどうにかして耳鳴りを止めてもらえれば,そうした不安が解消されるのではないかと思っていること。
本人に,4年間も前兆だけでけいれんして意識がなくなる発作が出ていないということは,きちんと服薬し,徹夜のような極端な行動をしなければ,よほどのことがなければ強直間代発作は再発しないことを説明し,数ヵ月に1度の耳鳴りに本当に困っていますか,耳鳴りがあるとけいれんする発作がまた起こってしまうのが怖いだけではないですかと尋ね,そのことに注意を促した。すると,彼は自分が耳鳴りそのものには特段困っていないこと,苦痛なのは大きな発作につながるのではないかという不安なのだということに思い至り,4年間大丈夫であったということはそう簡単に大きな発作は起こらないという説明に随分安心したようで,来週から職場復帰の診断書を書いてほしいと言われ,そのように手配した。
以降,耳鳴りは起こっているものの,特に問題なく勤務を続けられている。なお,本人と話し合い,万一,強直間代発作が再燃した場合,再び不安感が強くなるだろうという予想からその可能性をできるだけ減らすために,レベチラセタム2,000 mgに加えてラコサミド200 mgを1日量として追加している。耳鳴りの頻度は以前と比べさらに減っており,1年に2回程度となっている。
当事者が,前兆体験に苦痛を訴える場合,前兆体験そのものが苦痛なのか,そうではなくて,前兆体験が大きな発作につながるのではないかという予期による不安なのかを区別しておくことが必要です。この事例では大きな発作が出現するまでは,前兆体験は今より頻度が高かったにもかかわらず,ほとんど気にもなっていなかったことから,明らかに予期によるスティグマが,休職に至るほどの精神科的な不調の原因になっていると判断した事例です。
心理社会的な問題が医学的介入によって解決できない場合,当事者の心理的な特性に原因を求めるのは,脳神経内科の立場からは可能な限り避けておいたほうが無難だと思われます。予期によるスティグマは,その状況に置かれればどんな人でも起こりうる心理的反応だからです。
たとえばこの事例では,脳神経内科医として,意識がなくなる発作は出ない可能性が高いと判断できるのであれば,それを保証し,「前兆は止まらないかもしれないが,大きな発作は出ない」という前向きなメッセージを伝えることが何よりも肝要なことでした。残念ながら,てんかんに詳しくない一般的な精神科医には脳神経内科医の代わりにそれを行うことはできません。こうした事例は,精神科的な問題が主戦場の事例ではあるのですが,てんかんに詳しい医師にしか解決のできない事例でもあるのです。
文献
60)D’Souza C. “Out of the shadows”:the patient’s view. Epilepsia 2002;43 Suppl 6:18-19
119)岩佐博人,保阪玲子,兼子 直.てんかんに併存する精神症状とその対応─精神医学的視点を含む診療構造の提言.Brain Nerve 2018;70:1005-1016.
157)Kim MK, Kwon OY, Cho YW, et al. Marital status of people with epilepsy in Korea. Seizure 2010;19:573-579
158)Kirabira J, Forry JB, Kinengyere AA, et al. A systematic review protocol of stigma among children and adolescents with epilepsy. Syst Rev 2019;8:21
doi: 10. 1186/s13643-019-0940-9
不当な扱いによるスティグマと予期によるスティグマ:不当な扱いによるスティグマ(enacted stigma)とは,スティグマとなる属性を持つ人に対して実際に行われた差別のエピソードを指す。予期によるスティグマ(felt stigma)とは,差別や不利な扱いを自分がされるのではないかと予期,予想することで生ずる心理社会的な影響を指す。つまり後者は,差別される特徴を自分が持っていることへの羞恥心や,差別に遭遇するのではないかという恐怖心を指す。
Goffman E:Stigma:Notes on the Management of Spoiled Identity. Penguin, 1990
Scambler G(2004)[doi:10.1057/palgrave.sth.8700012]
社交恐怖症:知人と交わらなければならないという状況において特異的に生ずる恐怖や不安が病的なほど極端な状態。社交をしなければならない状況に直面した場合は,それを避けるか,苦痛に耐えて参加するかのいずれかになる。診断をするには,本人が感じている恐怖や不安は実際の状況とは著しく不釣り合いで,対人関係や職業など,複数の領域にわたって社会的機能が実質的に損なわれている必要がある。発症はほとんどが青年期であるが,それ以降に特定の出来事が引き金となって突然発症することもある。てんかん患者では,発作が人目にさらされたり,発作によって嫌がられたりすることへの不釣り合いな恐怖が特徴的である。
Rai D, et al(2012)[PMID:22578079]
苦手な人もこれで安心! 4つのStepで考える てんかんの精神症状
兼本先生、てんかんの精神症状ってどう対処したらいいんですか?
「てんかんの精神症状」、モヤモヤしたままにしていませんか? 4つのStepで、てんかんの精神症状をやさしく、わかりやすく解説! さらに著者の豊富な経験に基づく52のCaseを1つ1つ理解することで、これまで見えなかった患者さんの状況がグッとクリアに。「精神症状はよくわからない」とお悩みの脳神経内科の先生も、「てんかんは苦手」とお困りの精神科の先生も、この一冊で診療の幅がきっと広がります。
本書は、2023年7月にKindle Direct Publishingで自己出版された“Coping with PSYCHIATRIC ISSUES in Patients with Epilepsy”を著者自ら翻訳し、加筆修正を行った日本語版です。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。