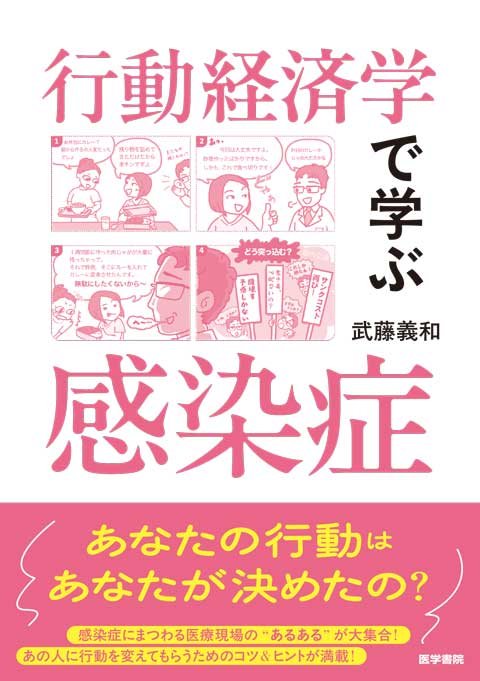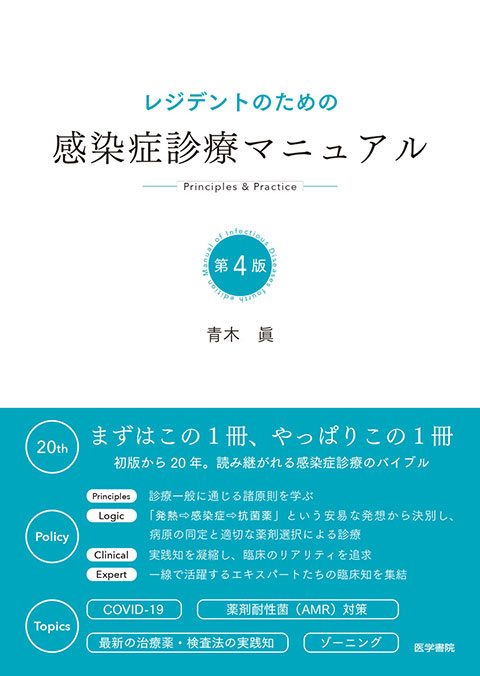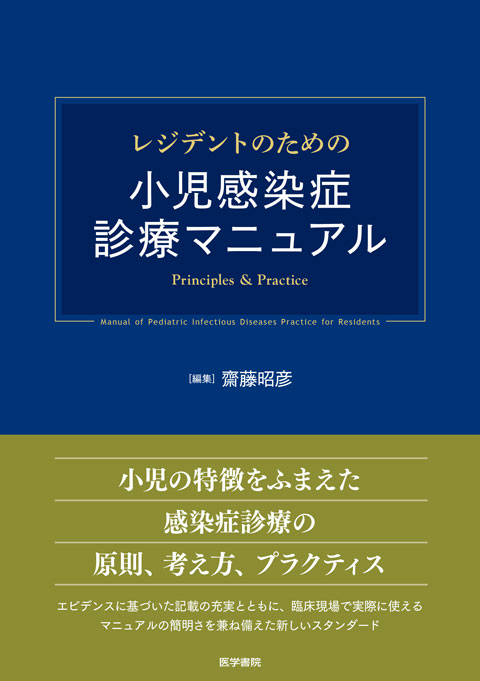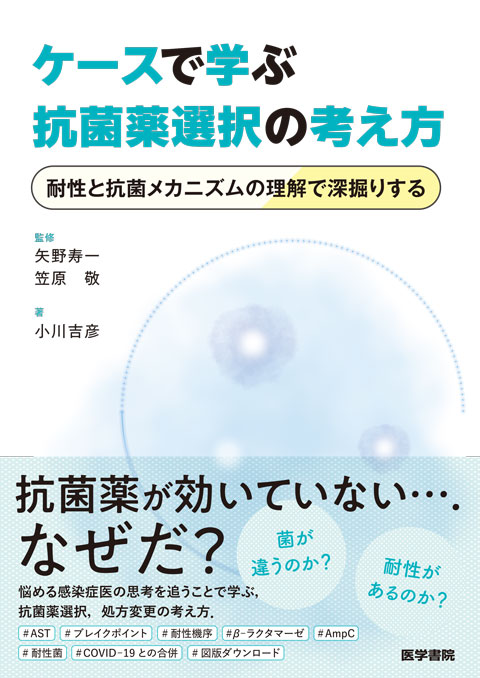- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第3回]人間ってこういうものだよね――プロスペクト理論 その3
医学界新聞プラス
[第3回]人間ってこういうものだよね――プロスペクト理論 その3
『行動経済学で学ぶ感染症』より
連載 武藤義和
2025.10.17
行動経済学で学ぶ感染症
「業種や業務はまったく違えども,人の考え方や行動には一定のパターンがあるなぁ」。東海地方にて新型コロナウイルス感染症診療の中核を担った公立陶生病院で感染症内科の主任部長を務める武藤義和氏は,このたび上梓した書籍『行動経済学で学ぶ感染症』の序文でこう語り,人が行動を選択する際の心理を研究する行動経済学に関心を寄せたきっかけに触れている。行動経済学と感染症診療の親和性を軸に書き下ろされた本書の一部を,医学界新聞プラスでお届けします。
(その2へもどる)
人は思い込む。それをバイアスという
プロスペクト理論でいうところの,「得するよりも損したくない」「確率が低いものは過大評価しがち」ということで人間の「そんな気がする」というのは全然当てにならないものです。そうすると,「アタクシの直感って正しいの」とか,「心の声に従う」とかはあまりに曖昧であることを理解する必要があります。数少ない成功したことはよく覚えているけど,多くの失敗は覚えていないから成功を過大評価しているんですよね。まさに「確率加重関数」ですね。
もちろん,往々にして「自分の経験則からだいたいそういうことが多い」ということは,いっぱいあります。スタバではMacBookの人が多いとか,大阪のおばちゃんは飴玉を持っているとか。ですが100%というわけでもないし,その度も時代や国によってまったく異なります。にもかかわらず,勝手に「そういうものだ」と決めつけてしまって思い込む,これがバイアス(偏見,先入観)です。おそらく,有史以前から生き残るために必要だった生活の知恵や経験則が遺伝子レベルでずっと残っているのかもしれません。まず知ってほしいのは「人間ってこういう生き物」なんです。
医療の現場はバイアスと不合理だらけ
人間はそもそも合理的に行動できないし,感情に動かされる。ダイエットも禁煙も学校の宿題も,「やらなきゃいけない」と思っても結局続かない。
結核の治療は,一般的に6か月間治療薬を内服します。患者さんからすれば治療しなければ死んでしまうはずだし薬を飲むだけでいいのに,多くの場合それを完遂できずに失敗していました。そこで「そもそも人間は継続なんかできないんだから直接観察するしかない」として,保健師や看護師・薬剤師などの協力のもとで,飲んでいるところをきちんと確認するDOTS(直接服薬確認療法)が導入されました。その結果,インドだけで約800万人の命を救い1),世界では3,600万人の治療ができたといわれています。
その点,細菌やウイルスなどの感染症はどうでしょう。自分の仲間がどれだけ減らされていっても,どれだけ感染対策をされても「ただ人から人へ感染させて自分の種を残すこと」に命をかけて全力を尽くす合理性の塊です。だったら人間もそれに対して全力で弾き返すしかありません。にもかかわらずCOVID-19の流行の時は感染対策や治療に関して,有象無象の方々が「自分の考えた奇をてらった最強のコロナ対策」みたいなことを叫ぶようになりました。こういう風潮に対して筆者はずっと,ウイルスはまっすぐの全力ストレートしか投げてこないのに,人間側がバットをテニスラケットやスリッパや大根にコロコロと変えて空振りするようなものだなぁと思っていました。一般の医療現場でも,菌に対して適切な抗菌薬があるのに「心配だから」と超広域抗菌薬を長期間使用したり,手洗いが必要な現場でも「めんどくさいから」とやらなかったり,エビデンスがあることも「上の先生がやっているから」と違うことをしたりと,バイアスや合理的ではないことだらけです。
感染症と行動経済学
行動経済学はあくまでも経済学分野の学問であり,最近ではNISAや資産運用などの投資における心理状態を言い表すということで,とても人気が出ている領域です。でもこういった人間の考え方や行動は,感染症診療においても非常に重なるものがあり,特に感染症内科として他の方々とディスカッションをする立場からすると,どの本にも書いていないのに(下手したら推奨しないと書いてあるのに),どこの病院でもやっている間違いをしばしば目撃するし,しかもそれが不思議なくらいみんな同じような行動や同じような失敗であることが多いです。さらにいうと,その不合理な選択は「一定の癖や似たようなパターン」があることにも気づくと思います。この「なんでか知らないけど,どの病院でもみんな同じようなことをしちゃってる」が,まさに行動経済学と親和性が高いのです。プロスペクト理論的にいえば,損をしたくないからと正解っぽい選択肢に流れてしまい,結果的に実は損をしていることや,そのことに気づいてすらいないということであり,医療現場という合理的な選択を迫られる環境において,そういったまったく合理的ではない意思決定がなされていることは実はとても多いのかもしれません。
行動経済学を学ぶことで,感染症対策を行う立場の人は「なぜ相手がこういった行動を取ってしまうのか」を理解できるし,そうでない人も「自分が取っている行動は,自分の意志ではなく誰もがなぜか陥るオソマツな間違いだったんだ」に気づけることができるのではないかと思い,本書をしたためました。
刮目せよ
■ 人間は合理的な生き物ではない。合理性は感情によって容易に排除される
■ 人間は勝手に基準を作って,それを参考にして行動をする習性がある
■ 人間は得をするより損をするほうが感情的に振れ幅が大きい
■ 人間は合理的でない選択をする時は,往々にして誰もが同じような選択する
■ そして感染症領域でも同じようなことが毎日起こっている
文献
1) Mandal S, et al:Counting the lives saved by DOTS in India:a model-based approach. BMC Med 15(1):47, 2017. PMID 28253922
行動経済学で学ぶ感染症
あなたの行動はあなたが決めたの? 医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?
あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの? 医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ&ヒントを教えます! 人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。