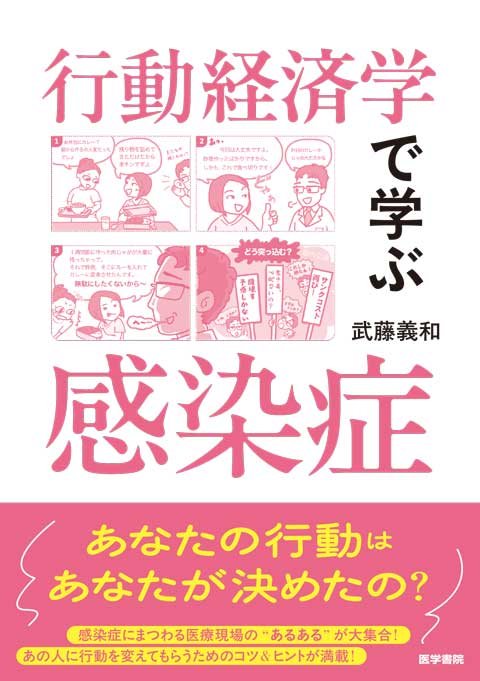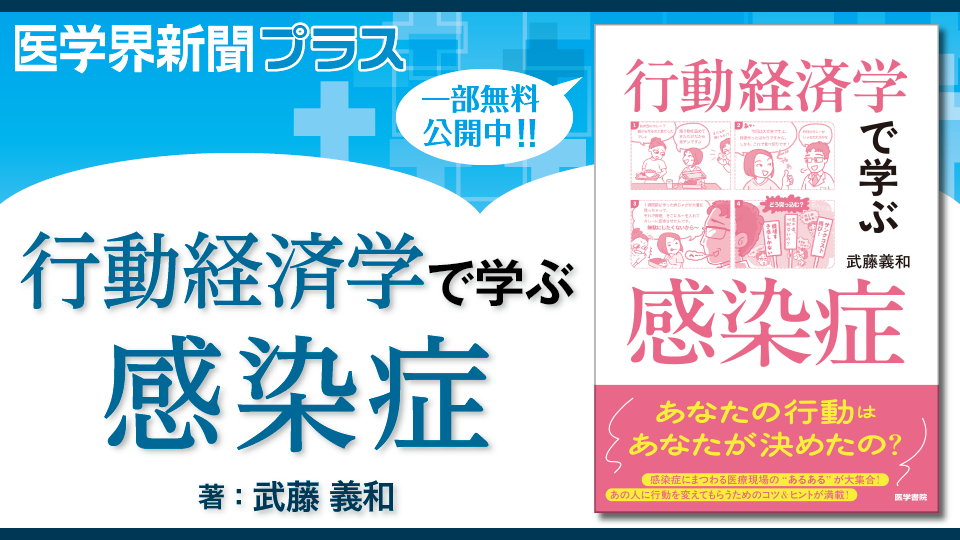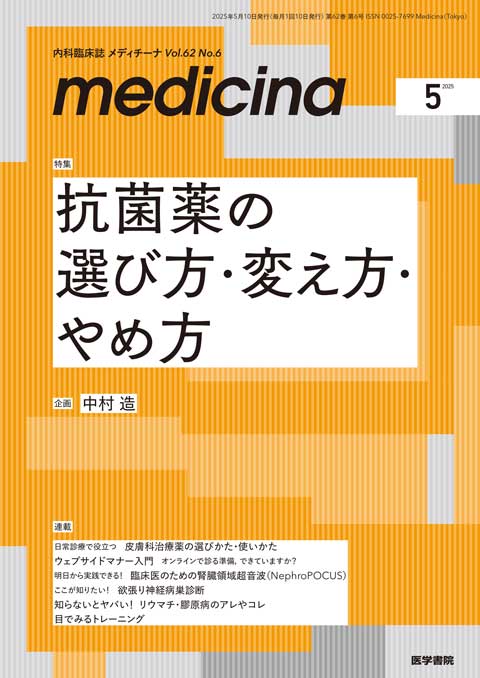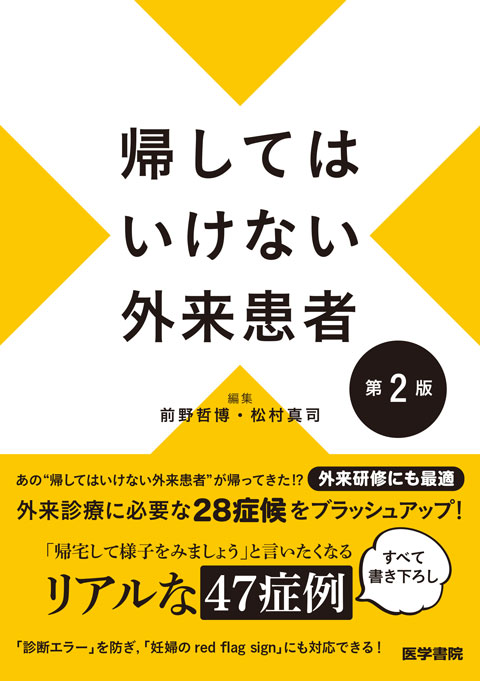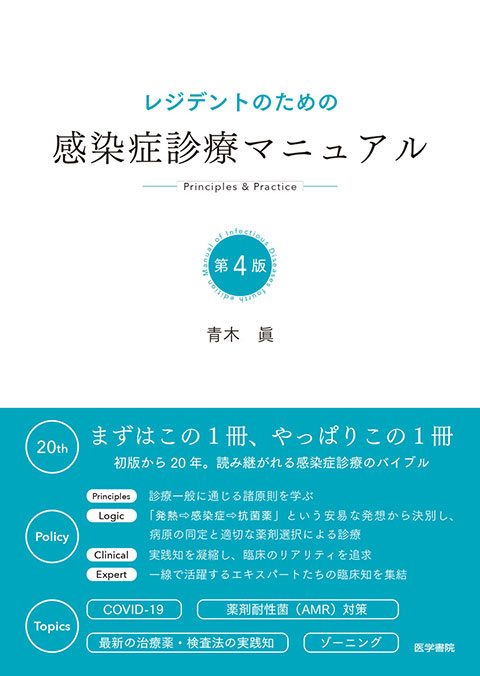行動経済学で学ぶ感染症
あなたの行動はあなたが決めたの? 医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?
もっと見る
あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの? 医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ&ヒントを教えます! 人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症の知識を楽しく学ぶことができます。
| 著 | 武藤 義和 |
|---|---|
| 発行 | 2025年10月判型:A5頁:212 |
| ISBN | 978-4-260-06249-7 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
まえがき
約15年前,当時駆け出しの医師だった筆者は,中小病院での当直勤務をすることがありました。そういった病院には医師の当直室があるのですが,日本全国どこであっても,必ず本棚には『ゴルゴ13』と『週刊少年ジャンプ』と雑誌『プレジデント』があり,机の引き出しにはイヤラシイ雑誌(付属のDVDは何者かにより持ち去りずみ)があったのでした。
『プレジデント』にはビジネスマインドや成功者の哲学,マネジメントのノウハウなどが毎号特集され,時々経済や株の話もあったので,当時若手医師だった筆者はなんとなく当直のたびに読んでおりました。最初は単なる意識高い系のビジネスマンが読む雑誌(失礼!)と思っていたのですが,社会ってこういうふうにできているんだぁ,エラい人ってこういうふうに考えているんだぁと,いつしか定期購読するようになっていました。
そうはいっても,所詮は3~5年目程度の若手医師。マネジメントなんて考える余裕もないし,24時間働けますかの精神で自分のことで精一杯。面白いと思っていても何ができるわけではない,という生活をしていました。しかし,「失敗する時って『プレジデント』に書いてあることとだいたい同じようなパターンだなぁ」とか「こういう勉強の仕方って『プレジデント』に書いてあったなぁ」というように,自分が仕事に慣れていくほどに実体験として先人たちの経験が理解できるようになっていきました。特に時間の使い方や人との関わり方,社会での立ち回り方などはとても勉強になり,いつしか『The New England Journal of Medicine』や『Mandell』の感染症学,『朝倉内科学』や『レジデントノート』より『プレジデント』のほうをよく読んでるじゃん,となっていました(巧妙なステマ!)。
その時代にずっと感じていたのは「業種や業務はまったく違えども,人の考え方や行動には一定のパターンがあるなぁ」ということでした。ああ言えばこう言う,コッチを立てればアッチが立たない,百人一首の決まり字を取るように,自分が出した行動に対して相手がどういう行動で返してくるかって,学校でも社会でもだいたい同じだぞと。
そして2020年,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が始まりました。そこで起きたのは他者否定と他責思考や,誹謗中傷と根拠のないデマなどによる人々の分断であり,ただ基本的な感染対策をするだけでいいのに,何かや誰かを攻撃していないと気がすまないという,みっともない社会でしたね。でも1980年代のHIV,2009年の新型インフルエンザのような世界的なパンデミックが起きた時にも,人類は同じようなことをしていました。人間って,どうせ今回もそういうことをするんだろうなと思っていた筆者は,2020年2月に当院に入院されたある香港の患者さんに「これから社会は分断と誹謗中傷だらけになる。COVID-19の患者さんを否定する人だらけになるから,決してそんな病気ではないということを知らせるために退院の時に素手で握手している写真を撮ろう」とお願いして,一緒に写真を撮ってもらいました(写真)。その後起きたことは,上述のとおり。人間というのは見たいものしか見ない,自分に都合のよいようにしか解釈しない,やっぱりそういう生き物でした。
でも逆にいえば,やってほしいことにつながるような行動をすれば,思ったとおりに動いてもらえる。少しだけ肘で小突いてあげれば,転がる石のように勝手に行動してくれる。人の行動は自分で選んでいるようにみえて実は選ばされている。世の中ってうまいことできているぞ,と感じた時に「行動経済学」と出会いました。
行動経済学は,まさに筆者がずっと考えていたこととまったく一緒。それからというもの,夢中で行動経済学の本や論文を読んでセオリーを勉強し,感染症の領域でとても使えるんじゃないかなと感じておりました。どの地域の病院,どの医師もどの医療者も,誰に習ったわけではないのになんで同じようなことをしているんだろう,どう伝えたら行動変容に結びつくんだろう。こういったことは,行動経済学で多く説明できることだらけだったのです。なので,いつかこれを形にしたいなぁと思っていたら,医学書院さんからお声がかかり,このような形で上梓することができました。
感染症を担当している医療者の皆さんが読めば「あーあるある,ホントそれな!」と思えて,その他の医療者の方が見ても「うわー,言われてみればそうだわー」と思えるような形を目指して執筆しました。行動経済学の視点から感染症を学んでもらい,皆さんの日常の医療で役に立てることができるなら,『プレジデント』をわざわざ定期購読していた甲斐があったというものです。
日本中の感染症診療と感染制御がさらに拡充して,多くの患者さんを救うことができる日を夢見て。
2025年8月
武藤義和
謝辞 本書の執筆にあたり,行動経済学の専門的な点に関して貴重なご助言と校正の労をいただいた大阪大学大学院人間科学研究科 准教授 平井 啓先生に深く感謝申し上げます。
目次
開く
まえがき
登場人物一覧
第0章 感染症と行動経済学
人間ってこういうものだよね──プロスペクト理論
第1章 感染症診療編
その検査,やる必要ありますか?──デュアルプロセス理論
とりあえずカルバペネムで──思考停止とヒューリスティック
手近なところですましちゃう──利用可能性ヒューリスティック
天上天下唯我独尊!──ダニング・クルーガー効果
見えている世界だけがすべてじゃない──確証バイアス
そんなにあっても選べないよ──決定回避の法則
検査陽性が意味することは?──少数・大数の法則
なんかそれっぽい気がするよね──連言錯誤
上の先生がやっているからついつい──バンドワゴン効果
抗菌薬はやめる時のほうが難しい──損失回避バイアスと出口戦略
ここまでやったんだからさ──サンクコスト効果
1回失敗したからって過剰な守りに入るヤツ──羹に懲りて膾を吹く
目は口ほどに物を言わない──フォールス・コンセンサス
clinical courseを制するものはすべてを制する──ラチェット効果
第2章 感染管理編
手指衛生を徹底してもらうには──沈没船のジョーク
誰を基準に考えているの?──フレーミング効果
遠くのバラより近くのタンポポ──ザイオンス効果
コケの一念岩をも通す──ピグマリオン効果
一番いいはずの選択肢が選べない?──囚人のジレンマ
ディープなインパクトを──初頭効果
人のやる気に口を出さない①──アンダーマイニング効果
人のやる気に口を出さない②──エンハンシング効果
その重症は誰が決めたの?──アインシュテルング効果
先送り癖はいいことない──現在バイアス
将来よりも,いまのこと?──時間選好と双曲割引
届け出は出せばいいってもんじゃないよ──クラウディングアウト
あの部長,全然やる気ないよね──ピーターの法則
よそはよそ,うちはうち──アンカリング効果(参照点依存性)
時間もお金もあればあるだけ使っちゃう──パーキンソンの法則
逃げるは恥だし役にも立たない──ハーディング効果
すべてはお釈迦様の手のひらの上──ナッジ理論
COLUMN
もしも未来が見えたなら
私,失敗しまくるので
他人の不幸は蜜の味
こんなはずじゃなかった気がする
イノベーションを起こせ
レモン市場にさせてはいけない
そ,そんなはずはない!
本書に登場する行動経済学(経済学・心理学)用語
索引
書評
開く
マスクも納得も行動経済学で
書評者:忽那 賢志(阪大大学院教授・感染制御学)
武藤義和先生の著作『行動経済学で学ぶ感染症』は,他の診療科から感染症のコンサルテーションを受ける医師や,病院内の感染対策を担当している医療従事者にとって,どうすれば業務を円滑に進めさせることができるのかという日ごろの悩みの大きなヒントとなる作品である。
武藤先生は国立国際医療研究センターで勤務していた際に私の後輩であったわけだが,彼がこのような作品を書き上げるというのはとても意外であった。私の彼のイメージは「『プレジデント』というオッサンが読む雑誌を読んでいる」「マリオカートがめちゃくちゃうまい」「とにかく滑舌が悪い」というもので,当時はこのような作品を作り上げるとは思っていなかった。とはいえ,コロナ禍においては彼は病院内のコロナ診療や感染対策だけでなく,論文の執筆,世間への情報発信など八面六臂の大活躍を見せており,彼の処理能力の高さやコミュニケーション力にうならされていたものである。
しかし,それでも,武藤先生が「行動経済学」の本を書いたというのは本当に驚いた。「なんで武藤先生が行動経済学の本を……?」と。しかし,本書を読み進めるにつれ,行動経済学と感染症の相性の良さを思い知ることとなった。
私自身,感染対策に行動経済学を取り入れたいと考えたことは何度もあった。コロナ禍が5類感染症に移行した直後,社会ではマスク着用が「個人の判断」とされる一方,病院内では依然として高齢者や免疫不全者を守るためマスク着用を求めざるを得ない状況が続いていた。その中で,マスク未着用で来院する患者や家族に職員が注意すると反発を受ける事例が頻発し,対応に苦慮していた。そこで行動経済学の専門家に相談したところ,「病院でマスクを着ける必要はない」として助言を拒まれた。この経験から,行動経済学は有用である一方,感染対策の文脈を欠いたまま用いれば,使い手の価値観に強く左右され得る学問でもあると感じ,距離を置くようになったのであった。
さて,武藤先生の著作を読んでわかったことは,やはり行動経済学は非常に興味深い学問であり,感染症診療・感染対策にかかわる医療従事者にとって重要なツールであるということである。私はつい専門家に頼ってしまったわけだが,自分自身が学んで業務に生かせばよかったのだと思い知った次第である。感染症・感染対策については,おそらく本書の読者にとっては当たり前のことが書かれているのだが,それをいかに現場に浸透させるかということが丁寧に書かれており,それが本書の核心である。「◯◯の法則」がたくさん出てくるので,一度読んだだけではなかなかすぐに応用とはいかなそうではあるが,本書を机に置いて行動経済学的なアプローチを業務に導入することで,今後の仕事が楽しくなることは間違いないだろう。
人の弱さを理解して感染対策に生かす
書評者:坂本 史衣(板橋中央総合病院院長補佐)
「制御のヒエラルキー」をご存じだろうか。感染や災害によって生じるリスクの管理法を,効果の高い順に階層化した考え方である。上位の対策ほど人の意思決定を必要としないため安定して効果を発揮し,下位の対策ほど,その効果が個々人の行動選択に依存しやすい。手指衛生や抗菌薬適正使用のように,ガイドラインで強く推奨される感染対策の多くは,このヒエラルキーの下位に偏っている。これらの「行動依存型対策」は,やってもやらなくても,あるいはやり方が少々おかしくても,直ちに目に見える異変を引き起こすわけではなく,仕事を滞らせることもない。そのため多忙な医療現場では,真っ先に省略されやすい。
それ故に,感染対策チーム(ICT)は,人の行動に関する難題に日々取り組んでいる。
人はなぜ不適切な感染対策を行うのか。
なぜ,一度始めた感染対策を止められないのか。
なぜ,感染対策への意欲を失ってしまうのか。
なぜ,話を聴いてもらえないのか。
本書は,こうした行動の背後に,しばしば人に内在する弱さがあることを,豊富な感染症診療・感染管理の事例を通じて示してくれる。例えば,経験豊富な役職者であっても,自分が正しいと考える情報を選択し(確証バイアス),損失を回避したいがために過剰な対策に走ることがある(プロスペクト理論)。若手もそのやり方に慣れることで思考停止に陥り(ヒューリスティック),他の方法を考えなくなってしまう(アインシュテルング効果)。こうした現象は,本書で紹介されている行動経済学の概念を用いると,ふに落ちる形で理解できる。感染対策チームも,例外ではない。相手も当然理解できるだろうと思い込み,熱心に説明したにもかかわらず,まったく理解されていなかった経験(フォールス・コンセンサス)や,せっかく芽生えた改善への意欲を,報酬を与えることで削いでしまった経験(アンダーマイニング効果)はないだろうか。
注意が必要なのは,こうした視点を得る目的は,相手を自分の思いどおりに操縦するためではないということだ。この点については,本書で繰り返し触れられている。より質の高い医療を提供したいという共通の目的の下,互いを尊重し,双方向のコミュニケーションを通して着地点を探ること――本書は,そのための考え方を示している。
最後に付け加えておくと,本書には随所に「昭和」がちりばめられていて,同世代として非常に楽しめた。著者の部下の皆様には,上司が中森明菜の「DESIRE」を歌うことがあったら,合いの手の「はー,どっこい!」を忘れないでもらいたい。何のことかわからなければ,ぜひ本書を手に取ってほしい。読めば得をする,いや,読まなければ損をする一冊である。
行動経済学で読む感染症医療の書
書評者:矢野 邦夫(浜松医療センター感染症内科)
本書『行動経済学で学ぶ感染症』は,診断・治療・感染管理といった医療現場での意思決定に,人間の非合理性や認知バイアスがどのように影響するのかを,やさしくひもとく一冊です。著者は公立陶生病院感染制御部部長の武藤義和氏で,2025年10月に医学書院から刊行されています。
本書の根底にあるのは,「人は必ずしも合理的に行動できず,感情によって判断を誤ることがある」という行動経済学の基本的な考え方です。医療の現場でも,職種を問わず非合理的な行動は繰り返されます。その背景を読み解く鍵として,行動経済学の理論が応用されています。特に,同じ額の利益よりも損失を2~3倍大きく感じる「プロスペクト理論(損失回避)」は,臨床判断に深くかかわると指摘されています。著者は,医療者が行動の背景を理解し,互いの立場を理解しながらより良い医療を届けてほしいと願っています。
第1章「感染症診療編」では,診断や治療に潜む思考の落とし穴が具体的に描かれています。広域抗菌薬を安易に選ぶ行為は「ヒューリスティック」による短絡的思考の典型であり,投与を始めた抗菌薬をやめられず長期化する現象は「サンクコスト効果」や損失回避バイアスの表れと説明されています。その対策として,抗菌薬を開始する時点で「どの条件で中止するか」をあらかじめ決めておく重要性が説かれます。また,CRP値だけに頼って治療方針を決めるのは「確証バイアス」に陥った例であり,検査値にとらわれず患者の経過を自ら観察する姿勢の大切さが強調されています。
第2章「感染管理編」では,チームや組織の行動変容に焦点が当てられます。手指衛生率を上げるために外的報酬を与えると,かえって内発的な動機づけが弱まり,遵守率が下がる「アンダーマイニング効果」が起こり得ます。一方で,努力や行動そのものを認める「エンハンシング効果」をうまく活用することが有効とされています。さらに,抗菌薬届出制が形骸化し目的を見失う「クラウディングアウト」にも注意を促し,目的と手段を見直すことの重要性を学ぶことができます。
本書は「ある日のこと」という身近なエピソードから始まり,理論やエビデンスを紹介し,最後に「刮目せよ」という言葉で教訓を締めくくります。難しい理論を直感的に理解でき,自分自身の行動を振り返るきっかけを与えてくれる構成です。
医療現場での意思決定は患者の命に直結します。本書は,その判断をより良い方向へ導く「ナッジ」の考え方を身につけられる一冊です。医療のアウトカムは「患者の改善」にあるという原点に立ち返り,自らの行動を見つめ直す大切さを教えてくれます。
感染症診療の質を高めたい医療従事者や,組織の行動変容を促したい管理職の方々に,ぜひ手に取っていただきたい良書です。