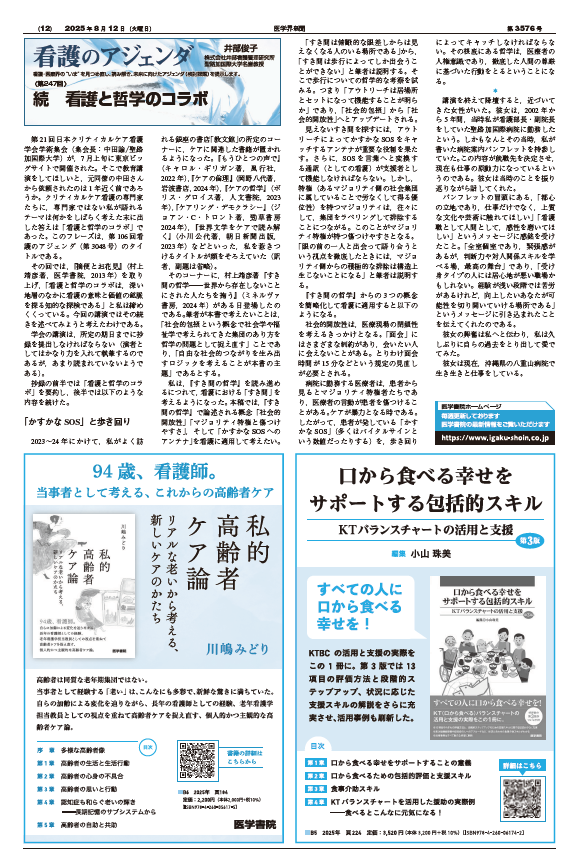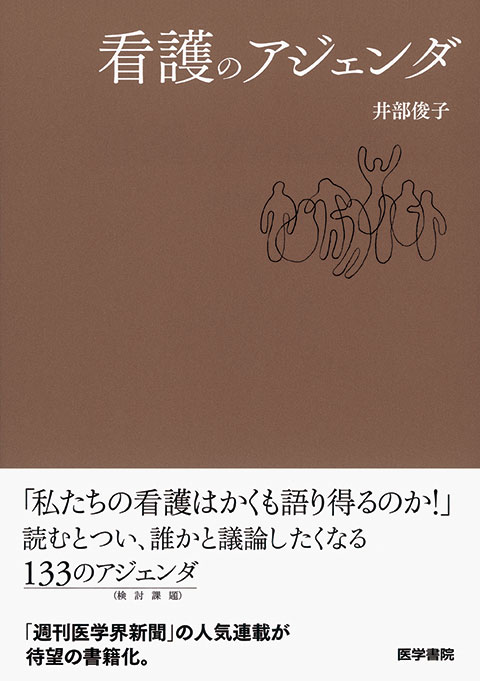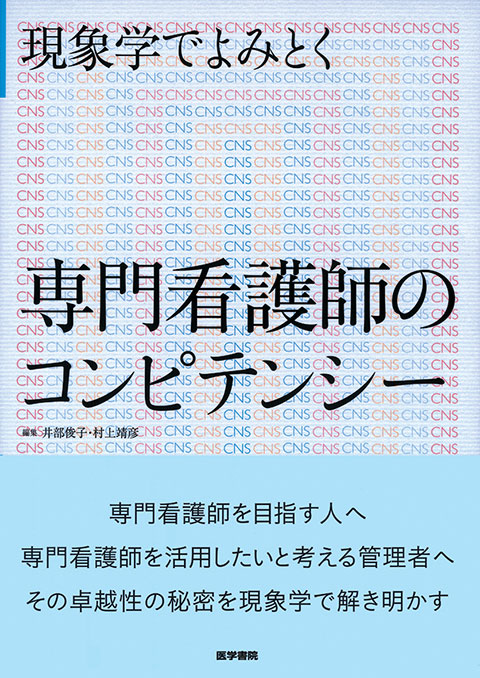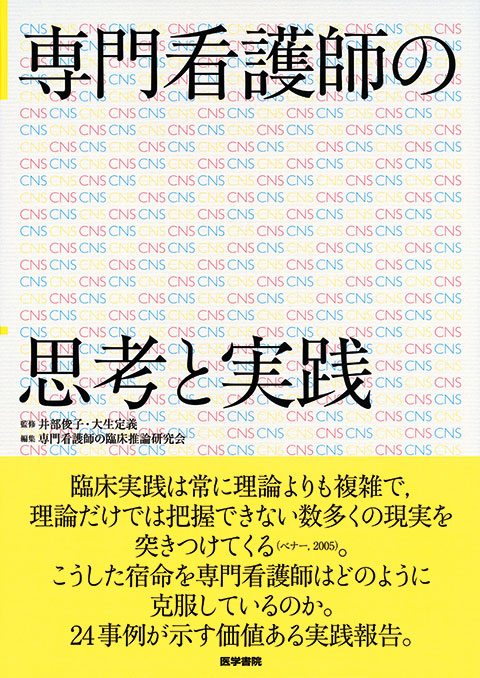看護のアジェンダ
[第247回] 続 看護と哲学のコラボ
連載 井部 俊子
2025.08.12 医学界新聞:第3576号より
第21回日本クリティカルケア看護学会学術集会(集会長:中田諭/聖路加国際大学)が,7月上旬に東京ビッグサイトで開催された。そこで教育講演をしてほしいと,元同僚の中田さんから依頼されたのは1年近く前であろうか。クリティカルケア看護の専門家たちに,専門家ではない私が語れるテーマは何かをしばらく考えた末に出した答えは「看護と哲学のコラボ」であった。このフレーズは,第106回看護のアジェンダ(第3048号)のタイトルである。
その回では,『摘便とお花見』(村上靖彦著,医学書院,2013年)を取り上げ,「看護と哲学のコラボは,深い地層のなかに看護の意味と価値の鉱脈を探る知的な探検である」と私は締めくくっている。今回の講演ではその続きを述べてみようと考えたわけである。
学会の講演は,所定の期日までに抄録を提出しなければならない(演者としてはかなり力を入れて執筆するのであるが,あまり読まれていないようである)。
抄録の前半では「看護と哲学のコラボ」を要約し,後半では以下のような内容を続けた。
「かすかなSOS」と歩き回り
2023~24年にかけて,私がよく訪れる銀座の書店「教文館」の所定のコーナーに,ケアに関連した書籍が置かれるようになった。『もうひとつの声で』(キャロル・ギリガン著,風行社,2022年),『ケアの倫理』(岡野八代著,岩波書店,2024年),『ケアの哲学』(ボリス・グロイス著,人文書院,2023年),『ケアリング・デモクラシー』(ジョアン・C・トロント著,勁草書房2024年),『世界文学をケアで読み解く』(小川公代著,朝日新聞出版,2023年)などといった,私を惹きつけるタイトルが顔をそろえていた(訳者,副題は省略)。
そのコーナーに,村上靖彦著『すき間の哲学――世界から存在しないことにされた人たちを掬う』(ミネルヴァ書房,2024年)がある日登場したのである。筆者が本書で考えたいことは,「社会的包摂という概念で社会学や福祉学で考えられてきた集団のあり方を哲学の問題として捉え直す」ことであり,「自由な社会的つながりを生み出すロジックを考えることが本書の主題」であるとする。
私は,『すき間の哲学』を読み進めるにつれて,看護における「すき間」を考えるようになった。本稿では,『すき間の哲学』で論述される概念「社会的開放性」「マジョリティ特権と傷つけやすさ」,そして「かすかなSOSへのアンテナ」を看護に適用して考えたい。
「すき間は俯瞰的な眼差しからは見えなくなる人のいる場所である」から,「すき間は歩行によってしか出会うことができない」と筆者は説明する。そこで歩行についての哲学的な考察を試みる。つまり「アウトリーチは居場所とセットになって機能することが明らか」であり,「社会的包摂」から「社会的開放性」へとアップデートされる。
見えないすき間を探すには,アウトリーチによってかすかなSOSをキャッチするアンテナが重要な役割を果たす。さらに,SOSを言葉へと変換する通訳(としての看護)が支援者として機能しなければならない。しかし,特権(あるマジョリティ側の社会集団に属していることで労なくして得る優位性)を持つマジョリティは,往々にして,集団をラベリングして排除することにつながる。このことがマジョリティ特権が持つ傷つけやすさとなる。「眼の前の一人と出会って語り合うという視点を徹底したときには,マジョリティ側からの積極的な排除は構造上生じないことになる」と筆者は説明する。
『すき間の哲学』からの3つの概念を簡略化して看護に適用すると以下のようになる。
社会的開放性は,医療現場の閉鎖性を考えるきっかけとなる。「面会」にはさまざまな制約があり,会いたい人に会えないことがある。とりわけ面会時間が15分などという規定の見直しが必要とされる。
病院に勤務する医療者は,患者から見るとマジョリティ特権者たちであり,医療者の言動が患者を傷つけることがある。ケアが暴力となる時である。したがって,患者が発している「かすかなSOS」(多くはバイタルサインという数値だったりする)を,歩き回りによってキャッチしなければならない。その根底にある哲学は,医療者の人権意識であり,徹底した人間の尊厳に基づいた行動をとるということになる。
*
講演を終えて降壇すると,近づいてきた女性がいた。彼女は,2002年から5年間,当時私が看護部長・副院長をしていた聖路加国際病院に勤務したという。しかもなんとその当時,私が書いた病院案内パンフレットを持参していた。この内容が就職先を決定させ,現在も仕事の原動力になっているというのである。彼女は当時のことを振り返りながら話してくれた。
パンフレットの冒頭にある,「都心の立地であり,仕事だけでなく,上質な文化や芸術に触れてほしい」「看護職として人間として,感性を磨いてほしい」というメッセージに感銘を受けたこと。「全室個室であり,緊張感があるが,判断力や対人関係スキルを学べる場,最高の舞台」であり,「受け身タイプの人には居心地が悪い職場かもしれない。経験が浅い段階では苦労があるけれど,向上したいあなたが可能性を切り開いていける場所である」というメッセージに引き込まれたことを伝えてくれたのである。
彼女の興奮は私へと伝わり,私は久しぶりに自らの過去をとり出して愛でてみた。
彼女は現在,沖縄県の八重山病院で生き生きと仕事をしている。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。