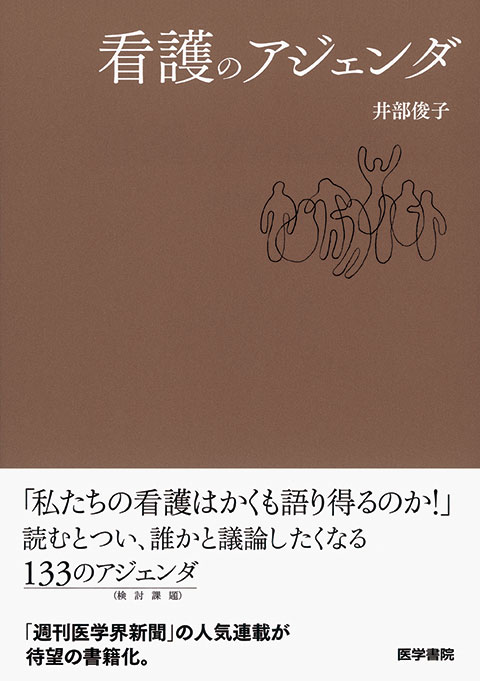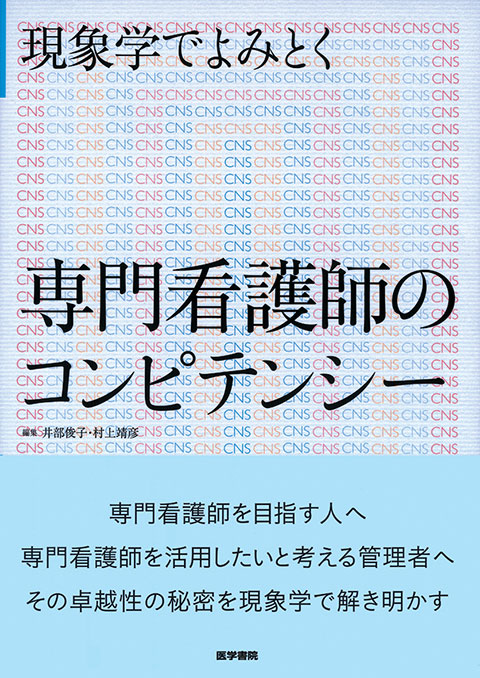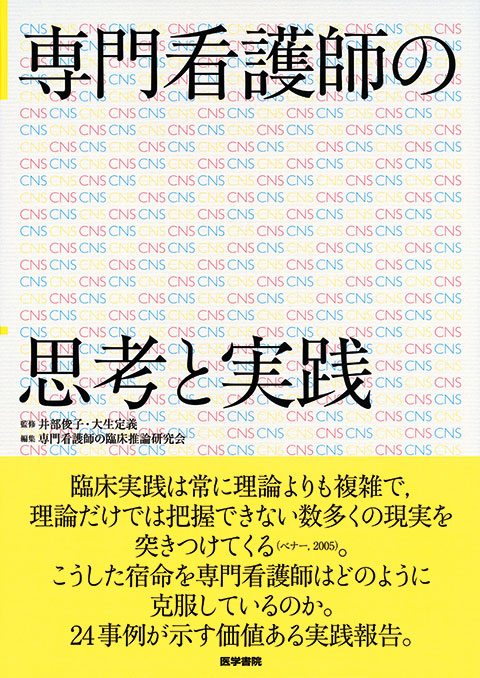看護のアジェンダ
[第248回] 旭川で「看護診断」を考える
連載 井部 俊子
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
2025年8月のはじめ,第31回日本看護診断学会学術大会(大会長=升田由美子/旭川医科大学医学部看護学科)に参加した。別の学会で,「ザ看護過程」を論じるに当たり,「看護診断」の現在地を知っておく必要があることと,私は日本看護診断学会の創設時にかかわっていたし,現在は評議員でもあるのだからと,自分に言い訳をして旭川に赴いた。学会の会期は2日間であったが,仕事の都合で,2日目のみの参加となった。オンラインではなく対面でプログラムが展開されたのも気に入った。
NANDA-International 2024-2026
学術大会のメインテーマ「もっと活かそう! 看護過程・看護診断」について,升田大会長は抄録で次のように述べている。「(前略)看護診断は臨床現場において十分に普及しているとは言いがたいのが現状です。その理由として,“時間がかかる”“実践に直結しない”といった誤解や,“看護診断を使うとアセスメント力が育たないのではないか”という懸念の声が挙げられます。これは,看護診断を単なる分類として形式的に扱うことに起因する課題であり,本来の診断的思考を浮かせば,むしろ深いアセスメントと臨床推論力が養われます」とした上で,「医師が医学診断をするように,看護師が看護診断を行うことが当然となる未来を見据え,私たちはその実践基盤を築いていかねばなりません」と前向きなメッセージを提示している。大会1日目の大会長講演に参加できなかった私は,大会長と意見交換できなかったことを悔やんだ。
抄録を見るに,1日目の特別講演も興味深い内容である。「NANDA-I看護診断分類2024-2026:何がどう変わった?」と題した上鶴重美氏(看護ラボラトリー代表)の講演である。抄録によると,看護診断が前版の267から277に増え,多くの診断名が刷新された。その背景には,①診断名が最新のエビデンスに基づくよう文献が再検討されたこと(例えば〈非効果的コーピング〉は〈コーピング不適応〉に変更された),②診断用語「過剰」「不良」などが多角的に追加され,診断概念が明確化されたこと(〈不安〉は〈不安過剰〉に,〈過体重〉は〈過体重自己管理不良〉に,〈便秘〉と〈下痢〉が〈排便...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。