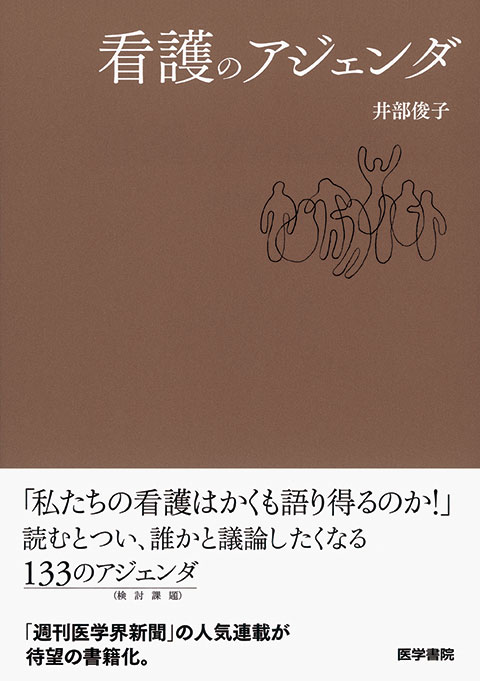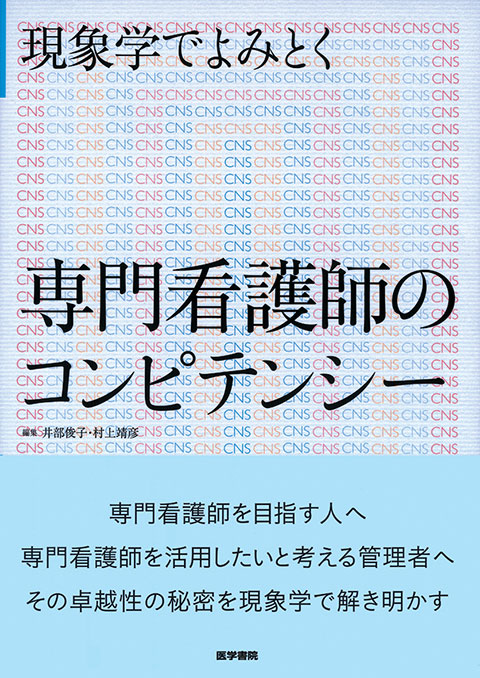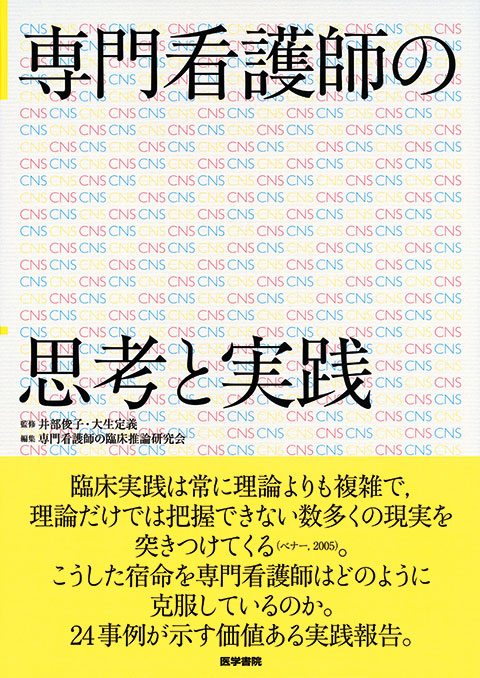看護のアジェンダ
[第243回] 申し送りの価値
連載 井部 俊子
2025.04.08 医学界新聞:第3572号より
このところ,勤務交代時に行う「申し送り」に関心を持っている。電子カルテが一般的となり,「カーデックス」なるものが姿を消した現場の申し送りには,単なる情報伝達のみならず,もっと深い意味があるのではないかと考えるからである。
そこで,まず「申し送り」について言及されている“文献”をひもとくことにした。
申し送りの風景
宮川香子さんが「申し送りの光景」1)と題してつづった,開放病棟で夜勤をされていたときの思い出話である。「朝の申し送りを始めます」と夜勤者から号令がかかると,詰所の小窓やドアが閉められる。これは個人情報が漏れないようにという配慮なのだが,どんな話をしているのか気になる患者がウロウロする姿が“見受けられた”というのである。「聞き耳をたてて,両耳を交互に窓に近づけていたり,しゃがんで小窓をゆっくり少し開けて内容を聞こうとする患者」もいた。それを見つけた看護師が小窓を閉めると,患者はそっと窓を開ける。看護師はそれを見つけて窓を締める“イタチごっこ”が展開されたという。
申し送りのあとに,数人の患者がニコニコしながら看護師に近づいてきて,申し送りのときに髪をずっと触っている看護師,あくびをしている看護師,眉毛がない看護師がいたことを知らせ,こう付け加える。「あのな,看護師は患者をみてると思ってるやろ。オレら患者もよく看護師を観察してるんやで。動物園のオリのなかをみてるのと一緒で,朝の集まりはみてておもろいわ」。宮川さんは,個人情報に配慮した看護師の行為がどこまで患者に理解してもらえているのだろうか,聞こえなかったから(窓を)開けて話をしてほしいという患者にどう対応すべきであったのかと“今さらながら”振り返る。「よかれと思って行っていた配慮に説明不足があり,相手がどんな気持ちになるかの想像力も不足していた」と反省している。
私にも病棟師長(当時,ヘッドナースと称していた)として申し送りをとりしきっていた時期がある。ある朝,5階外科病棟のエレベーターを降りてナースステーションに近づくと,何やらつぶやきが聞こえてくる。カーデックスを開いて準備している夜勤者に,何をしているのかと問うと,申し送りの練習をしているとのこと。ヘッドナース...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。