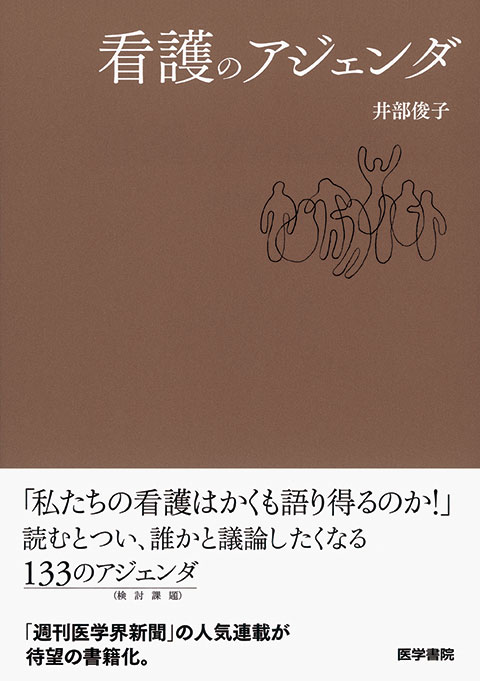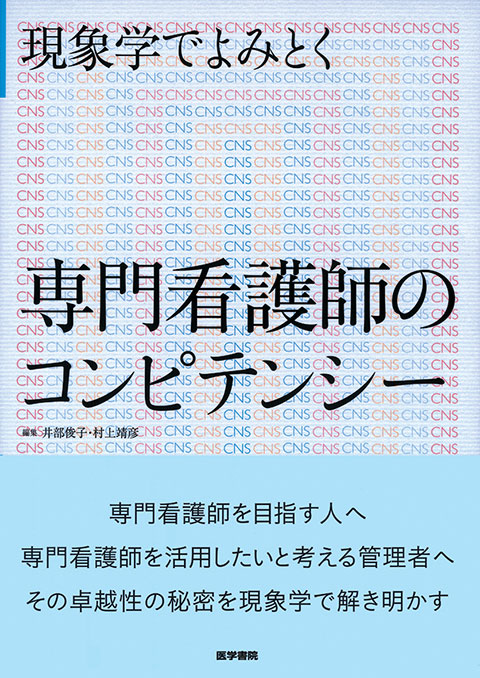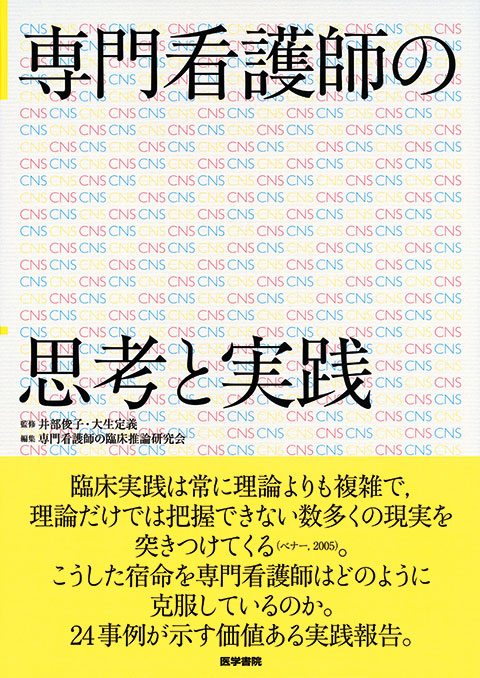看護のアジェンダ
[第242回] 「議事録事件」とやる気
連載 井部 俊子
2025.03.11 医学界新聞:第3571号より
看護管理塾(聖路加国際大学看護リカレント教育部主催,全10回)第9章は,「やる気にさせる職場」が主題でした。担当講師は中尾根功嗣さん(株式会社ファムリッジ代表取締役)。およそ3時間半のセッションです。看護管理塾は,各回の担当講師を決めて,講義とグループワークで進行します。毎回のコンテンツは6人の講師陣で“厳しい”意見交換を行い練られます。2024年度は発足してから11年目を迎え,看護管理の継続研修として一定の役割を果たしてきました。
第9章「やる気にさせる職場」を担当することになった中尾根さんは,「やる気が生まれる要因と失われる要因」として,自分自身の看護管理塾における体験を語りました。いみじくもその体験に,当時,塾長であった私が登場します。私にとっても大変興味深く,貴重な振り返りの機会となりました。そのお裾分けを本稿でいたします。
題して,「議事録事件」です。
「こんなものは議事録と言えない」
2013年,看護管理塾の講師として仲間入りした中尾根さんは最年少でした。会社を起業して1年目。看護管理塾の「仲間に加えてもらう」高揚感があったと言います。看護管理塾チームの一員となった中尾根さんの役割は,会議の議事録をとることでした。
これが大変なことでした。彼の言葉を借りると,「散々な目に遭った」のです。何度も看護管理塾を辞めようと思ったそうです。議事録とは何かがわかっていなかった中尾根さんは,会議で話し合われたことを,自分の記憶を頼りに日記のように書き連ねていました。議事録の体をなしていなかったのです。
「こんなものは議事録と言えない」と当時塾長であった私はムチを打ちました。当時の私がどんな指摘をしたのかを中尾根さんに改めて尋ねたところ,彼はパソコンを開きながら,わかりやすく説明してくれました。
・議事録に敬称は不要である。
・見出しとコンテンツは一致させる。
・項目の構成は,抽象から具象へと整理する。
・決定したことは何か,検討しなければならないことは何かがわかるように書く。
・会議中に話し合った“どうしようもない”話をどう
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。