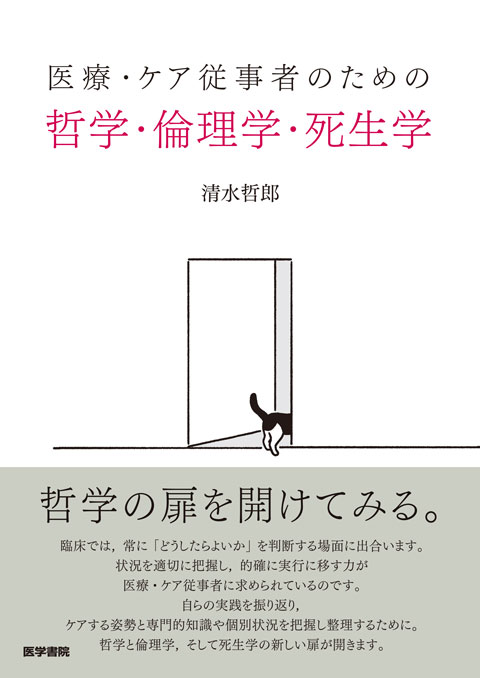応用倫理学入門
[第6回] 幇助死の倫理
連載 澤井 努
2025.02.11 医学界新聞:第3570号より
もしあなたが,不可逆的な病状によって余命6か月以内と診断され,激しい苦痛と日々向き合わざるを得ない状況に置かれたとしたら,どのような選択をするでしょうか。
医療の進歩に伴い,「生きる」ことの可能性が大きく広がった現代社会において,「死を迎える在り方」もまた多様な形で議論されるようになっています。その一端として,安楽死や自殺幇助などを含む「幇助死」(assisted dying)に関する法整備や制度設計の動きが,世界各国で加速してきました。特に,イギリス下院では2024年11月29日に終末期患者へ幇助死を認める法案が可決され,今後の最終採決や上院での審議に大きな注目が集まっています。
幇助死とは何か――定義と用語整理
「幇助死」という言葉の曖昧さには注意が必要です。一般に「安楽死」という用語は,医師などの第三者による患者への致死薬の投与を指すことが多いですが,「自殺幇助」は,医師が薬剤を用意して点滴を患者につなぎ,患者が自らバルブを開いて薬剤を体内に注入する行為を指します。イギリスで可決された法案の内容は後者に相当し,患者本人が致死薬を「自ら服用」する形式が特徴とされています。
また幇助死は,延命治療の中止や緩和ケアと混同されがちですが,これらは医療現場での「治療行為の最適化」や「苦痛の軽減」を目的とするケースが多く,必ずしも直接的に死をもたらすものではありません。幇助死を論じる際には,こうした関連概念との違いを正確に理解しておくことが大切です。
医療倫理の四原則と幇助死
医療倫理を語る上で欠かせないのが,「医療倫理の四原則」と呼ばれる以下の枠組みです(連載第3回参照)。
1.自律性の尊重(Respect for autonomy) 医療者は患者が自己の意思で治療方針を決定できるよう,十分な情報提供を行い,その決定を尊重するべきである。
2.善行(Beneficence) 医療者は患者の利益のために行動する義務を負う。
3.無危害(Non-maleficence) 医療者は患者に危害を及ぼさないよう配慮しなければならない。
4.正義(Justice) 資源配分や医療サービスの提供は,公平かつ平等であるべきである。
幇助死をめぐる議論では,患者の「自律性の尊重」と医療者の「善行」「無危害」の間でしばしば対立が起こります。患者自身が死を選ぶことを尊重すべきだという考え方と,「死に至らしめる行為」は医療者の使命に反する,あるいは危害を及ぼす行為であるという考え方の間で,医療者は深い倫理的葛藤を抱くことになります。さらに,「正義」の観点からも制度設計を慎重に考える必要があるでしょう。
イギリスにおける法整備と社会的背景
幇助死に関する近年の議論として注目されるのが,冒頭で言及したイギリスの事例です。2024年11月29日,下院において余命6か月以内の終末期患者に幇助死を認める法案が,賛成330票・反対275票で可決されました。これは,イングランドとウェールズに住む18歳以上の成人が対象で,医師2人と高等裁判所の承認を得た上で,患者が自ら致死薬を服用することを認める内容です。
法案成立には今後,下院での最終採決や上院での審議が必要とされ,成立までには最長2年かかると見込まれています。イギリスでは,2015年にも類似の法案が...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。