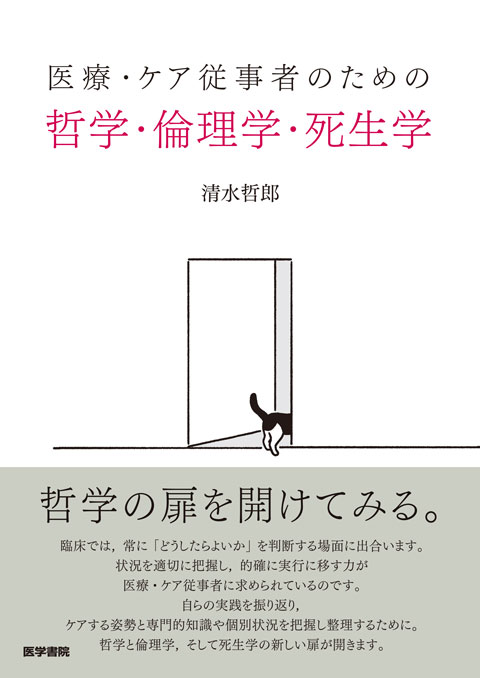応用倫理学入門
[第7回] 臓器移植の倫理(1)
連載 澤井 努
2025.03.11 医学界新聞:第3571号より
臓器移植は多くの命を救う医療行為として期待される一方,生命観や家族観,死生観などの価値観に深くかかわる倫理的ジレンマを伴います。日本で現在実施されている臓器提供には,生体からの提供(生体臓器移植),心停止後の臓器提供(死体臓器移植),脳死と判定された後の提供(脳死臓器移植)の3種類がありますが,いずれの場合も提供者本人や家族,そして医療従事者の間で大きな葛藤が生じやすいのが現状です。
一方,臓器移植の是非をめぐっては,「多くの命を救える」という肯定的な見方と,「身体を傷つける」ことに伴う慎重な見方が交錯するため,しばしば感情的な対立を招きます。とりわけ脳死臓器移植に対しては,「脳死を死とみなす」という点への抵抗も根強くあります。本稿では,そのような議論の複雑さを背景に,臓器移植に関する賛否両論を整理し,それらの背後にある倫理的課題を考察します。
本稿では,特定の結論を押し付けるのではなく,臓器移植に関する主な論点を整理することで,読者の皆さんが自ら考えるための材料を提供することを目的としました。
賛成派の主張
多くの命を救える善行
臓器の提供は重篤な患者の命を救うことにつながり,社会全体の福祉に貢献すると考えられています。移植用臓器に対する需要は供給をはるかに上回っており,移植を待ちながら亡くなる患者も少なくありません。したがって,臓器移植はこのギャップを埋め,失われかねない命を救う手段となり得ます。
ドナーの善意と自己決定の尊重
臓器提供は一般的に,ドナーの自主的な善意に基づくものと見なされます。特に本人が生前に提供の意思を示していた場合,その自己決定を尊重して死後に臓器移植を行うことは,倫理的に正当化されやすいと考えられます。例えば仏教圏の一部では,自らの意思による臓器提供は「慈悲の心」にもかなう行為だという見解が示されており,善意によって提供された臓器で他者の命が救われることを「命のリレー」として尊いものだと評価する意見もあります。家族間の深い絆に基づく自発的なドナー提供(親が子に腎臓を提供するなど)が行われることもあり,このような愛情に基づく決断が尊重されるケースも見られます。
最新医療の活用と人類の福祉向上
臓器移植は医学の進歩がもたらした恩恵であり,これを有効に活用すべきだという主張もあります。移植医療が発展した結果,以前は治療法がなかった重篤な心臓病や肝不全の患者が命を取り留め,生活を取り戻す例が増えました。医学の進歩を人類の福祉向上に生かすことは倫理的に正当とされ,臓器移植はその典型と言えます。医学的可能性を最大限に活用してより多くの患者を救うというのが,賛成派の大枠での主張です。
反対派の主張
脳死は本当に人の死か
脳死臓器移植にとって重要な問題として,脳死の定義そのものに根強い批判があるのも事実です。脳の機能が失われても,心臓が動き温かい体を目の当たりにすると,直観的には「まだ生きているのではないか」と感じる人も少なくありません。日本の伝統的な宗教界でも脳死を人の死と認めることに反対する見解は多く,脳死状態の人から臓器を摘出することに抵抗を示す立場があります。脳死を死とみなさない場合,脳死ドナーから臓器を取り出す行為は,生命を奪う行為(殺人)に等しいのではないかという倫理的批判も存在します。臓器移植推進のために法律で脳死を人の死と定義することに対しては,反対意見が根強く残っています。
ドナーへの危険と無危害原則
医療倫理の基本である「他者に危害を加えてはならない(do no harm)」という原則に反するとの懸念もあります。生体臓器移植では,健康なド...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。