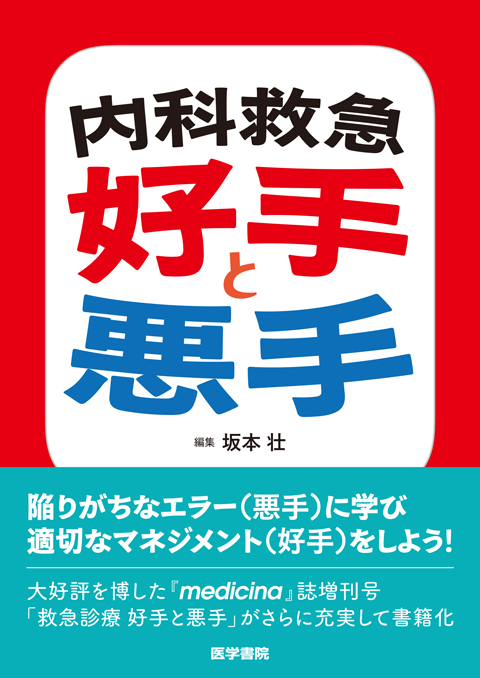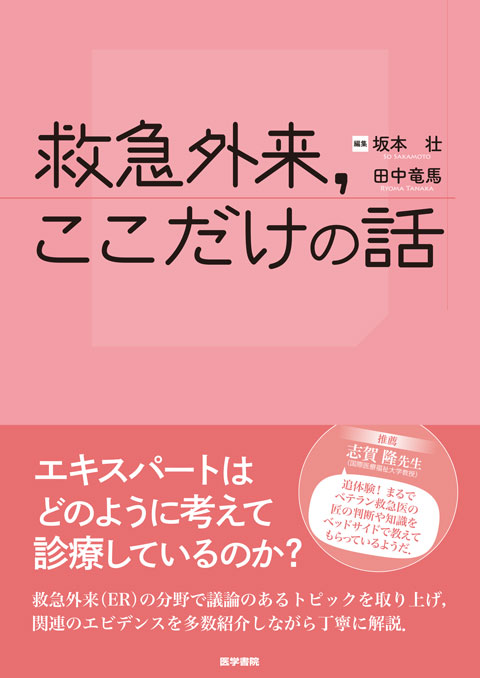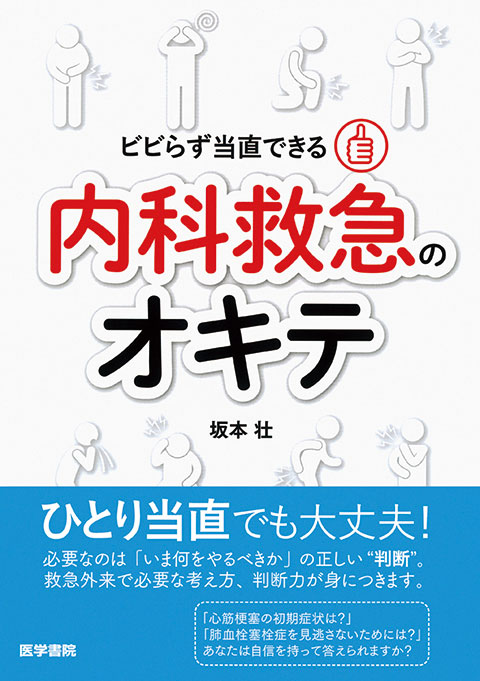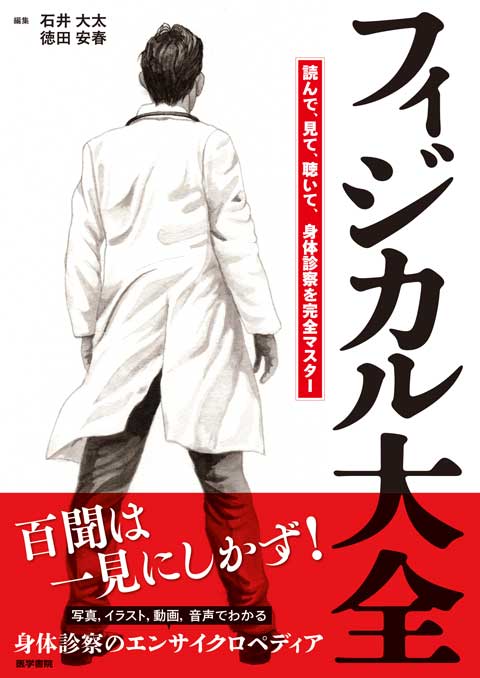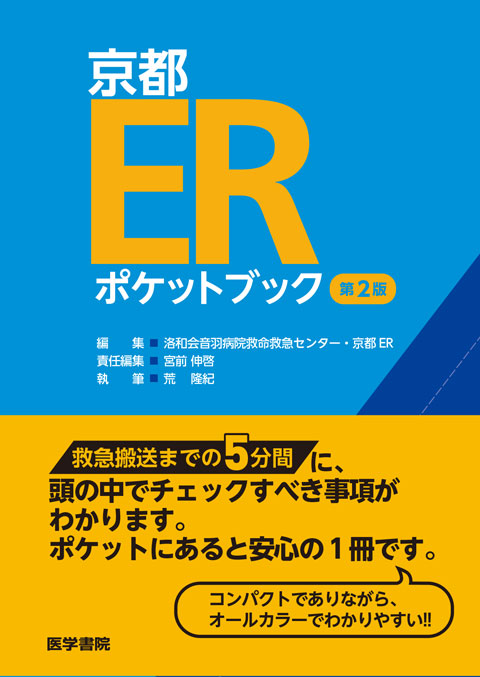- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第3回]低血糖
医学界新聞プラス
[第3回]低血糖――血糖補正だけで終わりじゃない!
『内科救急 好手と悪手』より
連載 糟谷 智史
2025.08.15
内科救急 好手と悪手
救急の現場で「もしかして見落としがあるかも?」と不安を感じることは少なくないでしょう。『内科救急 好手と悪手』は,救急外来で遭遇する頻度の高い疾患を中心に,鑑別診断のアプローチ,検査の考え方,そして時に起こり得る判断ミスまで具体的な「悪手」を提示し,それらを回避して適切な対応へと導く「好手」を紹介しています。『medicina』の特集で好評を博した内容に,今回新たに産婦人科や小児科などの項目を加え,さらに充実した内容になりました。救急診療に携わる全ての方にとって,日々の診療に役立つ一冊です。
「医学界新聞プラス」では,本書より「一過性脳虚血発作」「気管支喘息」「低血糖」「高K血症」の項目をピックアップし,ご紹介していきます。
❶低血糖を疑うサインを知らない
❷ビタミンB1投与を忘れる
❸低血糖の原因を検索・解決しない
❹適切な経過観察をしない
❺本人・家族・かかりつけ医に情報提供を行わない
キーワード|低血糖,糖尿病,ビタミンB1,インスリンボール
悪手① 低血糖を疑うサインを知らない
典型的な低血糖の病歴は,動悸や倦怠感,冷や汗,悪心,四肢の震えなどの自律神経症状に続いて意識障害,片麻痺,痙攣などの神経症状をきたします.目撃者や本人から糖尿病の持病や上記のような病歴を聴取することができれば低血糖の想起は容易ですが,意識障害で倒れているところを発見されて救急搬送された場合などではそのような病歴が取れないため,低血糖を念頭に置いて診療を開始することが重要です 1).意識障害だけでなく片麻痺,痙攣,構音障害などの神経症状や冷や汗をかいている患者をみた際には糖尿病の有無や病歴にかかわらず,まず血糖測定を行う癖をつけましょう.
低血糖が長時間になると意識の回復に関して予後不良(16.0時間 vs. 9.0時間:p <0.001)となるため,早期発見・介入が必要です 2).片麻痺や構音障害など脳卒中を疑うときには必ず低血糖を除外してから頭部CT・MRIを行うようにしましょう.
1型糖尿病や高齢,低血糖症の既往,β遮断薬内服など,患者背景によっては自律神経症状が出ずに突然意識障害や麻痺症状などの神経症状をきたすことがあり,典型例とは異なることがあることを念頭に置いて診療しましょう.
悪手② ビタミンB1投与を忘れる
細胞内でクエン酸回路を回すためにブドウ糖とともに補酵素であるビタミンB1が必須です.低血糖で運ばれてくる患者は高齢者が多く,背景に低栄養状態や利尿薬内服,透析などビタミンB1が不足しがちな状況にあります 3).Wernicke 脳症は決して珍しい疾患ではなく一般人口で2%,慢性アルコール中毒では12.5%ともいわれており,慢性アルコール中毒患者に限りません.アナフィラキシーを起こすことは稀であるため積極的にビタミンB1投与を行いましょう.Wernicke脳症の可能性が高い場合は500mg,ブドウ糖投与を必要とする患者には予防的に100mg のビタミンB1を投与しましょう.
悪手③ 低血糖の原因を検索・解決しない
低血糖はさまざまな原因で起きてしまいますが,血糖補正のみでその原因を特定しないと再度低血糖を起こしてしまう可能性があります.一度帰宅させた患者が症状再燃や交通事故などを起こし,重篤な病態で再度救急搬送されてくることは想像したくありません.
低血糖の原因
一般的な原因としてはスルホニル尿素(SU)薬やインスリン製剤を使用中の糖尿病患者のシックデイや過量投与などが多いです.
糖尿病が背景にない患者でも低血糖を起こすことがあり,敗血症やアルコール多飲,肝硬変,胃切除後のダンピング症候群やインスリノーマ,インスリン自己免疫症候群があります.また,抗不整脈薬であるシベンゾリンを,糖尿病治療薬を使用していない透析患者に数回使用したところ,低血糖を起こした症例報告 4)などもあり,薬剤性低血糖も原因として考える必要があります.その他にも抗うつ薬,β遮断薬,アンジオテンシン変換酵素(angiotensinconverting enzyme:ACE)阻害薬などの循環器系薬剤,非ステロイド性抗炎症薬(non-steroidal anti-inflammatory drugs:NSAIDs)やアセトアミノフェンなどの鎮痛薬,キノロンやST合剤など,機序的に判明しているものばかりではないものの,それ自体がインスリン分泌促進や感受性を亢進させるものや,肝臓CYP(シトクロムP450)の相互作用などによりSU 薬やインスリンの代謝・排泄に影響することで低血糖を引き起こしているものなどがあります.単独では低血糖を起こさないとされているdipeptidyl peptidase-4(DPP-4)阻害薬やsodium-glucose cotransporter 2(SGLT2)阻害薬なども飲み合わせにより低血糖を起こしうるため薬剤性低血糖は最後まで否定できません 5).
インスリンボール
低血糖の原因として手技に関わるものもあり,インスリンボールはpitfall になりうる原因です.インスリンボールとはインスリンを繰り返し同じ部位に打つことで穿刺部位に脂肪肥大またはアミロイド沈着を起こしてしまい腫瘤を作ることですが,ここにインスリンを投与すると吸収が阻害され効果が減弱してしまいます.症例数が7症例と少ないことから有意差は出なかったもののインスリンボールへの注射は正常部位への注射と比較して34%しか吸収されておらず,正常部位に投与するようにすることで1日に必要なインスリン量が平均27単位(53%)減少したという報告もあります 6).
外来でコントロール不良な患者が入院や訪問看護などによりインスリンを他人に打ってもらった際に低血糖を起こして気づくことがあり,診断した場合には必ず本人・家族・かかりつけ医に情報提供が必要となります.
上記の原因を鑑別して,感染症の治療,食事の取り方や手技の指導,原因薬剤の中止など,それぞれの原因に適切に対応することが今回の低血糖に関しても今後の再発予防でも重要になります.
悪手④ 適切な経過観察をしない
意識が悪い患者をみた際に低血糖を鑑別に挙げて血糖値を測定することは非常に重要ですが,血糖低値と低血糖症は異なるので,Whipple の3徴(①低血糖に矛盾しない症状,②発作時血糖が50mg/dL 以下,③ブドウ糖投与による症状改善)を満たすことが重要です.血糖補正した直後に意識状態が改善するかどうか必ず評価しましょう 7).血糖低値の患者に血糖補正しても意識が改善しない場合は他の疾患を注意深く探しましょう.また,ブドウ糖を投与して血糖が上昇し低血糖症状が改善したとしても,その後,血糖値が低下していき再度低血糖になってしまう可能性があります.そのため,1回の血糖測定で帰宅判断をせず,20~30分後など複数回の血糖測定を行う必要があります.
悪手③でも述べた通りシックデイによらない低血糖の場合には原因に応じた介入・治療が必要となり,シックデイでも原因薬剤や患者背景に合わせて経過観察をしましょう.超短時間型インスリンも大量投与すると長時間の補正が必要だったという報告 8)もあり,経口摂取が可能で,点滴などから補正しなくても正常血糖を維持できることを確認してから帰宅させることが重要です.
好手のおさらい
低血糖はさまざまな原因で起こしてしまう非常にcommonな疾患ですが,意識して血糖測定を行わないと診断ができず,不可逆的な神経障害をきたすなど予後不良な転帰になりうる恐ろしい疾患です.また,対応も単純に血糖補正をするだけでなく,原因検索のための詳細な問診や診察,適切な経過観察,帰宅時の指示やかかりつけへの情報提供など,丁寧な診療が必要であり,上記ポイントを押さえた診療を行いましょう.
(糟谷 智史)
- ●文献
- 1)岩倉敏夫:低血糖―重症低血糖の傾向と対策診断 と治療. 診断と治療104(suppl):142-148,2016
- 2)Ikeda T, et al:Predictors of outcome in hypoglycemic encephalopathy. Diabetes Res Clin Pract 101:159-163, 2013
- 3)Leon G:Clinicians who miss Wernicke encephalopathy are frequently called defendants. Emergency Medicine News 41:14, 2019
- 4)大槻郁人,他:コハク酸シベンゾリン中毒により 重篤な低血糖が遷延した透析患者の1 例.日救急医会誌24:941-946, 2013
- 5)池田香織:薬剤性低血糖とは?薬剤性低血糖の原 因について教えてください.肥満と糖尿8:214-215, 2009
- 6)Nagase T, et al:Insulin-derived amyloidosis and poor glycemic control;A case series. Am J Med 127:450-454, 2014
- 7)坂本 壮:救急外来ただいま診断中!,第2版,中 外医学社,2024
- 8)三島健太郎,他:自殺企図によるインスリングル リジンの大量注射で血糖降下作用が遷延した一例.日臨救医誌17:571-574, 2014
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。