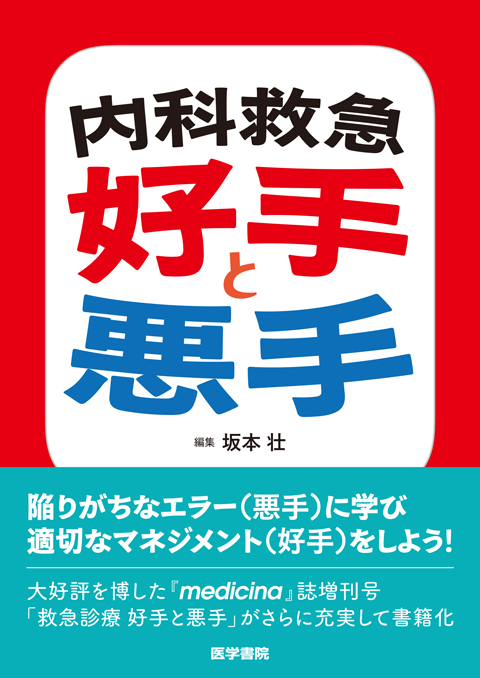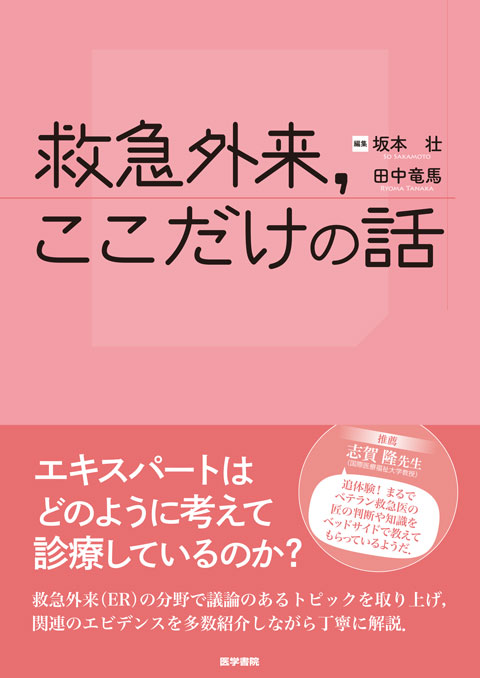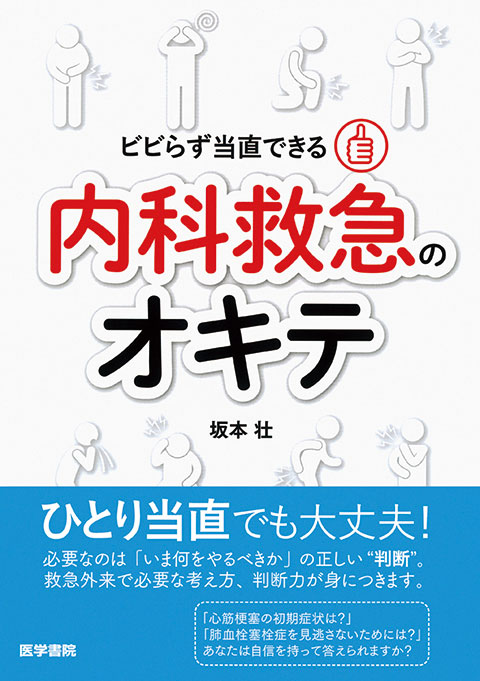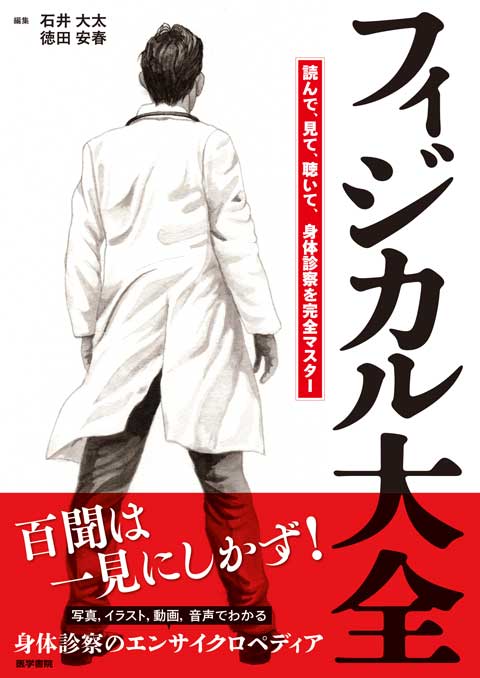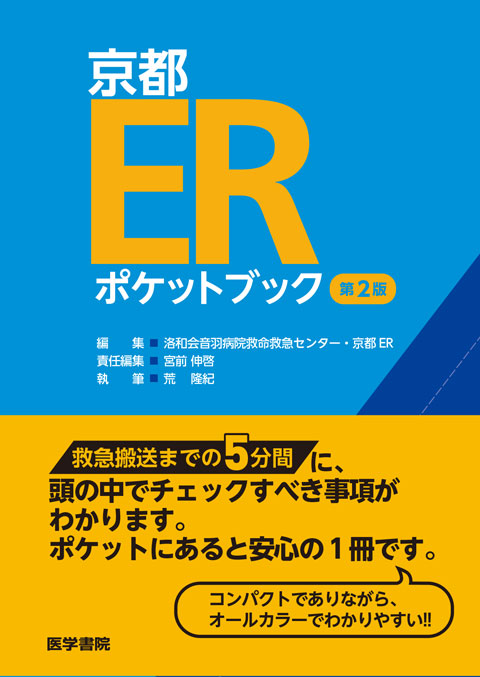- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2025年
- 医学界新聞プラス [第2回]気管支喘息
医学界新聞プラス
[第2回]気管支喘息――アクションプランで救急外来受診を減らそう!
『内科救急 好手と悪手』より
連載 倉原 優
2025.08.08
内科救急 好手と悪手
救急の現場で「もしかして見落としがあるかも?」と不安を感じることは少なくないでしょう。『内科救急 好手と悪手』は,救急外来で遭遇する頻度の高い疾患を中心に,鑑別診断のアプローチ,検査の考え方,そして時に起こり得る判断ミスまで具体的な「悪手」を提示し,それらを回避して適切な対応へと導く「好手」を紹介しています。『medicina』の特集で好評を博した内容に,今回新たに産婦人科や小児科などの項目を加え,さらに充実した内容になりました。救急診療に携わる全ての方にとって,日々の診療に役立つ一冊です。
「医学界新聞プラス」では,本書より「一過性脳虚血発作」「気管支喘息」「低血糖」「高K血症」の項目をピックアップし,ご紹介していきます。
❶聴診をしない
❷短時間作用性β2刺激薬(SABA)だけ処方して帰す
❸全身性ステロイドを使わない
❹アクションプランを決めておかない
キーワード|気管支喘息,喘息増悪,全身性ステロイド,アクションプラン
悪手① 聴診をしない
本項は気管支喘息(以下,喘息)を救急外来で診るというテーマであるため,増悪ないしはそれに準じる状態を想定して記載します.喘息増悪(発作)とは,既存の喘息が急速に悪化することを指しますが,国際的ガイドラインとして有名なGlobal Initiative for Asthma(GINA)1)は,喘息増悪のことを「flare-up(フレアアップ)」と呼ぶことを推奨しています.トリガー(アレルゲン曝露,気候変動,ウイルス感染など)が焚き木となって,まさに好酸球性気道炎症が燃え上がるというわけです.
救急外来に来るということは,患者さんには喘鳴などの自覚症状があるはずですから,喘息と過去に診断されている人の場合,増悪の判断は容易です.アフターコロナになって聴診器も再び活躍する時代に戻りましたが,これはかなりの武器になります.慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease:COPD)増悪にも共通することですが,「どのくらい気管支が狭窄しているのか」を判断するために,wheezesを聴診することはとても有用です.表1は筆者が作成したものですが,喘息の場合,wheezesの程度と範囲に応じて対応を決めてよいと考えています.
喘息増悪で入院する経過には個人差があります.例えば,若年層,BMI 低値,喫煙者では,びっくりするくらい急速に増悪することがあります 2).夜の接客業をしている人がアルコールをきっかけとして喘息増悪で救急搬送されてくるのが,まさにこれです.
悪手② SABAだけ処方して帰す
短時間作用性β2刺激薬(short-acting β2-agonist:SABA)は喘息増悪の際,まず選択される薬剤です.救急外来を受診してやってきた喘息患者さんに対して,SABAの処方箋だけを渡すのは得策ではありません.もちろん,「使っているSABAが切れてしまったから」という場合は仕方がありませんが,症状を緩和するために初回にSABA を処方するのは悪手なのです.
1つ目の理由は,特に喘息増悪を起こしている場合,SABAはまともに吸えないからです.ある程度慣れてくると,発作の予兆があったときにうまくSABAを吸入できるのですが,初回でSABA を処方されても,たとえ薬剤指導を受けたところで,喘鳴がひどくて吸入できないことが往々にしてあるのです.そのため,喘息増悪で受診した患者さんには,加圧式定量噴霧式吸入器(pressurized metered-dose inhaler:pMDI)やドライパウダー吸入器(drypowder inhaler:DPI)のSABAを処方するのではなく,ネブライザーのSABA〔サルブタモール(ベネトリンⓇ吸入液など)〕を用いるほうがベターです.
2つ目の理由は,救急受診する喘息患者さんがSABA のみで発作が解除できるかどうかは,ギャンブルだからです.軽症例で,SABAのみでスカっと良くなる人もいますが,救急受診するくらいしんどいわけですから,大多数がSABAのみで軽快しません.プレドニゾロン(プレドニンⓇ,プレドニゾロン)錠とともにSABAを処方するのはアリだと思いますが,SABA単独は結構リスキーです.
SABAを処方するくらいなら,吸入ステロイド/長時間作用性β2刺激薬(inhaled corticosteroid:ICS/long-acting β2-agonist:LABA)のほうがよいでしょう.救急外来を受診するような喘息の場合,長期管理薬としてどこかの時点でICS/LABAを処方することが重要です.それは,救急外来でも構いませんし,後日呼吸器内科受診でも構いません(救急外来では気道可逆性検査や呼気一酸化窒素濃度測定など,喘息の診断がなかなか難しいという現実があるのですが).近年,増悪や増悪予防に対してICS/LABA を頓用で使用するエビデンス注1)が支持されつつありますので,調子が良くないときにブデソニド/ホルモテロール(シムビコートⓇ,ブデホルⓇ)を吸入するという選択肢もよいでしょう.
悪手③ 全身性ステロイドを使わない
喘息増悪に関しては,全身性ステロイドの閾値をあまり高く設定しないほうがよいです.喘息の原因が帰宅後解除されていればよいのですが,ウイルス感染などは1週間くらい続くこともあります.そのため,比較的軽症例であっても,呼気時に明確なwheezesを聴取している場合,短期間の全身性ステロイド投与に踏み切る必要があります.
6研究のメタアナリシスによれば,全身性ステロイド投与は喘息増悪後1週間以内の再発を抑制することが示されています(相対リスク0.38,95%信頼区間:0.20~0.74)8).また,この効果は投与3週間後まで持続します(相対リスク0.47,95%信頼区間:0.25~0.89).
わが国のガイドライン 9)では以下のようなレジメンが推奨されています.
- ・ プレドニゾロン:0.5mg/kg/日を経口投与
- ・ メチルプレドニゾロン:40~125mg点滴,以後40~80mgを4~6時間ごとに点滴
- ・ ヒドロコルチゾン:200~500mg点滴,以後100~200mgを4~6時間ごとに点滴
- ・ デキサメタゾン:6.6~9.9mg点滴,以後6.6~9.9mgを6時間ごとに点滴
- ・ ベタメタゾン:4~8mg点滴,以後4~8mgを6時間ごとに点滴
わが国では,アスピリン喘息(aspirinexacerbated respiratory disease:AERD)に対するメチルプレドニゾロンは避けるべきという見解が根付いていますが,どうやらそれは都市伝説ではないかという見解が示されています10).アスピリンとコハク酸エステル型ステロイドの交差反応はさほど気にしなくてもよいのかもしれません.ただ,これについてはまだ質の高いエビデンスがないので,続報を待ちたいところです.
悪手④ アクションプランを決めておかない
つらければもちろん救急外来を受診してもらっても構わないのですが,喘息症状の悪化を自覚した場合に,家庭において何を行うかという「アクションプラン」を患者さんと話し合っておくことが望ましいです.これはどちらかといえば定期外来主治医の役割でもあります.
例えば,喘鳴や胸部絞扼感があったとき,SABAを吸入してもらい,30分後,1時間後に軽快しないようであれば,持参のプレドニゾロン錠を飲んでもらう,といったことです.頓用のステロイドを患者さんに持たせておくことについては議論の余地がありますが,特に医療アクセスが不良であったり,コロナ禍で受診控えがあったりする状況であれば,5mg 錠を4~6錠/回×5日分くらいは持たせておくとよいと思います.
アクションプランがしっかり決まっている病院は,喘息の救急搬送やウォークインが少ないです.
好手のおさらい
喘息の吸入薬にも,COPD と同じくトリプル吸入製剤が保険適用されるようになり,また生物学的製剤もラインナップが増え,治療は複雑化しているように思う読者もいるかもしれません.しかし,救急領域の喘息診療は10 年前からさほど変わっておらず,増悪時にSABA(あるいはブデソニド/ホルモテロール),全身性ステロイドを導入することが肝要です. 喘息搬送例が多い病院では,個々の患者さんにアクションプランが設定されているか確認しておきましょう.
(倉原 優)
- ●文献
- 1)Global Initiative for Asthma:Global Strategy for Asthma Management and Prevention(Updated 2024)
- https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_ 05_22_WMS.pdf (2025年5月閲覧)注2)
- 2)Tanaka H, et al:Identification of patterns of factors preceding severe or life-threatening asthma exacerbations in a nationwide study. Allergy 73:1110-1118, 2018
- 3)Bateman ED, et al:As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med 378:1877-1887, 2018
- 4)O’Byrne PM, et al:Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med 378:1865-1876, 2018
- 5)B e a s l e y R , e t a l :Cont rol led t r ial of budesonide-formoterol as needed for mild asthma. N Engl J Med 380:2020-2030, 2019
- 6)Hardy J, et al:Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL); A 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 394:919-928, 2019
- 7)Papi A, et al:European Respiratory Society short guidelines for the use of as-needed ICS/formoterol
in mild asthma. Eur Respir J 62:2300047, 2024 - 8)Rowe BH, et al:Corticosteroids for preventing relapse following acute exacerbations of asthma.
Cochrane Database Syst Rev 3:CD000195, 2007 - 9)日本アレルギー学会喘息ガイドライン専門部会(監):喘息予防・管理ガイドライン2024,協和企画,2024
- 10)鈴木俊一郎,他:アスピリン喘息患者に対するコハク酸エステル製剤の安全性に関する調査.セッションⅣ
注1)軽症喘息に対する長期管理薬としてICS ではなく頓用ブデソニド/ホルモテロールを用いてもよいとするランダム化比較試験がいくつか報告されており3~6),GINA1)だけでなく欧州呼吸器学会7)においても優先治療としてICS/ホルモテロールによる1剤管理を推奨しています.
注2)最新版としてGINA2025が公開されています.
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2025/05/GINA-Strategy-Report_2025-WEB-WMS.pdf
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。