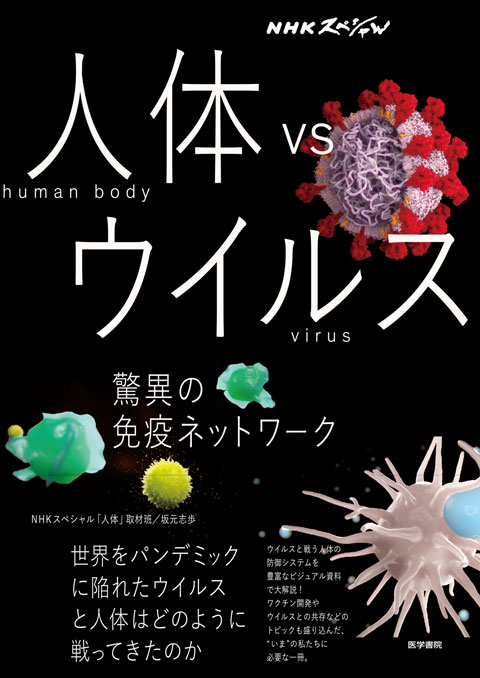新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフト
インタビュー 田中 良哉
2026.01.13 医学界新聞:第3581号より

免疫学の知見を疾患の病態解明や新たな治療法の開発につなげる「臨床免疫学」。免疫研究の対象がマウスからヒトへ移り,その重要性はますます高まっている。いまだ完全な治療法が見つからない無数の疾患に対し,創薬や研究においてどのような展望が見えており,国際的な研究競争が繰り広げられる中で日本の立ち位置はどこにあるのか。関節リウマチ(RA)や全身性エリテマトーデス(SLE)など全身性自己免疫疾患の専門家として研究・臨床をリードし,現在は日本臨床免疫学会の理事長を務める田中良哉氏に話を聞いた。
ドラッグ・ラグを解消し,患者に最新の医療を届ける
──基礎免疫学の成熟を背景に,臨床免疫学も創薬や病態の解明において多様な展開を見せています。自己免疫疾患の専門家として診療・研究に長年従事されてきた先生の目から見て,治療法開発におけるターニングポイントはどのあたりだと考えていますか。
田中 やはり分子標的薬の登場でしょう。私が医師になった1980年代,自己免疫疾患の治療はグルココルチコイド(ステロイド)以外の選択肢がほとんどありませんでした。ただしステロイドの効果は痛みや炎症の抑制です。すなわち免疫の異常や疾患の原因は解消できず,加えて副作用も大きい。できるならば使いたくないとの気持ちがあったのも事実です。その後1990年代に最初の分子標的薬であるTNF-α阻害薬が登場し,病態の原因分子を制御することが可能になりました。自己免疫疾患の分野でも臨床的寛解をめざせるようになったことは,極めて大きな変化でした。
──以降は画期的な分子標的薬が次々と登場する一方で,海外で承認された薬が日本ではなかなか承認されない「ドラッグ・ラグ」の問題も生じています。
田中 そもそも分子標的薬の登場前,アメリカでは免疫抑制薬であるメトトレキサートがRAの治療薬として1988年に承認されていました。しかし日本で承認されたのは1999年です。その後も日本で2003年に最初の分子標的薬として承認されたTNF-α阻害薬もアメリカでは1998年,ヨーロッパで1999年に承認済みであるなど,欧米に後れを取る状況が続きました。2000年に教授に就任して以来,「何とかこの差をゼロにしたい」との気持ちが,今日までの私の活動における原点の1つと言えます。
──ドラッグ・ラグ解消に向けた,田中先生ご自身の取り組みについてもお聞かせください。
田中 自己免疫疾患分野に限らず,かつて日本では欧米での治験が終わった後に同様の試験を国内で小規模に行う「ブリッジング試験」を実施するのが一般的でした。日本で1から始める治験より承認のスピードは上がるものの,この方法では欧米からの遅れは永遠に取り戻せません。ドラッグ・ラグをなくすには,開発の最初期からグローバルの開発コミュニティに入り,欧米と同時に治験を進めていくことが必須でした。そこで生物学的製剤による寛解後の休薬に関する研究1)などの実績を積み重ねて「日本は質の高いエビデンスを出せる」との信頼を獲得し,欧米と共同で治験に取り組む機会を増やしていったのです。
こうした努力が結実したのが,RA治療薬として2013年に承認されたJAK阻害薬です。私たちがアメリカと連携して治験を主導した結果,最初のJAK阻害薬であるトファシチニブはアメリカにわずか1年遅れ,欧州と比較すると4年も早く日本で承認されました。続くバリシチニブ2)も日米欧での同時発売を成し遂げており,現在リウマチ領域に限っては日本が世界をリードする立場にあると言っても過言ではありません。また近年では,SLEに用いられるⅠ型IFN受容体拮抗薬であるアニフロルマブも欧米と共同治験3)の上で同時に承認されるなど,自己免疫疾患の分野を中心にドラッグ・ラグの解消が広がっています。
「寛解」から「治癒」の実現へ
──分子標的薬によって疾患の寛解が現実的となった今,免疫分野の創薬は今後どのようなフェーズに向かっていくのでしょうか。
田中 寛解のさらに次のステップ,つまりは疾患の完全な治癒や,薬剤を使用せずとも寛解状態を維持できるドラッグフリーの実現に主眼を置いた研究がますます増えるでしょう。大きな視点では,既存の分子標的治療のさらなる精緻化と応用です。例えば,JAK阻害薬よりも選択性を高めたTYK2阻害薬や,免疫反応の司令塔である形質細胞様樹状細胞(plasmacytoid dendritic cells:pDCs)を標的とした抗体(BDCA2抗体など)の臨床試験4)が最終段階に入っています。また,がん治療で用いられる抗PD-1抗体などの免疫チェックポイント阻害薬は免疫のブレーキを外してがん細胞を攻撃させますが,このメカニズムを逆手にとって過剰な免疫にブレーキをかける,抗PD-1アゴニスト抗体の研究も進みつつあります5, 6)。
──さまざまな治療法の開発が進む中で,田中先生が特に注目している分野があれば教えてください。
田中 血液がんの治療で実績のあるキメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞(CAR-T細胞)療法の,自己免疫疾患への応用です。ドイツのSchettらの報告によれば,難治性SLE患者にCAR-T細胞療法を行ったところ,自己抗体が消失したまま長期間にわたりドラッグフリー寛解を維持できたそうです7)。CAR-T細胞によって除去された自己免疫性のリンパ球が,再生後は自己免疫反応を示さなかったのです。これは単なる病的細胞の除去ではなく免疫システムの再構築が起こったことを意味しており,今後多くの疾患治療に応用できるポテンシャルを秘めています。
──がん治療の技術が自己免疫疾患の治療につながるのは興味深いです。他方CAR-T細胞療法には時間的・金銭的コストなどの課題もあります。がん以外の領域への応用を見越した場合,これらのハードルを乗り越える算段はあるのでしょうか。
田中 有力な手立てとしてiPS細胞の活用があります。iPS細胞から作製したナチュラルキラー(NK)細胞やγδT細胞(白血球の一種)にCAR遺伝子を導入した,「iPS-CAR-NK細胞/T細胞」の実現に向けた研究が国内外で進んでいます8~11)。iPS細胞は体外で大量に培養できますし,患者の免疫細胞に由来しないので,一律に安定した品質を保てます。抗原特異性や細胞の機能にも手を加えた上で戻せることも強みです。実現すればがんや自己免疫疾患の治療だけでなく,移植医療や感染症対策などあらゆる領域で活用されるはずです。
また,細胞療法ではなく抗体医薬で同様の効果を狙うT細胞エンゲージャー(T Cell Engager:TCE)の開発も進んでいます。これは病的な細胞や病原体に免疫細胞を誘導して攻撃させるもので,いわば投薬により体内のT細胞でCAR-Tのような現象を再現する画期的な技術です。CAR-Tと比べれば低コストでの利用も見込めます。
領域横断的な臨床免疫学の推進に向けて
──お話を伺っていると,免疫という横軸があることで,本来全く異なる領域にある疾患同士の治療が相互補完的に発展していく印象を受けました。
田中 それこそが臨床免疫学の醍醐味です。例えば,最初にRA治療薬として承認されたTNF-α阻害薬はその後,乾癬,炎症性腸疾患(IBD),Behçet病など10以上の疾患に応用されました。かつては失明に至ることもあったBehçet病の予後を劇的に改善し,IBDにおける腸管合併症も激減させています。分子標的治療1つとっても,ある分野でのブレイクスルーが臓器別ではなく「メカニズム別」に展開できる点は,診療科ごとの壁を取り払った連携の促進にとっても重要であると感じています。
──国際的な視点で見たとき,臨床免疫学における日本の立ち位置をどう評価されていますか。
田中 全体的には国内外での差はそこまでないと考えています。特に日本独自の強みとして,臨床と研究を両立させているphysician scientistが多いことが挙げられます。欧米では臨床医と研究者の分業化が進んでおり,両方の言語がわかるphysician scientistの存在は,グローバルの共同研究においても非常に重宝されます。もちろん欧米にリードを許している部分があるのも事実です。今後はRAやSLEのように日本が先進的な分野をもっと広げていかねばなりません。
──そのために,日本臨床免疫学会としては今後どのような点に注力していくのでしょうか。
田中 まずは基礎と臨床の橋渡しです。日本には基礎免疫学の素晴らしい知見があり,制御性T細胞やiPS細胞,PD-1などノーベル賞級の成果も少なくありません。日本の強みでもある基礎と臨床の垣根の低さを最大限に発揮させ,基礎研究を患者さんの治療にしっかりと結び付けるサポートをしていかねばならないでしょう。
もう1つは若い研究者の育成です。実は臨床免疫学に携わる若手はそう多くありません。将来的にグローバル研究の中心を担う人材を増やしていくためにも,教育体制の強化や国際交流の機会創出に学会としても注力していきたいと思います。領域横断性の高さや基礎と臨床の距離の近さに裏付けされた臨床免疫学の魅力と可能性は他に類を見ないものだと思います。学会としても個人としても,でき得る限りの貢献を続けていきたいです。
(了)
参考文献・URL
1)Ann Rheum Dis. 2010[PMID:20360136]
2)N Engl J Med. 2017[PMID:28199814]
3)N Engl J Med. 2020[PMID:31851795]
4)N Engl J Med. 2022[PMID:36069871]
5)Sci Immunol. 2023[PMID:36638191]
6)J Graf, et al. Rosnilimab, a Selective and Potent Depleter of Pathogenic T Cells, Demonstrates Efficacy, Safety, and Translational Proof of Mechanism in a Rheumatoid Arthritis Phase 2B Trial.ACR onvergence 2025.2025.
7)Nat Med. 2022[PMID:36109639]
8)Cell Stem Cell. 2018[PMID:30082067]
9)EBioMedicine. 2020[PMID:32853984]
10)Nat Commun. 2021[PMID:33462228]
11)Stem Cell Reports. 2023[PMID:36963392]

田中 良哉(たなか・よしや)氏 日本臨床免疫学会 理事長 / 日本リウマチ学会 理事長 / 産業医科大学医学部分子標的治療内科学特別講座 特別教授
1984年産業医大医学部卒。88年同大大学院医学研究科修了。89年同大医学部第1内科学講座助手,同年より米国立衛生研究所(NIH)客員研究員。95年より産業医大医学部第1内科学講座で講師を務め,2000年から同講座教授。25年より同大医学部分子標的治療内科学特別講座特別教授に就任。19年から日本臨床免疫学会理事長,23年から日本リウマチ学会理事長を務める。23年に欧州リウマチ学会年次総会にて日本人で2人目の同学会栄誉会員賞を受賞し,25年には日本人で2人目の米国リウマチ学会名誉会員(ACR Master)に選出された。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第15回]患者さんの氏名をIDに置き換えて「匿名化」すれば,自由に使っても大丈夫ですよね?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.02.17
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。