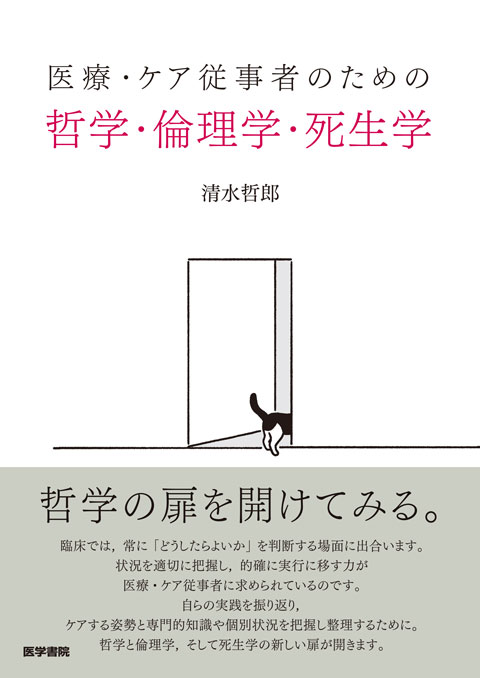応用倫理学入門
[第13回] 未来への責任あるイノベーション――ELSIとRRI(最終回)
連載 澤井 努
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
今日,人工知能(AI)やゲノム編集,再生医療をはじめとする科学・医学・工学の進展はめざましく,人々の生活や健康,そして生命観そのものを大きく変えつつあります。こうした新興技術は計り知れない恩恵をもたらす一方で,社会制度の設計に難しい課題を突きつけています。本連載では,倫理的相対主義や道徳的地位,研究倫理といった哲学・倫理学上の論点から,生殖医療,終末期医療,移植医療,脳神経科学,再生医療,遺伝子治療・遺伝子検査が提起する課題,さらに公衆衛生における正義の問題まで,科学・医学・工学のさまざまな分野を横断的に検討してきました。最終回となる本稿では,これらの分野を俯瞰的にとらえた上で,より広い視点でこれからの科学技術と社会の在り方を論じたいと思います。
科学技術と社会をつなぐELSIとRRI
科学・医学・工学は近年ますます深く結びつき,分野の境界は絶対的なものではなくなりつつあります。医工連携による新規医療機器の開発や,生命科学と情報科学の融合による創薬など,学際的アプローチがイノベーションの要となっています。こうした統合的な進歩は難病克服や生活の質の向上に大きく寄与し得る一方で,それぞれの分野の中では想定しにくかった複雑な倫理的課題を生み出しています。
例えば,AIを医療に応用すれば診断の効率化が期待できる一方で,診断エラーが発生した際の責任の所在が曖昧になったり,患者データの処理や分析の過程が不透明になったりする懸念があります。ゲノム編集技術の生殖医療への導入についても,将来世代への影響や「デザイナーベビー」の是非に関する社会的合意形成が不可欠です(第4回を参照)。新興技術の急速な進展を踏まえると,科学技術と社会との関係をこれまで以上に丁寧にとらえ直し,研究開発の進め方そのものを見直すことが求められます。言い換えれば,従来は別々に論じられがちだった技術面と倫理・社会面を統合し,多面的に考える視点が不可欠です。こうした文脈で注目されるのが「倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal, and Social Issues:ELSI)」と「責任ある研究・イノベーション(Responsible Research and Innovation:RRI)」の視点です。
2018年,中国の研究者が世界初のゲノム編集を用いた子どもの誕生を公表しました。この事例は,国際的な倫理基準を大きく逸脱するものとして論争を呼び,生命科学における倫理ガバナンスの脆弱さと,倫理指針・法制度の迅速な整備の必要性を浮き彫りにしました。その後,再発防止に向けた国際的な動きが加速し,幅広い協議を経て,2021年に世界保健機関(WHO)がヒトゲノム編集のガバナンスに関する初の包括的勧告を発表しました。勧告には,国際登録簿の整備,違法・非倫理的な研究への対処,市民参加に基づく教育・啓発など,多面的な提案が含まれています。
倫理ガバナンスにおいて考慮すべきことは,技術ごとに異なります。例えば新薬の研究開発では,有効性や安全性といった科学的側面に加え,必要な患者に適切に新薬が行き渡るアクセスの公平性が求められます。AIを活用した診断機器では,データの分析結果の公平性や,AIを用いた判断に伴う説明責任などが問題となります。このような課題を事前に洗い出し,必要なルール整備や合意形成へと結びつけることが,新興技術の円滑な社会実装には不可欠です。
ELSIとRRIの背景
米国では,1990年に始まったヒトゲノム計画において研究費の一部(全体の3~5%)をELSI研究に充てる枠組みを導入したのを嚆矢に,研究開発段階から社会への影響を検討する仕組みが組み込まれてきました。欧州では,市民参加型の科学技術ガバナンスの流れを背景に,RRIの概念が発展しました。EUの研究資金プログラム「Horizon 2020」ではRRIが主要課題に位置づけられ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。