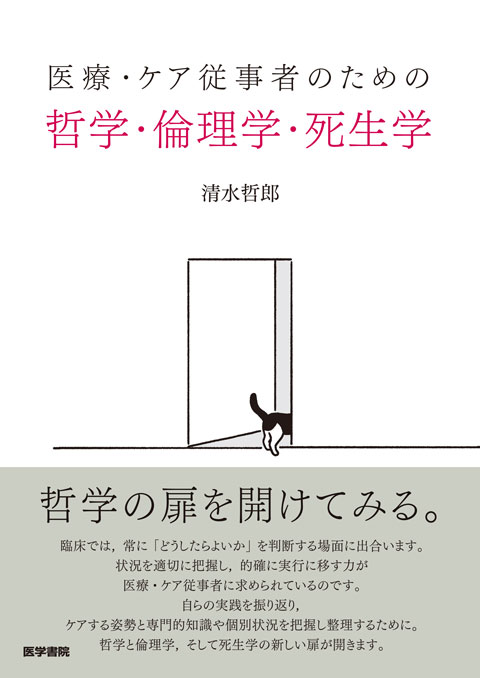応用倫理学入門
[第12回] パンデミックの倫理
連載 澤井 努
2025.08.12 医学界新聞:第3576号より
2020年初頭に世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は,2002年のSARS以来,最大規模の公衆衛生上の危機となり,医療従事者のみならず社会全体に多くの倫理的課題を突きつけました。パンデミックは社会構造・経済・政治・文化にまで影響を及ぼす複合的な災害であり,医療従事者には従来の医療倫理に加えて,社会全体の利益と個人の権利・自由を調整する視点,すなわち公衆衛生倫理が求められます。今回は,公衆衛生を最も深刻に揺るがす現象としてパンデミックに焦点を当て,そこから見えてくる主要な倫理的課題を概観します。
公衆衛生倫理の原則
従来の医療倫理は,患者や被験者といった個人を対象に,「自律性の尊重」「善行」「無危害」「正義」という四原則を適用してきました(連載第3回を参照)。これに対して公衆衛生倫理では,社会や集団を対象とし,「連帯」「比例性」「最小侵襲」「透明性」などの原則が意思決定の指針として示されています。パンデミックのような状況では,限られた資源をどう配分するか,集団の利益を守るために個人の行動や権利をどこまで制限すべきかといった,トレードオフを伴う判断が常に求められます。世界保健機関(WHO)や国連教育科学文化機関(UNESCO)による倫理的ガイダンスでも,公正で差別のない措置や脆弱な人々への特別な配慮の重要性が強調されています。しかし,こうした原則を各国の文化的・制度的文脈に即して具体化することは容易ではありません。
COVID-19パンデミックが提起した7つの倫理的課題
1.医療資源のトリアージ
感染拡大により重症者用ベッドや人工呼吸器が逼迫した局面では,誰に治療を優先的に提供すべきかを判断するトリアージの必要性が生じました。例えば,イタリアのある学会は「できるだけ多くの命を救う」ことを重視し,生存可能性が高い患者や,より多くの生存年数が見込まれる患者を優先するというガイドラインを示しました1)。しかし,こうした優先順位付けにおいては,正義(公平)とは何かという根本的な問いが再考されることになり,日本老年医学会が年齢のみを理由に患者を治療対象から除外するのは不当であるとする声明を発表しています。限られた医療資源のもとで,救命数の最大化と社会的弱者の保護をどのように両立させるかという課題は,今後の災害医療においても極めて重要な論点です。
2.ワクチン・ナショナリズムと分配の正義
各国でワクチン開発が進む中,高所得国がワクチンを大量に確保するワクチン・ナショナリズムが顕在化し,世界的な分配の不公平が深刻な問題となりました。国際的な枠組みであるCOVAX(COVID-19 Vaccines Global Access)は各国への公平なワクチン供給をめざしましたが,富裕国による囲い込みの影響で供給が追いつかず,その限界が指摘されています2)。また一部の国では,ワクチン提供と引き換えに外交的な譲歩を求めるワクチン外交が展開され,そうした行為の倫理的妥当性も問われています。グローバルな正義の観点から,医療資源を世界規模で公平に分配するための制度や仕組みの強化が求められています。
3.自由の制限と比例性の原則
感染拡大を防止するために各国で実施されたロックダウン(都市封鎖),マスク着用の義務化,行動追跡アプリの導入といった措置は,公衆衛生上一定の効果をもたらしたと評価されています。しかし,これらの強制的な措置は個人のプライバシーや経済活動の自由を制限する可能性があるため,その正当性については常に慎重な検討が求められます。倫理的観点からは,比例性の原則が重要な判断基準となります。すなわち,講じられる措置が感染リスクの低減という目的に対して,どの程度まで正当化されるかを評価することが不可欠です。日本においては,政府からの外出自粛要請や営業時間短縮要請が行われました。その際には,罰則を伴う命令に踏み切るべきかどうか,また「自粛警察」と呼ばれる市民による過剰な私的制裁の正当性について,社会的な議論も巻き起こりました。個人の基本的人権と公衆衛生上の利益とのバランスをいかに取るか。緊急時の場当たり的判断ではなく,平時からのガイドライン整備などが重要です。
4.デジタル・サーベイランス(監視)とプライバシー
COVID-19パンデミック時には,スマートフォンによる接触確認アプリや,店舗入店時のQRコード登録など,デジタル技術を活用した感染者の追跡手法が各国で導入されました。これらの施策は感染拡大の抑制に一定の効果を上げたものの,個人情報の収集・利用に対する懸念も高まりました。本来,疫学調査に必要な範囲を超える過剰なデータ収集は,目的限定性やデータ最小化の原則に反します。パンデミックを通じて多くの国でデータ・ガバナンスの脆弱性が露呈した一方,台湾では,法制度の整備と高い透明性によって市民の信頼を得ながら,デジタル技術を効果的に活用したと評価されています。感染状況を的確に監視しつつプライバシーを守るには,制度の透明性,法的な監督体制の構築,そして何よりも政策当局と市民との信頼関係が不可欠です。
5.医療従事者のリスクと義務
感染リスクの高い環境で治療にあたる医師や看護師などの医療従事者には,職業上の義務として患者の治療責任が広く認められています。しかし,命の危険が現実となったパンデミック下では,医療従事者にどこまで自己犠牲を求めるべきかという倫理的な葛藤が浮き彫りとなりました。特に感染防護具が不足していた時期には,医療従事者は職場にとどまる義務があるのか,それとも離れる自由があるのかをめぐって社会的な議論が起こりました。メディアでは,医療従事者を英雄として称賛する報道も見られましたが,当事者の中には,そのような英雄視によって自身の不安や脆弱性が軽視され,危険への懸念を口にしづらくなったと指摘する声もあります。また,過酷な勤務環境は医療事故のリスクを高めるだけでなく,医療従事者のメンタルヘルスにも長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。このような状況において医療提供体制を持続可能にするには,一方的な自己犠牲を求めるのではなく,組織的な安全管理と心理的サポート体制の整備が必要でしょう。
6.偏見・差別と社会的弱者への影響
感染症の流行時には,病気に対する過度な恐れや無理解から,偏見や差別が生じやすくなります。COVID-19パンデミックにおいても,感染者やその家族,濃厚接触者,さらには回復者に対する差別が深刻な問題となりました。感染したというだけで「自業自得」や「加害者」とみなされ,社会的孤立や誹謗中傷に晒されるケースも報告されています。差別を恐れて検査や治療を避ける人が増えれば,感染拡大につながる恐れもあります。また,公衆衛生上の措置は,しばしば社会経済的に脆弱な立場にある人々に,より大きな負担を強いる傾向があります。例えば,ロックダウンによる収入減少や雇用喪失は,非正規労働者,貧困家庭,高齢者,障害者など,社会的弱者に深刻な影響を与えました。公衆衛生政策を立案・実施する際には,こうした人々への影響を十分に考慮し,不利益が一部の層に集中しないよう制度設計を行うことが求められます。
7.インフォデミックとリスク・コミュニケーション
パンデミックにおいて見逃せないもう一つの課題が,情報の扱いです。COVID-19をめぐっては,SNSやインターネット上で根拠のないデマや陰謀論が拡散し,インフォデミック(情報の氾濫による混乱)と呼ばれる現象が深刻化しました。例えば,「特定の食品や健康法でウイルスを防げる」といった誤情報や,ワクチンに関する陰謀論が人々の不安を煽り,感染対策への協力やワクチン接種率に悪影響を及ぼしました。さらに,政府や専門家からの公式発表であっても,マスクの効果や検査方針に関する見解が時期によって変化したり,国ごとに異なったりしたことで,人々の混乱や不信感を招く要因となりました。公衆衛生において,信頼性の高い情報を迅速かつ継続的に発信すること,そして多様な価値観を持つ市民と双方向のコミュニケーションを図りながら,リスク認知のギャップを埋めていくことが極めて重要です。
*
COVID-19パンデミックを通じて,私たちは公衆衛生上の危機における倫理的課題の広がりと深刻さを改めて痛感させられました。そこでは,個人の生命や尊厳の尊重と社会全体の安全や正義との間でせめぎ合いが生じ,単純な解決策は存在しません。さらにパンデミックという性質上,時間をかけた丁寧な社会的合意形成を行うことも,必ずしも容易ではありませんでした。しかし,本稿で論じたような課題を改めて認識することによって,たとえ危機の最中にあっても,冷静かつ公正な意思決定への道筋を見いだすことは可能です。ポストコロナ時代に向けては,医療従事者を含む社会全体がこうした教訓を共有し,透明性と連帯に基づく倫理観を共に築いていくことが求められます。それによって,将来再び起こり得る公衆衛生上の緊急事態に対して,私たちはより良いかたちで立ち向かうことができるでしょう。
今回のPOINT
・公衆衛生倫理においては,個人の生命・尊厳の尊重と社会全体の安全・正義との間でジレンマが生じ,単純な解決策はない。
・再来し得る公衆衛生上の危機に向けて,透明性と連帯に基づく倫理観の構築が求められる。
参考文献
1)Ann Intensive Care. 2021[PMID:34189634]
2)BMJ Glob Health. 2023[PMID:37793808]
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。