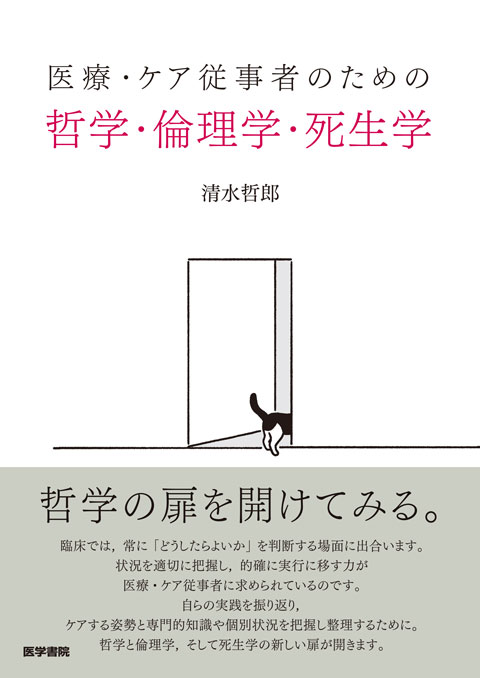応用倫理学入門
[第10回] 再生医療の倫理
連載 澤井 努
2025.06.10 医学界新聞:第3574号より
現在開催中の大阪・関西万博では,最先端の医療技術を象徴する展示として,大阪大学などが開発した「動くミニ心臓」が注目されています。これは後述するiPS細胞などを体外で培養して拍動する心臓組織を再現したもので,実際の心臓と同じようにリズミカルに動く様子が公開されています。この技術が今後さらに発展し,臨床応用が進めば,心不全をはじめとする難治性疾患に苦しむ患者に新たな治療手段を提供することが期待されます。かつて「夢の技術」と呼ばれた再生医療は,このような画期的な研究の積み重ねにより,実用化に向けて着実に前進していると言えるでしょう。
再生医療とは,損傷した細胞・組織・臓器の機能を回復させることを目的とした医療技術です。とりわけ注目されているのがiPS細胞です。体細胞に複数の遺伝子を導入して人工的に多能性を獲得させたこの細胞は,患者自身の細胞を使用することで免疫拒絶反応を抑えられると期待されています。
iPS細胞を用いた神経系疾患の臨床研究
2025年4月,実際にiPS細胞を用いたパーキンソン病の臨床研究が進行しているとの報道があり,根治が難しいとされてきた神経変性疾患においても,再生医療の実現性が高まっていることが示されました。以下では,Aさんの仮想事例を手がかりとして,再生医療が直面する代表的な倫理的課題について検討していきます。
30代前半のAさんは,数年前に若年性パーキンソン病を発症しました。動作緩慢や振戦などの症状が徐々に進行し,複数の薬物療法を試みても十分な改善が得られず,日常生活にも支障を来していました。そのような状況のなかで,主治医からiPS細胞を用いたパーキンソン病の臨床研究(治験)への参加を勧められます。主治医の説明によると,iPS細胞から作製したドーパミン神経細胞を脳内に移植することで,症状が大幅に改善する可能性があるようです。しかし,まだ研究段階であるため,長期的な安全性や有効性については十分な検証が行われていません。また,高額な費用や長期にわたる通院が必要になる可能性もあるとのことです。Aさんは治療への大きな期待を抱きつつも,未知のリスクに対する不安との間で揺れ動いています。
安全性と長期的予後の不確実性
再生医療は,細胞工学やゲノム編集技術の飛躍的な進歩を背景に,臨床応用に向けて急速に進展しており,その実用化が人類にもたらす恩恵は計り知れません。一方で,移植後に起こり得る長期的な変化を十分に追跡できる症例数は限られており,実用化に向けては,安全性と有効性を裏づけるデータが完全に揃っているとは言い切れない面もあります。例えば,体内に移植された細胞が腫瘍化して異常増殖したり,本来意図していた組織とは異なる組織に分化して臓器の機能を阻害したりするリスクがあります。また,免疫反応や炎症によって,二次的な障害が引き起こされる可能性も指摘されています。さらに,細胞の製造工程や輸送過程におけるわずかな変化が移植後の挙動に大きく影響することもあり,動物実験で安全性が確認された手法が,必ずしもヒトで同様に再現されるとは限りません。実際に,未承認の治療を海外で受ける「幹細胞ツーリズム」では,科学的に確立されていない治療による重篤な合併症が報告1)されており,安全性への懸念が抽象的な議論にとどまらないことを示しています。
こうした現状を踏まえると,Aさんのように症状の改善を強く望む患者であっても,科学的な検証が十分でない段階で,どこまでリスクを受け入れられるかという葛藤に直面せざるを得ません。医療従事者には,前臨床試験や既存の臨床データに基づいて,期待されるベネフィットと潜在的なリスクを正確かつ分かりやすく伝え,患者自身が適切な自己決定を行えるよう支援する責務があります。また,治験段階においては,長期的な経過を観察するための患者レジストリの整備や,...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。