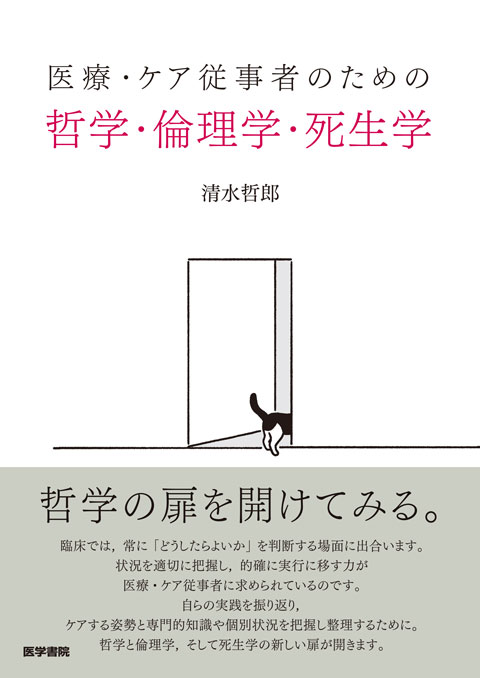応用倫理学入門
[第11回] 遺伝学の倫理
連載 澤井 努
2025.07.08 医学界新聞:第3575号より
遺伝子検査や治療技術の急速な進歩に伴い,医療者だけでなく社会全体が直面する倫理的課題も多様化しています。20世紀初頭,優生学は深刻な差別を招きましたが,最新技術にも同種の危険性が潜んでいると指摘されています。本稿では,着床前診断(Preimplantation Genetic Diagnosis:PGD)と消費者向け(Direct-to-Consumer:DTC)遺伝子検査に焦点を当てます。そして,優生思想や差別の再燃といった従来からの懸念に加え,遺伝情報の商業利用や消費者主導の医療選択など,近年浮上した課題も交えながら検討します。
PGDの倫理的課題
PGDとは,体外受精によって得られた胚(受精卵)を子宮に戻す前に遺伝子レベルで検査し,特定の遺伝的異常の有無を調べる技術です。主に重篤な遺伝性疾患を持たない胚を選んで移植し,子どもの病気の発症を避けることを目的としています。この技術は子どもが健康であってほしいという親の切実な願いを支援する一方で,倫理的懸念も少なくありません(PGDについては連載第4回も参照)。
「命の選別」につながる懸念
PGDが導入された当初から懸念されているのは,優生学の問題,つまりPGDが「命の選別」になってしまうのではないかという点です。遺伝子検査の結果を理由に胚を選別し,一部の胚は廃棄されます。このことが「特定の性質を持つ命を望まない」という否定的なメッセージを社会に与える可能性を生じさせます。また,PGDは国家主導の優生政策とは異なり,あくまで親の自主的選択によりますが,それでも「健常な子どもを産まなければならない」という暗黙の社会的圧力を生み,新たな差別や偏見につながる恐れがあります。宗教的・倫理的な観点からも,受精卵の段階とはいえ命(になり得る存在)を人為的に選別する行為自体に根強い反対意見があります。医療従事者も,この技術をどの範囲まで提供すべきかについて葛藤しています。
子どもの資質を親が選ぶ未来
PGDの適用範囲が重い病気を避けるという当初の目的からさらに拡大する可能性が,近年指摘されています。将来的には,才能や容姿といった子どもの資質を選択する技術へと発展する恐れもあります。当初は厳しい条件下で限定的に認められていたとしても,一度道が開かれれば,ニーズの高まりとともに制限が緩和される可能性があります。いわゆる「滑りやすい坂道(スリッパリー・スロープ)」の問題です。実際,海外では胚のゲノム情報を利用し,それぞれの胚が持つ将来の罹患リスクや能力傾向を数値(ポリジーンスコア)で表し,望ましい胚を順位付けするサービスまで登場しています。
しかし,大阪大学などの研究では,こうしたポリジーンスコアによる胚選別は信頼性がそもそも非常に低く,分析手法によって結果が大きく変動することが示されています1)。たとえ胚を選ぶこと自体に倫理的問題がなかったとしても,そして「生まれてくる子どもにはできるだけ幸福であってほしい」という親の願いを尊重するとしても,あまりに不確かなデータに基づいて胚を選ぶ行為がどれほど妥当なのかは,新たな倫理的懸念として生じます。PGDの適用範囲拡大は,技術的,社会的に望ましいとされる子どもの像を形成することになり,医療従事者はどこに境界線を引くべきか難しい判断を迫られています。
遺伝病保因者である夫婦の仮想事例
ある夫婦は共に重い遺伝病の保因者であり,自然妊娠では25%の確率で両親と同じ遺伝病を発症する子どもが生まれるためPGDを利用しました。胚を検査すると半数が疾患遺伝子を持っていたことから,夫婦は苦渋の思いで健康な胚のみを選びました。医師から病気のリスクをより低減する最新のスコアリング方法も勧められましたが,夫婦は病気でさえなければ十分として,これを拒否します。生まれた男...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
2026.01.13
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。