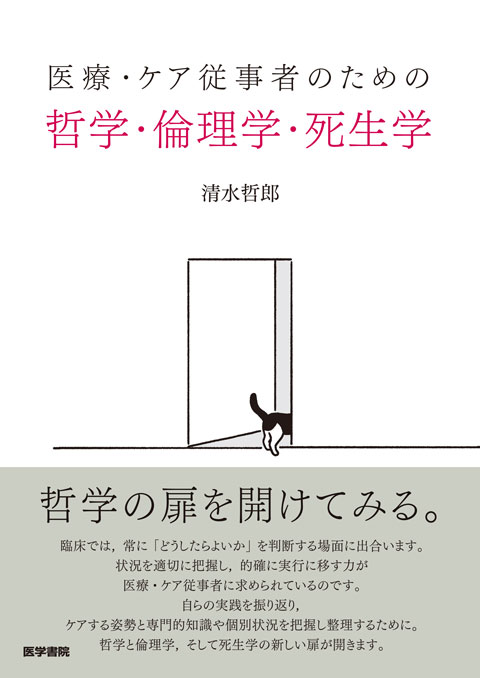応用倫理学入門
[第9回] 脳神経科学の倫理――脳への直接的な介入をする新技術が提起する課題
連載 澤井 努
2025.05.13 医学界新聞:第3573号より
近年,脳神経科学分野における急速な技術革新により,脳と外部機器を直接接続するブレイン・マシン・インターフェース(Brain-Machine Interface:BMI)や,深部脳刺激(Deep Brain Stimulation:DBS)などが,実際の臨床現場で応用され始めています。これらの技術は,難治性の運動障害や意思疎通に困難を抱える患者に対し,新たな治療や生活支援を提供する可能性を秘めています。その一方で,脳を直接的に操作・制御するこれらの技術は,プライバシーの保護,自己同一性や人格の尊厳の維持,治療適応範囲の拡大,インフォームド・コンセント(IC)の在り方など,従来の医療とは質的に異なる倫理的課題も提起しています。テクノロジーの利便性を最大限に活用しつつも,人間の尊厳を守り,公平で安全な利用を保証する視点が,医療従事者には求められます。本稿では,BMIとDBSに焦点を当てながら,脳神経科学技術(ニューロテクノロジー)の特徴を整理するとともに,それらに伴う主な倫理的課題を概観します。
BMI,DBSの概要と想定される懸念
BMIは,脳の神経活動を直接計測し,その信号を外部機器に伝達することで,コンピュータやロボットアームなどを制御する技術です。四肢麻痺を抱える患者がロボットアームや車椅子を操作する研究や,言語障害のある方が脳信号を用いて意思疎通を行う技術開発など,さまざまな応用が進められています。BMIに用いられる脳活動の計測手法には,頭皮上に電極を装着して脳波(EEG)のような電気的活動を計測する非侵襲的手法と,脳皮質上や深部に電極を埋め込むような侵襲的手法があり,それぞれの方法で精度とリスクが異なります。近年ではAI技術の進展により脳信号の解読精度が向上し,BMIの実用化が加速しています。
DBSは,脳の特定部位に電極を埋め込み,電気刺激を与えることで神経回路の活動を調整し,症状の改善を図る治療法です。主にパーキンソン病,本態性振戦,ジストニアなどの運動障害に対して用いられています。DBSは可逆的であり,刺激パラメータの調整が可能なため,患者の状態に応じた柔軟な対応が可能です。日本では2000年に保険適用となりました。
こうした技術は,脳を直接または間接的に操作する点で,従来の医療行為とは異なる特徴を持ちます。特に脳への直接介入は,身体的リスクのみならず,人格や精神的側面への影響をもたらす可能性があると懸念されており,倫理的に慎重な検討が必要とされます。
倫理的課題
プライバシーと情報セキュリティの課題
BMIにおいては,脳波や神経活動を解析することで,個人の思考や意思を読み取る可能性があります。現時点では具体的な思考内容を完全に読み取ることは難しいとされていますが,脳の活動パターンから個人の感情や意思決定の傾向を推測する研究が進展しています。また,BMIと外部機器がネットワークに接続される場合,サイバーセキュリティの観点から,不正アクセスやデータ漏洩のリスクが高まります。脳神経データは極めてセンシティブであるため厳重な管理が必要です。医療従事者としては,患者の脳神経データを含む個人情報を厳重に管理するとともに,利用目的や研究終了後のデータの廃棄方法などを明確化し,患者から適切にICを取得することが求められます。
自己同一性および行為者性への影響
DBSはパーキンソン病などの運動障害の症状を劇的に改善することがありますが,刺激の設定によって患者の情動や衝動性が変化し,結果として「自分らしさ」を失ったという症例報告もあります1)。また,BMIに関しても,外部機器を介した意思決定や行動の制御プロセスが,患者自身の主観的な「行為者性(agency)」を損なう可能性があります。患者本人は「自分が操作している」と感じていても,実際には機械のアルゴリズムや外部の要因がその意思決定に大...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。