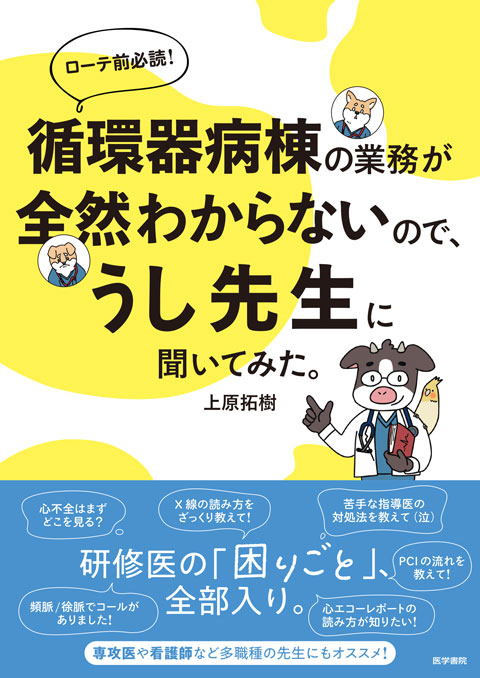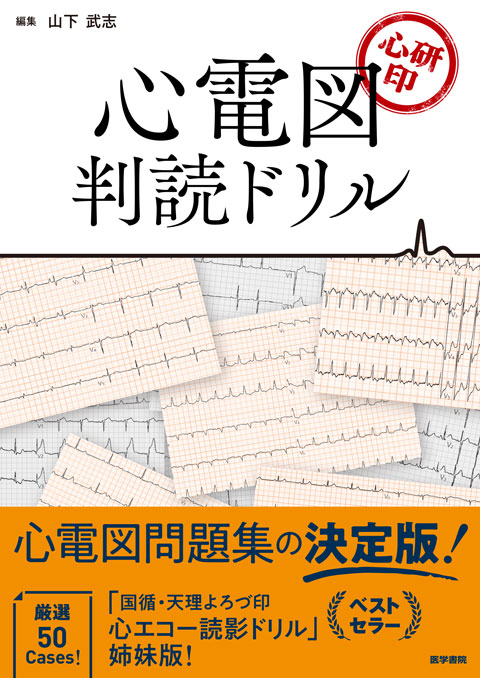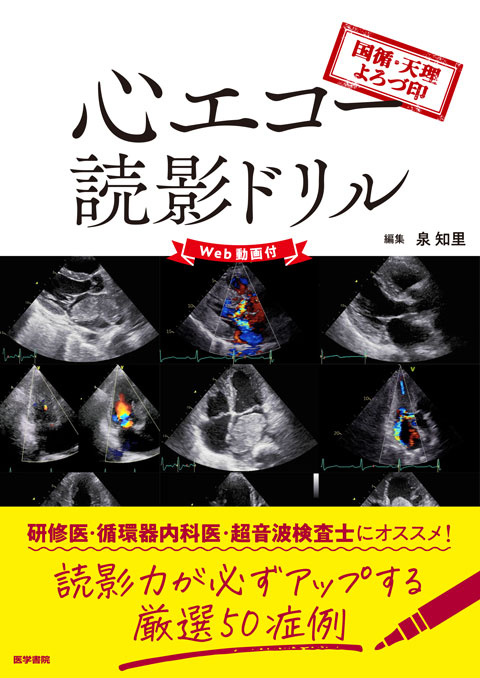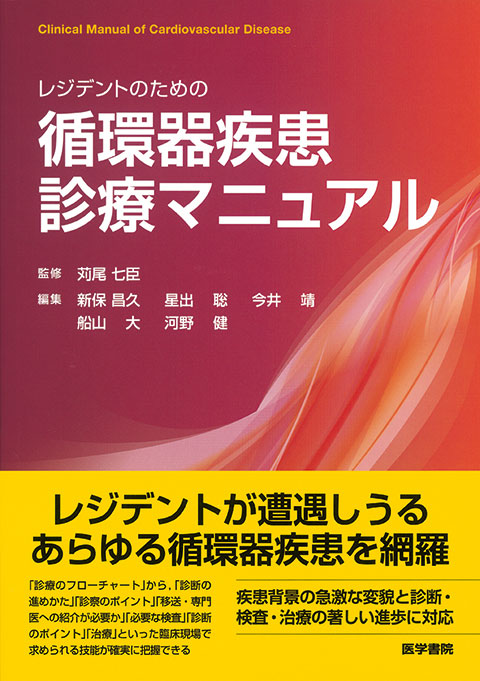循環器内科の学びかた・教えかたを先輩に聞いてみた。
対談・座談会 佐藤宏行,上原拓樹
2024.05.14 医学界新聞(通常号):第3561号より

循環器内科領域は,心不全・不整脈・虚血性心疾患・弁膜症などの多様な疾患を包含し,またその診断・治療に有効なモダリティも多岐にわたることから,勉強方法に迷う研修医の方が多いのではないでしょうか。そうした研修医をサポートすべく,このたび『循環器病棟の業務が全然わからないので,うし先生に聞いてみた。』(医学書院)が出版されました。そこで今回,X(旧・Twitter),YouTubeなどのSNSにて「うし先生」として発信を続ける同書執筆者の上原拓樹先生と,循環器領域において研修医教育に長年携わってきた佐藤宏行先生との対談を通じて,ローテート中の過ごし方や研修医としての心得を伺いました。
佐藤 今回の対談に臨むに当たって上原先生が執筆された『循環器病棟の業務が全然わからないので,うし先生に聞いてみた。』を読ませていただきました。循環器内科をローテート中の研修医が抱きやすい100個の疑問に対してきめ細かな解説がされていて,私自身,大変勉強になりました。そもそも上原先生は,循環器内科のどの部分に惹かれたのでしょうか。
上原 デバイスや薬物療法の進歩に伴い,疾患によっては状態の悪い方でも元気に歩いて自宅へ帰れるほどに治療成績が近年向上してきたことが,循環器内科を選んだ理由の一つです。また,終末期医療や慢性期の予防にも携われるなど,提供できる医療の形に幅があり,どれだけ学んでも尽きることがない点に惹かれました。
佐藤 自らの手で治療介入ができる側面もあれば,心不全や心房細動の予防,動脈硬化のリスク管理,救急医療など,循環器の知識はさまざまな場面で役に立ちやすいですよね。患者数も他の診療科と比較して多いために,地域連携の面でも循環器医は活躍しやすいと言えます。
上原 そうですね。将来的に循環器内科へ進まない方にとっても,こうした幅広い循環器の知識は有用でしょう。
循環器内科をローテートする研修医は何に困っている?
上原 一方で,今話題にしたように循環器内科が取り扱う領域は広大であり,全ての知識をカバーすることはなかなか難しいです。
佐藤 その点では,日本循環器学会が無料で公開するガイドラインは心強い味方ですよね。
上原 ええ。大変わかりやすく内容もまとまっていて,循環器内科医として診療に当たる際はとても頼りになる代物です。けれども研修医にとって使いやすいものかと問われるとやや疑問を抱きます。例えば心不全の患者さんを受け持った際,心房細動や心筋症の可能性も考えた時に,それぞれの疾患に対してガイドラインが存在することから,欲しい情報にすぐにたどり着けず,四苦八苦しながら調べている姿をよく見かけました。診療ガイドラインはとても有用ですが,循環器を学ぶための入り口としてはやや不向きではと個人的に考えています。
佐藤 難しい問題ですね。ただ,その他に頼れる質の担保されたアクセスしやすい資料があまりないというのも事実です。家に帰って一息ついた時や,当直の空き時間などに気軽に目を通せる資料が手元にあると,ベッドサイドでの研修が面白く感じるようになると思います。座学と実践のバランスをどう保っていくかが大事なのでしょう。
上原 まさにそこが今回出版した書籍でコンセプトに据えた点です。循環器内科のローテート時に必要な最低限の知識を網羅し,パッと理解できるよう「臨床に近い」書籍になることをめざしてまとめました。
佐藤 「臨床に近い」とはどういう意味ですか。
上原 臨床現場での肌感覚と言い換えられるかもしれません。臨床医が何を考えて診療に当たっているのかという思考の言語化を目標にしました。例えば直接経口抗凝固薬(DOAC)を使うとなった時に,ガイドラインを参照すると選択できる4剤(ダビガトラン,リバーロキサバン,アピキサバン,エドキサバン)は並列表記されていて,経験のない研修医は「結局どれを使えばいいのだろう」と迷ってしまいます。ですので今回まとめた書籍では,4剤に関するエビデンスの紹介と併せて,私がどう考えて薬剤選択しているかを具体的に解説するようにしました。
研修医のキャラクターに合わせた個別化指導
佐藤 では教える側の目線から循環器内科の世界を見たらどうでしょう。研修医が循環器内科をローテートする期間は数週間です。教えることが膨大だからこそ,何を,どこまで教えるべきか悩む指導医も多いはずです。前任の勤医協中央病院で上原先生が研修医教育に深く携わられていた際,意識していた点はありましたか。
上原 ローテーションしてきてからの2~4週間程度は投資期間だととらえて,各研修医のキャラクターの把握に時間をかけることです。具体的には,患者さんとの付き合い方のスタイル,循環器内科との相性,ローテート中にどんなことを勉強したいのかなど,研修医と対話する機会を設けながら判断し,教える内容や受け持ち患者数(3~6人程度)に差をつけて指導するようにしていました。
佐藤 患者さんを割り当てる時は,さまざまな疾患の方を受け持てるようにされているでしょうか。と言うのも,以前勤めていた手稲渓仁会病院においては各研修医の関心度合いに基づいて同じく3~6人の患者を受け持ってもらっており,心筋梗塞後の二次予防を考慮すべき患者さん,Stanford B型の大動脈解離の患者さん,心不全の患者さん,術前の弁膜症の精査の患者さんなどのバリエーションを持たせていたからです。そうした診療を通じて,マネジメント時の優先順位のつけ方や,患者家族とのやり取りも学んでもらおうとの狙いがありました。
上原 勤医協中央病院でも同様のスタイルを取っており,多彩な症例から学びを得られるように振り分けていました。
佐藤 や...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

上原 拓樹(うえはら・ひろき)氏 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室
2015年北大医学部卒。勤医協中央病院で初期研修を修了。17年より同院循環器内科に所属。循環器診療と研修医教育を行う傍ら,SNSで「うし先生」として初学者向けの情報発信を行い,X(@muhammedi_ali)のフォロワーは1万4000人,YouTubeのチャンネル登録者数は1万2000人を超える。24年4月より現職。著書に『循環器病棟の業務が全然わからないので,うし先生に聞いてみた。』(医学書院)。

佐藤 宏行(さとう・ひろゆき)氏 東北大学大学院医学系研究科 先制循環器医療学寄附講座 助手
2011年東北大卒。武蔵野赤十字病院にて初期研修,内科後期研修修了後,14年手稲渓仁会病院循環器内科。22年より現職。U-40心不全ネットワーク2022-23年代表幹事。編著に『循環器のトビラ』(メディカル・サイエンス・インターナショナル)。X ID:@foreverhero0819
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。