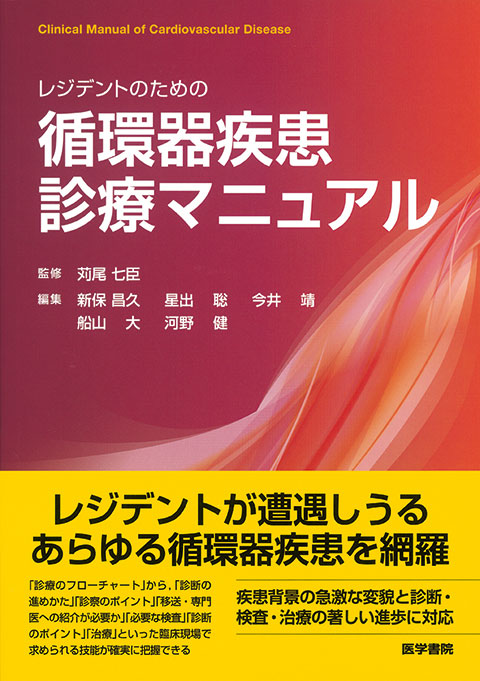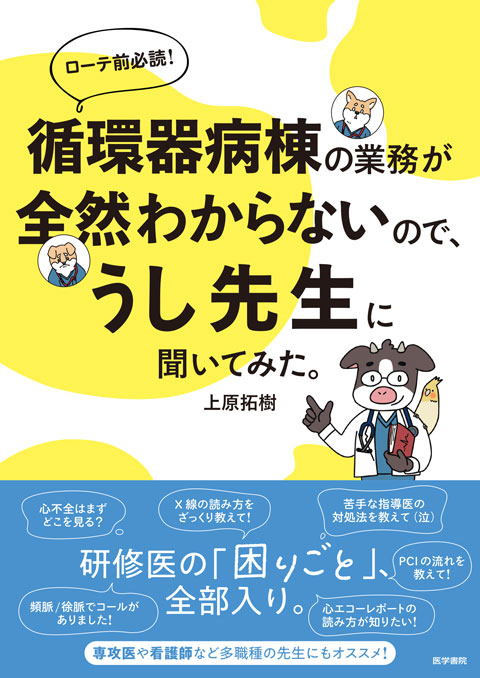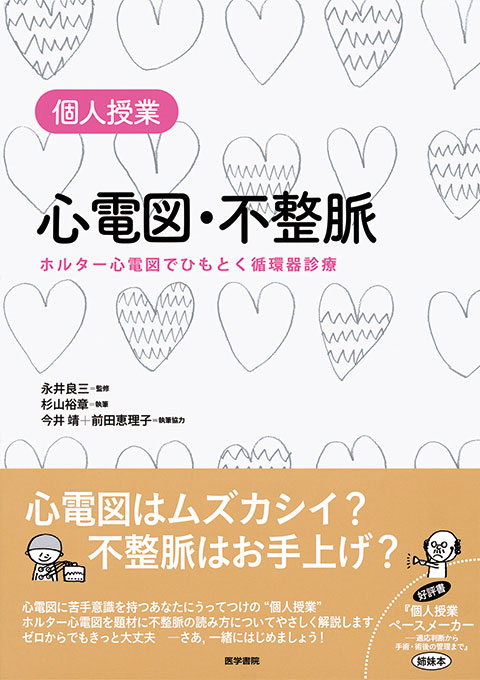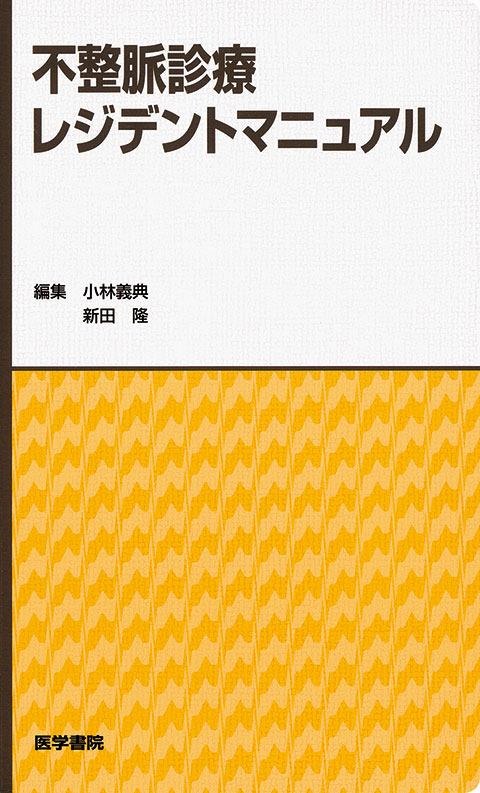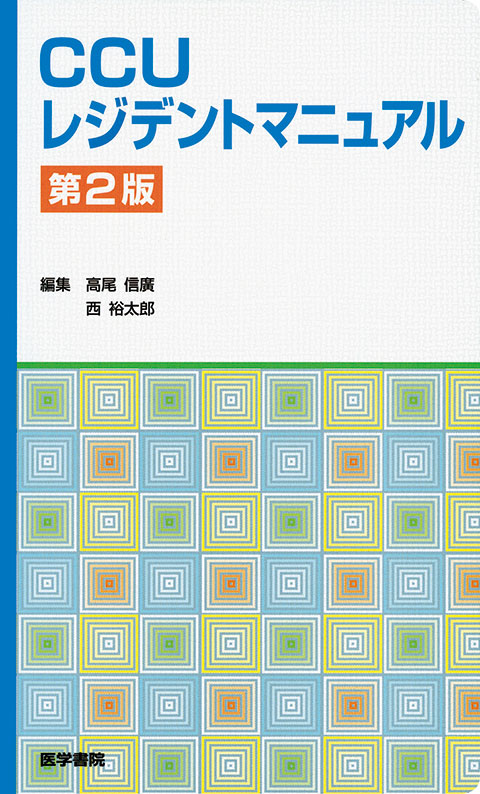レジデントのための循環器疾患診療マニュアル
循環器診療の最新かつ実践的な情報を網羅!
もっと見る
高齢化社会の進展と診断・治療の技術進歩により、循環器疾患の診療は近年めまぐるしい変化を遂げている。本書はその最新の状況をふまえ、レジデントが遭遇しうる主な循環器疾患について、問診、検査、診断から治療(一般的な薬物治療も含む)まで、研修医に必要な実践的診療情報を網羅し、最低限知っておきたい臨床上のノウハウについてポイントを絞って解説した。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
近年,人口の急激な高齢化に伴い,循環器疾患罹患者はますます増加しています.2017年の厚生労働省人口動態統計では,心疾患,脳血管疾患が,日本人の死因として悪性新生物に次いで上位となっています.特に心不全患者の増加は著しく,爆発的な広がりのイメージから「心不全パンデミック」という言葉も聞かれます.このように循環器内科の診療業務がますます過密化する中,われわれはよりよい医療を提供するため,日々の診療にあたっています.
循環器診療は,予防から急性期治療,さらに慢性期管理に至る一連の流れの中にあります.診療においては,「どうして,この方に,このタイミングで発症してしまったのだろうか」と疑問を持つことが重要です.つまり,個人の発症機序を考えることが,疾患病態への執着になり,新たな発見につながります.循環器疾患を患者生涯の時間軸でとらえて,個々の疾患に対処することが大切です.
本書は自治医科大学循環器内科のメンバーが,われわれの循環器センターにおいて行っている循環器疾患の診断と治療を短時間で習得してもらうため,レジデント向けの簡便なマニュアルとしてまとめたものです.研修医に必要な実践的な診療情報を網羅し,レジデントが最低限知っておきたい臨床上のノウハウをピンポイントで紹介しています.「第2章 疾患・症状のマネジメント」ではそれぞれ「診療のフローチャート」を示し,ガイドラインの内容も押さえつつ,診断,検査,治療について,図表を多用し臨床上実践的な事項に焦点を絞り,できる限りコンパクトにまとめてあります.忙しい診療業務の中,疾患病態のエッセンスを効果的に習得するには最適な1冊であると思います.多忙なレジデントの皆さんにはまさに「必携の書」といえるでしょう.
2019年1月
苅尾 七臣
近年,人口の急激な高齢化に伴い,循環器疾患罹患者はますます増加しています.2017年の厚生労働省人口動態統計では,心疾患,脳血管疾患が,日本人の死因として悪性新生物に次いで上位となっています.特に心不全患者の増加は著しく,爆発的な広がりのイメージから「心不全パンデミック」という言葉も聞かれます.このように循環器内科の診療業務がますます過密化する中,われわれはよりよい医療を提供するため,日々の診療にあたっています.
循環器診療は,予防から急性期治療,さらに慢性期管理に至る一連の流れの中にあります.診療においては,「どうして,この方に,このタイミングで発症してしまったのだろうか」と疑問を持つことが重要です.つまり,個人の発症機序を考えることが,疾患病態への執着になり,新たな発見につながります.循環器疾患を患者生涯の時間軸でとらえて,個々の疾患に対処することが大切です.
本書は自治医科大学循環器内科のメンバーが,われわれの循環器センターにおいて行っている循環器疾患の診断と治療を短時間で習得してもらうため,レジデント向けの簡便なマニュアルとしてまとめたものです.研修医に必要な実践的な診療情報を網羅し,レジデントが最低限知っておきたい臨床上のノウハウをピンポイントで紹介しています.「第2章 疾患・症状のマネジメント」ではそれぞれ「診療のフローチャート」を示し,ガイドラインの内容も押さえつつ,診断,検査,治療について,図表を多用し臨床上実践的な事項に焦点を絞り,できる限りコンパクトにまとめてあります.忙しい診療業務の中,疾患病態のエッセンスを効果的に習得するには最適な1冊であると思います.多忙なレジデントの皆さんにはまさに「必携の書」といえるでしょう.
*
個人が抱える疾患を包括的にとらえ,最善の医療を提供するため「目の前の1例に全力を尽くす」ことを実践し,日々の診療にあたる自治医科大学循環器内科の診療ノウハウを詰め込んだ本書が,読者の皆さまのお役に立てば幸いです.2019年1月
苅尾 七臣
目次
開く
第1章 序章
1 循環器疾患のみかた,考えかた
第2章 疾患・症状のマネジメント
1 問診・診察のポイント
2 入院患者の基本指示,医療スタッフとの連携
3 狭心症
4 急性冠症候群 急性心筋梗塞,不安定狭心症
5 急性心不全
6 慢性心不全
7 心筋症 拡張型心筋症,肥大型心筋症,不整脈源性右室心筋症,
左室緻密化障害など
8 心臓サルコイドーシス・アミロイドーシス
9 心臓弁膜症
10 感染性心内膜炎
11 心筋炎,心膜疾患,たこつぼ心筋症
12 成人先天性心疾患
13 不整脈
14 大動脈瘤,大動脈解離
15 閉塞性動脈硬化症,急性動脈閉塞
16 高血圧症
17 肺血栓塞栓症,深部静脈血栓症
18 肺高血圧症
19 睡眠時無呼吸症候群
第3章 特別な配慮を要する患者
1 慢性腎不全,血液透析症例
2 妊娠・周産期管理
3 高齢者
4 がん診療と循環器疾患
第4章 循環器系検査・手技
1 血圧の評価 診察室血圧,家庭血圧,24時間血圧計
2 心電図,ホルター心電図
3 運動負荷心電図
4 循環器疾患のためのX線読影法
5 心エコー
6 血管エコー,血管機能検査
7 心肺運動負荷試験(CPX)の実際と解釈
8 心臓核医学検査(SPECT)
9 心臓CT,心臓MRI
10 中心静脈穿刺・カテーテル挿入のコツとピットフォール
11 冠動脈造影検査,右心・左心カテーテル検査
12 電気生理学的検査
13 副腎静脈サンプリング
14 head-up tilt(HUT)試験
第5章 循環器疾患に対する治療
1 生活習慣病,冠危険因子の管理 高血圧,脂質代謝異常,糖尿病,肥満
2 冠動脈インターベンション
3 心臓血管外科との連携 冠動脈バイパス術,弁膜症手術
4 急性期管理における循環器作動薬の使用法
5 不整脈に対する薬物治療,電気的除細動
6 ペースメーカ
7 ICD,CRT
8 カテーテルアブレーション
9 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)
10 補助循環 IABP,PCPS
11 酸素療法,人工呼吸器(NPPVも含む)
12 心臓リハビリテーション
第6章 レジデント 押さえておくべき業務・診療のポイント
1 カルテ・サマリー作成
2 インフォームドコンセント
3 術前コンサルト 非心臓手術における心臓疾患のリスク評価
4 放射線被曝とその防護・低減策
5 医療安全 リスク管理とインシデント・アクシデントへの対応
索引
1 循環器疾患のみかた,考えかた
第2章 疾患・症状のマネジメント
1 問診・診察のポイント
2 入院患者の基本指示,医療スタッフとの連携
3 狭心症
4 急性冠症候群 急性心筋梗塞,不安定狭心症
5 急性心不全
6 慢性心不全
7 心筋症 拡張型心筋症,肥大型心筋症,不整脈源性右室心筋症,
左室緻密化障害など
8 心臓サルコイドーシス・アミロイドーシス
9 心臓弁膜症
10 感染性心内膜炎
11 心筋炎,心膜疾患,たこつぼ心筋症
12 成人先天性心疾患
13 不整脈
14 大動脈瘤,大動脈解離
15 閉塞性動脈硬化症,急性動脈閉塞
16 高血圧症
17 肺血栓塞栓症,深部静脈血栓症
18 肺高血圧症
19 睡眠時無呼吸症候群
第3章 特別な配慮を要する患者
1 慢性腎不全,血液透析症例
2 妊娠・周産期管理
3 高齢者
4 がん診療と循環器疾患
第4章 循環器系検査・手技
1 血圧の評価 診察室血圧,家庭血圧,24時間血圧計
2 心電図,ホルター心電図
3 運動負荷心電図
4 循環器疾患のためのX線読影法
5 心エコー
6 血管エコー,血管機能検査
7 心肺運動負荷試験(CPX)の実際と解釈
8 心臓核医学検査(SPECT)
9 心臓CT,心臓MRI
10 中心静脈穿刺・カテーテル挿入のコツとピットフォール
11 冠動脈造影検査,右心・左心カテーテル検査
12 電気生理学的検査
13 副腎静脈サンプリング
14 head-up tilt(HUT)試験
第5章 循環器疾患に対する治療
1 生活習慣病,冠危険因子の管理 高血圧,脂質代謝異常,糖尿病,肥満
2 冠動脈インターベンション
3 心臓血管外科との連携 冠動脈バイパス術,弁膜症手術
4 急性期管理における循環器作動薬の使用法
5 不整脈に対する薬物治療,電気的除細動
6 ペースメーカ
7 ICD,CRT
8 カテーテルアブレーション
9 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)
10 補助循環 IABP,PCPS
11 酸素療法,人工呼吸器(NPPVも含む)
12 心臓リハビリテーション
第6章 レジデント 押さえておくべき業務・診療のポイント
1 カルテ・サマリー作成
2 インフォームドコンセント
3 術前コンサルト 非心臓手術における心臓疾患のリスク評価
4 放射線被曝とその防護・低減策
5 医療安全 リスク管理とインシデント・アクシデントへの対応
索引
書評
開く
よく遭遇する病態・疾病の診療をフローチャートやチェックリストも用いてわかりやすく整理
書評者: 細田 瑳一 (自治医大名誉教授/公益財団法人政策医療振興財団理事長)
本書は,自治医大循環器内科で現在レジデントを指導している教官が,それぞれの経験を踏まえて,比較的よく遭遇する病態・疾病について,総合的診療,検査処置,診断基準,病型,重症度分類,ガイドライン,そして標準的治療の選択と長期予後を判定する試験結果までを整理した実用的診療マニュアルである。各疾患について記録すべきポイントを箇条書きにして概説し,次に診療のフローチャートを掲げ,診療と心電図,X線検査,血液検査,カテーテル検査や心筋生検,心エコー,核医学検査などの主要検査を挙げ,初期対応と治療の選択,特に酸素吸入,静脈確保,カテーテル治療や外科的治療のタイミングと薬物療法の選択,治療開始後の変化の記録,治療効果の評価法,退院時のチェックリストなどが丁寧に記述されている。
診療録,特にそのまとめや紹介者への報告を書く上でも参考になる。例えば,パンデミックと叫ばれる急性心不全と慢性心不全の項では,急性心不全の原因疾患とそれぞれの特異的な治療,心不全増悪の誘因,右心不全と左心不全の症状の違いの表,Framingham criteriaによる診断基準,クリニカルシナリオによる入院時管理,CS1~5の分類(初期評価と治療)および治療の目標など多くの図表で各病期の治療を選択して,その効果を評価させようとしている。近年増加し,治療法も進んでいる肺血栓塞栓症,深部静脈血栓症,肺高血圧症,睡眠時無呼吸症候群などについても詳しく記述されている。特別な配慮を要する患者として,慢性腎不全・血液透析症例,がんと循環器疾患の合併,高齢者の診療も取り上げられている。特に高齢者での認知機能障害と総合機能評価(CGA7)は日常必須の常識である。検査手技,電気生理検査,カテーテルの手技,ペースメーカ,ICDやCRT,補助循環の適応,管理も,欠かせない手技である。リハビリテーションについては,外来・在宅診療で今後ますます重要になる。
最後に,このマニュアルでは精神心理的問題が,チーム医療でのコミュニケーションの項で取り上げられているが,インフォームドコンセントの説明や,医療者と患者・家族とのコミュニケーションには,精神心理的配慮が重要である。対等の人間としての対話と信頼関係を醸成する行動(Humanitude)が常に実践されるべきである。レジデントは,地域医療の立場から,総合診療としてのシステムレビューの徹底や,健康の回復・維持・増進を目標とする姿勢を身につけるべきである。そのことに関連して,循環器領域の疾患と関連の深い呼吸器疾患,脳卒中,糖尿病,腎障害などとともに,その他の急性関連重症疾患として取り上げ,注意を喚起することが望ましい。監修者の意図にもそのことが含まれているようであるが,わが国の医療が専門技術偏重になっている現状を反省し,医療職の研修では常に住民の保健健康増進を総合的に考える姿勢を養うように努めなければならない。
書評者: 細田 瑳一 (自治医大名誉教授/公益財団法人政策医療振興財団理事長)
本書は,自治医大循環器内科で現在レジデントを指導している教官が,それぞれの経験を踏まえて,比較的よく遭遇する病態・疾病について,総合的診療,検査処置,診断基準,病型,重症度分類,ガイドライン,そして標準的治療の選択と長期予後を判定する試験結果までを整理した実用的診療マニュアルである。各疾患について記録すべきポイントを箇条書きにして概説し,次に診療のフローチャートを掲げ,診療と心電図,X線検査,血液検査,カテーテル検査や心筋生検,心エコー,核医学検査などの主要検査を挙げ,初期対応と治療の選択,特に酸素吸入,静脈確保,カテーテル治療や外科的治療のタイミングと薬物療法の選択,治療開始後の変化の記録,治療効果の評価法,退院時のチェックリストなどが丁寧に記述されている。
診療録,特にそのまとめや紹介者への報告を書く上でも参考になる。例えば,パンデミックと叫ばれる急性心不全と慢性心不全の項では,急性心不全の原因疾患とそれぞれの特異的な治療,心不全増悪の誘因,右心不全と左心不全の症状の違いの表,Framingham criteriaによる診断基準,クリニカルシナリオによる入院時管理,CS1~5の分類(初期評価と治療)および治療の目標など多くの図表で各病期の治療を選択して,その効果を評価させようとしている。近年増加し,治療法も進んでいる肺血栓塞栓症,深部静脈血栓症,肺高血圧症,睡眠時無呼吸症候群などについても詳しく記述されている。特別な配慮を要する患者として,慢性腎不全・血液透析症例,がんと循環器疾患の合併,高齢者の診療も取り上げられている。特に高齢者での認知機能障害と総合機能評価(CGA7)は日常必須の常識である。検査手技,電気生理検査,カテーテルの手技,ペースメーカ,ICDやCRT,補助循環の適応,管理も,欠かせない手技である。リハビリテーションについては,外来・在宅診療で今後ますます重要になる。
最後に,このマニュアルでは精神心理的問題が,チーム医療でのコミュニケーションの項で取り上げられているが,インフォームドコンセントの説明や,医療者と患者・家族とのコミュニケーションには,精神心理的配慮が重要である。対等の人間としての対話と信頼関係を醸成する行動(Humanitude)が常に実践されるべきである。レジデントは,地域医療の立場から,総合診療としてのシステムレビューの徹底や,健康の回復・維持・増進を目標とする姿勢を身につけるべきである。そのことに関連して,循環器領域の疾患と関連の深い呼吸器疾患,脳卒中,糖尿病,腎障害などとともに,その他の急性関連重症疾患として取り上げ,注意を喚起することが望ましい。監修者の意図にもそのことが含まれているようであるが,わが国の医療が専門技術偏重になっている現状を反省し,医療職の研修では常に住民の保健健康増進を総合的に考える姿勢を養うように努めなければならない。