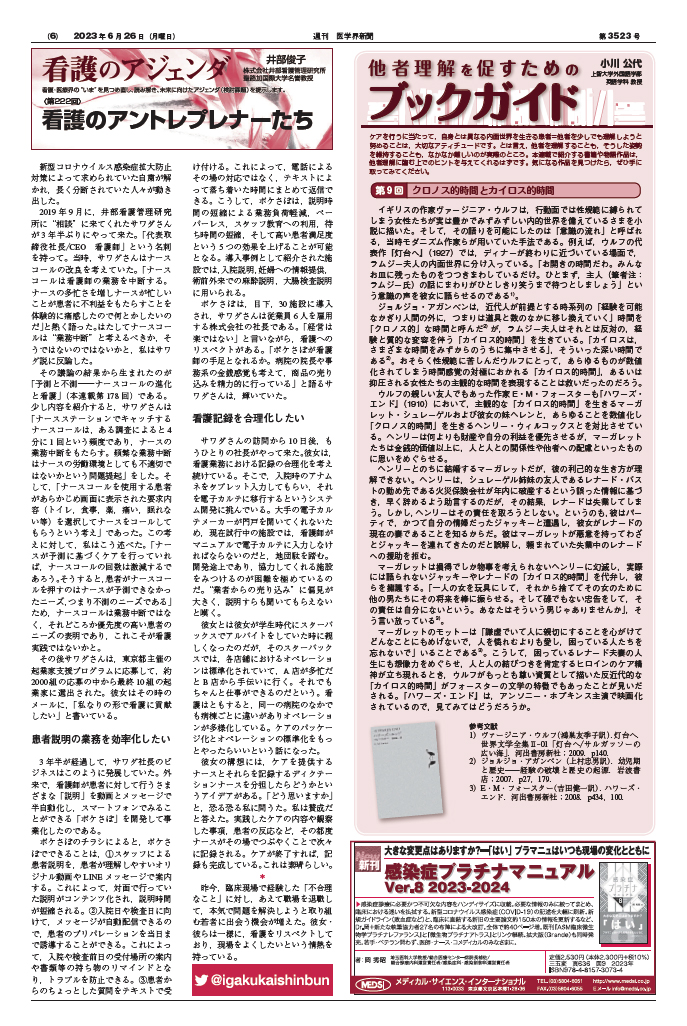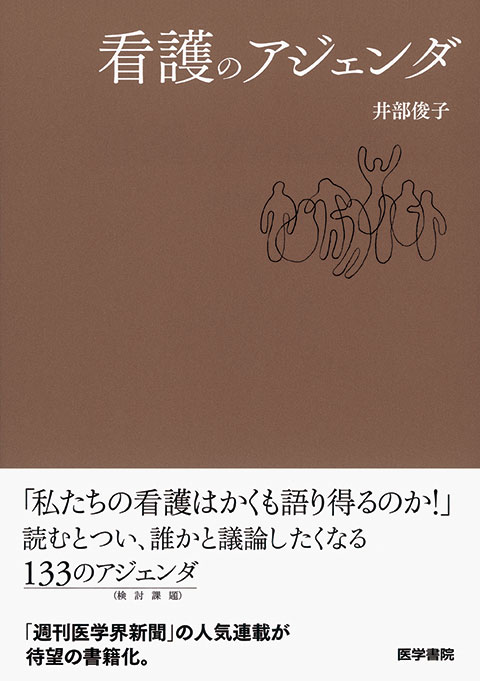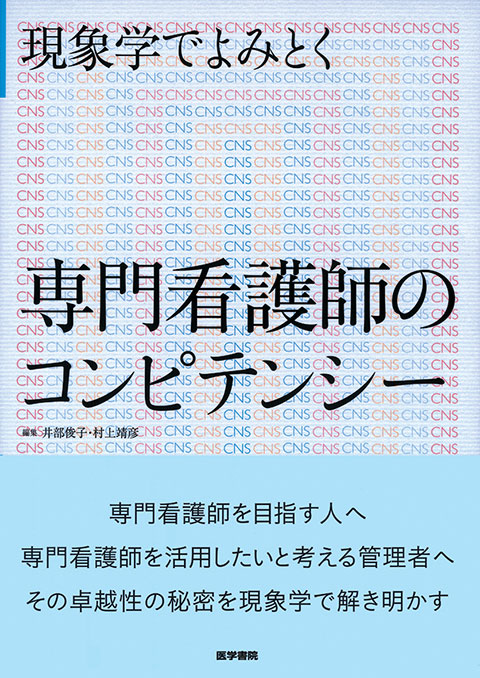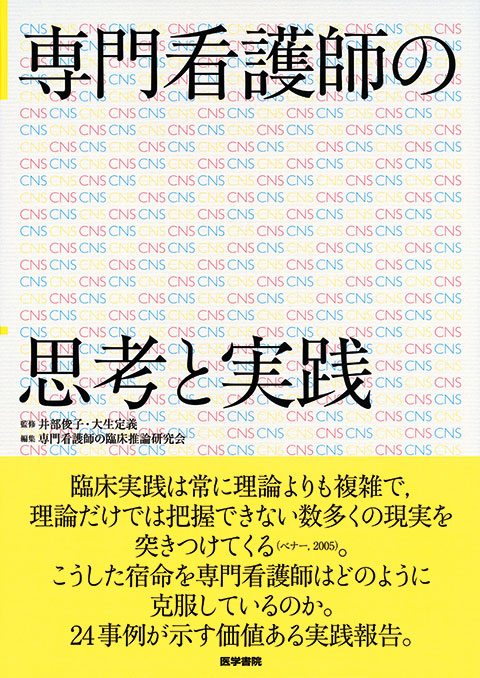看護のアジェンダ
[第222回] 看護のアントレプレナーたち
連載 井部俊子
2023.06.26 週刊医学界新聞(看護号):第3523号より
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策によって求められていた自粛が解かれ,長く分断されていた人々が動き出した。
2019年9月に,井部看護管理研究所に“相談”に来てくれたサワダさんが3年半ぶりにやって来た。「代表取締役社長/CEO 看護師」という名刺を持って。当時,サワダさんはナースコールの改良を考えていた。「ナースコールは看護師の業務を中断する。ナースの多忙さを増しナースが忙しいことが患者に不利益をもたらすことを体験的に痛感したので何とかしたいのだ」と熱く語った。はたしてナースコールは“業務中断”と考えるべきか,そうではないのではないかと,私はサワダ説に反論した。
その議論の結果から生まれたのが「予測と不測――ナースコールの進化と看護」(本連載第178回)である。少し内容を紹介すると,サワダさんは「ナースステーションでキャッチするナースコールは,ある調査によると4分に1回という頻度であり,ナースの業務中断をもたらす。頻繁な業務中断はナースの労働環境としても不適切ではないかという問題提起」をした。そして,「ナースコールを使用する患者があらかじめ画面に表示された要求内容(トイレ,食事,薬,痛い,眠れない等)を選択してナースをコールしてもらうという考え」であった。この考えに対して,私はこう述べた。「ナースが予測に基づくケアを行っていれば,ナースコールの回数は激減するであろう。そうすると,患者がナースコールを押すのはナースが予測できなかったニーズ,つまり不測のニーズである」ため,ナースコールは業務中断ではなく,それどころか優先度の高い患者のニーズの表明であり,これこそが看護実践ではないかと。
その後サワダさんは,東京都主催の起業家支援プログラムに応募して,約2000組の応募の中から最終10組の起業家に選出された。彼女はその時のメールに,「私なりの形で看護に貢献したい」と書いている。
患者説明の業務を効率化したい
3年半が経過して,サワダ社長のビジネスはこのように発展していた。外来で,看護師が患者に対して行うさまざまな「説明」を動画とメッセージで半自動化し,スマートフォンでみることができる「ポケさぽ」を開発して事業化したのである。
ポケさぽのチラシによると,ポケさぽでできることは,①スタッフによる患者説明を,患者が理解しやすいオリジナル動画やLINEメッセージで案内する。これによって,対面で行っていた説明がコンテンツ化され,説明時間が短縮される。②入院日や検査日に向けて,メッセージが自動配信できるので,患者のプリパレーションを当日まで誘導することができる。これによって,入院や検査前日の受付場所の案内や書類等の持ち物のリマインドとなり,トラブルを防止できる。③患者からのちょっとした質問をテキストで受け付ける。これによって,電話によるその場の対応ではなく,テキストによって落ち着いた時間にまとめて返信できる。こうして,ポケさぽは,説明時間の短縮による業務負荷軽減,ペーパーレス,スタッフ教育への利用,待ち時間の短縮,そして高い患者満足度という5つの効果を上げることが可能となる。導入事例として紹介された施設では,入院説明,妊婦への情報提供,術前外来での麻酔説明,大腸検査説明に用いられる。
ポケさぽは,目下,30施設に導入され,サワダさんは従業員6人を雇用する株式会社の社長である。「経営は楽ではない」と言いながら,看護へのリスペクトがある。「ポケさぽが看護師の手足となれるか。病院の院長や事務系の金銭感覚も考えて,商品の売り込みを精力的に行っている」と語るサワダさんは,輝いていた。
看護記録を合理化したい
サワダさんの訪問から10日後,もうひとりの社長がやって来た。彼女は,看護業務における記録の合理化を考え続けている。そこで,入院時のアナムネをタブレット入力してもらい,それを電子カルテに移行するというシステム開発に挑んでいる。大手の電子カルテメーカーが門戸を開いてくれないため,現在試行中の施設では,看護師がマニュアルで電子カルテに入力しなければならないのだと,地団駄を踏む。開発途上であり,協力してくれる施設をみつけるのが困難を極めているのだ。“業者からの売り込み”に偏見が大きく,説明すらも聞いてもらえないと嘆く。
彼女とは彼女が学生時代にスターバックスでアルバイトをしていた時に親しくなったのだが,そのスターバックスでは,各店舗におけるオペレーションは標準化されていて,A店が多忙だとB店から手伝いに行く。それでもちゃんと仕事ができるのだという。看護はともすると,同一の病院のなかでも病棟ごとに違いがありオペレーションが多様化している。ケアのパッケージ化とオペレーションの標準化をもっとやったらいいという話になった。
彼女の構想には,ケアを提供するナースとそれらを記録するディクテーションナースを分担したらどうかというアイデアがある。「どう思いますか」と,恐る恐る私に問うた。私は賛成だと答えた。実践したケアの内容や観察した事項,患者の反応など,その都度ナースがその場でつぶやくことで次々に記録される。ケアが終了すれば,記録も完成している。これは素晴らしい。
*
昨今,臨床現場で経験した「不合理なこと」に対し,あえて職場を退職して,本気で問題を解決しようと取り組む若者に出会う機会が増えた。彼女・彼らは一様に,看護をリスペクトしており,現場をよくしたいという情熱を持っている。
関連書籍
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。