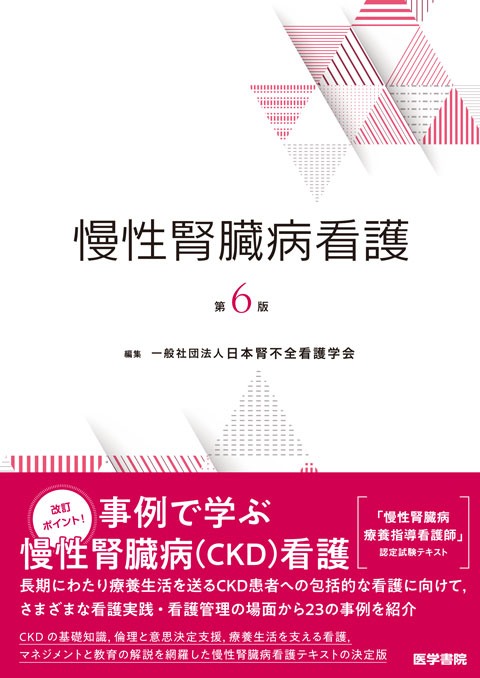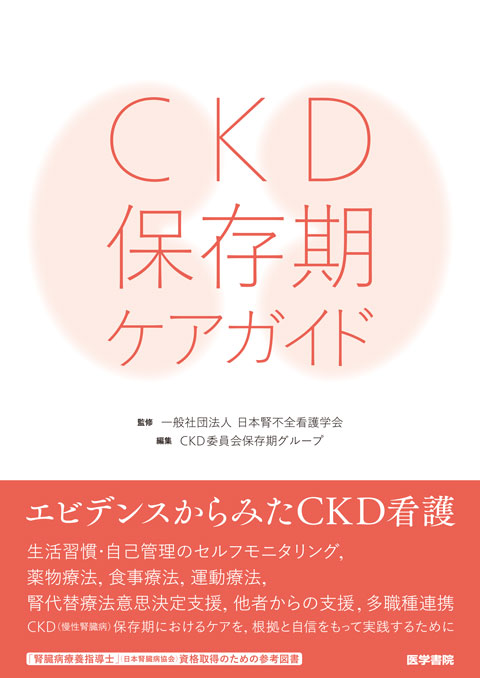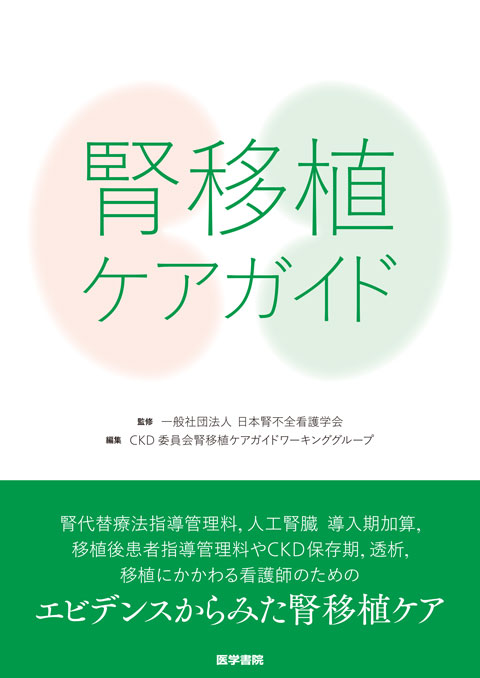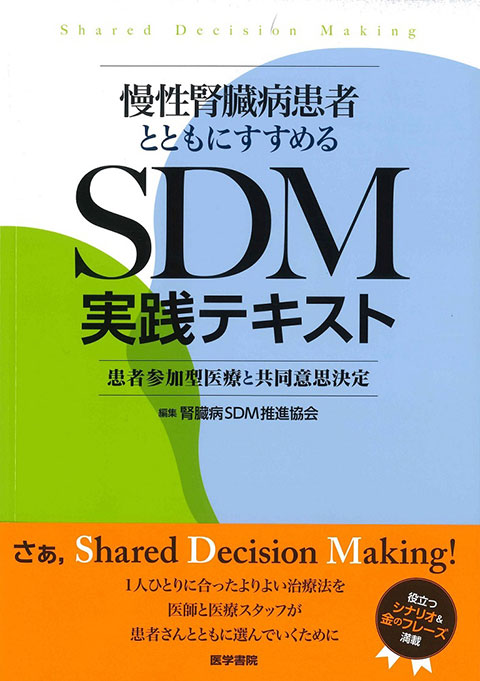慢性腎臓病看護のいま
変わったこと,変わらないこと
対談・座談会 髙井奈美,柏原直樹,内田明子,齋藤凡
2022.08.29 週刊医学界新聞(看護号):第3483号より

2009年に行われた座談会「変わる腎不全看護と看護師の役割」(本紙2852号)当時は,慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)の概念が国内で導入され始めた頃であり,腎臓病看護の在り方がまさに変化するタイミングであった。それから約10年。糖尿病透析予防指導管理料(2012年)や腎代替療法指導管理料の新設(2020年),腎臓病療養指導士制度の誕生(2018年),保存的腎臓療法(Conservative Kidney Management:CKM)の導入など,本領域を取り巻く環境は大きく変化した。科学的な知見も集積されてきた現在,エビデンスに基づくCKD看護の実践がますます求められるようになっている。CKD患者に対する新たな看護の在り方を模索した。
髙井 日本におけるCKDの患者数は約1300万人。成人の8人に1人が罹患する時代であり,今や国民病と言えます。また毎年約4万人の末期腎不全患者さんに対して新規に透析療法が導入され,透析患者の総数は34万人を超えました1)。「CKD看護」という言葉が身近になったことも,患者数が増加する現状を表す1つの指標なのかもしれません。
議論の開始に当たり,日本腎臓学会前理事長の柏原先生から,腎臓病の変遷を簡単に共有していただけますか。
柏原 腎臓病に対する医療は,直近の40年間でドラスティックに変化しました。最もわかりやすい例は,透析導入される患者さんの原因疾患の構成でしょう。1980年代頃は約70%が慢性糸球体腎炎であり,比較的若い方が透析導入の対象となっていました。それが1998年以降,糖尿病性腎症が原因疾患の第1位となり,2020年現在は透析導入の約40%を占めます1)。併せて注意しなければならないのは,加齢と深い関係にある腎硬化症です。近年増加を続け,ついに原因疾患の第2位となりました。超高齢社会に突入した現代では,対応すべき患者さんが右肩上がりに増加していくことは間違いないでしょう。
看護師が療養指導・療法選択の場に積極的に介入できる時代に
髙井 柏原先生が話されたように,患者さんの背景が変化し提供される医療も高度化・複雑化してきた中で,透析導入前の保存期のCKD患者さんに対して「どのような看護が必要とされているのか」「看護職として何ができるか」と,近年では具体的な看護実践を検討できるようになりました。
CKD看護に長年携わられ,日本腎不全看護学会の理事長も務められた内田先生は,本領域の変化をどのように感じていますか。
内田 私が腎臓病の患者さんのケアに携わるようになって約40年。40年前は,救命した患者さんの社会復帰をいかに実現するかが目標でしたが,今では社会復帰は前提となり,議論の中心が,より良い人生を送るためにはどのような医療を提供するべきかとの話題に移っています。合併症に関しても研究が進んだことで,予防的視点でのケアも検討できるようになりました。
一方で,病いとともに生きる「人」に焦点を当ててケアを実践する看護の本質部分は変化していません。療養指導や療法選択の場面に看護師が積極的にかかわることも近年では増えてきたために,患者さんに寄り添ったケアを行う意義を改めて考え直すべき時期が訪れていると感じます。
髙井 確かに,2012年に「糖尿病透析予防指導管理料」が診療報酬上で算定可能となったことを契機に,保存期のCKD患者さん(糖尿病性腎症に限る)への療養指導に看護師が積極的に介入できるようになりました。また2020年に新設された「腎代替療法指導管理料」では,療法選択の場への看護師の参画を後押ししています。
看護師をはじめとした多職種による介入の専門性の確立という点では,腎臓病療養指導士制度の誕生は追い風になりました。柏原先生は本制度の立ち上げに中心となって尽力されたはずです。制度ができた背景にはどのような考えがあったのでしょうか。
柏原 腎臓病療養指導士制度を立ち上げる前年に,腎臓病にかかわる医療者を増やすことを目的としたNPO法人「日本腎臓病協会」を立ち上げました。学問としての高みをめざす日本腎臓学会とは相補的な立ち位置と言えます。「病気と闘うあなたを1人にしない」を理念に掲げ,同協会で取り組む事業は主に4つ。①CKDの予防や早期発見のための普及啓発活動,②患者会・関連団体との連携,③産官学による腎臓病の診断・治療法開発のプラットフォーム(Kidney Research Initiative-Japan)構築,そして本協会で最も重視する,④腎臓病療養指導士制度です。現在は,腎臓病療養指導士による療養指導に診療報酬が付与されるよう準備しています。
髙井 進捗はどうなのでしょう。
柏原 2020年から厚労科研として「慢性腎臓病(CKD)患者に特有の健康課題に適合した多職種連携による生活・食事指導等の実証研究」(研究代表:杏林大・要伸也氏)がなされており,今年度が研究の最終年です。エビデンスも概ね構築されてきましたので,診療報酬の獲得に向け働き掛けを強めていきたいと考えています。
髙井 医療施設としては,診療報酬が付与されていないと人的資源を充当しにくいでしょう。現状の療養指導は,どうしても看護師をはじめとした医療者のボランティア精神に依存している部分が大きいために,近い将来,診療報酬が付くことを願っています。
高齢腎不全患者のための保存的腎臓療法
髙井 診療報酬の動きに加えて注目されるのはCKMの話題です。本年6月には,2019年よりAMED研究として行われてきた「高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始/見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医療・ケアの構築」の成果をまとめたガイドも刊行されました。同研究事業の研究代表を務めた柏原先生から経緯を伺えますか。
柏原 毎年1000人以上に透析開始の見合わせや透析中止がなされている状況下,高齢の腎不全患者さんの尊厳を守りつつ,家族も安心できる標準的なCKMの在り方を提示できればと検討を続けてきました。分担研究では,漫画も織り交ぜられた「高齢腎不全患者に対応する医療・ケア従事者のための意思決定支援ツール」を齋藤先生に作成していただきましたね。
齋藤 ええ。意思決定支援時の医療者の参考となるべく,できるだけ手に取りやすいよう漫画での表現を採用しました。多くの方の目に触れ,現場での対応に生かしてもらえればと願っています。
柏原 AMED研究ではそうした成果も挙げながら,ようやく先日『高齢腎不全患者のための保存...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙井 奈美(たかい・なみ)氏 名古屋大学 医学部附属病院看護部
看護師資格を取得後,衆済会増子記念病院にて勤務。2001年豪ニューキャッスル大へ留学。帰国後,病いとともに生活するCKD患者のセルフマネジメント方法やその人らしさの看護の在り方を学ぶため,岐阜県立看護大大学院修了。修士(看護学)。15年より現職。慢性疾患看護専門看護師,腎臓病療養指導士。日本腎不全看護学会理事。『慢性腎臓病看護 第6版』(医学書院)にて責任編集を務める。

柏原 直樹(かしはら・なおき)氏 川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 教授
1982年岡山大医学部卒。岡山大病院,呉共済病院にて臨床研修。88~90年米ノースウエスタン大に研究留学。帰国後,岡山大講師,助教授を経て,98年より川崎医大教授。2004年より臨床教育研修センター長。前日本腎臓学会理事長。日本腎臓病協会理事長として腎臓病療養指導士制度の立ち上げに尽力した。

内田 明子(うちだ・あきこ)氏 聖隷佐倉市民病院 総看護部長
看護師,保健師資格を取得後,千葉社会保険病院透析センター,千葉社会保険介護老人保健施設勤務を経て,2006年聖隷佐倉市民病院看護次長。同年千葉大大学院修了。修士(看護学)。聖隷横浜病院総看護部長を経て,21年より現職。1997年の日本腎不全看護学会設立当初から理事を務め,2014~17年まで理事長職を担った。

齋藤 凡(さいとう・なみ)氏 東京大学 医学部附属病院看護部
東大医学部健康総合科学科看護科学専修卒業。同大病院で看護師として勤務。同大大学院医学系研究科修士課程を修了後,同研究科助教を経て2015年より現職。腎臓内科,アレルギー・リウマチ内科,心療内科の混合病棟で副看護師長として日々奮闘中。21年まで日本腎不全看護学会の理事を務めた。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。