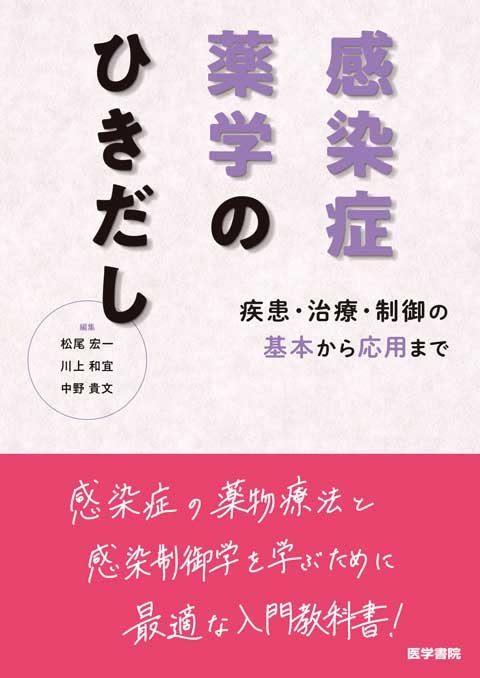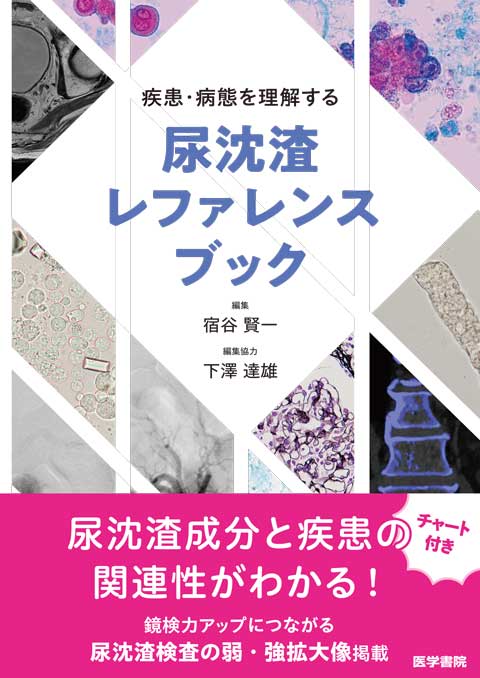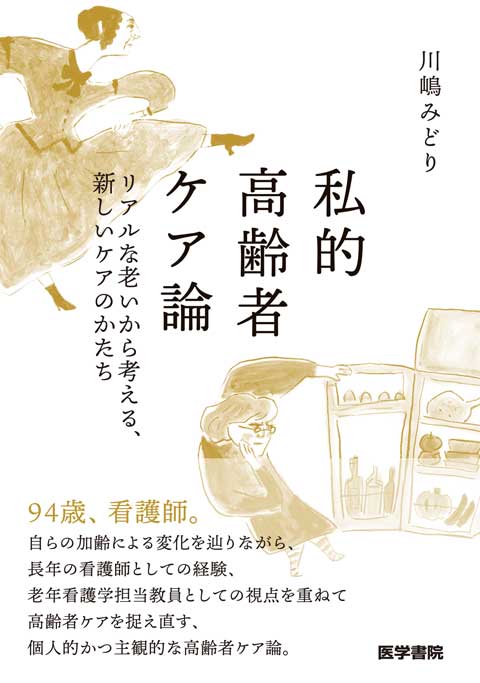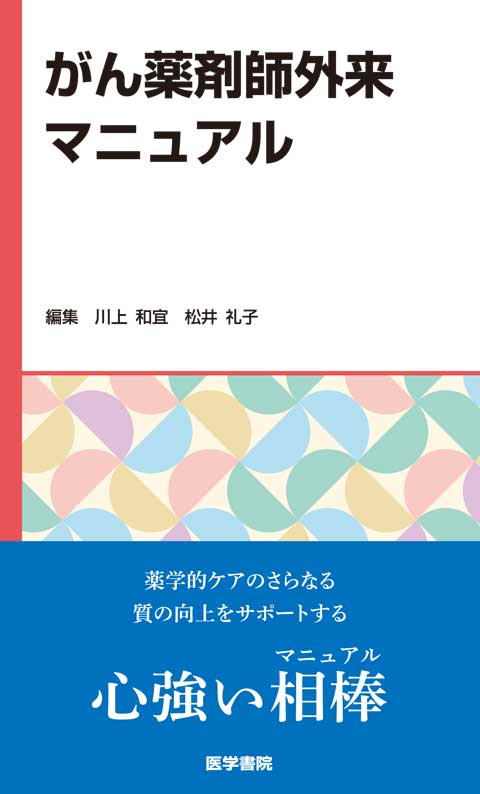MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.09.09 医学界新聞:第3577号より
《評者》 中山 祐次郎 湘南東部総合病院外科・作家
自ら「キング」を名乗る怪しい男の本をプロ作家が切る
セザキングって誰だ。初めて会ったのは六本木の美術館の中で開かれた某YouTuber心臓外科医の結婚パーティー。某社の編集者と3人席であった。席について私はその小柄な男と乾杯し,酔いに任せていじり倒した。初対面からセザキングと呼び,列席のアイドルと乾杯するのに無理やり連れて行った。お堅いスーツ姿のこの男は挙動不審で,間違っても「キング」を自称するタイプには見えない。正直胡散臭いとは思ったが,小説の変なキャラのモデルに使えるかとLINEを交換した。
2回目に会ったのは横浜だった。私が歯医者前だと言っているのに「うしごろ」という焼肉屋の予約をしてきた。平日昼間の半個室,網を隔てたおっさん二人が向かい合って話し始める。名古屋生まれ山形大学卒の精神科医で,臨床は週一回,それ以外は会社を作りUSMLE(米国医師国家試験)のオンラインサロン運営と。やっぱり怪しい。
だが,そこから聞いた話はすごかった。帰国子女でもないのに当時の最高点でUSMLEに一発合格,以降は勉強法を教え続けている。サロンには220人以上も会員がいて,2020年に勉強法を本にまとめた。つまり,「自ら達成」×「指導経験豊富」×「その知見を発表済」である。おわかりだろうか。これ以上,この試験勉強に詳しい人間は少なくとも日本にはいない。間違いなく第一人者だ。つまりキングである。少々イラっとするが,たしかにセザキングだ。
そんな彼の本が大幅改訂され,こともあろうかUSMLE受験経験のない私に書評依頼が来た。私は現役外科医であり,プロの作家でもある。これまで出した本は命懸けで書いたものばかりで,嫌味だがすべて売れている。医学書も三冊単著で出した。一旦は引き受けたものの,おべっかを書く主義ではない。生半可な本であったら書評を断ろうと思っていた。焼肉代も私が払ったし。
だが,読み始めてすぐに惹き込まれた。まず文章が上手い。本の中にもあるが,USMLEの学習と指導で日本語が上達したのだろう。そして挟まれるコラムも洒脱だ。だがそんなことより本書のような実践書に必要なのは,
①正しく②豊富な情報が,③すぐ実践できる形で提示されていること
である。①の検証は私には叶わぬが,例えば「選択肢だけで答えを選ぶ」ようなトリッキーなものも含めて圧倒的な説得力がある。②は間違いない。このページ数に巻末付録がついたら,8,000円でも安いと作家の感覚で思う(定価3,960円)。なにより本書が素晴らしいのは③だろう。読んで,この通りに努力をするだけで合格できそうである。医学生向けのスケジュールや,誰でも使える学習スケジュール表がダウンロードもできるのである。これは編集者の努力の賜物であろう。磨き込まれた,プロの仕事だ。悔しいが,いい本だ。中山祐次郎,責任を持って本書を推薦する。
《評者》 池末 裕明 名大病院薬剤部 教授・薬剤部長
感染症治療と感染制御学を実践的・体系的に学べる教科書
近年,薬剤耐性の問題を考慮した適切な薬物療法や感染制御における薬剤師の役割はますます重要になっており,一層積極的な関与が求められています。本書はそうした時代の要請に応える形で編集され,感染症分野で必要とされる理論と実践を体系的に学ぶことができます。ぜひ多くの薬剤師の方や,感染症治療や感染制御学を学ぶ薬学生に本書を手に取っていただきたく,ご紹介します。
本書は「総論」「感染臓器・原因微生物からみた感染症」「感染症の治療薬」「感染制御学」と大きく4つのまとまり(「ひきだし」のタイトルになぞらえて「段目」)から成り立っています。
・1段目「総論」では,感染症の基本や抗菌薬の選択と適正使用,PK/PDなどの基礎的な内容が網羅されています。
・2段目「感染臓器・原因微生物からみた感染症」では各臓器や原因微生物に焦点を当てた感染症の解説が続き,実際の臨床現場で遭遇する症例に即した知識が盛り込まれています。
・3段目「感染症の治療薬」では,各薬剤の特徴を理解し,代謝や病態による薬の使い分けなどの実践的な知識が満載です。各項目の解説が相互につながっているため,薬剤師としての実践力を重層的に養うことができます。
・感染制御活動を担当する場合は,AST(抗菌薬適正使用支援チーム),ICT(感染制御チーム)の一員として,感染症を専門としていない医療従事者に適切な助言をしたり院内の運用を定めて説明したりするなど,指導的役割が求められます。4段目「感染制御学」の段では,これらの理論的背景もまとめられており,業務を進めていく支えになってくれるでしょう。
さらに各章の構成も工夫されています。最初に要点がまとめられ,その後に解説を読むことで体系的に知識を得ることができます。加えて随所に示された「ステップアップのひきだし」には,専門性をより深めていくためのさまざまな気付きが用意されており,実践力を養うことができます。
ところで臨床現場では救急や悪性腫瘍,循環器領域など,各疾患の薬物療法と感染症治療の両面を十分理解して対応する必要があります。本書では各領域にそれぞれ精通したエキスパートの著者陣がそろい,多様な視点と豊富な経験に基づく実践的知識がまとめられている点も魅力です。
以上,『感染症薬学のひきだし』は感染症薬学の基礎から応用までを網羅した,実践的かつ体系的な教科書であり,薬学生や,感染制御活動を担当している,あるいは認定資格をめざす薬剤師の方など幅広い読者に役立つ一冊と言えます。感染症の薬物療法と感染制御学を学ぶ基礎として,本書を手に取っていただくことを強くお勧めします。
《評者》 矢冨 裕 国際医療福祉大大学院 大学院長
鏡検のレベルアップをめざす臨床検査技師,尿検査結果を活用する医師に
簡便に実施でき,非侵襲的検査の代表でありながら,多くの情報を提供してくれる尿検査を有効活用する意義は論をまちません。尿沈渣検査は,尿を遠心分離して得られる沈渣を顕微鏡で観察するものですが,腎臓・尿路系疾患を中心に多くの疾病を発見する手がかりとなります。この検査においては,種々の沈渣成分を正確に観察・記述することが重要ですが,本検査のプロとしては,診断・病態解明に資することができる,より多くの付加価値情報を臨床に提示する必要があります。そのためには,尿沈渣検査の鑑別技術の向上はもちろんのこと,疾患・病態との関連性を十分に理解している必要があります。
本書は,2018年春に発刊され,好評を博した「臨床検査」誌62巻4号(2018年4月・増刊号)「疾患・病態を理解する尿沈渣レファレンスブック」を書籍化したものと伺っていますが,まさに,「疾患・病態を理解する」助けになってくれると信じています。編集担当の宿谷賢一教授,編集協力の下澤達雄教授は,それぞれ,一般検査を専門とする,わが国を代表する臨床検査技師,臨床検査医です。
本書はわかりやすい二部構成になっていますが,前半の基礎編では,解剖,尿路の検査・処置・手術,尿沈渣成分,後半の疾患編では,尿沈渣成分と疾患との関連について解説されています。基礎編では解説が充実している一方,疾患編は見開きでたいへん読みやすくなっています。
本書では美しい写真がふんだんに使われ,まさに,尿沈渣と疾患の関連性を体感できると感じています。本書により,尿沈渣成分と疾患・病態の関連性に関する知識を深め,鏡検のレベルアップにつなげていただくことを願っています。また,本書は,評者のように,尿沈渣検査に自ら接する機会がなく,オーダーした結果だけを確認するような方にとっても,たいへん勉強になります。鏡検のレベルアップをめざす臨床検査技師はもちろんのこと,尿検査結果を活用する医師にも,ぜひ手にとっていただければと思います。
本書は,レファレンスブックという書名の通り,個々の事項を調べるのにも有効活用できますが,最初から最後まで通読いただくことで,尿沈渣検査の体系的かつ深い理解につなげていただけるのではと思います。多くの方々に有効活用されることを願うものです。
《評者》 徳永 進 野の花診療所 医師
下降と上昇の「ケア論」――自分の老いをフィールドに
著者は94歳の看護師。「看護」という言葉を追い続け,看護を人生の揺るぎない課題とし,自身を支える1本のいわば“柱言葉”としてきた。手を患者さんに当てることの中に看護の本質があることを直感的に,また自身の経験から学び,「てあて学」という新しい言葉を編み出した。老いを決して否定的にとらえるのではなく,同情的にとらえるのでもなく,「不具合や不調とともに生きる健康」,「加齢による不調を“正常に異常な状態”」と肯定的にとらえ,老いへのケアを考え直している。
高齢者といっても心身の姿はそれぞれに多様で,その個別性,その固有な人生に関心を持ちつつ必要なケアを見つけ出し実践してほしい,と従来から揺らぐことのない看護の基本が述べられている。さらに形而上的には,戦争のない社会をつくること,地球の温暖化現象を食い止めることを,老いの看護を含めた看護そのものの真中に置いている。そして対極に位置する形而下には「看護という職業は,“小さなこまごまとしたこと”から成り立っており,〈小さなこまごまとしたこと〉の中での高度の優秀性が要求される職である」1)の一節を愛着を持って引用している。形而下などとは言えない(一見形而下のようでも,実はそう見たままの単純なものでもない)。
ある集まりで,「体力は生誕から経年とともに上昇し,天体的に言うなら一番元気な地点,中天を通りそれを過ぎると,ゆっくりと下降する。精神は中天を過ぎると,下がりそうに見えるが,そこから上昇する。〈下がりながら上がる〉とも言われている」との発言に対して,同席していた著者が印象に残る発言をした。「精神だけじゃないの,肉体も再び上昇していく,って私,発見したの」。どう考えても肉体は衰えていくと思うのに,合気道,つま先立ちの訓練や呼吸法を欠かさずすることで,体力は中天を越えても少しずつ上昇する事がある,と著者は言う。
考えてみれば身体を構成する筋肉たち,ケアが届かねば弱体化するが,「肛門締め締め体操」で骨盤底筋を鍛えたり,舌を斜め前方遠くへ出す「舌出し体操」「咬む咬む体操」で顔の咬筋を鍛えたり,「顔くしゃくしゃ体操」で顔面筋を日々鍛える,なども中天から決して下がる一方ではない筋力アップがトレーニングによって可能となるようだ。老いてなお上昇する可能性もある。
本書の本質は,自らの老いの現実の日々をフィールドとした点である。そこでの観察の集積が今までの著作とは異なるケア論を醸し出す。高齢者となった著者の日常生活の一端が20個記載されている。「冷蔵庫を開けてから,取り出すものは何だった?」「食器洗いの後,汚れがきちんと落ちていないと指摘され,自尊感情を損なう」「瓶詰めの蓋を開ける指の力が弱くなり,他人に頼まねばならない不自由」「公文書の文字が小さく薄く,老眼鏡に加えて虫眼鏡が要る」などなど。思わず笑う20項目。
挿入されている日々のつづりを読んでいると,98歳で亡くなった米国のヴァージニア・ヘンダーソン(「看護の基本となる14項目」の枠組みを提唱)を継いでいる日本の94歳の著者が,下降と上昇を含めて書いた「ケア論」だと思う。
参考文献
1)湯槇ます,小玉香津子,薄井坦子,他(編訳).新訳・ナイチンゲール書簡集――看護婦と見習生への書簡.現代社;1977.pp109.
《評者》
向坂 くじら
詩人
「国語教室ことぱ舎」(埼玉県桶川市) 代表
ケアが迂遠であること
◆増補版までの5年間
本書は,2020年2月に刊行された同タイトルの書籍に補遺と索引を加えた増補版である。本書が論じるのは,「対話や承認それ自体がケアになるという可能性」だ。そのために,医療やヘルスケアの現場で行われてきた「ナラティブ・アプローチ」(個人によって語られる物語=ナラティブを用いたさまざまなケア実践)を,解釈・調停・介入の三つに分類しながら幅広く検討する。そのためにまず,文学や言語学の物語論,哲学の存在論を経由し,「ナラティブとは何か」を考える。そして,それが本書の「骨」であると語る。その頑強さにうっとりと引きこまれる。
評者も刊行当初に本書を手に取り,刺激を受けたひとりだ。特に終章にある「私たちは〈いずれ死んでしまう存在〉どうしであるがゆえに,適切な聞き手になれる」という洞察には目を開かされ,評者の専門分野である教育や文芸について考えるときにも要所でそれと引き比べてきた,手放しがたい一冊である。
いま振り返ると,2020年からの5年はまさに,本書タイトルに含まれる「対話」と「ケア」という二つのキーワードのありようが様変わりしていく期間であったように思う。文芸誌で「ケア」特集が組まれ,家庭内でケアの役割を担わされる子どもを指す「ヤングケアラー」という言葉が「2021 ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされた。個人的な体感としても,教育について話しているときに「ケア」や「対話」というキーワードが話題に上ることが明らかに増えた。
◆「ケア」と「対話」ブームの中で
一方で,その広がりに首を傾げたくなることも多々あった。「ケア」「対話」の重要さが広まったゆえに,いまや「ケア」的であること,「対話」的であることとはどのようなことで,何に適しているのか,ということが,ときに語るまでもないこととして通り過ぎられやすい。
「ヤングケアラー」をはじめとする,これまでケア者に押しつけられてきた役割を語る言葉が増えたことには深い意義を認める一方,「ケア」や「対話」がある種のマジックワードとして使われる場面も増えたように思う。ともすれば,「ケア」だからよいのだ,「対話」だからよいのだ,というところで会話が閉ざされてしまう。SNS上で「風俗嬢と客の関係はケアである(だからよいのだ)」という言説を見たときにはおどろいた。本書でも非医療者によるケアが重要な位置を占めているように,「ケア」と「対話」とが医療を超えた普遍的な問題であることには間違いがないだろう。しかしそのために,「ケア」や「対話」が一時的にある種の乱暴さがまとわりつく言葉に変容してしまったようで,もどかしく思っていた。
◆増補版で語られる“ケア者と被ケア者とが共有するもの”
だから,いま本書が増補版として再び刊行されたことに,2020年当時の刊行とは異なる意義があると思えてならない。本書の特筆すべき点は,ケアをする人とケアをされる人とにそれぞれナラティブ(物語)があるととらえることで,むしろケアという関係の非対称性をありありと示しているところだ。
増補版で加わった補遺「話を聞くことの意味について」では,ケア者と被ケア者とが決してお互いに成り代わることのできない点に留意した上で,「語りにおける役割の交換可能性」を示す。ケアをする人とされる人とが役割を交換することは困難でも,語りにおける役割であれば交換可能である。そのことを,ナラティブ・アプローチが示しているというのだ。それはつまり,わたしがあなたに,あなたがわたしになることはできないけれど,しかしわたしがわたしであるというそのことをこそ,わたしたちは共有している,ということではないか。著者は補遺をこう締めくくる。「こうした(評者注:ケア者と被ケア者との)非対称性は私たちに冷たい不安を感じさせるが,ナラティブ・アプローチには,それを多少なりとも温めてくれるものが含まれているように思えてならない」。
ケアだから,対話だから対等,になれるわけではない。むしろ反対である。しかしその「冷たさ」を引き受けた上で著者は,「いずれ死んでしまう」という弱さのほかに,「決してお互いに成り代わることができない」ということもまた,ケア者と被ケア者とが共有できるわずかなものとして示しているように思えるのだ。
そのような迂遠さこそ,2025年にケアを考えるわたしたちに必要なものではないだろうか。
《評者》 山口 正和 がん研有明病院 院長補佐・薬剤部長
実際の外来業務で即戦力となるための情報が満載
『がん薬剤師外来マニュアル』は,がん薬物治療にかかわる多くの薬剤師にとってまさに必携の一冊です。2024(令和6)年の診療報酬改定で新設されたがん薬物療法体制充実加算が注目される中,本書は「がん薬剤師外来」において医師の診察前に行う薬剤師による面談のプロセスや治療ごとに使用されるレジメンと患者面談のポイントを詳細に解説しています。
本書の最大の特徴は,診療報酬として新設される以前からさまざまな試練を乗り越え実際にがん薬剤師外来の立ち上げを経験した最前線で活躍する薬剤師によって執筆されている点です。この実体験に基づく内容は,実際の現場で直面する課題を鮮明に描き出し,薬剤師がどのような対応をすれば患者に安心と信頼を提供できるかを具体的に示しています。患者への説明は丁寧でわかりやすく,また医師に対する支持療法薬の提案やその使い方の共有方法にも十分配慮されており,エビデンスに裏付けられた説得力ある内容です。
特に印象的なのは,患者とのコミュニケーションに重きを置いた構成です。薬剤師は単に薬を渡すだけでなく,患者の不安を解消し,治療方針に納得してもらうことで治療の効果を最大限に引き出す役割を果たします。本書では,具体的な患者との対話例や,患者の理解を助けるための工夫についても詳述されており,実際の外来業務で即戦力となるための情報が満載です。
また,本書では支持療法薬の選択や提案プロセスにおいても,エビデンスを踏まえた提案方法が具体的に解説されており,そして「副作用の重篤度評価と薬学的ACTION」の項目では,薬剤師がどのように効果的に治療に参加するのか,具体的なアプローチが示されています。
さらに,がん薬剤師外来の立ち上げを志す人々に向けて,ステップバイステップで理解できるよう配慮されている点も見逃せません。本書を手に取ることで,外来業務の基本から応用までをしっかりと学ぶことができ,実際の業務においてどのように実践していくかの具体的なビジョンを得られるでしょう。
まとめると,『がん薬剤師外来マニュアル』は,がん薬物療法に携わる薬剤師にとって欠かせない指南書であり,ここには患者や医師とのコミュニケーションを向上させるための実践的な知識が詰まっています。これからがん薬剤師外来を始める方,また既に外来業務を行っている方のいずれにとっても,大変価値のある一冊といえるでしょう。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。