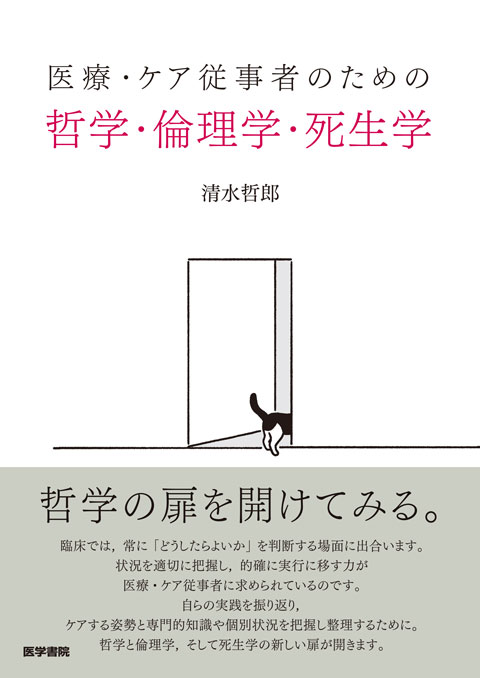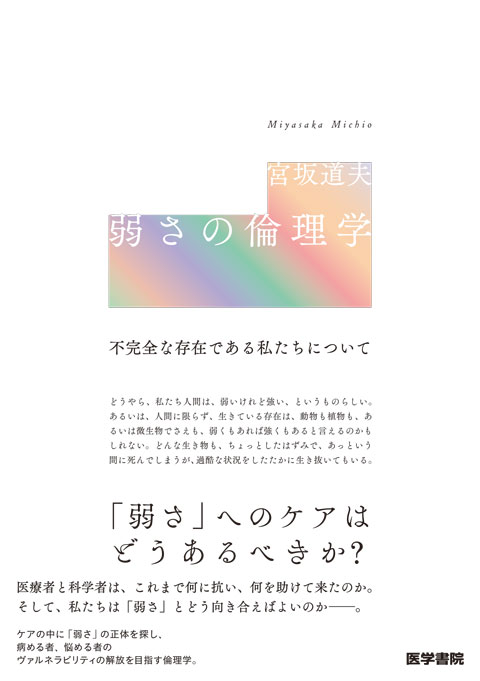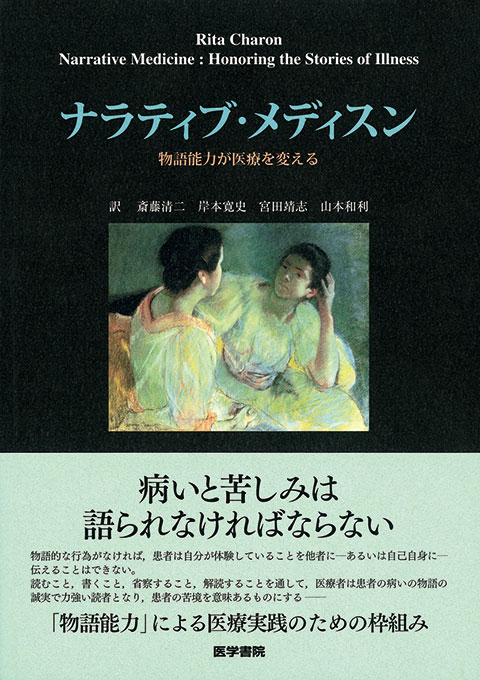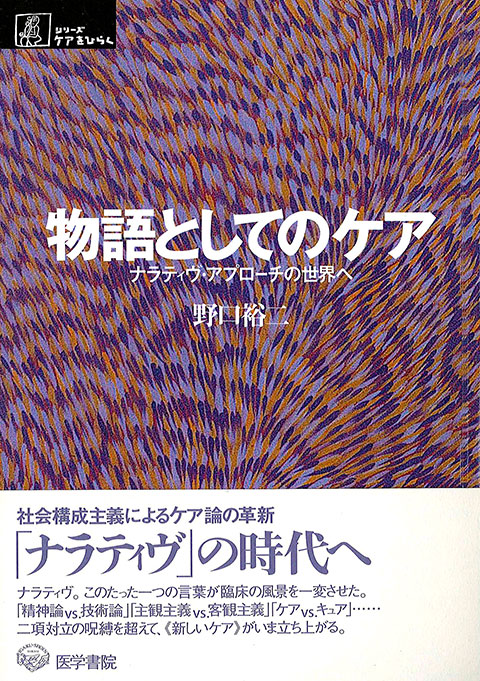対話と承認のケア 増補版
ナラティヴが生み出す世界
ナラティヴ・アプローチ探求の金字塔『対話と承認のケア』の増補版!
もっと見る
多くの方に愛読されている『対話と承認のケア──ナラティヴが生み出す世界』の増補版。補遺(ほい)にて、ナラティヴ・アプローチの有効性とこれからの展望を初版から一歩進めて解説。巻末には索引が付き利便性もアップ。研究職のみならず、臨床の医療職にも有用な1冊となって再登場!
| 著 | 宮坂 道夫 |
|---|---|
| 発行 | 2025年03月判型:A5頁:298 |
| ISBN | 978-4-260-06181-0 |
| 定価 | 2,750円 (本体2,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
増補版へのまえがき
本書の刊行からおよそ五年の歳月が流れた。
この間に生じた「ナラティヴ」関連の出来事について、ヘルスケアの領域に限定せずに振り返ると、最も目につくのは、残念ながら、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻だと言わざるを得ない。
本書では、ヘルスケアの領域でのナラティヴ・アプローチを考えている。本書での「ナラティヴ」とは、主には患者や医療従事者などの「個人のナラティヴ」である。これに対して、ウクライナ戦争における「ナラティヴ」は、国家や社会などの「集団のナラティヴ」である。ナラティヴ研究の第一人者の一人であるキャサリン・リースマンが「集団は、人を動かし、帰属意識を強めるためにナラティヴを用いる」と述べている通りで、戦争を始めようとする指導者たちは、戦争を正当化する集団のナラティヴをつくり出し、それによって国民を団結させ、兵士たちに命を捨てる覚悟をもたせようとする。ウクライナへの軍事侵攻を正当化するナラティヴによって、今日までに少なくとも十一万人の兵士の命が失われてしまった。ナラティヴとケアを考えてきた立場からすれば、まことに悲しい現実である。
***
さて、ヘルスケアの領域に目を向けよう。
幸いにも、そこでは人の命を助け、心を癒すために、ナラティヴが用いられている。
この五年の歳月のヘルスケアの状況を大きく俯瞰すれば、ナラティヴ・アプローチを含めた「対話」や「心のケア」への関心は、確実に高まっている。
その典型が、命の始まりと終わりの局面に見られる。
命の始まりの医療の一つに、出生前診断(または出生前遺伝学的検査)がある。これは、妊娠中に胚や胎児の状態を調べる検査である。異常が見つかった場合に、産むか否かという意思決定をすることになるのだが、その際に、遺伝カウンセリングを受けたうえで意思決定を行えるようにする体制の充実が図られている。遺伝カウンセリングの内容は、患者や家族に幅広い情報提供を行い、心理的・社会的サポートを行うことで、自律的な意思決定を支援することとされている。
死が近づいた段階の医療では、ACP(アドバンス・ケア・プランニング、または「人生会議」)の普及が促進されている。厚生労働省によるACP普及啓発のためのホームページによると、これは「もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組」である。
これらは、ケアを受ける立場の人と、ケアを提供する立場の人とが、ある程度の時間をかけて言葉を交わし、治療などについての方針を決めていくための「対話」である。このように、「対話」が医療のなかに組み込まれる機会は、間違いなく増加しているように思う。
「対話」からさらに一歩踏み込んだものとしての、「心のケア」についてはどうだろうか。
これについても、日本社会では着実な前進が見られる。「心のケア」の専門家として本書でも触れている公認心理師は、二〇二四年九月時点で七万三千六二八人となった。これは、人口一万人あたり六人ほどという計算になり、この資格が国家資格としてスタートした当初の、二〇一九年三月の登録者数二万四千五六人から三倍に増加した。
***
このように、「対話」や「心のケア」は、私たちの社会のヘルスケアのなかで、確かに前進しつつあるのだが、出生前診断に伴う遺伝カウンセリングにしても、終末期などのACPにしても、さらには公認心理師の活動についても、いずれも十分な状況にあるとは言いがたい。「対話」や「心のケア」のための制度が整い、そうした機会が増えつつあると言っても、それがどの程度充実したものになっているかという「質」にまで目を向ければ、いまだ緒についたばかりだと言わざるを得ない。
本書で考えるナラティヴ・アプローチとは、まさしく「対話」や「心のケア」の質を高めていくための方法論と言って差しつかえない。その意味では、このタイミングで増補版を刊行できたことを喜びたい。増補版では、新たに補遺を設けて、本書から漏れ落ちた問題の一部を議論した。また、全体を行き来しながら読むのに使える索引を設けた。
最後に、本書の増補版の刊行に際して尽力していただいた医学書院の金子力丸氏と、筆者の文章に忌憚のない意見を述べてくれた宮坂徳子氏に、あらためて感謝の意を表する。
二〇二五年一月 筆者
目次
開く
増補版へのまえがき
はじめに
第一章 日々のケアにひそむナラティヴ
1 日々のケアにひそむナラティヴ・アプローチ
2 ナラティヴのブームと誤解
第二章 ナラティヴとは何か
1 言葉の話
2 文学と言語学の物語論
3 現実世界の物語論
4 ヘルスケアの物語論
第三章 ケアする私、ケアされる私
1 〈ケアする私〉の物語論
2 〈ケアされる私〉の物語論
3 ケアし、ケアされる〈私たち〉の物語論
第四章 他者のナラティヴを読む──解釈的ナラティヴ・アプローチ
1 医療制度の入口で
2 急性疾患の臨床現場で
3 慢性疾患の臨床現場で
4 日常臨床での解釈的ナラティヴ・アプローチ
5 ナラティヴの解釈が「ケア」になるとき
第五章 複数のナラティヴの前で──調停的ナラティヴ・アプローチ
1 ナラティヴの不調和
2 調停における実在論と構築論
3 ナラティヴの調停が「ケア」になるとき
第六章 他者のナラティヴに立ち入る──介入的ナラティヴ・アプローチ
1 心のケアと心の病い
2 〈私の物語〉への介入
終章 ナラティヴがケアになるとき
補遺 話を聞くことの意味について
あとがき
文献・註
索引
書評
開く
ケアが迂遠であること
書評者:向坂 くじら(詩人/「国語教室ことぱ舎」(埼玉県桶川市)代表)
◆増補版までの5年間
本書は,2020年2月に刊行された同タイトルの書籍に補遺と索引を加えた増補版である。本書が論じるのは,「対話や承認それ自体がケアになるという可能性」だ。そのために,医療やヘルスケアの現場で行われてきた「ナラティブ・アプローチ」(個人によって語られる物語=ナラティブを用いたさまざまなケア実践)を,解釈・調停・介入の三つに分類しながら幅広く検討する。そのためにまず,文学や言語学の物語論,哲学の存在論を経由し,「ナラティブとは何か」を考える。そして,それが本書の「骨」であると語る。その頑強さにうっとりと引きこまれる。
評者も刊行当初に本書を手に取り,刺激を受けたひとりだ。特に終章にある「私たちは〈いずれ死んでしまう存在〉どうしであるがゆえに,適切な聞き手になれる」という洞察には目を開かされ,評者の専門分野である教育や文芸について考えるときにも要所でそれと引き比べてきた,手放しがたい一冊である。
いま振り返ると,2020年からの5年はまさに,本書タイトルに含まれる「対話」と「ケア」という二つのキーワードのありようが様変わりしていく期間であったように思う。文芸誌で「ケア」特集が組まれ,家庭内でケアの役割を担わされる子どもを指す「ヤングケアラー」という言葉が「2021 ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされた。個人的な体感としても,教育について話しているときに「ケア」や「対話」というキーワードが話題に上ることが明らかに増えた。
◆「ケア」と「対話」ブームの中で
一方で,その広がりに首を傾げたくなることも多々あった。「ケア」「対話」の重要さが広まったゆえに,いまや「ケア」的であること,「対話」的であることとはどのようなことで,何に適しているのか,ということが,ときに語るまでもないこととして通り過ぎられやすい。
「ヤングケアラー」をはじめとする,これまでケア者に押しつけられてきた役割を語る言葉が増えたことには深い意義を認める一方,「ケア」や「対話」がある種のマジックワードとして使われる場面も増えたように思う。ともすれば,「ケア」だからよいのだ,「対話」だからよいのだ,というところで会話が閉ざされてしまう。SNS上で「風俗嬢と客の関係はケアである(だからよいのだ)」という言説を見たときにはおどろいた。本書でも非医療者によるケアが重要な位置を占めているように,「ケア」と「対話」とが医療を超えた普遍的な問題であることには間違いがないだろう。しかしそのために,「ケア」や「対話」が一時的にある種の乱暴さがまとわりつく言葉に変容してしまったようで,もどかしく思っていた。
◆増補版で語られる“ケア者と被ケア者とが共有するもの”
だから,いま本書が増補版として再び刊行されたことに,2020年当時の刊行とは異なる意義があると思えてならない。本書の特筆すべき点は,ケアをする人とケアをされる人とにそれぞれナラティブ(物語)があるととらえることで,むしろケアという関係の非対称性をありありと示しているところだ。
増補版で加わった補遺「話を聞くことの意味について」では,ケア者と被ケア者とが決してお互いに成り代わることのできない点に留意した上で,「語りにおける役割の交換可能性」を示す。ケアをする人とされる人とが役割を交換することは困難でも,語りにおける役割であれば交換可能である。そのことを,ナラティブ・アプローチが示しているというのだ。それはつまり,わたしがあなたに,あなたがわたしになることはできないけれど,しかしわたしがわたしであるというそのことをこそ,わたしたちは共有している,ということではないか。著者は補遺をこう締めくくる。「こうした(評者注:ケア者と被ケア者との)非対称性は私たちに冷たい不安を感じさせるが,ナラティブ・アプローチには,それを多少なりとも温めてくれるものが含まれているように思えてならない」。
ケアだから,対話だから対等,になれるわけではない。むしろ反対である。しかしその「冷たさ」を引き受けた上で著者は,「いずれ死んでしまう」という弱さのほかに,「決してお互いに成り代わることができない」ということもまた,ケア者と被ケア者とが共有できるわずかなものとして示しているように思えるのだ。
そのような迂遠さこそ,2025年にケアを考えるわたしたちに必要なものではないだろうか。