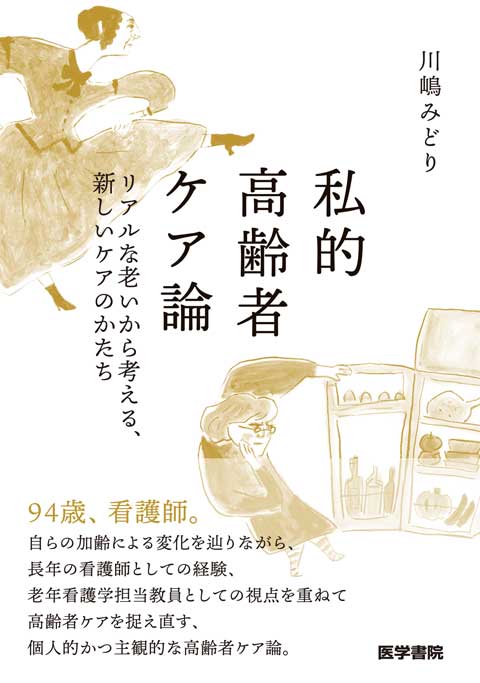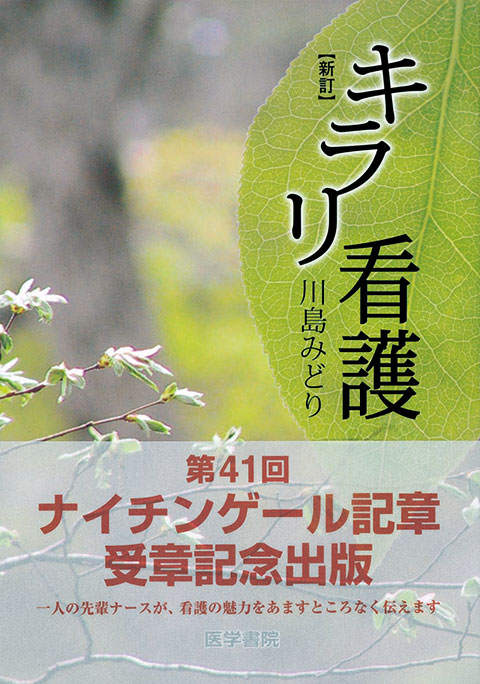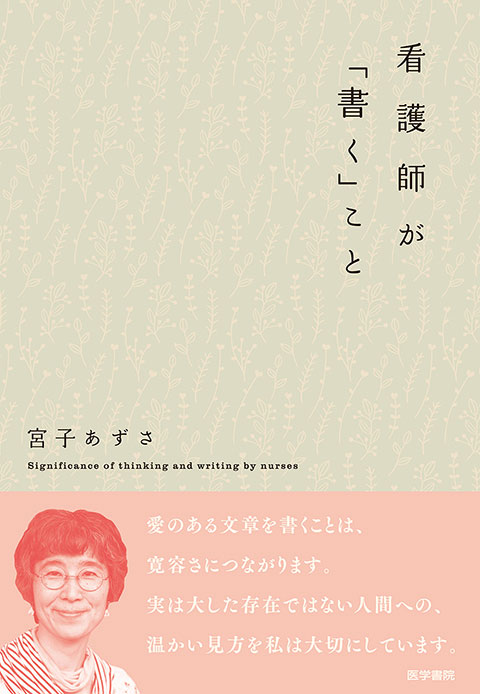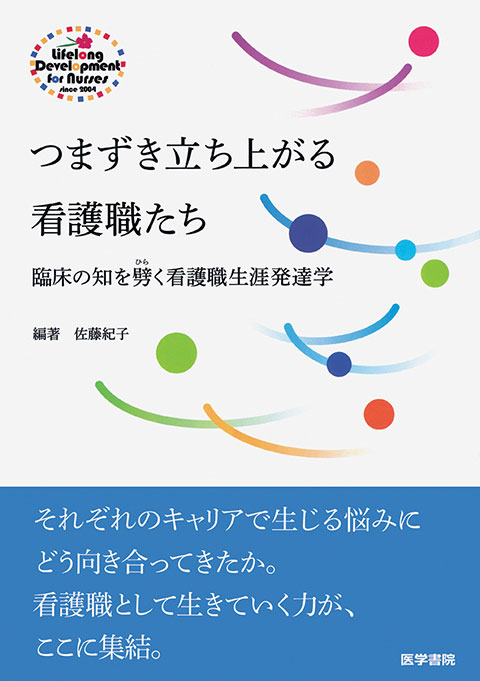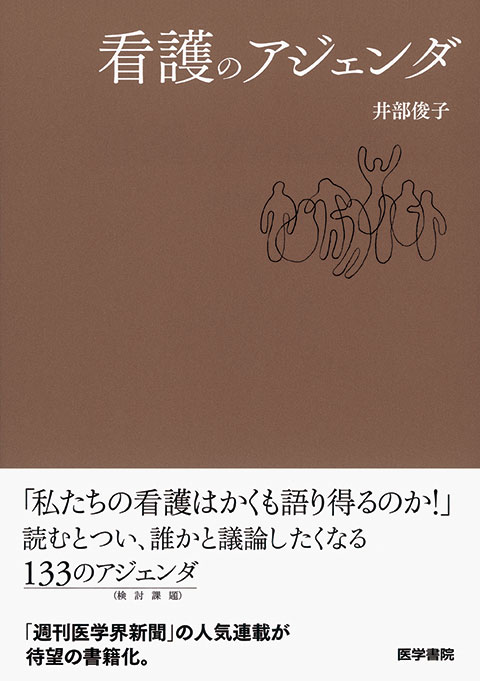私的高齢者ケア論
リアルな老いから考える、新しいケアのかたち
94歳、看護師。当事者として考える、これからの高齢者ケア
もっと見る
高齢者は同質な老年期集団ではない。
当事者として経験する「老い」は、こんなにも多彩で、新鮮な驚きに満ちていた。
自らの加齢による変化を辿りながら、長年の看護師としての経験、老年看護学担当教員としての視点を重ねて高齢者ケアを捉え直す、個人的かつ主観的な高齢者ケア論。
| 著 | 川嶋 みどり |
|---|---|
| 発行 | 2025年05月判型:B6頁:184 |
| ISBN | 978-4-260-05617-5 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
少し長いまえがき
◆“老い”を読む
「老年とは未知の世界の探訪 そう考えれば何とか受け入れられる1)」──メイ・サートン
誰もが、やがて老いることは頭の中で理解していても、「老いの実感」は、そこに来てみないとわからないものである。加齢によって避けられない心身の変化を“老い”であると自覚するのは、わが身に現れる諸々の事象を次々と受け入れる体験の積み重ねによると思う。
また、老親をはじめ、身近な高齢者との関わりなどを通して想像する“老い”もある。職業として高齢者の看護に携わる看護師や介護職らは、基礎教育の場で学び、専門書を通して高齢者ケアに必要な知識を得て、日々の実践を通して高齢者像を形づくっていくことだろう。さらに、“老い”は、生・老・病・死という人生の四大イベントの1つでもあるので、小説や随筆のモチーフとしても古くから取り上げられ語られてきた。
私の場合、“老い”についての問題意識を持つきっかけとなったのは、ボーヴォワールの著書『老い2)』を読んだことであった。個人の老いと、老いの社会的・文化的な側面を歴史的視点を踏まえて幅広く奥深くとらえられていると感じながら、40歳台になったばかりの自分自身のこととしては実感のわかないまま読んだ。一読しただけでは、“老いる”ことの意味に関するかなりリスキーな著者の考えを理解するのは至難であった。
ただ、文中に引用されていた「老いは正常に異常な状態(古代ギリシャの医者、ガレノスによる)」という言葉が印象的であったことから、今回、再読してみた。そこには、現在超高齢の私自身の実感にフィットする哲学者ジョルジュ・カンギレム(1904-1995)の説明があり、改めて納得した次第であった。すなわち老化現象とは、「安全さのゆとりが次第に減少する結果、環境からの攻撃に対する抵抗力が低下すること……」、そして「老人における正常は、同じ人間の壮年期においては欠陥とみなされたであろう3)」と。
医学の流れを汲んだ看護学領域での人間の成長発達段階から考える老年期の変化は、身体・生理学的な面がほとんどであるのに対して、前掲書『老い』では、“老い”がその個人の生活背景や経済問題、社会的地位、人生観によっても多様化されることが示唆される。全人的アプローチを標榜する看護の立場であるからこそ、さまざまな人生遍歴を経た高齢者個々の複雑な背景や心のありようを総合的に理解することは必須である。その理解のためには、専門書から得られる高齢者像に加えて、作家の目を通して描かれる小説や、実体験からの随筆などが有用ではないかと考えた次第であった。
たとえば古くからの棄老伝説をもとにしながら人間としての葛藤や愛憎を描いた『楢山節考』(深沢七郎)、『蕨野行』(村田喜代子)をはじめ、『海辺の風景』(安岡章太郎)、『恍惚の人』(有吉佐和子)など。最近では、『おらおらでひとりいぐも』(若竹千佐子)や『土の記』(髙村薫)などの他、老々介護や高齢者施設等を題材にした書籍なども多く出版されている。いずれも、読み手の年齢や立場によってさまざまな高齢者像を結ぶ想像力をかき立てられることだろう。
このように、時代や社会の織りなす風景のもとでの多彩な人間関係、それにまつわる人々の生き方や考え方が縦横に展開される小説は、読み手の立場や経験に照らしてその内容の解釈は異なることは当然である。だが、専門書を通じて理解するのとはやや異質の、しかし、現実にこの社会に生きている人の“老い”を、その人の多彩な人生経験や人間関係を通して想像することは、それなりに意味があると思われる。特に、高齢者へのケア提供者としての看護師は、その高齢者の背景や思いに心を寄せたケアを実践する上からも、是非多くの作品を読んでほしいと思う。
私の場合、高齢者群の1人になったばかりの頃、目にしたのが、冒頭のメイ・サートンの『一日一日が旅だから』に所収の詩“新しい地形”の冒頭のフレーズ、「老年とは未知の世界の探訪」であった。胸にすとんと落ちてから幾度も読み返してきた。一般的な寿命から見たら次第に残り少なくなる時間を生きる高齢者であっても、これから先、生きていく道が未知であるがゆえの冒険的要素を含んでいること、その未知の魅力探索の旅が老年であると思えば、“老いる”ことの体験自体に希望が持てた。そして、私自身の心身上に秘めやかに進行する“老い”と向き合いながら、日々の小さな変化や心の動きを、既成の高齢者看護学の知識と重ねてみようというのが本書執筆の動機となった。
◆“老い”を迎える
書物を通して想像する“老い”への私のイメージは、身近な高齢者との生活や介護を通して現実味を帯びてきたものの、自身の老化に関しては自覚のないままに暦年齢を重ねた感が強い。毎朝必ず眺める鏡の向こうの自分から老いの徴候をとらえることは難しく、どうやら内面的変化による心身機能低下の先行によって、老いの自覚は促されるのではないかと思っている。新聞の文字が読みづらくなったり、聞き返しやテレビの音を大きくしたりなど、まず感覚器官に現れる現象がその例である。
私の場合に限ると、暦年齢を重ねながらも、このような感覚の変化に老いを感じるゆとりのない生活が続いた。所長をつとめる健和会臨床看護学研究所の仕事も軌道に乗り、研究や卒後研修、執筆や講演などに追われているさなか、大学での教職を兼務することになったのが70歳過ぎてからであった。そして、学部長という要職に就いて間もなく始まった亡夫のがん手術後の在宅ケアを挟んで、老後というには余りにも濃密なフルタイムの日々を重ねた。
今にして思えば、この70歳を過ぎてからも続けざるを得なかった度重なる激しい移動や時間管理、変化に富んだ人間関係、各種の情報処理や判断を要する場面の多さなど、一般の高齢者が陥りがちな役割喪失感や孤独とは無縁の生活が、老化自体のスピードを落とす結果となったのではないだろうか。
こうして、80歳になってから、東日本大震災の発災後間もなく支援チームを組織しての活動が加わり、90歳を過ぎた今も、自分なりのペースを維持しながら目前の課題をこなす日々を何とか続けている。
とはいえ、加齢自体がもたらす心身の変化や生活諸行動の不具合のあれこれは、日常の生活の中で露呈することもしばしばである。自覚のないまま、うっかり頻度が高まって起こすあれこれへの、遠慮のない家族の指摘や苦言が、その時々の葛藤になりながら、否応なしに“老い”を受け入れざるを得ない状況を生んでいる。
また、同年代の友人たちとの交信や身近な親族らの日常のありようから、加齢以外の要因が高齢者の生き方に影響していることを教えられることもしばしばである。それらの要因の多彩さからも、普遍的な高齢者ケアを土台にしつつ、新しい視点から高齢者ケアを見直す必要を痛感した次第である。
◆“老い”をケアする
超高齢社会が現実のものにはなったが、高齢者を除く人口比率から見ても、“老い”を体験している者の数は未だ圧倒的に少ない。その未体験者が、施設、在宅を問わず、介護や支援を必要とする高齢者ケアの主力になっているのも事実である。
年齢差は、育ってきた時代や環境の相違から相互の価値観にも影響する。その差を無理に埋めるよりも、まずは、ケアを必要としている個々の高齢者を理解することから始めよう。たとえ目の前の高齢者が、起居動作をはじめ、生活諸行動の不調や認知レベルが低下していても、長い人生を生き抜いてきた先達であることを忘れてはならない。そして、老年期を、人間の発達段階の最終章と決めつけるのではなく、“老い”というプロセスの中で、老年期以前からの自己の連続性を見出しながら適応している存在であることを承知してほしい。必ずしも死に向かって衰える一方ではなく、機能面での心身の変化があっても、その変化に適応していく能力はむしろ衰えないことをケアに当たって心がけてほしいと願う。
今年は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、在宅ケアはもとより特別養護老人ホームや各種高齢者施設での介護需要がいっそう高まることが予想されている。一方、家族機能が次第に弱まっているのに加えて、人材不足や運営コストの上昇、介護報酬のマイナス改定などにより、倒産や廃業などに追い込まれる介護事業者が増えている実態もある。20年以上続いた介護保険制度をめぐっても、利用者の負担増やサービス内容の低下など数々の問題点が指摘されている。人間が人間をケアする仕事への社会的評価も決して高いとはいえない。そうした現実を踏まえて超高齢の域に達した私自身に引きつけてみても、ケアを必要とするのは時間の問題であることは間違いない。
そこで、受け手の立場から“老い”のケアへの期待を述べると、まず、リストバンドなどで識別する患者・利用者としてではなく、固有の氏名を持ってこれまで生きてきた1人の人格ある存在として受け入れてほしい。そのためには、その高齢者がこれまで生きてきた背景を知り、今、どのように暮らしているのか、この先、どのように生きたいと願っているのかなどの思いを知り、心のこもったあたたかいケアの提供をこそ普遍化すべきであると思う。
また、「できるだけ世話になりたくない」思いと「必要になったら親身な世話を受けたい」思いが錯綜するのが高齢者である。この相反する思いを汲み取って、「依存と自立」のバランスをその時々のケアに活かしてほしい。
本書は、私自身が迎えた“老い”への実感の一端を見つめながら、新たな高齢者ケアに資することを願って80歳から書き始め、書き終わるまで12年もの歳月を費やす結果になった。その時間推移を通して、必ずしも加齢の進行と老化の進行は比例するわけではないことを身をもって体験した。高齢者は、常に新たな体験へのチャレンジをする存在であり、心身ともに衰退の一途を辿るわけではないとの仮説を、検証する一例になった感じがしている。
主観的で私的な高齢者像とケア論ではあるが、新たな高齢者ケアの手がかりをつかんでいただければ幸いである。
2025年3月
川嶋みどり
1) メイ・サートン(著),武田尚子(訳):一日一日が旅だから.p.52,みすず書房,2001.
2) シモール・ド・ボーヴォワール(著),朝吹三吉(訳):老い 上/下.人文書院,1972.
3) 前掲書 2)下巻,p.336.
目次
開く
少し長いまえがき
序章 多様な高齢者像
1 ごく私的な老いの実感から
2 加齢と老い(老化)は必ずしも一致しない
3 高齢者は同質な老年期集団ではない
4 老いても成長し続ける存在として
第1章 高齢者の生活と生活行動
1 生活と生活行動
2 高齢者の生活行動
第2章 高齢者の心身の不具合
1 高齢者に特有な不具合とその対処
2 未病状態の高齢者
第3章 高齢者の思いと行動
1 スローテンポを理解して
2 高齢者特有の事故防止──暮らしの中の安全性
3 高齢者の願いに耳を傾けて
第4章 認知症も和らぐ老いの輝き──長期記憶のサブシステムから
1 認知症高齢者へのケアの基本
2 快適刺激による記憶再生の根拠
3 心地よい記憶へのアプローチの例
第5章 高齢者の自助と共助
1 脳卒中後遺症て右片麻痺の母と暮らす
2 リタイア看護師のキャリアを活かす
結びにかえて
引用・参考文献
書評
開く
下降と上昇の「ケア論」――自分の老いをフィールドに
書評者:徳永 進(野の花診療所医師)
著者は94歳の看護師。「看護」という言葉を追い続け,看護を人生の揺るぎない課題とし,自身を支える1本のいわば“柱言葉”としてきた。手を患者さんに当てることの中に看護の本質があることを直感的に,また自身の経験から学び,「てあて学」という新しい言葉を編み出した。老いを決して否定的に捉えるのではなく,同情的に捉えるのでもなく,「不具合や不調とともに生きる健康」,「加齢による不調を“正常に異常な状態”」と肯定的にとらえ,老いへのケアを考え直している。
高齢者といっても心身の姿はそれぞれに多様で,その個別性,その固有な人生に関心を持ちつつ必要なケアを見つけ出し実践して欲しい,と従来から揺らぐことのない看護の基本が述べられている。さらに形而上的には,戦争のない社会をつくること,地球の温暖化現象を食い止めることを,老いの看護を含めた看護そのものの真中に置いている。そして対極に位置する形而下には「看護という職業は,“小さなこまごまとしたこと”から成り立っており,〈小さなこまごまとしたこと〉の中での高度の優秀性が要求される職である」1)の一節を愛着を持って引用している。形而下などとは言えない(一見形而下のようでも,実はそう見たままの単純なものでもない)。
ある集まりで,「体力は生誕から経年とともに上昇し,天体的に言うなら一番元気な地点,中天を通りそれを過ぎると,ゆっくりと下降する。精神は中天を過ぎると,下がりそうに見えるが,そこから上昇する。〈下がりながら上がる〉とも言われている」との発言に対して,同席していた著者が印象に残る発言をした。「精神だけじゃないの,肉体も再び上昇していく,って私,発見したの」。どう考えても肉体は衰えていくと思うのに,合気道,つま先立ちの訓練や呼吸法を欠かさずすることで,体力は中天を越えても少しずつ上昇する事がある,と著者は言う。
考えてみれば身体を構成する筋肉たち,ケアが届かねば弱体化するが,「肛門締め締め体操」で骨盤底筋を鍛えたり,舌を斜め前方遠くへ出す「舌(べろ)出し体操」,「咬む咬む体操」で顔の咬筋を鍛えたり,「顔くしゃくしゃ体操」で顔面筋を日々鍛える,なども中天から決して下がる一方ではない筋力アップがトレーニングによって可能となるようだ。老いてなお上昇する可能性もある。
本書の本質は,自らの老いの現実の日々をフィールドとした点である。そこでの観察の集積が今までの著作とは異なるケア論を醸し出す。高齢者となった著者の日常生活の一端が20個記載されている。「冷蔵庫を開けてから,取り出すものは何だった?」「食器洗いの後,汚れがきちんと落ちていないと指摘され,自尊感情を損なう」「瓶詰めの蓋を開ける指の力が弱くなり,他人に頼まねばならない不自由」「公文書の文字が小さく薄く,老眼鏡に加えて虫眼鏡が要る」などなど。思わず笑う20項目。
挿入されている日々の綴りを読んでいると,98歳で亡くなった米国のヴァージニア・ヘンダーソン(「看護の基本となる14項目」の枠組みを提唱)を継いでいる日本の94歳の著者が,下降と上昇を含めて書いた「ケア論」だと思う。
1)湯槇ます,小玉香津子,薄井坦子,他(編訳):新訳・ナイチンゲール書簡集―看護婦と見習生への書簡.p.109,現代社,1977.