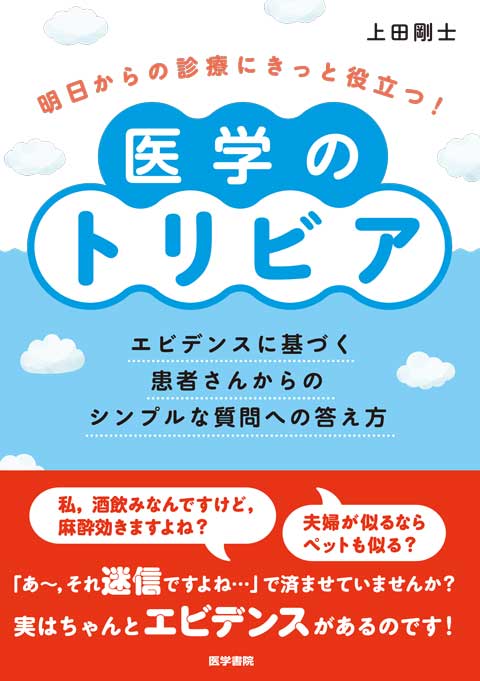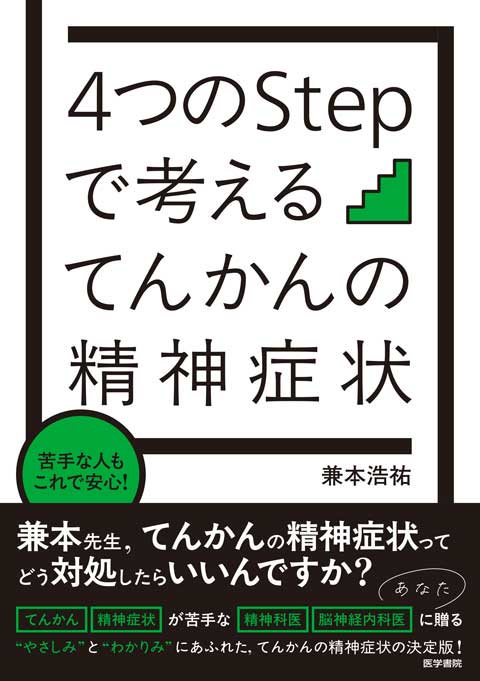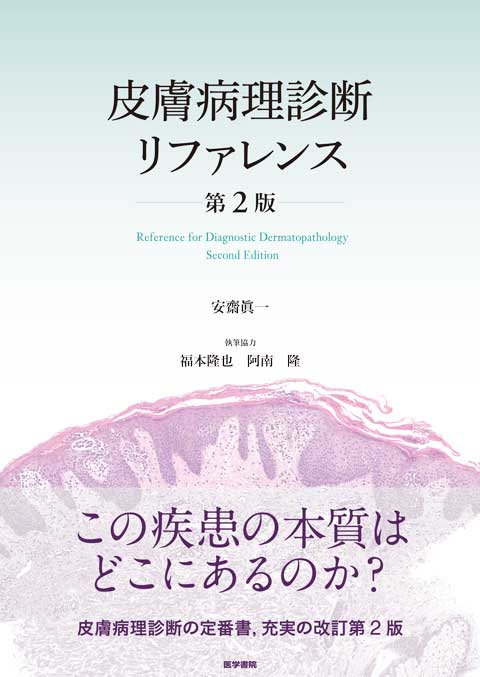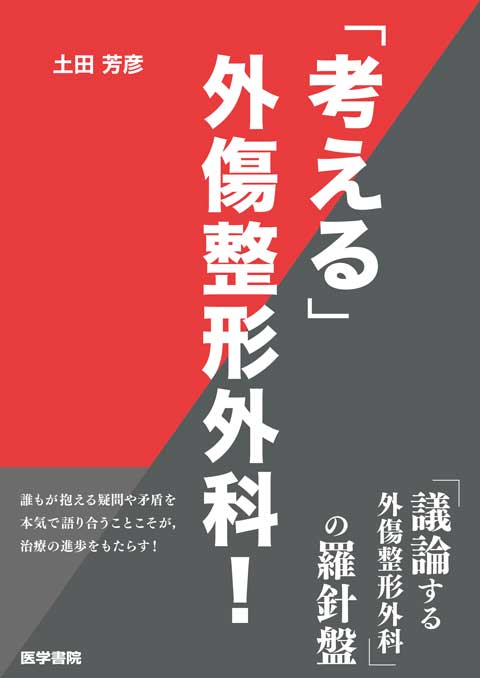MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.08.12 医学界新聞:第3576号より
《評者》
小林 光恵
作家
エンゼルメイク研究会 代表
訪問看護の本質に触れることばに出会う
幼児が転んだりしたとき,泣き出す前に絶句する間あいが見られることがある。驚きながら不安を覚えながら,事態を必死に把握しようとしているような瞬間。マンガなら目を見開いた顔のそばに心の声が太く大きく「え!?」と書かれているような一コマ。
勤め人の母が家にいる満ち足りた気持ちの日曜日の午後,母が買い物に出かける支度をしはじめたのを察知した幼い私にいつもこの「え!?」がやってきた。寂しくて大泣きをするために必要な助走のような時間だった。母の外出後,私は割と長く泣き続けた。
時を経て,2023年の秋に,年老いた母を私の自宅で看取った。そのときまでの3か月あまり,介護をする私の中にこの「え!?」の心境が生じて膨らんだ。そのときがまだ来ていないのにフライングで次の段階に進んでしまい大泣きしてしまったなら,私の立場として恥ずかしい気がしたし,なんといっても母の介護体制が崩れてしまうため,そうならないようにと気持ちが張りつめていた部分があった。
そんな私が無事に母を看取り,その後大泣きし,いまも心の中で静かに泣き続けて順調にグリーフワークを歩むことができているのは,ひとえに訪問看護ステーショングリーン(株式会社コメディコつくば)のサポートが素晴らしかったからだと思っている。母と私の状況をしっかり見極め,絶妙な距離感を保ちつつ,必要時には素早く手厚く適切に対処してくれたのだった。実はこのご縁もあって2025年2月から,この会社の介護事業のほうで週15時間,パート勤務をしている。
初回訪問から看取りケアまでの訪問看護師の頭の中を言葉にしてみた,という本書の目次に記された大見出し「距離感をはかる」に触れるやいなや,前述の訪問看護ステーションの皆さまの顔が一気に浮かんだ。そして,本書の著者の鈴木沙織さんと彼らをだぶらせて読み進めることになった。やはりそうだったんだ,こんなふうに考えていたんだな,と納得しながら。
例えばセミナーで,ひと通りの解説が終わり雑談の段になってから講師が発したフレーズによって,理解が一気に進むことがある。それは飾らない平易な言葉が,伝えたいことの微妙なニュアンスや肌ざわりのようなものを含んで言い得て妙な表現となり,本質がストレートに伝わってくるからではないだろうか。本書では,そんな表現にあちこちで出会った。そのうちのほんの一部を次に紹介する。
見出しより「自分を相手の〈温度感〉に合わせる」「応え続ける」「〈今〉だけでなく,〈前後〉までを意識する」「〈意味を伝える言葉〉で説明する」「安心を置いてくる」「ご家族の張り詰める気持ちをゆるめる」「不安や心配を前提にしない」
本文中より「~という的の絞れない不安や心配事を抱えながらも生活は続きます」「過度な共感でその問題を際立たせるような反応をせず」「病院が療養者さんに少しでも〈愛着〉をもって対応していただけるといいな」「また少し,その空間の〈時〉を進めます」
――著者の鈴木さんは,たぶん言葉選びにすぐには妥協しない方なのだと思う。2作目もぜひ読みたい。
《評者》
山本 晴康
愛媛大 名誉教授
千葉・柏リハビリテーション病院 病院長
「足の外科」の集大成
日本足の外科学会理事長の仁木久照先生が教科書『誰も教えてくれなかった足の外科』を出版された。副題は「NIKIメソッドによる治療戦略」である。仁木先生が聖マリアンナ医大整形外科学講座主任教授を退職されるのに合わせて出版された。メンターがいなかった先生が患者さんの足から学び,創意・工夫を凝らし,切り開いてきた「足の外科」の集大成である。
ぱらぱらとページをめくると,写真,図が多く,文章が少なく余白があり,読む気を起こさせる。ポイントを示すため,文字の色を変えたり,字体を太字にしたり,下線も引いたりして,文意を理解しやすい。図・写真は明確で,ポイントの部分に矢印があり,Web動画で理解を深めることができる。このように,読者の立場から本書は成り立っている。
内容は第1章「足部の痛み・変形のみかた――SOSを見逃さない」,第2章「足の外科手術を成功させる戦略」,第3章「一筋縄ではいかないケース」の3章から構成されている。仁木先生はこれまで,扁平足の生力学的研究,ばね靭帯の破綻から進行する扁平足の臨床研究,関節リウマチの足趾変形に対する関節温存手術,先天性内反足に対するPonseti法のアキレス腱皮下切腱術後のアキレス腱の再生など世界的研究をされ,足の外科をリードされてきた。これらの研究が行われた基盤である病態の解明,治療法の開発をベースとして,これらの3章は成り立っている。
それぞれの章では症例を提示し,その症例が持つ課題に対してどのように考えて理解し,どのような方法で解決するかというNIKIメソッドが示されている。第1章では,痛みと変形について診断へのアルゴリズムを提示し,症例を供覧して画像,動画で理解を深めさせてくれる。第2章では人工距骨併用人工足関節全置換術,外反母趾,関節リウマチ足趾変形,progressive collapsing foot deformity(進行性扁平足)などについて,症例を供覧し,術前の作図,術中の所見を普通写真,透視画像,動画で精緻に説明し,手術のコツと落とし穴など手術を成功させる秘訣も述べ,あたかも手術に立ち会い,仁木先生から直接説明を受けているように手術手技を理解できる。第3章は,仁木先生の戦略的思考が最もよく理解できる章である。一筋縄ではいかない症例を,問題点を分析し,どのような方法で解決するかという先生の思考の流れがよく理解でき,素晴らしい結果に感嘆する。
本書で取り扱われている疾患は限られているが,いずれもよく遭遇し,治療に悩む疾患である。取り上げられていない疾患も,「NIKIメソッドによる治療戦略」をマスターすれば対処できるのではないかと考えられる。
読者の方々にはこの素晴らしい教科書をメンターとして,患者さんに多大な裨益をもたらすとともに,足の外科をさらに発展させていただければと期待したい。
《評者》 山中 克郎 諏訪中央病院
日常診療に少しのユーモアと深い思索を添えたい医療者に
本書は,まるで著者・上田剛士先生の診察室を訪ねたかのような1冊だ。患者から投げかけられる質問の多くは,生活に根ざした素朴な疑問である。例えば「おならがよく出て困る」「指を鳴らすと指が太くなるのか」「タマゴは1日1個までにすべきか」といった問いは,一見些細なことに思えるが,患者にとっては健康を左右する切実な関心である。こうした問いに対して,ユーモアを交えながら科学的根拠に基づいて明快に解説するユニークな本である。文献的な考察をせず,適当に答えていた自分の外来診療を反省した。
「寝る子は育つ」という昔ながらの言い伝えに対し,著者は睡眠が成長ホルモンの分泌を促すだけでなく,摂食行動とも関連することを紹介し,睡眠不足は食べ過ぎから肥満になりやすいと説明する。寝ない人は「横に」育つとの絶妙なオチに,思わず笑ってしまう。そこには医師としての深い探究心と,健康に対する真剣なまなざしが通っている。評者の場合は,田舎で診療していると,畑仕事で真っ黒に日焼けした元気な高齢者に出会うことが多い。隣の畑の世話をする友人とおしゃべりし,食事だけで補えないビタミンDの不足分を日光浴で補っていたのか。さらに収穫の楽しみを得て,家族やご近所の人とその喜びを共有することが高齢者の生きがいになっているようだとか。
本書の特徴は,「シンプルな問い」に対し「過不足ない答え方」を提示している点にある。根拠は常にエビデンスに基づいているので,臨床医が自信を持って患者に説明できるだけの論拠を備えている。患者の疑問に対して,ただ事実を押しつけるのではなく,背景にある社会的・文化的背景を受け入れながら,科学的に正しい情報を提供するという医療者としての姿勢が全編を通じて貫かれている。
若手医師や医学生にとっては,教科書では取り上げられにくいが臨床現場で頻出するテーマについて,正確かつ実践的な回答例を学ぶ機会となる。また,患者とのコミュニケーションにおける言葉の選び方や距離感といった「語りの技術」も自然に身につく構成となっている。エビデンスに裏付けられた説明は,患者の信頼を得る上で不可欠であり,診療の質そのものを高める。本書は,まさにその姿勢を体現した1冊である。医師のみならず,日常診療に少しばかりのユーモアと深い思索を添えたい全ての医療関係者に本書を推薦したい。
《評者》 音成 秀一郎 広島大病院脳神経内科
てんかんと精神症状の交差点のロジックと深み
てんかんと精神障害――非専門医にとって,この組み合わせほど「コモン」でありながら,「自分が診るものではないランキング」の上位に入るものはない。多くの身体科の医師が避けてきた分野である。思うにこの絶妙な距離感は,学問側の責任でもあるだろう。てんかん発作の分類は複雑で分類はすぐに改訂されるし,精神疾患の用語もややこしくユーザーフレンドリーとは言い難い。
しかし,当直前夜にどれだけ願ったとしてもERで遭遇するのが「発作」であり,対応に困るのが関連する精神症状である。もちろん精神科医に相談したくなるが,「それほど頼りにならなかった」と感じた経験もあるだろう。ただし,これは精神科医の力量の問題ではない。むしろわれわれ身体科の医師がてんかんに関連する精神症状への理解を十分に持たず,「丸投げ」してきた構造的な問題ととらえるべきである。
実際,「発作」の鑑別には精神障害も含まれ,さらに,てんかん患者の精神症状の背景には薬剤の副作用や,脳炎などの内因性の病態がかかわることもある。すなわち,精神症状のアセスメントに内科的アプローチが欠かせないのだ。最終的な治療を精神科に委ねるとしても,その質を最大限に引き出すには,身体科の並診という土台が欠かせないし,身体科による適切な前段階の内科的な視点を持つことが求められている。そしてそこにメスを入れたのが本書である。
とはいえ,多くの身体科の医師は精神科的なトレーニングを受けていない。そこで本書は,こうした“苦手意識”に正面から取り組んでいる。特に,精神症状の拾い上げから始まる4つのステップは,非専門医でも取り組めるアプローチだ。一見とっつきにくい精神症状も,実際には構造化されており,極めて『ロジック』であることを本書で実感できるだろう。どのように問診し,どの視点で考えるかといった“型”が自然に身につくのである。
ところで本書のタイトル「苦手な人でもこれで安心! 4つのStep……」には少々驚いた。あの兼本浩祐先生が,手に取りやすさを優先したのかと。しかし,それは評者のハヤトチリで,やはり『兼本節』,そこは期待を裏切らない。本書の骨格となる4ステップの輪郭をつかんでいく過程で,兼本先生の膨大な臨床経験とそれに資する底なしの知識によって裏付けられた考察に随所で触れることができる。症例の提示数は50を超え,文献の参照数も300を優に超え,まさに兼本先生にしか書けない唯一無二の本であった。一方で,症例としては各種の自己免疫性脳炎や,てんかん術後の難治てんかんの精神症状,各種薬剤での注意点,神経発達症に伴うてんかん,そしてPNESなど,精神科医ではないわれわれを意識したラインナップで実にありがたい。ところで生成AIによって知識のアクセス性が大幅に向上した現在,表層的な知識を並べただけの医学書の価値は相対的に低迷し,アンチョコ本の賞味期限は短くなってきた。しかし,そのような「知識」に加えて,臨床現場での“思考的・経験的な視座”が加わることによって,これからの医学書に価値が与えられる。本書はまさにそのハイブリッド型の医書である。臨床医である読者が,著者である兼本先生と,本書の症例を通じて思考をぶつけあうような「知的ラリー」も楽しめる医学書の深みがある。レジェンドの臨床の追体験もできるのだから破格としかいいようがない。
これまで避けて通ってきた「てんかんと精神症状の交差点」,本書がその道筋を明確に示してくれるのは間違いない。自分は専門外と思ってきた方にこそ手に取ってみてほしい一冊である。もちろん読むかどうかは自由だが,読後に「読んでおけばよかった」と思っても,その時点ですでに読んでいるので問題はないし,もっとも,副作用として「もっと早く読めばよかった」はあるかもしれないが,それは本書評のせいでもなければ読者自身のせいでもない。本書の良さのせいである。
《評者》 山本 明美 旭川医大 名誉教授
痒いところに手が届く皮膚病理診断にかかわる医師必携の一冊
この度,安齋眞一先生の名著『皮膚病理診断リファレンス』第2版が刊行されました。安齋先生とは長年の友人関係にありますが,それにとらわれることなく,この本が本当に役立つものであることを実感しましたので,書評をお届けします。
皮膚病理組織学の分野では,『Lever's Dermatopathology:Histopathology of the Skin』などの成書を手元に置き,迷った際に参考にしている方も多いでしょう。しかし,安齋先生の著書は日本語で書かれているため,私たち日本人にとって圧倒的に短時間で内容を把握できるという利点があります。特に,総論的な記載が少なく,すぐに疾患各論が始まる構成となっているため,見た目の厚さや重さから想像する以上に幅広い疾患が網羅されています。このため,本書を辞書代わりに利用することができます。
さらに,最新の疾患分類や遺伝子変異,転座などの情報が加えられており,いまだ意見の一致を見ていない疾患概念についても丁寧に説明されています。厳選された典型的でわかりやすい病理組織の図が使用されている点も魅力の一つです。
日々病理組織診断に携わる先生だからこそ可能な,診断や鑑別診断に役立つ知識が満載で,初学者からベテランまで幅広い読者層に有益な内容となっています。日ごろ,疑問に感じていたことにも的確に答えてくれる点が本書の特長です。例えば,「リポイド類壊死の『類壊死』とは何なのか?」という疑問には,「変性と表現すればよい」と簡潔に説明されています。また,「最大径が4 cmを超えるBowen病で,基底膜をわずかに破った真皮内浸潤がみられた場合,TNM分類ではT3として扱われるがどうすべきか?」という問題については,「真皮網状層にまで及ぶものを浸潤性有棘細胞癌として考える」との記載があり,実用的で納得のいく内容です。
巻末の用語集も充実していてとても便利です。「縁取りサインって,言葉から連想するとアイライナーサインと同じような印象だけど,どう違うの?」といった疑問もすぐ解決できます。あるいは,ときどき学会で大御所の先生が「Kogoj海綿状膿疱では海綿状態はみられない」,という発言をされるのを聞いたことがあるけど,これはいったいどういうことなのかよくわからない,でも,大御所本人に聞くのはためらわれる,と思っている若手にわかりやすいように答えてくれています。皮膚病理診断にかかわる方にとって,本書はまさに“痒いところに手が届く”一冊と言えます。ぜひ一度手に取って,その有用性を実感していただきたいと思います。
《評者》 辻 英樹 札幌琴似整形外科 副院長
稀代の外科医が知識と哲学を惜しげもなくわかりやすく表現
私は著者の土田芳彦先生より札幌医大整形外科医局の6年後輩である。若い時分より土田先生の明敏な頭脳と分析力,また強さと行動力に魅せられ,外傷整形外科,重度四肢外傷治療に携わってきた。多分に僭越ながら本書の書評をさせていただきたいと思う。
本書の内容の土台となっているのは,外傷整形外科を議論する「場」において議論されてきたものである。コロナ禍において,土田先生は「webセミナー」「webカンファ」「webミーディング」を精力的に開催した。議論は的が絞られ,事前・事後討論もFacebook上で徹底的に行われた。そして全ての「場」で先生はコメントし続けてきた。私がいつも感心するのは,「top contributor」として求められる「言葉」「文章」が,常に迅速かつ的確であったことである。またさらに驚くのは,ご自身の外傷センターにおけるカンファレンス全症例に対しても同様の形式で議論し続けてきたこと,そしてその全議論の文章化に努められてきたことである。本書のタイトル「考える」を実践し続けてきたのは,紛れもなく土田先生ご自身である。本書の執筆作業も,ものすごい推進力で行われたと想像する。いまさらながら先生の明敏な頭脳と分析力,そして強さと行動力に感服するばかりである。
本書では,まず代表的症例のX線経過が数例提示され,次に分類や手術適応,手術方法などについての疑問点,論点がQ&A形式で解説される。そして土田先生が推奨する治療方法が提示され,その根拠とポイントが一つひとつ丁寧に解説されていく。手術動画も随所に盛り込まれている。内容の濃さ,わかりやすさ,そして実践に即した医学書として,私はこれ以上のものを知らない。「物事を常に理論的に考え,本質を追求する」という先生の人生哲学がその根底にある。そのため読むほどに「理解と共感」が深まっていく。本書はちまたに溢れる多数の執筆者の寄せ集めによる「教科書」とは全く異なるものである,ということをここで強調したい。
個人的には「ちょっと深掘り」と「Column」を大変興味深く拝読した。前者はいわば「マスター」向けの内容となっており,外傷整形外科の治療を常に「オーダーメイド」なものとして考え,追求していなければここまで深掘りすることはできないものである。また後者には外傷整形外科教育や学ぶ姿勢について,さらに本質的なコメントがちりばめられている。以前からいわれていたこと,最近いわれ出したこと,長くお付き合いさせていただいている私としては,常に進化し続けている先生の考えを活字で知ることができ,大変興味深い。
ここまで考え尽くされて完成した本書であるが,決してこれで「完璧」であってはならないと土田先生自身が思われているだろう。序文にも「本書は『羅針盤』である」と明記されている。われわれは常に考え,議論し,そして本書においてもいまだ解決されていない問題の最適解を考え続ける必要があろう。
最後に,外傷整形外科治療に興味がある方,今現在患者と向き合っている方,そして指導的立場にある方,また土田先生に興味がある方……いずれの方にも私はぜひ本書の通読を推奨する。もちろん通読が叶わなくとも,症例に遭遇した時,その部分だけを熟読するのもよい。この稀代の外科医が自分の知識と哲学を惜しげもなくわかりやすく表現してくれているのである。外傷整形外科治療に対する「理解と共感」が得られるのは間違いない。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

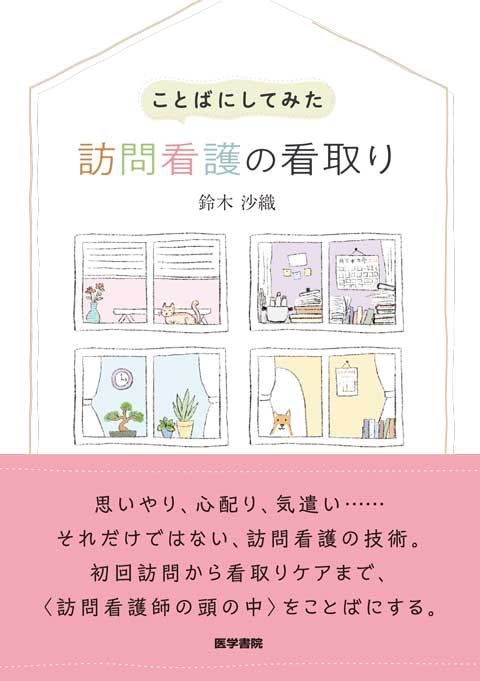
![誰も教えてくれなかった足の外科[Web動画付]NIKIメソッドによる治療戦略](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9617/4658/5769/113741.jpg)