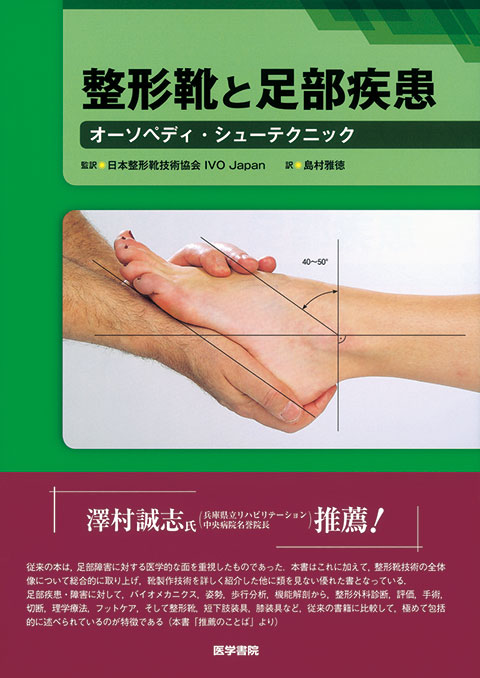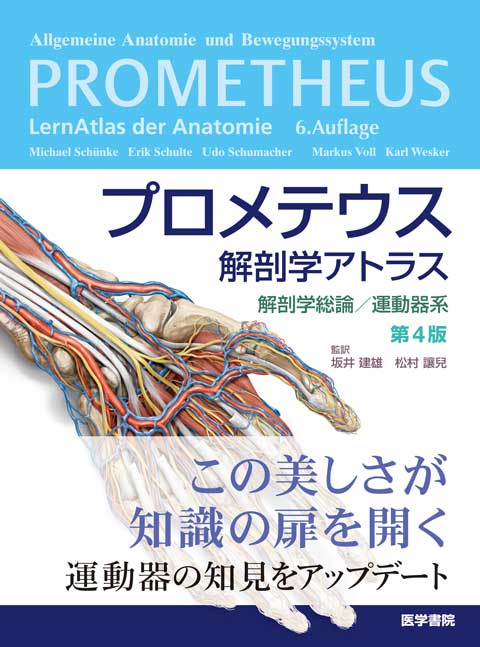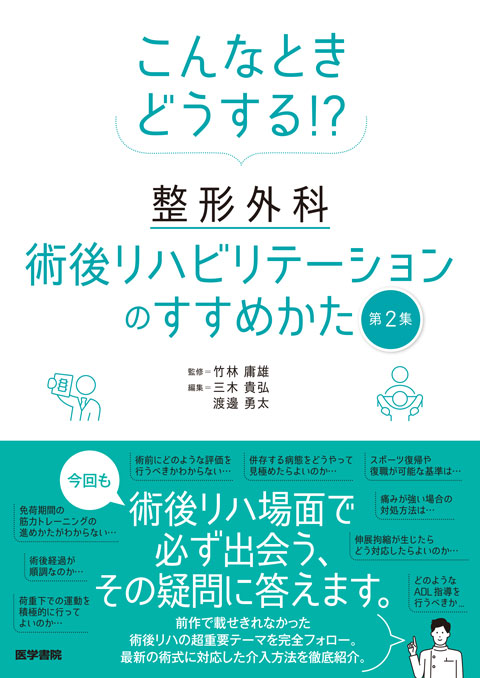誰も教えてくれなかった足の外科[Web動画付]
NIKIメソッドによる治療戦略
足の外科手術で起こる「こんなときどうしたらいいのか」に答える
もっと見る
この1冊が足の外科を学ぶ人のメンターになる! 解剖学と病態の詳細な観察から本領域を開拓してきた著者直伝の「NIKIメソッド」による手術戦略を、100本を超える動画と豊富な画像を交えて惜しみなく解説。多様な症例をベースに、足の外科手術で起こる「こんなときどうしたらいいのか」という疑問に、エキスパートの視点から答える。ワンランク上を目指す足の専門医必読のテキスト。
| 著 | 仁木 久照 |
|---|---|
| 発行 | 2025年03月判型:B5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-05743-1 |
| 定価 | 13,200円 (本体12,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
以前から,足の外科に関する教科書執筆のお話はいくつか頂戴していた.しかし,既知の内容をあらためて羅列する教科書執筆は筆者には魅力的ではなく,「教科書はほかにも沢山あるので……」と敬遠していた.ある日,「先生が日頃の診療,手術で考えていること,つまり仁木先生の哲学そのものと解剖と身体所見の重要性を再認識し,学ぶ楽しさが詰まった本にしたい」と医学書院から話があった.「それならば,書いてみます」と回答した.教授退任3年前の2022年4月,『誰も教えてくれなかった足の外科』の始まりである.
なぜ,「誰も教えてくれなかった足の外科」なのか?
自慢できることではないが,筆者には足の外科の師匠はいない.たまたま留学し,たまたま参加したAAOSのFoot & Ankleセッションで驚愕の事実を目の当たりにした.当時の日本とは異次元の内容のオンパレードは,筆者の足の外科に対するイメージを一掃した.なかでも「扁平足」「バイオメカニクス」「新鮮屍体」という言葉がとても魅力的だった.紆余曲折あったが〔このエピソードは,J Orthop Sci.2024 Sep;29(5):1159-1161.のeditorialに掲載〕,幸運にも新鮮屍体の実験に関わることができ,そこで初めて足の解剖の大切さと魅力を知った.以後,足の外科は筆者のライフワークとなったが,師匠もいない,教科書もない,そうした状況で診療していくには,目の前の患者さんを教科書にして,文献を読み漁り,細切れの情報を収集し,知恵を振り絞って結びつけて1つひとつ解決し,それを繰り返していくしかなかった.そうした苦行のなかでも幸運だったのは,足の外科医を目指して一緒に臨床・研究をしてくれた聖マリアンナ医科大学整形外科の足の外科診療班の多くの仲間たちに恵まれ,切磋琢磨できたことである.こうした背景から,医学書院の方から『誰も教えてくれなかった足の外科』というタイトルを提案され,筆者が仲間に足を語る表紙デザインが誕生した.
当初は,足のすべての疾患をどう考えるかとしていたが,読者対象を足の外科専門医に絞るなら,手術の詳細にページを割いたほうがよいのでは,という意見があり,すべての疾患を網羅することをやめて,教科書やガイドラインには載っていないこと,診断に悩む・迷うケース,一筋縄ではいかない症例などに対する筆者の「思考の流れ」を解説したものとする方向に転換した.これが「NIKIメソッド」と命名した所以である.
臨床成績がよくも悪くも過去に印象に残った症例を呈示しながら,誰に遠慮することなく自分の中で論理立てた診察や手術を行ったときにタイムスリップし,細部にまで拘って後輩に指導するつもりで執筆したので,自分でも驚くほどのスピードで書き進めることができた.多くの写真・画像に加え動画もふんだんに取り入れたので,足の診療の醍醐味に触れていただけるはずである.限られた疾患が対象となったが,困ったとき,迷ったときに読みたくなる内容,さらに病態解明や治療法開発のヒントを掴める内容になっていれば幸いである.
最後に,医学書院医学書籍編集部の石井美香氏をはじめ,皆様のご理解とご協力に感謝いたします.また,大学での就業に理解を示し常に協力してくれた妻と子どもたち,長年,私と臨床・研究をともにしてきた聖マリアンナ医科大学整形外科の足の外科診療班に所属したすべての先生に感謝し,本書を捧げます.
2025年3月
仁木 久照
目次
開く
本書の付録Web動画について
略語一覧
PCFD分類のみかた
第1章 足部の痛み・変形のみかた──SOSを見逃さない
1 足根洞から外果先端周辺の痛み──原因はたくさんあるけれど,何が答えなの?
2 捻挫後の凹足と跛行──保存か・保存じゃないか,それが問題だ!
(Column) 低エネルギー外傷で腫脹がないにもかかわらず,Chopart関節脱臼と誤診されたケース
3 腓骨筋痙性扁平足をみたら,あらゆる疾患,外傷を考える!──腓骨筋痙性扁平足の診断はどうする?
4 片側の成人期扁平足!──つま先立ちができない!「Single heel rise test陽性」 すぐにPTTDと診断して大丈夫?
5 Lisfranc靱帯・関節損傷──見逃さない・長引かせないために何を診る? 見つけたらどうする?
(Column) 繰り返しでみる目を養う
6 母趾の伸展ができない──それって強剛母趾ですか?
第2章 足の外科手術を成功させる戦略
1 人工距骨併用人工足関節全置換術(CTAA)──従来法はこうカスタムする
2 外反母趾手術を成功させるには?──重症度に合わせた手術で柔軟に対応し,短縮をためらわない
(Column) 治療法は常に変化する
3 外反母趾Mann変法──矯正を限界ギリギリまで攻めるには?
4 外反母趾に対するMTP関節固定術──労せずにM1M2矯正をするコツ
5 関節リウマチ足趾変形に対する関節温存手術
6 PCFD手術を成功させるコツ
7 3関節固定の際の矯正と固定──どこから固定するのが正解?
8 外脛骨障害に対する治療戦略──保存療法はどうする? 手術療法はこうする!
9 Ponseti法を深掘りする──内反足治療のパラダイムシフトをもたらした手法
(Column) 乳児足の練習用模型
(Column) AAOS 3年連続oral発表の始まり
(Column) 内反足治療の歴史的変遷
(Column) Ponseti法との出会い
10 Ponseti法後再発例に対する前脛骨筋腱外側移行──成功させるコツ
11 距骨下関節全周解離後のK-wire固定方法──コツはあるの?
12 足部内視鏡で低侵襲手術を極める
13 足底鏡(plantar endoscopy)による滑膜切除──safe zoneってどこにある?
第3章 一筋縄ではいかないケース
1 扁平足+内反型変形性足関節症──それってPCFD Class Eと違う? どう治療する?
2 QOL低下が顕著なTTC固定を避ける──「ハイリスク・ローリターン」から「ローリスク・ハイリターン」手術へ
3 内反凹尖足変形,どこから何を治療する?──何に注目して術式を決めるのか,その順番をどうする? 手術のタイミングはいつ?
4 内反凹足を伴った重度内反型Ankle OAに対するTAA──「足関節だけを見て足部全体を見ず」ではダメ!
5 Ponse-Taylor法──成功の決め手は術前プランニングにあり
6 足根骨癒合に症状のないaccessory antero-lateral talar facetを伴う場合,どうする?
7 難治性PSFFに腱延長または腱切りは有効か?
8 RAのskewfootはどうする?──所見をとりながら,手術の順序を組み立てていく!
9 見逃しやすいRA Chopart関節病変──もし初期にみつけられたらどうする?
10 多種多様な外反母趾,どう解決する?
[1] Lisfranc関節OAを伴う外反母趾はどうする?
11 多種多様な外反母趾,どう解決する?
[2] 第2趾外反を伴った重度外反母趾はLapidus法単独でOK?
12 多種多様な外反母趾,どう解決する?
[3] 超重度の外反母趾 関節温存にこだわるか,固定術を選ぶか,それが問題だ!
13 多種多様な外反母趾,どう解決する?
[4] 内転足を伴ったイレギュラーな外反母趾
14 外脛骨障害によるばね靱帯損傷を見逃さない!
15 強剛母趾──Cheilectomyか,固定か,それとも?
索引
書評
開く
すぐにでも臨床で実践できる実用書
書評者:田中 康仁(医真会八尾総合病院足の疾患センターセンター長)
日本足の外科学会理事長である仁木久照先生が,ライフワークとしている足の外科の集大成とも言える書籍を出版されました。一人の足の外科医として足の疾患と真摯に向き合い,難しい病態に対する治療法を,聖マリアンナ医科大整形外科・足の外科班の仲間と一緒に,まさに紡ぎ出したと表現するのがふさわしい,ご苦労の跡が手にとるようにわかる感動的な内容になっています。
仁木先生は物事を非常に緻密に考えられ,構想されたことを形にする実行力と決断力を兼ね備えた素晴らしいリーダーであります。日本で初めての足疾患に特化した患者立脚方評価法であるSAFE-Qを,仁木先生は日本足の外科学会の当該委員会の委員長として一から作り上げ,まとめあげられました。私も委員の一人として参加し,つぶさにその作成過程を拝見しました。何もないところから質問項目を選定し,統計学的な手法を駆使して下位尺度を順序立てて決められて,さまざまなことを積み上げられてできた最終案をさらに検証されて論文として完成させるという仁木先生の素晴らしい才能に感服した覚えがあります。
本書はまさにこれと同様に治療法を紡ぎ出し,そのポイントを惜しげもなくつまびらかにした内容になっています。「NIKIメソッド」というネーミングは,緻密で論理的な仁木先生の手技を的確に表現されており,非常にチャーミングな言葉であると感じました。
仁木先生といえば扁平足の第一人者ということで有名でありますが,2020年に成人期扁平足のPCFD(Progressive Collapsing Foot Deformity)分類という概念が米国を中心として提唱されました。日本足の外科学会ではPCFDの和訳を進行性扁平足といたしました。本書では,その治療戦略についても詳細に述べられています。その他の疾患においても,アルゴリズムを駆使して,明確に基準を決めて術式を選択していくという大変わかりやすい構成になっています。足の外科のベテランの先生にはNIKIメソッドを取り入れていただき,ご自身の診療の幅を広げていただきたいと思いますし,足の外科を始めたばかりの先生方にも非常に参考になる内容が網羅されております。また,Web動画がついており,実際の手技がわかりすぐにでも臨床で実践できる実用書であります。
足の外科に少しでも興味がある先生はぜひ一度手に取っていただきたいと思います。
仁木先生から足の外科を教えてもらえるわれわれは幸せだ
書評者:寺本 篤史(札幌医大教授・整形外科学)
2025年3月31日,仁木久照先生が聖マリアンナ医大整形外科の主任教授をご退任された。足の外科を長年けん引されてきたトップリーダーが第一線を退かれることに,大きな喪失感を抱かずにはいられなかった。同時に,これからの足の外科の未来に対する一抹の不安も覚えていた。しかし,その思いを払拭するかのように,まさに同日,本書が刊行された。副題に掲げられた「NIKIメソッドによる治療戦略」が示すとおり,既存の教科書には見られない,仁木先生独自の診断と治療のアプローチが随所に盛り込まれている。
本書を開いて最初に驚かされたのは,第1章,1のテーマが「足根洞から外果先端周辺の痛み」であったことだ。いきなり専門的かつ臨床現場でしばしば見逃されがちな病態から始まる点に,ただならぬ熱量を感じた。足根洞部の痛みは日常診療でも遭遇するが,原因や病態の解明が難しく,漫然と「足根洞症候群」として扱ってしまうことも少なくない。足の外科を専門としない限り,その存在すら知られていないこともあるだろう。そんな領域に対し,わかりやすい診断アルゴリズムと症例提示をもって,極めて実践的に解説されている点に深い感銘を受けた。
第2章「足の外科手術を成功させる戦略」は,本書の核心部分である。特に外反母趾手術へのこだわり,関節リウマチに対するCMOS(Combination Metatarsal Osteotomies for Shortening:中足骨近位短縮骨切りによる関節温存手術)の実際,さらにPCFD(progressive collapsing foot deformity)手術の要点に至るまで,圧巻の内容が続く。術前計画から実際の手技に至るまで,tipsとpitfallsを交えて非常に詳細に解説されており,理論と実践の両面から理解が深まる構成となっている。一読してすぐにまねできる手技書とは異なり,それぞれの手技の背景にある思考や工夫が丁寧に示されている点が,むしろ本書の価値を際立たせている。
特筆すべきは,書籍全体を通して144本にも及ぶ動画コンテンツが提供されている点だ。「Web動画付」と表紙に小さく記されているが,その充実度からするともはや“付録”ではない。むしろ動画視聴が主軸となり得る内容であり,読者の理解を飛躍的に深めてくれる。
第3章「一筋縄ではいかないケース」では,極めて難渋した症例に対する治療戦略が紹介されている。私自身,長年足の外科に携わっているが,診断や治療の道筋が立てられずに悩むことが少なくない。そんなとき,この章が道しるべとなり,救いとなる場面が何度も訪れることだろう。いずれの症例も記憶に刻み,必要なときには再読して臨床に生かしたい。
『誰も教えてくれなかった足の外科』というタイトルどおり,仁木先生のご苦労と積み重ねてこられたご努力,そして情熱の源泉は,巻頭の「序」に記されている。教授退任を機に執筆されたという経緯も,先生の誠実なお人柄を感じさせ,深く胸を打たれる。
本書には,仁木先生の思考,技術,そして哲学が惜しみなく詰め込まれており,足の外科の本質的な魅力と奥深さを私たちに教えてくれる。仁木先生から直接,足の外科を教えてもらえる私たちはとても幸せであると,改めて感じさせられる一冊である。
「足の外科」の集大成
書評者:山本 晴康(愛媛大名誉教授/千葉・柏リハビリテーション病院病院長)
日本足の外科学会理事長の仁木久照先生が教科書『誰も教えてくれなかった足の外科』を出版された。副題は「NIKIメソッドによる治療戦略」である。仁木先生が聖マリアンナ医大整形外科学講座主任教授を退職されるのに合わせて出版された。メンターがいなかった先生が患者さんの足から学び,創意・工夫を凝らし,切り開いてきた「足の外科」の集大成である。
ぱらぱらとページをめくると,写真,図が多く,文章が少なく余白があり,読む気を起こさせる。ポイントを示すため,文字の色を変えたり,字体を太字にしたり,下線も引いたりして,文意を理解しやすい。図・写真は明確で,ポイントの部分に矢印があり,Web動画で理解を深めることができる。このように,読者の立場から本書は成り立っている。
内容は第1章「足部の痛み・変形のみかた―SOSを見逃さない」,第2章「足の外科手術を成功させる戦略」,第3章「一筋縄ではいかないケース」の3章から構成されている。仁木先生はこれまで,扁平足の生力学的研究,ばね靭帯の破綻から進行する扁平足の臨床研究,関節リウマチの足趾変形に対する関節温存手術,先天性内反足に対するPonseti法のアキレス腱皮下切腱術後のアキレス腱の再生など世界的研究をされ,足の外科をリードされてきた。これらの研究が行われた基盤である病態の解明,治療法の開発をベースとして,これらの3章は成り立っている。
それぞれの章では症例を提示し,その症例が持つ課題に対してどのように考えて理解し,どのような方法で解決するかというNIKIメソッドが示されている。第1章では,痛みと変形について診断へのアルゴリズムを提示し,症例を供覧して画像,動画で理解を深めさせてくれる。第2章では人工距骨併用人工足関節全置換術,外反母趾,関節リウマチ足趾変形,progressive collapsing foot deformity(進行性扁平足)などについて,症例を供覧し,術前の作図,術中の所見を普通写真,透視画像,動画で精緻に説明し,手術のコツと落とし穴など手術を成功させる秘訣も述べ,あたかも手術に立ち会い,仁木先生から直接説明を受けているように手術手技を理解できる。第3章は,仁木先生の戦略的思考が最もよく理解できる章である。一筋縄ではいかない症例を,問題点を分析し,どのような方法で解決するかという先生の思考の流れがよく理解でき,素晴らしい結果に感嘆する。
本書で取り扱われている疾患は限られているが,いずれもよく遭遇し,治療に悩む疾患である。取り上げられていない疾患も,「NIKIメソッドによる治療戦略」をマスターすれば対処できるのではないかと考えられる。
読者の方々にはこの素晴らしい教科書をメンターとして,患者さんに多大な裨益をもたらすとともに,足の外科をさらに発展させていただければと期待したい。
![誰も教えてくれなかった足の外科[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9617/4658/5769/113741.jpg)
![AO法骨折治療 Foot and Ankle [英語版Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/5616/8248/3611/110660.jpg)