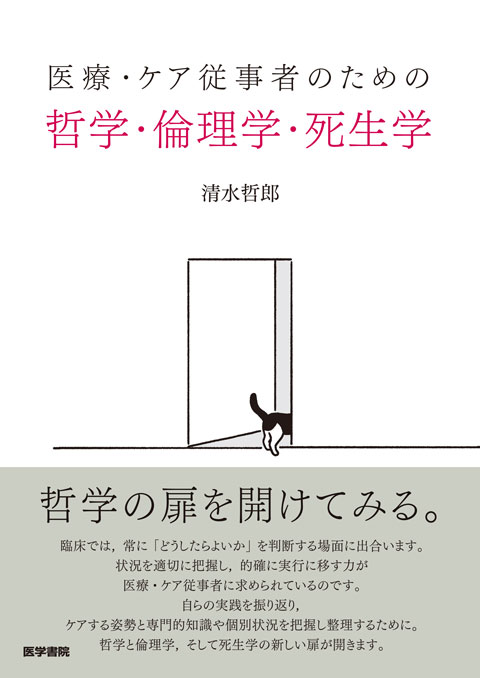応用倫理学入門
[第8回] 臓器移植の倫理(2)――新たな技術が拓く未来
連載 澤井 努
2025.04.08 医学界新聞:第3572号より
新たな臓器移植技術は,慢性的な臓器不足の解消に大きな可能性をもたらす一方,動物の利用をめぐる根本的な倫理的課題や技術の社会的受容の課題を提起しています。今回は,30年後の未来を展望し,異種移植や動物体内で作製されたヒト臓器の移植について,生命倫理,動物福祉,患者の権利保障,公平性といった多角的な視点から,未来の移植医療の方向性を考えていきたいと思います。
30年後の未来
今から30年後の2055年,腎不全を患うAさん(55歳,男性)は,総合病院で人工透析を受けながらドナーを待っています。この時代では,移植用の臓器不足が大幅に改善され,Aさんには次の2つの方法が提示されます。「拒絶反応を抑えた遺伝子改変ブタの腎臓を移植する」方法Xと,「Aさん自身の細胞を使い,ブタの体内で腎臓を育てて移植する」方法Yです。いずれも数か月以内に移植が可能だと聞き,Aさんと家族は安堵します。しかし同時に,「動物を犠牲にすることへの戸惑い」や「移植後にブタ由来の臓器が自分の体内にあることへの抵抗感」も抱えています。
主治医は次のように説明します。方法Xでは,移植される臓器こそブタの腎臓ですが,最新の技術で拒絶反応を大幅に軽減しており,安全性が確立されています。これに対して方法Yでは,Aさんの細胞をもとにブタの体内で腎臓を育てるため,移植臓器はあくまでAさん自身の細胞から作られた腎臓です。また,方法Xと方法Yのどちらについても,提供手術の際にはブタに十分な麻酔を施すなど動物福祉に配慮し,また移植に用いられた動物への慰霊式も定期的に行っているとのことです。
さらに,臓器移植を専門とする倫理カウンセラーから,「動物が人の意識を持たないよう科学的・法的に対策が取られている」「臓器を提供するブタは適切な環境で飼育・生産されている」など,詳しい説明も受けました。こうした情報を踏まえ,最終的に方法Yを選択することにしたAさんは手術を受け,移植した新しい腎臓も順調に機能しています。
異種移植と動物体内で作製されたヒト臓器の移植
異種移植とは,ヒト以外の動物(主にブタ)の臓器を人に移植する技術です。かつては免疫拒絶反応や未知の感染症リスクが大きな懸念でしたが,近年の遺伝子編集技術(CRISPR-Cas9など)を用いることで,ブタの臓器をヒトに適合させる研究が急速に進んでいます。具体的には,拒絶反応の原因となる分子の除去や,ブタ細胞に潜むウイルスの不活化が進められています。2022年には,アメリカで遺伝子操作したブタの心臓を末期の心臓疾患患者に移植する世界初の手術が行われ,大きな注目を集めました。
動物体内で作製されたヒト臓器の移植は,ヒトの細胞で作られた臓器を動物の体内で育てて移植するという別の方法です。まず,あらかじめ特定の臓器が形成できないよう遺伝子操作した動物の胚(胚盤胞)を用意します。その胚にヒトの多能性幹細胞(例:iPS細胞)を注入すると,動物の胚は自分で作れない臓器の「空き領域」にヒトの細胞を取り込み,ヒト細胞で形成された臓器を持つキメラ動物が生まれます。実際にこの方法によって,マウス体内で育てたラット由来の膵臓を移植することに成功しているため,ブタなどの大型動物でヒトの臓器を移植することも期待されているのです。
生命倫理と動物福祉をめぐる課題
新たな臓器移植技術には,人の生命観のみならず,動物の福祉や権利にも深くかかわる課題があります(臓器移植をめぐる一般的な倫理的課題については連載第7回を参照)。例えば異種移植では,ブタなどの提供動物が無菌環境で飼育され,人工授精や帝王切開で繁殖されるほか,移植に適した臓器を得るための外科的処置や採血が繰り返されます。その過程で動物に大きな負担や苦痛が伴うため,「たとえ人を救...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
取材記事 2026.02.10
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。