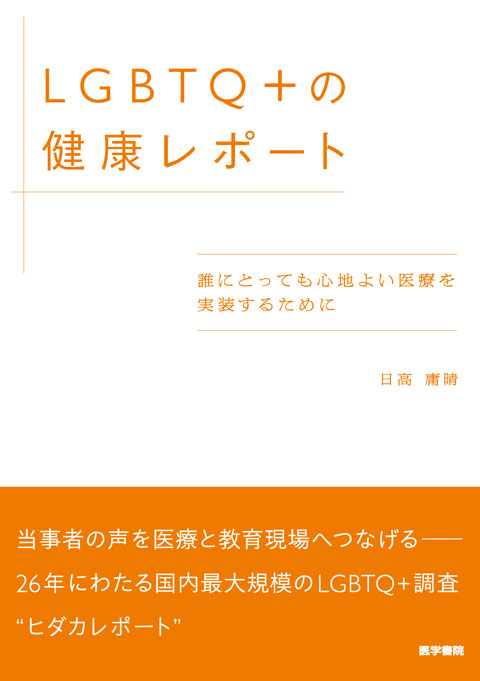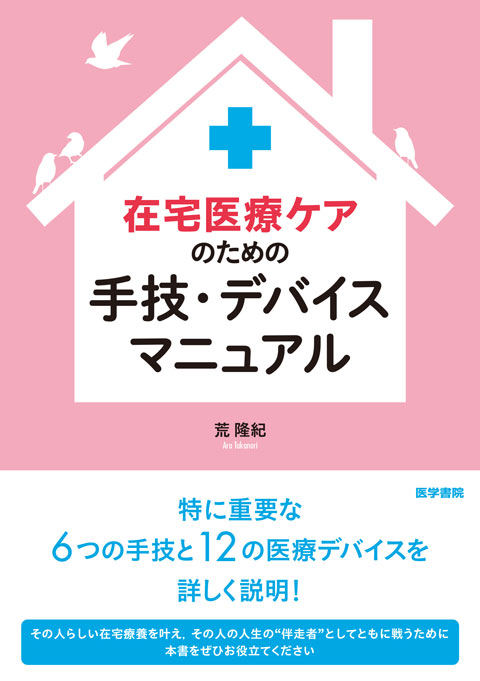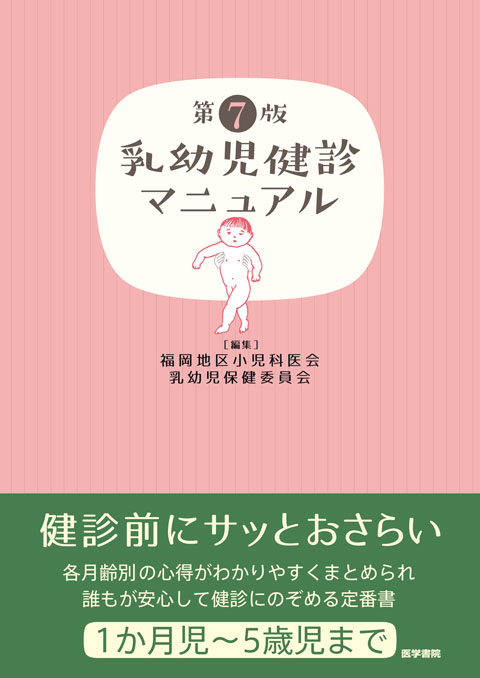MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.04.08 医学界新聞:第3572号より
《評者》 片岡 仁美 京大医学教育・国際化推進センター 副センター長
世の中が変わる以前からの丹念な科学的データの集積
歴史に残る1冊である,ということをまず述べたい。歴史が動く時がある。その渦中に居る時,たった数年間で世の中が変わった,とわれわれは実感する。しかし,その動きの速さに流されながら「世の中は変わった」と,わかったように納得してはいないだろうか。
本書はまさにLGBTQ+について世の中が大きく変わっていくさなかに出版されたが,著者による科学的な検証の端緒は27年前にさかのぼる。精緻で科学的な視点で丹念にデータを集積し,経時的にそれを分析した結果の重さは,潮目が大きく変わる時期においてその価値は一層大きい。
そして,科学的,歴史的な価値のみならず,私は著者の一貫した考え方に非常に感銘を受ける。それは「社会的に可視化困難であるとは,つまり存在そのものが見えにくいことを意味するが,だからといって社会的に存在していない訳では決してない。(中略)存在が可視化されないことによっていつまでも現状が把握されず,その結果としてニーズがあるにもかかわらず公の施策の対象となりにくいという現実である」(「はじめに」)という文章に端的に表れている。見えにくいからないのではない。見えにくいから見なくてよいのではない。その信念に触れ,特に医療にかかわるものとして背筋を伸ばさざるを得ない。
本書には本来悩みや苦しみをもって訪れる方の癒しの場であるはずの病院が,LGBTQ+の方にとっては期待とともに「恐れ」を抱く場であることを多くのデータとともに示している。性的指向は隠すことも話すことも不安が伴う。これらのことが受診を控えることにつながることも少なくなく,無理解による辛い体験はさらに受診への障壁を大きくする。自身も患者の立場になった時,医療従事者の何気ない一言をどんなに深く受け止めてしまうかということを経験した。LGBTQ+の方が受診そのもののハードルを乗り越え,勇気を振り絞って自身の奥深い部分まで開示して,そこで理解が得られなかったら,その失望と苦痛はいかほどだろう。
著者は,「専門職として医療従事者に求められること」という第6章の冒頭で「個々の患者はさまざまな生活実態や背景を持ち,その背景の1つに性的指向やジェンダーアイデンティティを含むセクシュアリティの多様性がある。そしてそれらは,人格形成の根幹をなす基本的人権の1つであることを,医療従事者は認識する必要がある」(p.121)と述べている。患者の背景を理解する必要がある,ということを私たちは意識すべき,したいと思っている。しかし,そのためにはいつも自分が見えているものは十分だろうか,と振り返ることが必要である。患者の大切な部分に触れることの重さを本書を通して改めて問われた気がした。本書に込められた思いをわれわれは深く受け止めたい。
《評者》 樋口 秋緒 社会医療法人北晨会恵み野 訪問看護ステーション「はあと」管理者 / 保健師 / 診療看護師(NPプライマリ・ケア分野)
訪問の現場に持ち歩いて活用したい一冊
この本は,在宅医療にかかわる全ての事業所,特に訪問看護ステーション全てに置いてほしい一冊だ。
いや,置くだけでなく,ボロボロになるまで使ってほしい本かもしれない。
もっと言うと,「手技・デバイスマニュアル」という題名ではあるが,手技=手順書ではない。看護手順書のように,細かな処置の手順が書かれているわけではないが,日常管理における留意すべき点が,医療職・看護職として診るべきエビデンスに則って記載されていて説得力のある内容であり,しかも在宅ならではのポイント解説付き。なので,訪問の現場に持ち歩いて活用したい一冊なのだ。
評者は長年,訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護に携わっている診療看護師(NP)だ。日本ではまだ国家資格化はされていないが,より高度な医学・看護アセスメントを学び患者さんのケアに還元できるようにと,今は多くの大学院にて診療看護師(NP)コースが開講されている。そこでは,「今までこうだった」「私はこうやってきた」では通用しない。この診療看護師(NP)コース履修中は「なぜそれが必要なのか」「なぜ?」「なぜ?」とずっと問われ,今までの知識や持っている看護書だけでは到底解決できない多くのことにぶつかった。その頃この本があったら,もう少し楽できたのに(笑)。以降,後輩たちの育成に携わり,気管切開カニューレ,膀胱瘻カテーテルの交換や管理について伝授する機会をいただいたが,その準備においても,手技だけでなく,診療看護師(NP)として知っておくべき裏付け(エビデンス)を伝えたく,あの本この論文とたくさんの書物をあさっていた。それがこの一冊でほぼ賄えるのだから,間違いなく「待っていました!こんな本」なのだ。
本の構成は,在宅デバイス学と在宅手技学の二つに分類されており,どの項においても実際の手技が記されている。特に目を引いたのは,人工呼吸器の項で,加温加湿器や吸引器の扱いも取り上げていることである。特に痰吸引は看護学生のときから学ぶ項目だが,加湿器と絡めて説明されているので改めて勉強になる。
在宅手技学の項では,トリガーポイント注射や腹腔穿刺,胸腔穿刺が取り上げられている。これらの処置は,看護師が実践することはできないが,訪問先で腹水や胸水除去の必要性やタイミングなどをアセスメントする際の指南にもなり,患者さんやご家族に説明する時の具体的なイメージ共有に活用できて,それは安心の提供につながる。
医療が病院から在宅へ切り替わろうとしている昨今,住み慣れた地域で安心安全な療養生活を支えるべく医療従事者にとって,医療の質の担保と向上の取り組みに飽くことはない。この本に出合ったことに感謝し,これを機に,一層,在宅療養支援チームの一員として精進していきたいと思った。
《評者》 永光 信一郎 福岡大主任教授・小児科
生物学的・心理的・社会的視点から乳幼児の成長と発達を記した健診マニュアルの成書
2023年4月にこども家庭庁が創設されて以来,子ども政策にかかわる事業が積極的に推進されています。その1つが効果的な乳幼児健診の拡充で,2024年1月から1か月児健診と5歳児健診が母子保健医療対策総合支援事業となりました。1か月児健診は乳児早期の疾病および異常を早期に発見し適切な指導を行い,さらに養育環境の評価と,養育者への育児に関する助言を行う目的で実施され,5歳児健診は成長・発達に影響を及ぼす発達障害の早期発見・支援と生活習慣に関する指導を目的としています。
福岡地区小児科医会では,40年以上前より,4か月,10か月,1歳6か月,3歳の公費で実施する悉皆の乳幼児健診以外に,1か月,7か月,12か月,2歳,4歳,5歳,6歳の乳幼児健診を,希望者を対象に実施していました。1992年の初版以来,本マニュアルは最新の情報に改訂され,かつトピックスを掲載しながら,このたび第7版を発刊することになりました。今までの健診事業で培われた知見がこのマニュアルに詳細にわかりやす...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。