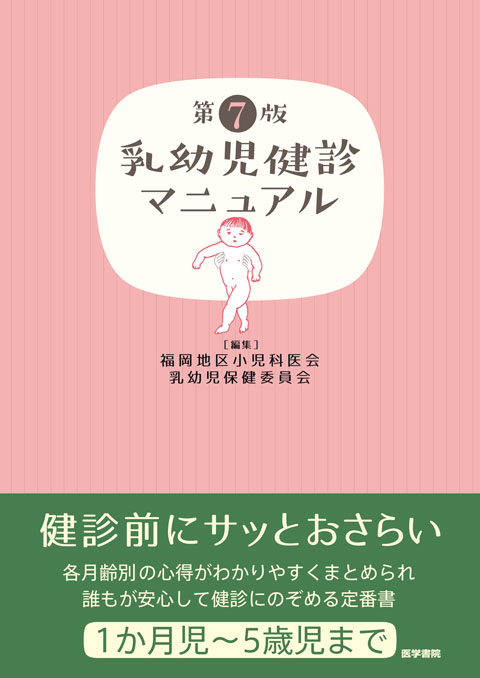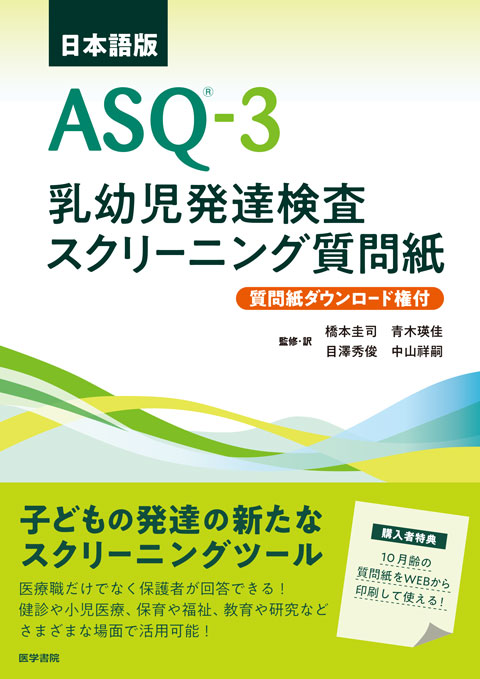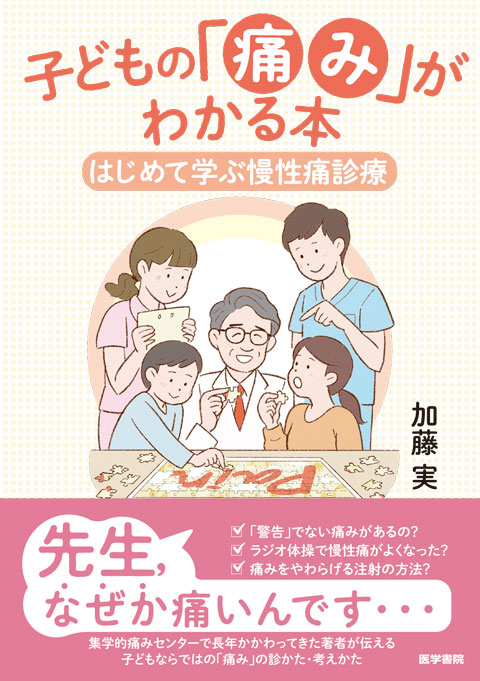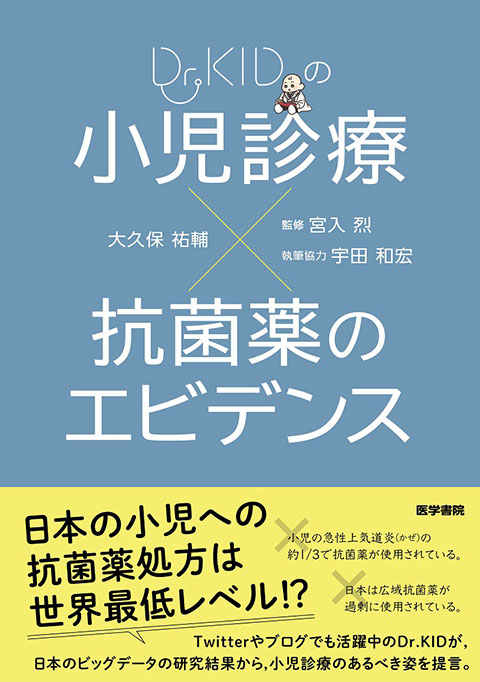乳幼児健診マニュアル 第7版
サッと読めてすぐにわかる、誰もが安心して乳幼児健診にのぞめる定番書
もっと見る
本書の編集委員会は、長いあいだアクティブに活動する団体として小児科領域を先導しており、特に乳幼児健診では「福岡式」として全国的な認知度も高い。基本的なコンセプトは前版までを踏襲し、誰もがすぐに目を通せる要点をまとめたマニュアルとして、乳幼児健診をあまり良く知らない人でも合格点の健診ができる1冊となっている。今版では情報内容が更新され、乳幼児にかかわるトピックやコラムもさらに充実した改訂となった。
| 編集 | 福岡地区小児科医会 乳幼児保健委員会 |
|---|---|
| 発行 | 2025年01月判型:B5頁:178 |
| ISBN | 978-4-260-05756-1 |
| 定価 | 3,520円 (本体3,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
第7版を編集するにあたって
2023(令和5)年に閣議決定された成育医療等基本方針により,母子保健施策の一環として,出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を整備することを目的とし,全国の自治体での健康診査の実施を目指す「1か月児」および「5歳児」健康診査支援事業が開始されました.成育基本法には,医療関係者などの責務として「国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力し,成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努めるとともに,成育医療等を必要とする者の置かれている状況を深く認識し,良質かつ適切な成育医療等を提供するよう努めなければならない」とされています.
核家族化,貧困や格差の問題,コロナ禍以降の急激な少子化の進行に加え,家族の役割分担の変化,生活の多様化など,子育てにかかわる課題は複雑になっています.従来からある健診についても,新たな年齢の健診についても,健診医には診断につながる知識・スキルとともに,養育者の置かれた環境を理解し寄り添った支援を行うことが求められます.本マニュアルでは初版から,育児不安を抱えた養育者に対する心構えや,養育者の立場を理解した対応の大切さについても触れてきました.
今版では,月齢別の健診のしかたの「1か月児健診」において,公費健診となることを念頭に,1か月児健診をかかりつけ医による子育て支援の起点と位置付け,周産期の情報収集のポイントとなる母子手帳の確認事項をわかりやすく記載しました.後半部の育児相談・育児支援については新項目として「食物アレルギー」,「スキンケア」,「子どもの虐待への気づきと支援」を新たな執筆者にお願いしました.また,コラムとして「DOHaD説」,「拡大新生児マススクリーニング」,「新生児聴覚スクリーニング後の支援」,「こども家庭センターについて」,「スポットビジョンスクリーナー」を追加しました.
ご多忙ななか,作業に多くの時間を割いていただいた執筆者の皆様,第4版から細部にわたって目を配り編集に携わっていただいている花井敏男先生,今版担当の医学書院の塩田高明・小野田恵実氏に心より感謝申し上げます.
本書が乳幼児健診に携わる医師をはじめ,関係者の皆様にご活用いただければ幸いです.
2024年11月
乳幼児健診マニュアル編集委員会
編集責任者 稲光 毅
目次
開く
乳幼児健診について
健診の心構え
乳幼児健診はいつ行うか
乳幼児健診の実際
診察の前に行うことがら
一般理学的所見の取り方
発達診断学的診察の実際
発達障害が疑われる子どものみかたと対応
月齢別の健診のしかた
1か月児健診
4か月児健診
7か月児健診
10か月児健診
12か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診
5歳児健診
育児相談・育児支援
1.育児相談のポイント──健診現場における育児支援の実際
2.乳幼児の生活習慣
3.乳幼児期の栄養指導
4.事故防止
5.食物アレルギー
6.スキンケア
7.禁煙指導
8.子どもの歯の衛生
9.母親(養育者)のメンタルヘルスと育児支援
10.子どもの虐待への気づきと支援
11.予防接種
文献
索引
コラム
発達検査
ペリネイタルビジット(出産前後子育て支援事業)
日本語版M-CHATと使用法
臍ヘルニア圧迫療法
シャフリングベビー
早産児と修正月齢
母斑とレーザー治療
虐待による乳幼児頭部外傷(乳幼児揺さぶられっ子症候群)
真性・仮性包茎
保育園・幼稚園と健康診断
障害をもつ子の育児
病児保育
お乳離れの時期は?
DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)説
乳幼児突然死症候群(SIDS)
子どもの便秘
拡大新生児マススクリーニング
新生児聴覚スクリーニング後の支援
こども家庭センターについて
スポットビジョンスクリーナー(SVS:spot vision screener)
書評
開く
疾病志向型から健康志向型へ,実践者のための指南書
書評者:小倉 加恵子(鳥取県倉吉保健所長)
本書を手に取り,まず強いインパクトがあったのが,冒頭の節でした。乳幼児健診の「基本的な心構え」として,「健診は医療の延長ではありません」という文章から始まります。最近では子育てが「孤育て」としばしば表現されるように,孤立した育児環境に伴う保護者の育児不安や育児負担感の増大は社会課題の一つであり,そこから発展し得る児童虐待のリスクが指摘されています。乳幼児健診の意義として,子どもの健康状態の確認や疾病スクリーニングとともに,子育て支援の意味合いがますます大きくなってきました。また,2024年から始まった国民健康づくり運動プラン「健康日本21(第三次)」では,ライフコースアプローチとして胎児期から高齢期に至るまでの生涯を踏まえることが必要とされ,乳幼児健診はそのキーポイントの一つとなります。本書はこうした社会ニーズにコミットしており,冒頭の言を通じて,乳幼児健診にむかう医師の構えを疾病志向型から健康志向型へ切り替える,実践者のための指南書であると感じました。
本書の内容も充実しています。初めに総論として「乳幼児健診の実際」が示された後に,各論として「月齢別の健診のしかた」に続きます。各月齢の健診における診察方法が手順に沿ってわかりやすく解説されており,シンプルな図表とかわいらしいイラストにより理解が進みます。また,それぞれの月齢の保健指導の要点やよくある質問への対応についても解説があります。健診現場ですぐに使える具体的な指導法が簡潔に記され,後に続く「育児相談・育児支援」の詳細な解説により理解が深まるよう工夫されています。さらに,「各月齢の発達の目安・ポイント一覧」が本書の見開きにあり,健診直前にサッと確認事項をおさらいするのに役立ちます。この内容はしおりとして付録にもなっていて,読者への細やかな配慮を感じました。
さらに本書の特徴は,情報の適時更新にもあると思います。第7版が改訂された2024年度現在,「こどもまんなか社会」の実現をめざして国がこども家庭庁を設置して1年が経過しました。母子保健行政において,これまでにない勢いでさまざまな政策が打ち出されています。乳幼児健診についても,こども未来戦略「加速化プラン」において推進することが明示され,1か月児健診と5歳児健診が国庫補助事業となりました。本書はこうした状況を遅滞なく捕捉して内容を更新し,コラムに新項目も取り入れられています。一般的に医療現場に新しい政策情報は届きにくいものです。本書は改訂を重ねることにより時勢をとらえ,現場において必要な情報を遅れることなく紹介しています。本書の編集委員会である福岡地区小児科医会のご尽力はいかばかりかと心からの敬意を表するとともに,小児科医はもとより多くの乳幼児健診関係者に広くご活用いただきたい一冊であると思います。
生物学的・心理的・社会的視点から乳幼児の成長と発達を記した健診マニュアルの成書
書評者:永光 信一郎(福岡大主任教授・小児科)
2023年4月にこども家庭庁が創設されて以来,子ども政策にかかわる事業が積極的に推進されています。その1つが効果的な乳幼児健診の拡充で,2024年1月から1か月児健診と5歳児健診が母子保健医療対策総合支援事業となりました。1か月児健診は乳児早期の疾病および異常を早期に発見し適切な指導を行い,さらに養育環境の評価と,養育者への育児に関する助言を行う目的で実施され,5歳児健診は成長・発達に影響を及ぼす発達障害の早期発見・支援と生活習慣に関する指導を目的としています。
福岡地区小児科医会では,40年以上前より,4か月,10か月,1歳6か月,3歳の公費で実施する悉皆の乳幼児健診以外に,1か月,7か月,12か月,2歳,4歳,5歳,6歳の乳幼児健診を,希望者を対象に実施していました。1992年の初版以来,本マニュアルは最新の情報に改訂され,かつトピックスを掲載しながら,このたび第7版を発刊することになりました。今までの健診事業で培われた知見がこのマニュアルに詳細にわかりやすく記載されています。
今後,かかりつけ小児科クリニックや病院小児科で提供していく医療サービスは,大きく変革していきます。病気の子の治療だけではなく,子どもの健康のヘルスプロモーションを担う役割がますます増して,生物学的・心理的・社会的課題に起因する疾病の未病対策を提供していくことが重要になります。本書は,健診における理解的所見の取り方,発達診断学的診察の仕方はもとより,子どもの心の問題やきょうだい児,養育者の健康,家庭環境など,子どもの健康を決定する社会的要因(social determinants of health)のアセスメントについても詳細に記されており,乳幼児健診に関わる医師や保健師,看護師にとって必携の書となります。月齢別の健診のしかたの項目では,1か月児健診が今後,かかりつけ医による子育て支援の起点となることから,拡大新生児マススクリーニング,新生児聴覚マススクリーニングなども含め,保健指導の要点が詳細に記されています。
また,2022年の児童福祉法の改正により,市町村に新しく設置された「こども家庭センター」のことも明記されています。出産後の母親(養育者)のメンタルヘルス支援が重要視されている中,精神面から直接的に母親(養育者)に介入しても心を閉ざされて支援が難しい場合もありますが,本書に記されている栄養指導,事故予防や予防接種の説明,スキンケアなど保健指導を通して,間接的に母親(養育者)の精神面の評価や支援をしていくことも大切と思われます。
乳幼児健診の拡充が,今後の子ども政策の中心として展開されたとき,子どもたちの健やかな成長と発達を地域で見守っていく観点から,個別健診の割合が増えていくことが予想されます。その際にも,本書はこれから小児科医をめざす若い医師の育成に寄与することと思います。
保護者への配慮が詰まった,健診に望むマインドが感じられる1冊
書評者:植木 慎悟(九大大学院准教授・小児看護学)
少子化の昨今,子どもと接した経験に乏しく相談相手も少ない人が急に保護者になる乳幼児期は,常に心配がつきまといます。私自身,子どもを10か月健診に連れて行った際,当時11 kgあった私の子を見た周囲の人は目を丸くしていました。そうした周囲の反応は保護者をとても心配させるものです。私も妻からあれやこれやと多くの心配事が書かれたメモを渡され,聞いてくるようにと頼まれていました。そのような状況の私に,診てくださった先生から「大きいだけ。大丈夫」と笑顔で言っていただき大変心が救われました。本書では,このように何事にも心配する保護者へ配慮する医師の気持ちが随所に感じられる内容が盛り込まれており,感銘を受けました。
健診は「疑わしいものをスクリーニングする」ことが目的であるという発達診断学的診察に加えて,本書では育児相談を必ず行うことが記載されています。健診には,子育てに暗中模索する保護者,昼夜問わずミルクに追われ心身ともに疲れている保護者が子どもを連れてくることになります。保護者は数少ない健診の機会に解消したい疑問を抱きつつ,「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と混雑する診察時間に遠慮する気持ちを抱いているものです。健診の最後に「聞き漏らしたことやまだ心配なことはありませんか」と尋ね,保護者の心配事を漏れなく聞こうとする姿勢は,保護者の疑問を解消する機会を逃さず安心感を与えることにつながると思います。
本書では,各時期における健診の診察手順はもちろん,保護者からよく受ける質問と,その考え方を記してあり,さらに上記のような具体的な声掛けの例を示してくれています。慣れていない医師にとっても実践に生かせる内容になっています。また,保護者にはこの健診の場で自身の子育てのやり方が合っているのかを確認してもらいたい気持ちもあります。保護者のエンパワメントを高めるための「〇〇さん,非常に順調ですよ」という日頃の頑張りを労う声掛けの必要性も本書に書かれており,保護者の立場としてはそうした姿勢で取り組んでくれる医師に診てもらいたいと思えるようなマニュアルになっています。
また,本書では忙しい医師でも読みやすく理解しやすい工夫がなされています。例えば重要な箇所にハイライトされていたり,一部(口腔内)のカラー表示がなされていたりと,読み手のことを考えて丁寧に執筆されていることが感じられます。また,本書全体が「です・ます」調で書かれていることも親しみやすい細かな配慮とお見受けしました。
日頃から健診や診療に奮闘されている多くの小児科医の知識・経験・技術・工夫がふんだんに盛り込まれている本書は,臨床現場の決定版と言えるでしょう。執筆された先生方に敬意を表しつつ,そのマインドが次の世代へ受け継がれていくことを期待しております。