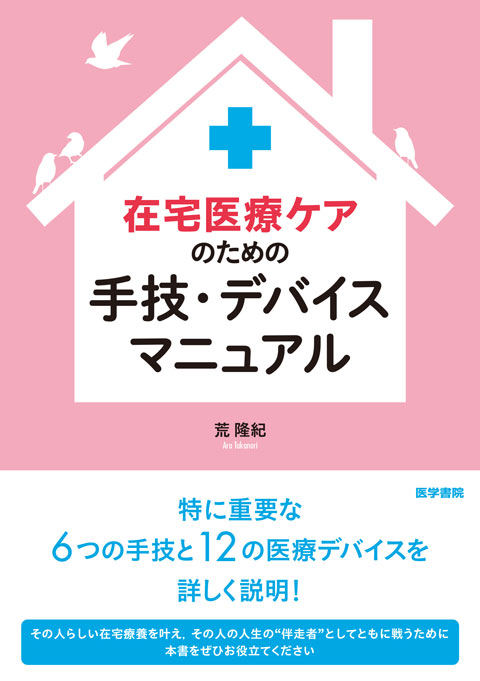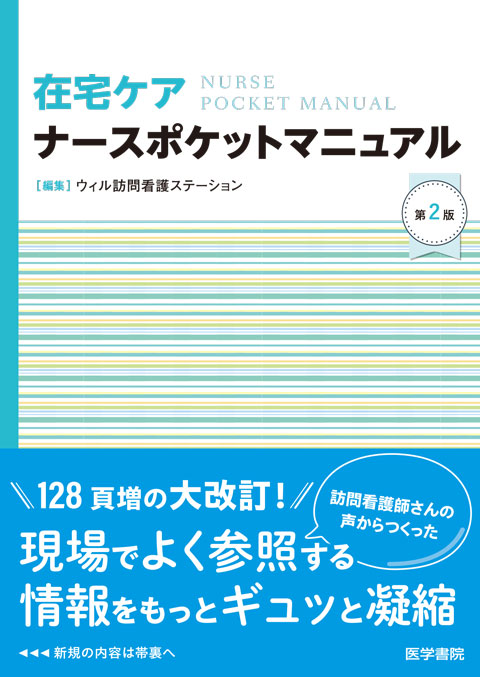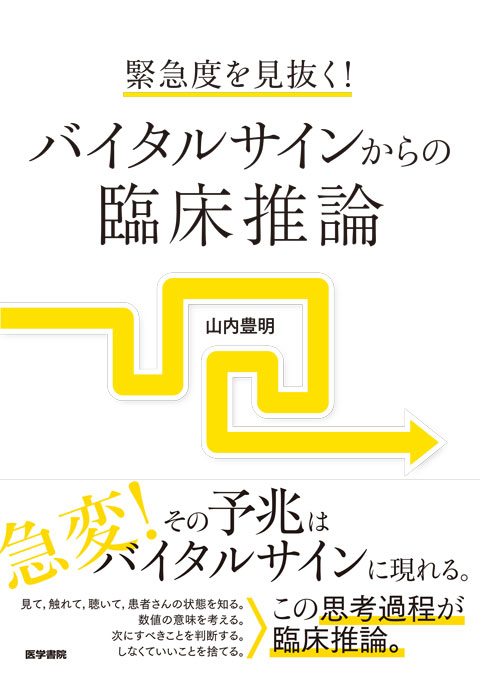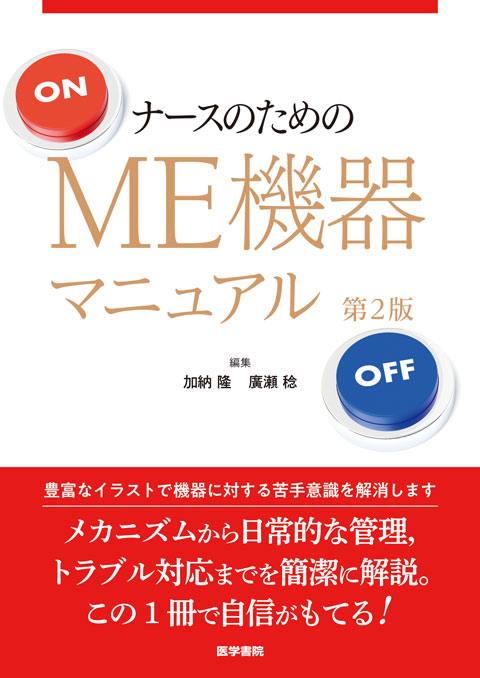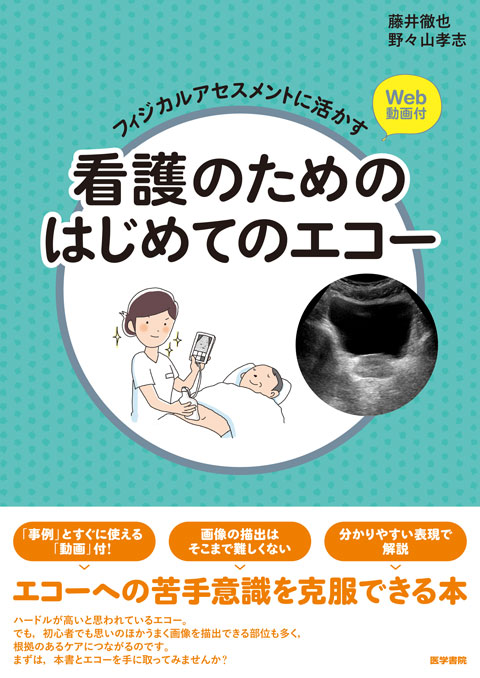在宅医療ケアのための手技・デバイスマニュアル
その人らしい在宅療養を叶え、その人の人生の伴走者として、ともに戦う医療者のために
もっと見る
在宅医療ケアの手技やデバイスに特化したマニュアル。現場の感覚を盛り込んだ実践的な内容を特徴とし、多くのイラスト、図表を用いて直感的に理解しやすい書を目指す。今後、地域医療は「病院完結型」から「地域完結型」へ切り替わっていくはず。在宅医、訪問看護師はもちろん、在宅医療に興味のある研修医、専攻医、さらには薬剤師、介護職、そして患者・家族にも大いに参考にして頂きたい。よく聞かれる質問への回答も収載。
| 著 | 荒 隆紀 |
|---|---|
| 発行 | 2024年08月判型:A5頁:184 |
| ISBN | 978-4-260-05444-7 |
| 定価 | 3,850円 (本体3,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
在宅医療を始めたばかりのとき,多くの医師や看護師の前に立ちはだかるさまざまな壁があります.
いままで診療したことのない幅広い疾患や愁訴への対応,リソースの少ないなかで行わなければならない往診,それぞれ固有のルールが渦巻く地域の医療・介護・福祉機関との協働,患者家族の価値観を考慮した共同意思決定支援など…….
そのなかでも,実際の診療で特に困るのが「患者さんに装着されたデバイス管理や手技」です.
正直に申し上げて,筆者自身が医師7年目で在宅医療の世界に入った際にいちばん悩んだのがここでした.「気管切開カニューレの使い分け」,「挿入困難な尿道カテーテル留置」,「訪問看護師や家族から尋ねられるデバイスに関する質問対応」など,専門書を読み漁ったり,業者の説明会を聞いたりしながら少しずつ知識と経験を蓄積していったものです.
一方で,近年の医療レベルの向上に伴い,在宅医療の現場で医療機器や医療材料を必要とする医療依存度の高い患者は増加しています.また,地域包括ケアシステムのもと,地域医療が「病院完結型」から「地域完結型」へと切り替わるように2024年の診療報酬改定でも誘導されており,自宅や施設で行われる医療の幅はますます広がっていくでしょう.
その反面,医師や看護師など在宅医療に関わるスタッフの多くが,こうした医療機器や手技,デバイスのすべてに精通するのは非常に困難です.実際に,こうした手技やデバイス対応が理由で,在宅医療の受け入れを断る医療機関や訪問看護ステーションが存在することも幾度か耳にしたことがあります.
医療法人おひさま会では後進教育のため院内マニュアルを3年前から制作してきました.いまでは法人内の新入職員にとってはなくてはならない資料です.在宅医療の現場で頻度が多く,かつ重要な医療デバイスや手技に精通できるよう系統的にまとめ,また,在宅における処置を実施するためのポイントや適応,仕様,管理上の注意点などについて豊富なイラストを加えてわかりやすく解説しています.
今回,そのコンセプトを継承しながら,日進月歩の医療デバイス業界に合わせて内容を更新し,頻繁に尋ねられる質問(FAQ)に対する回答と「在宅ならでは!」のポイントを追加し,本書は刊行に至りました.在宅医療へ実際に参加されている在宅医や訪問看護師はもちろんのこと,研修で在宅医療を経験するようになった研修医や専攻医,薬剤師,介護職や患者家族にも参考になると思います.
本書が,“さまざまな病気や障害を持ちながらも,その人らしい在宅療養を叶える人生”に伴走するいわば戦士たる皆様にとって,日々のケアの一助となることを願っています.
2024年初夏
コロナ禍明けを祝うかのような青空を映す,新潟の田んぼに張られた水を横目に見ながら
荒 隆紀
目次
開く
はじめに──なぜ在宅医療においてデバイス管理や手技が大事なのか?
I 在宅デバイス学
1章 尿道カテーテル,膀胱瘻,腎瘻
2章 経鼻胃管,胃瘻,腸瘻,PTEG
3章 ストーマ
4章 在宅酸素療法(HOT)
5章 気管カニューレ
6章 人工呼吸器
7章 吸引器
8章 加温加湿器
9章 排痰補助装置
10章 インスリン自己注射とCGM
11章 CVポート
12章 持続皮下注射方法(CSI)
II 在宅手技学
1章 皮下点滴
2章 在宅輸血
3章 トリガーポイント注射
4章 腹腔穿刺,腹水排液
5章 胸腔穿刺,胸水排液
6章 褥瘡デブリードマン
索引
書評
開く
訪問の現場に持ち歩いて活用したい一冊
書評者:樋口 秋緒(社会医療法人北晨会恵み野訪問看護ステーション「はあと」管理者/保健師/診療看護師(NPプライマリ・ケア分野))
この本は,在宅医療にかかわる全ての事業所,特に訪問看護ステーション全てに置いてほしい一冊だ。
いや,置くだけでなく,ボロボロになるまで使ってほしい本かもしれない。
もっと言うと,「手技・デバイスマニュアル」という題名ではあるが,手技=手順書ではない。看護手順書のように,細かな処置の手順が書かれているわけではないが,日常管理における留意すべき点が,医療職・看護職として診るべきエビデンスに則って記載されていて説得力のある内容であり,しかも在宅ならではのポイント解説付き。なので,訪問の現場に持ち歩いて活用したい一冊なのだ。
評者は長年,訪問看護や看護小規模多機能居宅介護に携わっている診療看護師(NP)だ。日本ではまだ国家資格化はされていないが,より高度な医学・看護アセスメントを学び患者さんのケアに還元できるようにと,今は多くの大学院にて診療看護師(NP)コースが開講されている。そこでは,「今までこうだった」「私はこうやってきた」では通用しない。この診療看護師(NP)コース履修中は「なぜそれが必要なのか」「なぜ?」「なぜ?」とずっと問われ,今までの知識や持っている看護書だけでは到底解決できない多くのことにぶつかった。その頃この本があったら,もう少し楽できたのに(笑)。以降,後輩たちの育成に携わり,気管切開カニューレ,膀胱瘻カテーテルの交換や管理について伝授する機会をいただいたが,その準備においても,手技だけでなく,診療看護師(NP)として知っておくべき裏付け(エビデンス)を伝えたく,あの本この論文とたくさんの書物を漁っていた。それがこの一冊でほぼ賄えるのだから,間違いなく「待っていました!こんな本」なのだ。
本の構成は,在宅デバイス学と在宅手技学の二つに分類されており,どの項においても実際の手技が記されている。特に目を引いたのは,人工呼吸器の項で,加温加湿器や吸引器の扱いも取り上げていることである。特に痰吸引は看護学生のときから学ぶ項目だが,加湿器と絡めて説明されているので改めて勉強になる。
在宅手技学の項では,トリガーポイント注射や腹腔穿刺,胸腔穿刺が取り上げられている。これらの処置は,看護師が実践することはできないが,訪問先で腹水や胸水除去の必要性やタイミングなどをアセスメントする際の指南にもなり,患者さんやご家族に説明する時の具体的なイメージ共有に活用できて,それは安心の提供につながる。
医療が病院から在宅へ切り替わろうとしている昨今,住み慣れた地域で安心安全な療養生活を支えるべく医療従事者にとって,医療の質の担保と向上の取り組みに飽くことはない。この本に出合ったことに感謝し,これを機に,一層,在宅療養支援チームの一員として精進していきたいと思った。
在宅医療の現場で役立つ実践的ガイド
書評者:菊池 亮(ファストドクター株式会社代表取締役・医師)
荒隆紀先生の『在宅医療ケアのための手技・デバイスマニュアル』は,在宅医療に携わる医師や看護師をはじめ,多職種の方々に向けた極めて実践的で包括的なガイドです。在宅医療は,特殊な環境下での診療を要するため,多様な手技やデバイスの適切な使用が求められますが,本書はその現場のニーズにしっかりと応えています。具体的には,在宅で必要となる医療技術やデバイスの使用方法が詳細に解説され,現場で即座に活用できる知識が詰まっています。
本書の特徴は,技術の説明にとどまらず,それを支える理論や背景知識にも重点を置いている点です。特に,PEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術)やHOT(在宅酸素療法)などの医療機器については,その適用範囲や手技が明確に説明されており,初学者から経験豊富な医療従事者まで,幅広い読者にとって参考となる構成です。また,在宅での医療機器使用に関するよくある疑問やトラブルへの的確なアドバイスも含まれており,日常業務に直結する有用な知識が得られるでしょう。
加えて,在宅手技に関する章では,トリガーポイント注射や胸水排液といった頻繁に行われる技術がイラスト付きでわかりやすく説明されています。在宅医療の現場では,患者一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が求められるため,これらの手技の習熟が不可欠です。本書を通じて,読者は実践的な応用力を身につけ,より自信を持って診療に臨むことができるでしょう。
本書は在宅医療の基礎から応用までを網羅した一冊であり,医療従事者が現場で頼りにできる重要なツールです。個別的な判断や対応力が問われる在宅医療において,本書は確実に役立つ実践的な参考書として活用されることが期待されます。
さらには,本書が単なる技術的なマニュアルにとどまらず,医療従事者の思考や判断をサポートし,在宅医療の未来を切り開くための一助となることを願っています。