腹痛診療アップデート
「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく
対談・座談会 三原 弘,亀井 誠二,高山 祐一,亀田 徹
2025.04.08 医学界新聞:第3572号より

突然発症の腹痛,いわゆる急性腹症を訴える患者に遭遇することは珍しくありません。その原因・症状は多岐にわたるものの,中には重篤な疾患が隠れている場合もあり,迅速かつ的確な診断と対応が求められることから,苦手意識を持つ医師も少なくないはずです。
8つの学会(註)が協働して急性腹症の診療の基準を示した『急性腹症診療ガイドライン2025 第2版』(医学書院)の発行に当たり,本紙では改訂委員会のメンバーによる座談会を企画。改訂のポイントから急性腹症診療における科学的知見の発展までを幅広く語り合いました。
三原 『急性腹症診療ガイドライン2025 第2版』1)は8つの関連学会(註)から専門家が集結し,豊富な知見から内容がアップデートされました。私は日本腹部救急医学会から参加し改訂委員会の委員長を務めました。本日は改訂委員会のメンバーから同じく日本腹部救急医学会の高山先生,日本超音波医学会の亀田先生,日本医学放射線学会の亀井先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
腹痛診療でも重要度を増す画像診断技術
三原 初版となる『急性腹症診療ガイドライン』が刊行されてから10年が経過し,ようやく改訂の運びとなりました。この間,急性腹症診療にはどのような変化があったのでしょうか。まずは外科の観点から伺えますか。
高山 画像診断技術の進化は特筆すべきでしょう。CTやMRIの診断精度が飛躍的に向上したことで,従来は手術しか選択肢がなかった病態の患者に対しても保存的治療で改善を図れるケースが増えました。より侵襲度の低い治療で対応できるようになってきたことは,患者にとってもメリットが大きいと感じています。
亀田 画像診断技術という点では,超音波診断,特にベッドサイドで行われるpoint-of-care超音波(POCUS)の概念がここ数年で普及してきました。私自身,救急医として活動する中で超音波診療の有用性に注目し,2000年代初頭からERやICUでの超音波活用に取り組んできました。当時は急性期診療で超音波検査に関心を持つ医師は限られ,もどかしさも感じていましたが,2011年にThe New England Journal of Medicine(NEJM)でPOCUSが取り上げられた2)のを契機に国内でも広まり始め,現在では急性腹症診療での超音波活用法をレクチャーする機会も増えました。しかし研修医の超音波検査の実施率は依然として低いままですので,今後さらなる普及に努めていきたい所存です。
亀井 超音波検査が普及しきっていない背景には,CT,特にマルチスライスCTがこの10年で急速に広まった影響があるのかもしれません。一方で,あまりにも安易にCTが行われすぎている状況も招いています。亀田先生がおっしゃるように今後は超音波検査の教育にも注力していくべきでしょう。
また画像診断に関連して付け加えると,せっかくCT,MRIが撮影されても,夜間・休日などの時間外だった場合,画像診断専門医による読影が行われず,ときには重篤な疾患が見落とされている,という事態は10年前と変わらず見受けられます。急性腹症診療をアップデートしていくには,こうした課題にも向き合っていかなくてはなりません。
8つの学会が結集したガイドライン改訂委員会
三原 ガイドライン改訂の話題にも触れていきたいと思います。今回,初版制作に携わった5つの学会に加えて,新たに日本病院総合診療医学会,日本超音波医学会,日本超音波検査学会を迎え,計8学会で知見を共有し合いながら改訂作業を進めました。3学会が加わったことの意義を,皆さんはどうとらえていますか。
亀田 今回から日本病院総合診療医学会が加わったことで,急性腹症をジェネラルに分析する視点がより強化されたことは間違いないでしょう。疾患名の診断がついていない中で臨床推論を働かせて必要な検査を検討し,治療までの見通しを立てていく役割は本領域で欠かせません。
亀井 そうですね。今回のガイドライン改訂のように救急診療が絡む標準化の議論に当たっては,各領域の専門家だけではどうしても議論が偏ってしまう可能性があります。最近は専門化が進みすぎてそのリスクがより顕著になっていると感じるので,総合診療のように横断的な考え方を持つ医師がますます求められていくでしょう。
高山 新たに加わっていただいた3学会は外科の立場では普段なかなかかかわる機会がないので,そうした先生方と急性腹症診療について議論できた経験自体も貴重でした。日本産科婦人科学会の先生と超音波関連の先生方が経腹・経腟エコーの議論をされていたのも印象に残っています。個人的には,亀田先生が先ほど触れていたPOCUSの有用性を学べたことが意義深かったです。日本超音波医学会,日本超音波検査学会が加わったことで本ガイドラインには超音波検査に関する記述が充実しましたし,超音波検査よりどうしてもCT検査ファーストになりがちな自施設にも,今回得た知見を還元したいとの思いがあります。
三原 確かに,複数の診療科の医師が急性腹症診療に関して侃々諤々と議論している場面は普段なかなか見られませんので,ガイドラインの制作過程を通じてそうした交流の場ができたのも印象的ですね。いい意味で刺激を受けた委員は多いでしょうし,ガイドラインもより多角的な視点を踏まえた内容になったとの自負もあります。
初版よりも臨床の視点に根差したアップデート
三原 今回の改訂において,思い入れのあるアップデート点があればぜひお聞かせください。
高山 腸閉塞とイレウスに関連する用語の整理ですね(表)2)。今回は厳密にそれぞれを区別しました。例えば絞扼性イレウスを絞扼性腸閉塞症にするなど,具体的なレベルにまで言及して個々の用語を定義しました。保険病名が変わっていないために日本では学会発表や論文,教科書などにもイレウスという表現が根強く残っていますが,こうしたガイドラインからの提言などを積み重ねて見直されていくことが大事だと思います。また虫垂炎についても,国内ではカタル性,蜂窩織炎性,壊疽性と分類されてきましたが,これらはあくまでも組織学的な分類でしたので,今回は海外に準じて臨床的な視点に立脚し,単純...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三原 弘(みはら・ひろし)氏 札幌医科大学医療人育成センター 教育開発研究部門 准教授 / 総合診療医学講座
2002年富山医薬大(当時)卒。同大内科学第三講座(消化器内科)入局。08年生理学研究所・岡崎統合バイオサイエンスセンター細胞生理研究部門に国内留学。15年富山大医学部医学教育センター助教。21年同大医師キャリアパス創造センター副センター長。22年9月から現職。急性腹症診療ガイドライン2025改訂出版委員会では委員長を務めた。

亀井 誠二(かめい・せいじ)氏 JA愛知厚生連海南病院 放射線診断科代表部長
1994年徳島大医学部卒。2001年より愛知医大放射線科。14年から現職。放射線科専門医,日本医学放射線学会診断専門医,日本IVR学会専門医,腹部救急認定医・教育医。第44回日本腹部救急医学会総会イメージ・インタープリテーション・セッションでは最優秀賞を受賞。

高山 祐一(たかやま・ゆういち)氏 大垣市民病院外科部長
1995年名大医学部卒。同大腫瘍外科学教室に入局。日赤愛知医療センター名古屋第一病院,名古屋第二病院などで勤務したのち,2010年7月から大垣市民病院にて勤務。20年4月から現職。年間全身麻酔手術約1600件,うち緊急手術約500件を統括する。『Acute Care Surgery認定外科医テキスト』(へるす出版)など書籍の執筆も手掛ける。

亀田 徹(かめだ・とおる)氏 済生会宇都宮病院 超音波診断科主任診療科長
1996年北大医学部卒。救急・集中治療・超音波検査の研修後,超音波検査をサブスペシャリティとして救急医療に長年従事。日本超音波医学会指導医,日本救急医学会指導医,日本ポイントオブケア超音波学会代表理事。『救急超音波診療ガイド』『レジデントのための腹部エコーの鉄則』(いずれも医学書院)など編著書多数。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

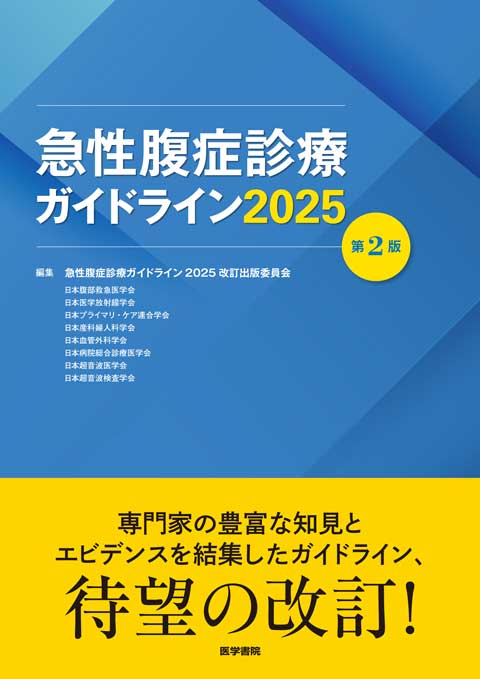
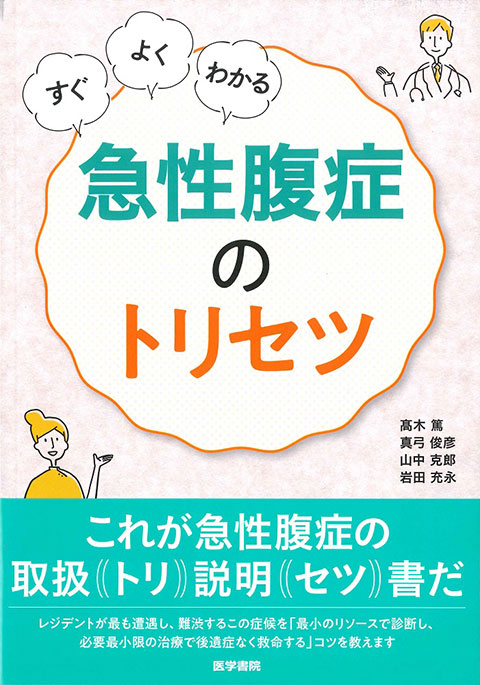
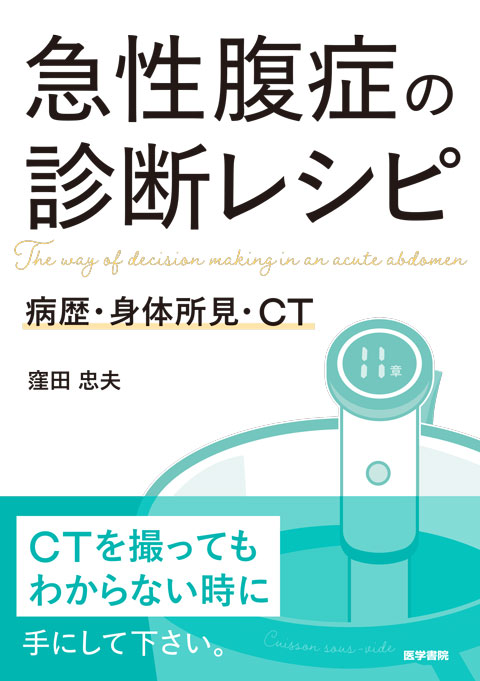
![連続スライスで学ぶ レジデントのための急性腹症のCT[Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9416/7895/2666/112253.jpg)