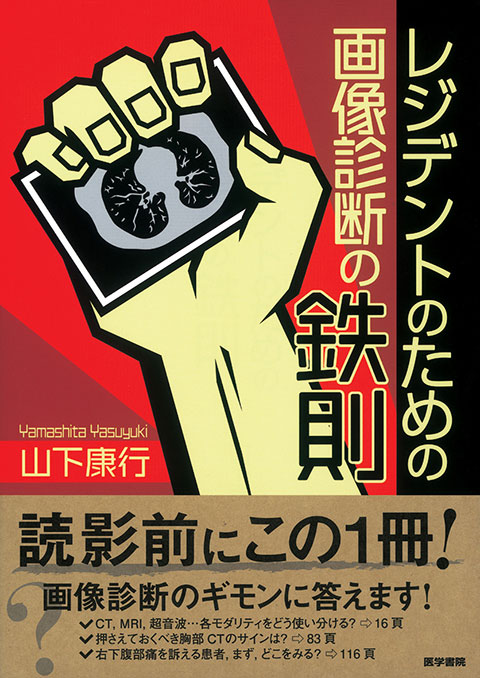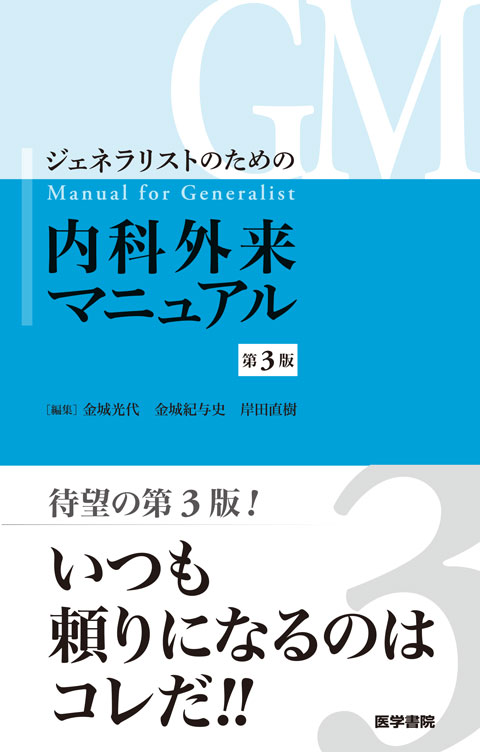レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]
プローブを握る前にこの1冊!
もっと見る
解剖学的知識、走査法といった基本から、画像の解釈、病態の把握、そして日常臨床でよく出会うものの、実はどこにも対応法が載っていないものまで、腹部エコーを行ううえで知っておきたい“鉄則”をまとめた1冊。悩みがち・迷いがちなテーマを中心に取り上げ、症例をもとに実践的な対応策を示す。実践編1「超音波解剖とプローブ走査法」では、丁寧な解説とWeb動画でハンズオンセミナーのように走査のコツを修得できる。
| 編集 | 亀田 徹 |
|---|---|
| 発行 | 2023年09月判型:B5頁:288 |
| ISBN | 978-4-260-05085-2 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
更新情報
-
【2025年2月1日開催終了】本書を用いたWebセミナーを開催しました
2025.02.03
- サンプル動画
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
サンプル動画
開く
動画より一部をご紹介します。
序文
開く
序
腹部エコーに関する書籍や雑誌の特集はこれまで数多く出版されています。そんななか,医学書院の天野さんから「腹部エコーの本をつくりたいので協力いただけないか」と持ち掛けられたときは正直なところ戸惑いました。「腹部エコーの教材はたくさんあるのでもう十分じゃないですか」と思わず答えてしまったのを覚えています。「レジデントが自ら腹部エコーを行う際に,身に付けておくべき基本を『鉄則』形式でまとめた1冊にしたいのです。レジデントが悩みがち・迷いがちなテーマを取り上げ,症例をもとに実践的な対応策を示すような内容でご検討いただけないでしょうか。明日から自分でプローブを持って当ててみようと思ってもらえるような1冊を目指したいのです」と天野さんから熱意のある説明を受け,少し考える時間をいただくことにしました。
天野さんの熱意,そして時間も解決してくれたのでしょうか,新しい書籍をつくることに気持ちが少しずつ前向きになっていきました。提案の内容を実現するためには,具体的にどのような内容にすべきか,日々考える自分がいました。
2020年代,腹部エコーの在り方があらためて問われているように感じます。検査室で行われる系統的超音波検査は確立されて久しいですが,近年はベッドサイドで行うPoint-of-Care Ultrasonography(POCUS)の概念が世界中で共有されるようになりました。今後それぞれがどのような役割を担っていくべきか,2020年代にある程度の見通しがつくのではないかと想像します。その時代を生き抜くレジデントのみなさんに手にとってもらえる「腹部エコーの本」をイメージしながら案を練っていきました。腹部超音波検査,POCUSの考え方を併せ持った書籍にするために,それぞれのエキスパートの諸先生方に執筆を依頼し,ご多忙ながら快くお引き受けいただきました。
基礎編では,腹部エコー研修者の心得から始まり,レジデントのみなさんにぜひ押さえていただきたい超音波検査の基本事項について解説しました。POCUSの考え方,その発展の原動力である携帯型超音波診断装置(ポケットエコー)についても取り上げています。
実践編は3つのパートに分けました。「1 超音波解剖と走査法」では,ほぼすべての領域の基本検査法をここに集約しました。本書の特長の1つである画像と手元(プローブの操作)をリンクした動画を豊富に用意し,走査法のコツをナレーションで解説しています。テキストと動画を併用することで超音波検査手技を自己学習しやすくなっています。検査室での腹部エコー研修前,ベッドサイドでPOCUSを始める前の自己学習教材としてもぜひご活用ください。きっとスムーズに研修が進められると思います。
「2 部位・領域別エコーの実践」は,腹部エコーのテキストでは核となるところです。紙幅の都合で疾患を網羅的に取り上げることはできませんが,commonな疾患,プライマリケアや救急外来で遭遇することの多い疾患を中心に取り上げました。鉄則形式ですので,各著者が伝えたいポイントがすっきりまとめられており,わかりやすいと思います。
「3 症候別エコーの実践」では,執筆にあたりベッドサイドで診療する医師の視点で,症候に基づいたPOCUSの活用を意識していただきました。POCUSに精通した総合診療,救急診療を専門にする先生方に担当いただいています。
本書には,エコー(echo),超音波(ultrasound),エコー検査(echography),超音波検査(ultrasonography)など様々な用語が出てきますが,今回はあえて用語を統一しませんでした。原稿を通読し,それぞれの言葉に各著者の思い入れがあると感じたからです。本来「エコー」は反響,「超音波」は耳に聞こえない音波を指しますが,今や検査そのものを指す用語として広く普及しています。本書のタイトルでは,親しみやすさから「エコー」を用いることにしました。
ようこそ,新しい時代の腹部エコーの世界へ!
2023年9月
亀田 徹
目次
開く
基礎編
1 腹部エコー研修者の心得
2 音響工学の基礎知識
3 プローブとオリエンテーション
4 超音波診断装置本体の取り扱い
5 腹部エコーでみられるアーチファクト
6 超音波検査と医療安全
7 被検者への事前依頼と配慮
8 系統的超音波検査とPoint-of-Care Ultrasound(POCUS)
9 携帯型超音波診断装置
実践編1 超音波解剖と走査法
腹部エコーのポイント
超音波解剖と走査法
1 胆囊・肝外胆管
2 肝臓
3 膵臓
4 脾臓
5 消化管
6 腹部血管
7 腎臓・膀胱
8 腹腔
9 子宮・付属器
実践編2 部位・領域別エコーの実践
1 胆囊・肝外胆管
2 肝臓
3 膵臓
4 脾臓
5 消化管
6 腹部血管
7 腎臓・膀胱
8 婦人科
9 小児
実践編3 症候別エコーの実践
1 上腹部痛
2 下腹部痛
3 側腹部痛
4 黄疸
5 発熱
6 外傷
7 内因性ショック
Column
ALARA(as low as reasonably achievable)の原則
SARS-CoV-2感染拡大時
seven-eleven rule
つり上げ肥厚
縦断走査
横断走査
婦人科経腹エコーの観察手順
Howship-Romberg徴候
エコーと他のモダリティの使い分け
女性患者の側腹部痛におけるピットフォール
無石性胆囊炎
敗血症性ショックとエコー
索引
書評
開く
一人一台エコーの時代に
書評者:矢吹 拓(国立病院機構栃木医療センター内科副部長)
現代医療において,エコーの果たす役割は年々大きくなっています。Point-of-Care Ultrasound(POCUS)などのベッドサイドエコースキルが体系化され,スマホに接続できるような小型軽量化したポケットエコーも開発され,技術革新は日進月歩です。一人一台エコーの時代も夢ではなく,医療機関によっては実現しているところもあると聞きます。ベッドサイドで手軽に検査ができ,低侵襲であることも大きな魅力で,これからますます重要性が増していくと思います。一方で,術者の技量によって検査を通して得られる情報が大きく異なるのが課題の一つです。自ら行った検査ではわからなかった所見が,上級医や検査技師によって指摘されることも少なくないでしょう。エコー技術の習熟や標準化がこれからの重要な課題です。
『レジデントのための腹部エコーの鉄則』は,これからの腹部エコー学習の新たなバイブルとなる一冊です。この書籍の特徴は何といっても,経験豊かなスペシャリストによる「鉄則」です。エコー技術のclinical pearlともいえるこの鉄則一覧が本書の冒頭にまとめられています。
「すべての膵囊胞は膵癌に通じている⇆膵囊胞は見逃すな」
「肝内胆管は,はっきりと見えたら異常,肝外胆管はseven-eleven rule」
「FAST陰性=出血なしではない。FASTは後腹膜臓器・骨盤損傷の出血は評価できない」
腹部エコーを実施する上で重要なポイントではありますが,何より臨床推論において重要な内容が多く含まれており秀逸です。エコー検査はあくまで臨床推論に基づいて行うべきという諸先生の熱い思いが伝わってきます。
本書の構成は,基礎編と実践編に分かれていますが,特に実践編ではQRコードで確認できる動画が満載で,その数実に80本以上です。エコー技術の習得には,書籍を読むだけでは伝わりにくい,具体的なプローブのあて方や声掛けなども重要です。動画を通して,まるで指導医が隣にいて教えてくれているような体験学習が可能です。また,実践編2,3では,まず症例の病歴・身体所見による診断推論があり,その推論に基づいたエコー所見とその解釈が解説されています。検査前確率を意識してエコーをどのように用いるか,所見の解釈やその後のアプローチなど,その後の臨床経過をリアルに体験することができます。
『レジデントのための腹部エコーの鉄則』は,腹部エコーを学ぶ全ての医療従事者にとっての実践的なガイドです。本書を通して,多くの医療者がエコー技術の向上だけでなく,臨床推論においてエコーをどのように用いるかを学ぶことができると確信しています。
付録・特典
開く
付録Web動画のご案内
本書の付録として、関連する動画をPC、タブレット端末、スマートフォン(iOS、Android)でご覧いただけます。フィーチャーフォンには対応していません。
下記のリンクボタンから動画一覧画面にアクセスできます。
![レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8316/9578/9401/112069.jpg)
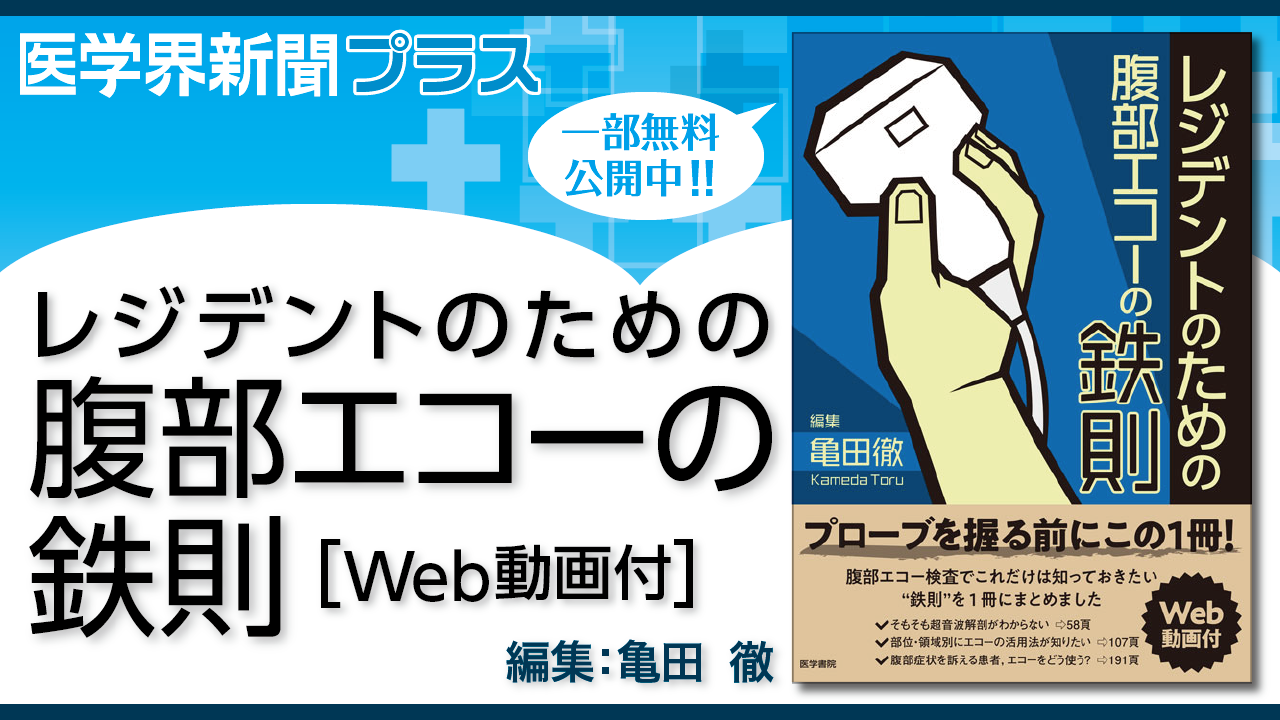
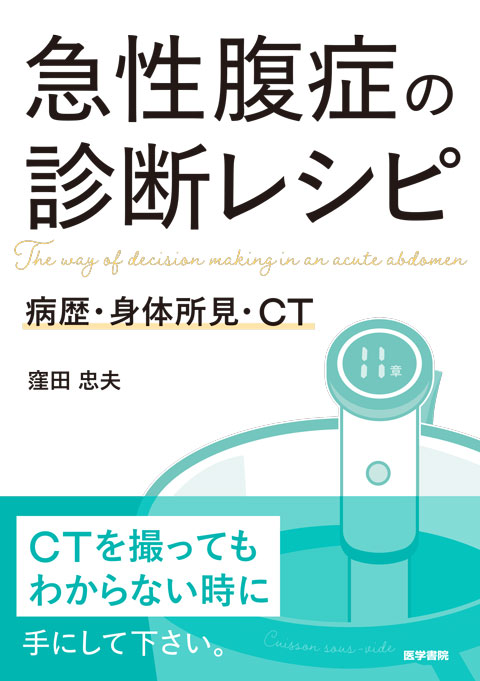
![連続スライスで学ぶ レジデントのための急性腹症のCT[Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9416/7895/2666/112253.jpg)