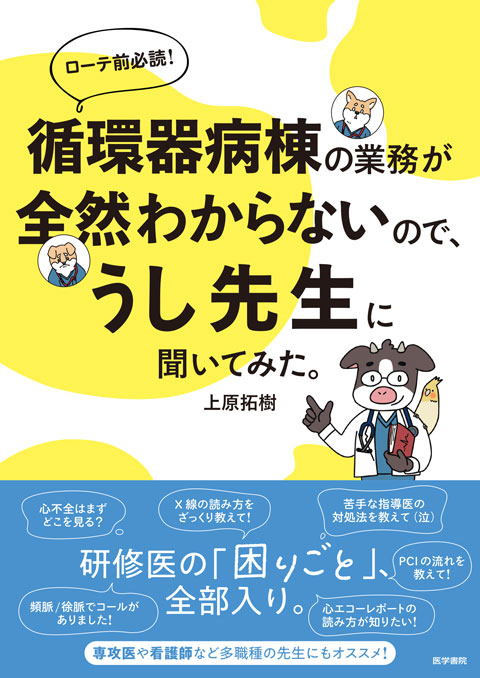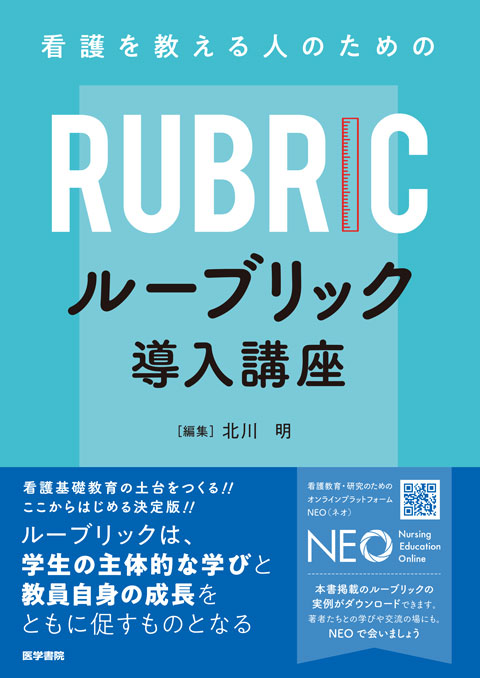MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.11.12 医学界新聞(通常号):第3567号より
《評者》 相澤 純也 順大大学院教授・理学療法学
脊椎疾患リハの確実な結果と成果を出すための羅針盤
リハビリテーション専門職・理学療法士,そして研究・教育者として心から尊敬している古谷英孝先生が編集した書籍が星野雅洋先生監修のもと発刊された。白と青を基調としたシンプルで洗練された光沢感のあるジャケットに「脊椎疾患のリハビリテーション」というタイトルが目に飛び込んでくる。ジャケットをめくると6名の執筆者リスト。脊椎疾患のリハビリテーション医療,理学療法を専門とする名の知れた臨床家ばかり。特筆すべきは全員が脊椎疾患の臨床・実践研究に携わっている点であり,このリストを見ただけで本書が単に“他から持ってきた情報”を整理したありふれた書籍ではなく,「脊椎疾患のリハビリテーションにおいて結果・成果を出すには具体的にどうするのか?」という読者の問いに答えてくれるものだろうと期待が膨らむ。続いて,星野先生,古谷先生による監修・編集の序があり,本書がこれまでの書籍と一線を画していることが確信できた。次に,新書の充実度をはかるために索引にジャンプし,収載されている用語の数々を見て,内容の網羅性,エビデンス,最新知見を実感した。
「第1章 脊椎の機能解剖」では脊椎はもちろん,関連の深い胸郭や骨盤帯の機能解剖学や運動学に関する知識がきれいなカラー図とともに集約され,続く第2章での理解をより深めるための土台を過不足なく提供している。まずはこの章をじっくり読むだけでも普段の臨床推論の内省につながるであろう。
「第2章 各疾患へのリハビリテーションアプローチ」では,臨床現場で“避けては通れない”「6つの脊椎疾患」を取り上げ,リハビリテーション医療に必要な検査・測定,徒手療法,運動療法に関するスタンダードを系統的に解説している。いずれもトレンドにこびることなく,解剖学,生理学,臨床運動学,病理学,整形外科学がベースとなっているため,5年後,10年後も情報が古くならず長く愛読される構成となっている。特筆すべきは「結果・成果を出すには具体的にどうするのか?」という読者の問いに豊富なカラー図で答えてくれている点であり,Web動画まで視聴できる徹底ぶり。ここには医学書院の方々の本書にかける気概を大いに感じ取れた。最後に引用文献リストにも注目してほしい。質の高い原著論文やこれに基づくメタアナリシスなど本文や図表の根拠を明示してくれている点はビギナーだけでなく,エキスパートにとっても信用するに足る内容であることがわかる。
本書を一人でも多くの方に手に取っていただくことを切に願う。そして読者の皆様の臨床活動に役立ち,脊椎疾患をもつ患者様のリハビリテーション,さらにはその安心・安全に寄与されるのであれば幸いに思う。最後に友人である古谷先生が入魂された本書の書評を担える幸せをかみしめながら筆をおきたい。
《評者》 深谷 英平 北里大講師・循環器内科学
医業の入り口に立った諸君,まずはこれを持っていけ
本書を手に取り,初めに感じたことは,「自分の研修医開始時点に読みたかった……」の一言に尽きる。なんなら,専攻医や看護師にもとても役に立つ内容ですよ,これは。
第1章は,医学部の座学では全く教わることのない,現場の話から始まる。それぞれの病院・病棟には仕事をする上でのルール〔一部はローカルルール(汗)〕があるが,そのお作法は,都度現場の先輩方に口頭で教わってきた。時に別のローテーション先の先輩医師だったり,先輩看護師だったり,同僚だったりとコミュニケーションを取りながら,その不文律をなんとなく自分の中で習得していった。昔はそのような“俺流かもしれない不文律”が通用したが,昨今は医療安全の観点からも,ある程度型にはまったものが必要になってきている。本書はまさにその点を,具体例と共に記載している。とりあえずこれを読んでおけば大きく外れることはなさそうである。さらには,プレゼン,コンサルテーション,学会発表,論文,SNSの使い方と続く。まさに痒いところに手が届いている感じ。世の中には医学書といえば専門書が多く,より細分化された,マニアックな教科書が増えつつある中,本書のような,いわば“医業の入口部分”にこれだけ手厚く解説を加えている著書を私は見たことがない。
第2章は,膨大な循環器領域の疾患や検査を全体的に網羅しつつも,素朴な疑問にうし先生が答えるスタイルの解説で,理解しやすい構成だ。各タイトルを見ただけで読みたくなる。しかも,私が普段若手から質問される内容とかなり似ているじゃないか。今後はこの本を読め,と言おうと思う。それくらい,スーッと入ってくる解説である。
さらに第3章では,より深いテーマを取り上げている。ここは専攻医や循環器スタッフでも知りたいような複雑な内容を,これまたシンプルにまとめている。第3章の最初の項目が,「患者さんが帰りたいと言って制止がききません……」という,テーマ。そこきたかっ! と思ったが,結構現場ではある話。なかなかこういう解説は目にしないので,ありがたい。それ以外の項目も,読みたくなるテーマがめじろ押しだった。「苦手な指導医・上司の対処法を教えてください(泣)」なんていう項目がある医学書,初めて見たわ(笑)。
それはさておき,全体の構成として,全てのテーマが見開き2ページでまとまるコンパクトさは,まさに秀逸である。結構ボリュームがある著書だが,さらっと気になるパートだけを開いても,1話完結ストーリーとして実に読みやすい。忙しい研修が始まった後でも,役に立つこと間違いなしだ。
一通り読んでみて,なんとも読みやすい本であった。うし先生の単著でこのクオリティ,彼の教育への情熱を感じる作品である。ぜひ,一読あれ。
《評者》 辻野 睦子 大阪成蹊大講師・看護学
学生の成長を支え,自らも成長したい看護教員の必携書
教える立場にある者には,「学生に何ができるようになってほしいのか,どうなってほしいのかを具体的にイメージしていくことが必要であろう」(p.v)―――看護教員にとっては,臨地実習で求められる知識や看護師国家試験の出題基準といった「学生に教えなければならないこと」への意識が向きやすい。しかし,その先に「学生にどうなってほしいか」まで,私自身が考えられていただろうかと省みる。
本書は,看護教育における教育評価について,その本質をわかりやすく解説し,ルーブリックづくりの手法を学べる入門書である。私は,今秋から開講する小児看護学演習を準備中で,領域会議でルーブリックを用いた評価を提案しようとしていた矢先,運命的に本書に出会い,その内容に興味を惹かれた。すでに演習や実習でのルーブリックを作成してきた経験として,評価...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![保存から術後まで 脊椎疾患のリハビリテーション[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2317/2490/4752/113621.jpg)