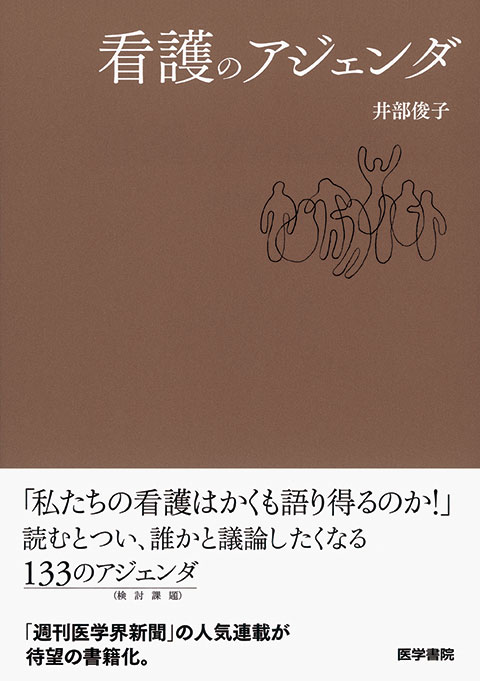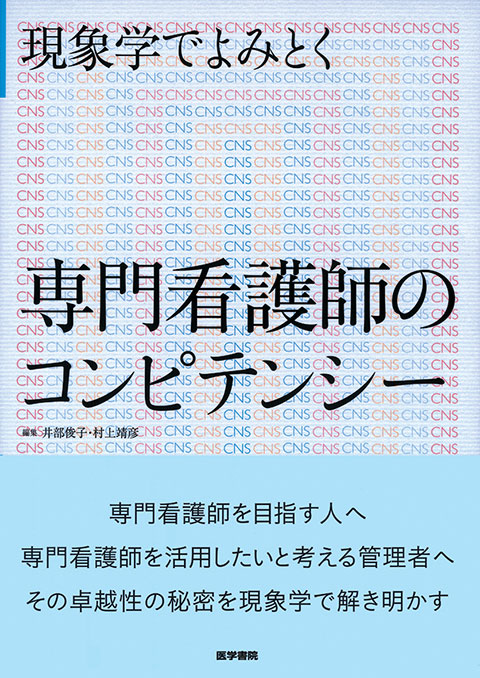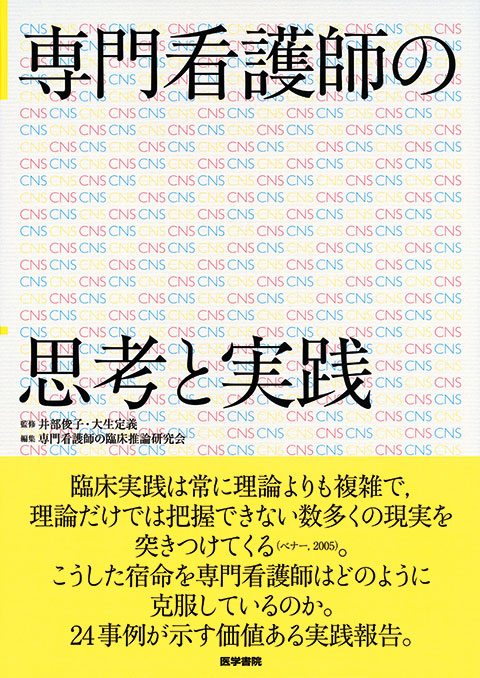看護のアジェンダ
[第225回] なぜ「させていただく」のか
連載 井部俊子
2023.09.25 週刊医学界新聞(看護号):第3534号より
看護管理者研修で伝える2つの禁句
私は,管理とはどのような言葉をどのように使うかが決め手であると考えている。
看護管理者の研修では,始めに「禁句」を2つ伝える。1つ目は「させていただく」であり,2つ目は「(うちの)子」である。「私は教育師長をさせていただいています」とか「研修に参加させていただきました」とか,「今年の4月から看護部長を拝命させていただいています」とか,耳をこらすと結構な頻度である。さらに,「今日,受講している子たちはよくやっている」とか,「私のところの子はおとなしい」とか,使う。すると私の琴線が反応する。「させていただく」は弱いリーダーをイメージし,「子」は同僚たちを庇護の対象としてみている,と私は解釈するのでイエローカードを出すのである。
看護管理者の研修のたびに「させていただく」が浮上し,モンモンとしていたところ,私の意図を察してくれたような,私を諭してくれるような書籍が刊行された(正確にいえば2022年12月23日に刊行されていた)。題して『「させていただく」大研究』(椎名美智・滝浦真人編,くろしお出版)である。表紙をめくるとこんな文字が飛び込んで来る。「なぜ皆,こんなにも『させていただいて』いるのか?」と。
授受動詞には「やる・あげる・さしあげる」「もらう・いただく」「くれる・くださる」という3系列7動詞があり,本動詞としてだけではなく,他の動詞の後ろにつく補助動詞として使われている。この補助動詞として使われている授受動詞「させていただく」に焦点を当てて,さまざまな分野の言語学者が各自の専門の視点から分析した論考を集めた論文集である。
この「させていただく」論文集は,コロナ禍をきっかけに生まれたものであると,あとがきに紹介される。それまで「ベネファクティブ(註)とポライトネス研究集会」を開いていたが,コロナ禍で研究集会が開催できなくなり,この論文集の発刊をもって発展的解散の形となったという。
批判されるべき日本語はなぜ生き残ったのか
では,「させていただく」に関連して,私の興味を引いた論考をみていきたい。
多くの日本語話者は,成人して社会生活を行うなかで,尊敬・謙譲・丁寧から成る敬語体系を身につける。ところが...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。