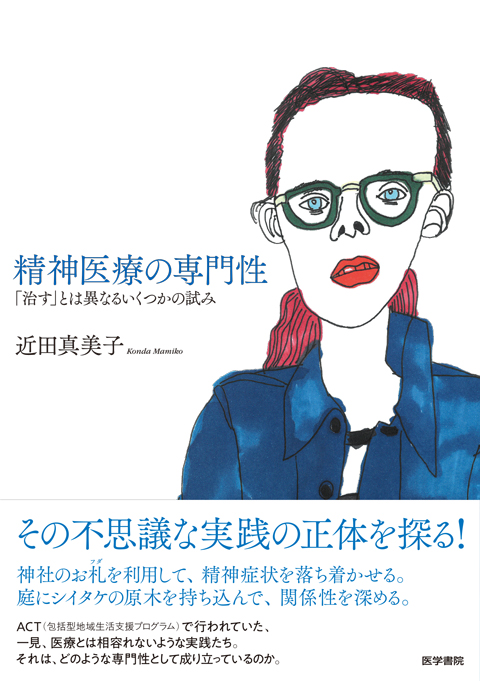Sweet Memories
うまくいかない日々も,きっと未来につながっている
寄稿 近田 真美子,岡山 久代,岩間 恵子,川岡 和也,本田 和也,榊原 千秋
2025.06.10 医学界新聞:第3574号より

春に入職してから1か月あまり。少しずつ仕事に慣れてきた一方で,「自分だけができていない気がする」「この先,本当にやっていけるのかな」と不安を抱えている新人ナースの方は少なくないと思います。今,現場で頼れる存在となっている先輩ナースたちも,かつては同じように戸惑い,つまずきながら一歩ずつ前に進んできました。
本特集では,そんな先輩ナースから「新人時代の失敗談」を紹介していただきました。未来のあなたにきっとつながる,温かい言葉の数々をぜひ受け取ってください。
▼ 目次
こんなことを聞いてみました
❶新人ナース時代の「今だから笑って 話せるトホホ体験・失敗談」
❷忘れ得ぬ出会い
❸あの頃にタイムスリップ! 思い出の曲とその理由
❹新人ナースへのメッセージ
❶「いつか行きたい!」と考え,希望調査の第5希望にこっそりと書いた精神科病棟。「希望者があなたしかいなかったから」というあっけない理由で精神科開放病棟への配属が決まり,看護師としてのキャリアをスタートさせました。新人時代というのは,今後の看護観を育む大切な時間だったんだなぁ……と今になって思います。
多くの新人看護師同様,私もたくさんの失敗を経験しました。看護技術がうまく習得できない,患者さんの容態が急変しても先輩のようにテキパキと対応できないというのはもちろん,精神科ならではの苦労もありました。
例えば,入院中のアルコール依存症の患者さんたちは私が新人看護師だとわかると,身体症状を訴えつつ睡眠薬が欲しい等,さまざまな要求を突き付けてきました。新人なので,訴えの背景に飲酒欲求があることを想像できず,懇切丁寧に話を聞き頓服薬を渡し,翌日先輩看護師に対応について苦言を呈されることが何度もありました。その後,病棟医がアルコール依存症の患者さんに,「近田看護師さんは,新人さんだから噓つかないであげてね。ちゃんとしらふで話すための練習相手だと思ってね」と,うまく役割を付与してくださいましたが……。
他にも,日勤帯で担当していた統合失調症の患者さんの話に聞き入ってしまい,ナースステーションに戻ってくるよう看護師長から呼び戻されることが何度もありました(これには,患者さんからもよく笑われておりました)。
つまり,新人時代の私は,患者さんの話を丁寧に聴きすぎるが故,患者さんの病いをかえって助長させたり,チーム全体の動きが見えなくなったりするといった失敗をたくさん経験してきたのです。裏を返せば,新人である自分には,患者さんの話を聴くことしかできないとの思いがあったのかもしれません。
❷学生時代に受け持たせていただいた患者さんと病棟で再会できたことです。この患者さんは,リストラに遭い統合失調症を発病された方で,ストレスがかかると妄想様の言動が生じるため長期入院となっていました。ただ,私には学生時代同様,父親のようなまなざしで接してくださり,精神の病いが決して特殊なものではなく,誰にでも起こり得るものであることを教えてくれたのです。
病棟の精神科医には,専門職として「すべきこと」と「してはいけないこと」の境界を常に見極める姿勢を学びました。病棟の規則やルールを遵守する以前に,そもそも私たち専門職の行為が,患者さんにとってどのような意味があるのかを常に問い,考えて,実践に落とし込んでいくことの大切さを教えていただきました。
❹不安もあると思いますが,1年目は看護師としてうまく振る舞えなくて当然です。うまくやろうとするよりも,まずは,できるだけ職場の人とコミュニケーションを図り自分の存在を知ってもらうこと,助けてくれる宛先を増やしながら場に慣れることが大事です。そして,自分を褒めてあげること! 少しゆとりが持てるようになったら,患者さんにとって自分が良き支え手となれているのか振り返りつつ,看護師としての自分をゆっくり成長させていくと良いと思います。
❶私は,学生時代から分娩介助させていただいたお産を「My分娩台帳」に記載しています。日付,かかわった助産師や医師の名前,いただいたアドバイス,感じたこと,失敗してしまったことなどを日記のように書き留めています。今回の原稿執筆に当たって,これを読み返しています。懐かしい思い出と苦い記憶がよみがえってきますが,初心に返るという意味で良い機会をいただいたと思っています。
1993年の京都大学医学部附属病院産科分娩部・未熟児センターへの入職が,私のキャリアのスタートです。入職を決めた理由は,実習でお世話になった親しみのある病院であり,自律した先輩方がかっこよくて,いつか自分もあんなふうになりたいと思ったためです。当時の新人は,1週間程度の集合研修を受けて,その後に配属先での研修を受けました。
研修が終了し,初めての分娩室担当の日のことでした。「今日は先輩について分娩室担当の仕事を覚えよう」と思いながら出勤すると,分娩経過中の産婦さんがいらっしゃいました。先輩が「分娩介助のやり方を思い出すために一度見学してから実際に介助するのが良いけれど,私がサポートするから一緒にお産をとろう。実習の時を思い出して」と後押ししてくださり,私がその産婦さんを受け持つことになりました。経過は順調で,数時間後に子宮口全開大となりました。私は先輩に言われるまま分娩に必要な器具のセットを開いて,周囲が誘導する呼吸法に合わせて,ただ手を添えるだけの分娩介助をしました。My分娩台帳には「就職して勤務初日に思ってもみなかったお産。何もわからないまま,スタッフの皆さんの協力のもと介助しました……」と書かれていました。頭が真っ白になり,十分な声かけもできず,言われるままに動いた助産学生のような分娩介助でした。先輩からは,「最初は誰でもこんな感じよ。これから頑張って磨いていけばいいから」と声を掛けていただいたのですが,学生時代の最後に介助した10例目から少しも成長してない(むしろ後退している)自分がふがいなく,苦くて落ち込むばかりの分娩介助デビューでした。
❷病棟には助産学生が実習に来ていましたし,同期の新人助産師は5人でしたので,1年目に自分が分娩介助できたのは15例だけでした。「このままでは自律した助産師には永遠になれない。何か手を打たないと。何でもいいから分娩にかかわろう」と考え,作戦を立てました。例えば,先輩が学生に指導されている様子をこっそりとのぞき見したり,分娩記録をみながら「なぜ先輩はこの時にこのアセスメントをされたのですか?」と質問したりして,色々な場面で教えていただきました。今思うと,苦くて落ち込むばかりの分娩介助デビューと,少しでも分娩にかかわるという作戦が成長するための基盤になったのかなと思います。
当時一緒に働いていた憧れの先輩とは,今もつながっています。今はお互い教員になっていますので,学会で一緒になった折には,苦すぎる分娩介助デビューのこと,仕事帰りに焼き肉を爆食いしたことなど,お酒を飲みながら話しています。憧れの先輩に近づきたい気持ちは今も変わりません。これからも置いて行かれないように走り続けたいと思っています。
❸入職当時にはやった曲の中で,特に印象に残っているのはZARDの『負けないで』です。この曲は,頑張る気持ちを高めてくれるので,当時もよく聴いていました。今でも「がんばるぞー」と思うときには,自然に口ずさんでしまいます。新人時代の苦い経験を乗り越えるための励ましの曲,そして今も走り続けるためのパワーの源となる曲として,心の中に住み着いています。
❹新人の皆さん,苦い経験や落ち込む体験は大事なことです。体験には意味があり,必ずそこから得られることがあります。自分がなりたい姿を思い描いて,少しずつ前進していってくださいね! なお,「My分娩台帳」はCLoCMiPレベルⅢ認証申請の時に役立ちました。皆さんにもご自身のポートフォリオの作成をお薦めします。
❶❷米国のGallup社による世論調査Gallup-Pollにおいて,看護師は誠実さと倫理に長け,最も信頼される職業として,過去23年間連続で1位に輝き続けています。私たちはこの職業に誇りを持ち,看護に力を注いでいます。しかしその裏には,日々の努力と苦労が繰り広げられているのです。
私も,涙と汗を流しながら一人前に成長した看護師の1人です。米国でスタートした新人時代は,毎日自分のできなさに落胆し,反省の連続で帰宅の途につきました。自宅へ向かう車の中であまりにも考え込んでしまい,時速20 kmでハイウェイをのろのろと運転し,警察官に止められてしまったことさえあります。
急性期医療の総合病院で新人看護師として働き始め,言葉の壁と文化の違いに適応するのはとても難しいことでした。その中で,ロールモデルとして私の成長を支えてくれたのが,プリセプターのロゼラです。ロゼラはイタリア系アメリカ人で,50歳代のベテラン看護師でした。物腰が柔らかで,患者さんに対しても優しいまなざしで接し,いつも落ち着いて仕事をこなす。彼女が慌てて走る姿を見たことがありませんでした。そして,私の拙い英語にも辛抱強く耳を傾けてくれ,看護の手順についても1つひとつ丁寧に教えてくれました。
新人教育も終わりに近づき,英語,看護スキルともに通常の業務をこなすことができるレベルまで上達したある日,担当する患者さんが亡くなりました。家族が急いで駆けつけたのですが死の瞬間には間に合わず,その悲しみを想像して心が痛みました。しかし,それ以上にショックを受けたのは,悲しむ家族に言葉の1つもかけられず,ただ突っ立っているしかできなかった自分自身に対してです。ちょうどその時,ロゼラが静...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。