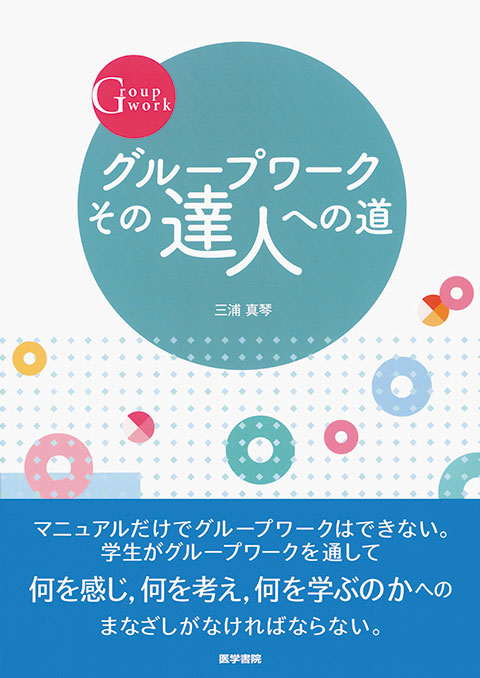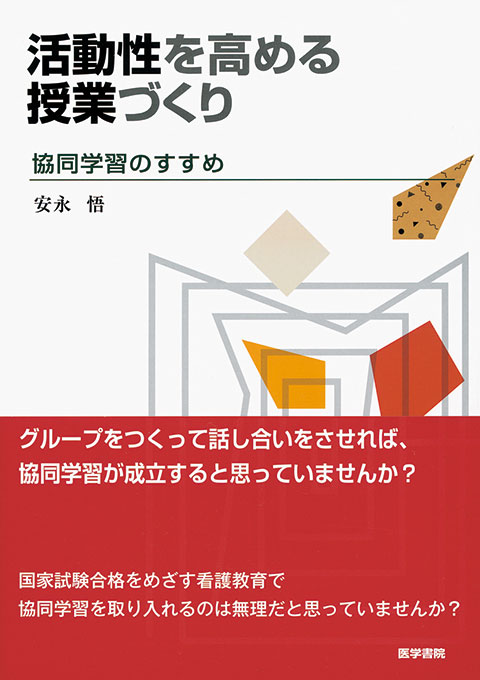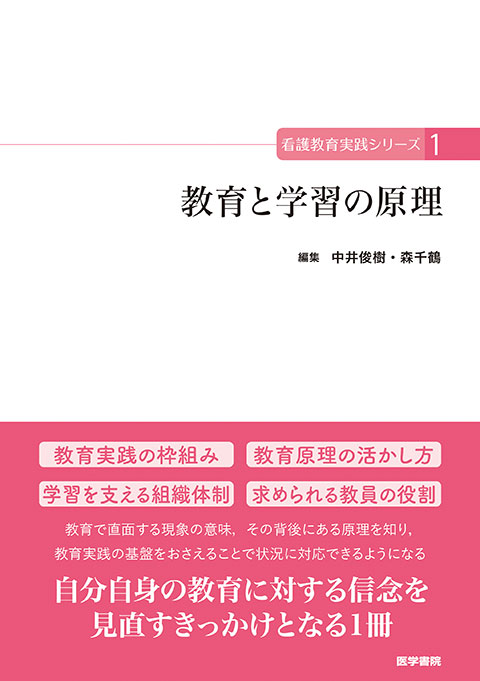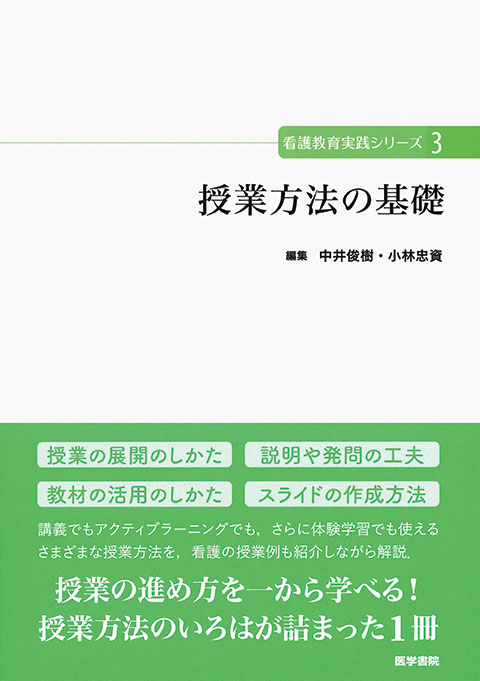教えるを学ぶエッセンス
[第11回] 教師が学びあう専門職の学習共同体
連載 杉森公一
2023.02.27 週刊医学界新聞(看護号):第3507号より
今回のポイント
✓ 自身の経験に基づくバイアスにとらわれないために,学習共同体を形成し協働的に省察を行う。
✓ 専門職同士が集まった時,半自律的な知識ネットワークであるマイクロカルチャーが形成される。
✓ コモンズを実践コミュニティへ転換させるには,無意識的な境界線を横断する意図的な仕組みが必要となる。
教師には,担当する教科を教えるに当たって教科の内容(Content Knowledge)だけでなく,教えるための知識(Pedagogical Knowledge)を併せ持つ教科を教えるための知識(Pedagogical Content Knowledge)が必要になる1)。ところが,看護教員はどのレベルまで教えるかにとらわれた結果,「看護学や看護技術に関する専門知の熟達(あるいは,看護学や看護技術に関する専門知を極めること)こそが重要である」との考えにしばしば固執してしまう。学校では教師のように専門職が学びあう学習共同体(Professional Learning Community:PLC)を形成し,教育者同士が「人から学ぶ」ことによって,教えるための「わざ」(あるいは,教えることの「わざ」)についての省察的実践を促すことができると言われている2)。「学習する組織」3)を起源としたPLCは,前回取りあげた実践共同体とほぼ同義とされることが多いが,専門職である教員や教育者の集団での学びや成長に焦点を当てたものである。個人が自分の経験を振り返ることを仲間と共に協働的に行っていくには,どのような工夫や場が求められるだろうか。
固定観念にとらわれないために他者の視点を借りよう
PLCは,「教師たちが重要と考える領域について自らの実践をいかに改善できるのかを協働で探究し,それからその探究した実践を現実化するために学んだことを実行する場」4)と言われている。また,教育学のHordらは,PLCには次の5つの特徴があるとしている5, 6)。
1)学習に向けた信念,価値観,ヴィジョンの共有
2)共有された支援的なリーダーシップ
3)集団的な学習とその応用
4)構造的・関係的な支援的条件
5)個人的実践の共有
PLCは教師にとっての学習環境と言い換えてもよい。なぜなら,PLCは看護教員や実習指導者が授業の質を高めるために定期的に集まるだけではなく,「同じ場にいて,それぞれの教員が何をしているかを見る,場をともにすること」7)に価値を置く環境だからだ。私たち教師は,過去の経験から「学生は不完全であり,全ての学生が同じような学習方法やカリキュラムで学ぶべき」との固定観念(思い込み)を抱いてしまう。こうした思考のくせを,Sengeは「メンタル・モデル」と呼んでいる3)。こうした思考にとらわれず,言語化されてこなかった自分自身や周囲の態度や認識について気付くためには,教育法に関する小グループでの対話(ダイアローグ)やチーム学習を行うことが望ましい。これは一過性の研修とは異なる。他者の視点(レンズ)を借りて授業を協働的に振り返ることによって,今まで見えていた現実が実際のデータとして立ち現れてくるだろう。
コモンズを実践共同体に転換する方法
ところが,大学や病...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。