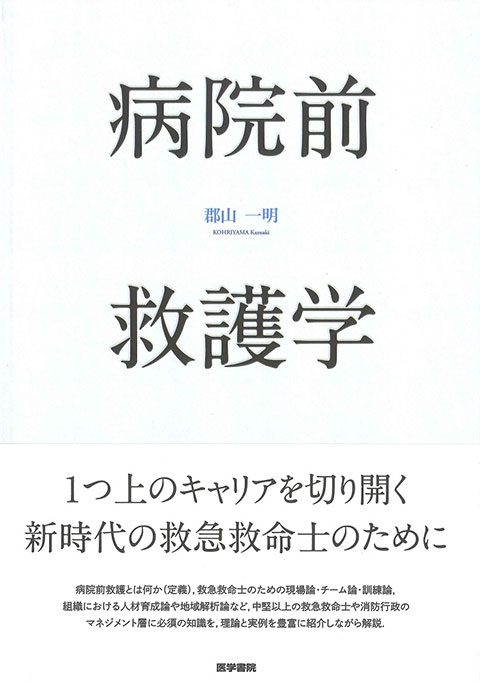病院前救護の教育から救急医療を変革する
郡山 一明氏に聞く
インタビュー 郡山 一明
2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

このほど,救急救命士の現場活動のトレーニング書である『救急救命士によるファーストコンタクト[Web動画付]第3版──病院前救護の観察トレーニング』(医学書院)が刊行されました。本書の執筆者であり,長年にわたり救急救命士教育に携わってきた医師の郡山氏は,「目の前の患者だけでなく,より多くの命を救うためのシステムを整える鍵は病院前救護にある」と語ります。厚労省でのテロ対策従事や救命士教育への注力など異色のキャリアを歩んできた同氏が救急救命士,ひいては救急初療に携わるあらゆる医療者への教育にかける思いと,その背景に迫りました。
――まずは先生が救急救命士(以下,救命士)の教育に携わるまでの経緯を伺います。救急医療の道はもともと志していたのでしょうか。
郡山 いいえ,大学院では中毒学を研究しており,医学部卒業後は神経内科医になろうと考えていました。研修医のときも珍しい症例の中毒患者に偶然対応することが何度かあり,中毒に関する論文も早期から執筆していました。ところが研修医生活の中で死に瀕した患者の救急処置をなんとか乗り越えたり,乗り越えられなかったりする経験を繰り返すうちに,「まずは生命に直結する呼吸・循環管理を身につけたい」と次第に考えるようになりました。そこで大きく方向転換し,神経内科ではなく麻酔科に入局したのです。そこから救急医療の世界に足を踏み入れていくことになります。
厚労省でのテロ対策従事を経て救命士教育へ
――救急医療の世界で研鑽を積む中で,キャリアにとっての転換点はどのあたりだったのでしょう。
郡山 麻酔科指導医と救急科専門医の資格を取得し,救急医療で実践できることの幅も広がっていた頃です。世間では地下鉄サリン事件(1995年)や和歌山毒物カレー事件(1998年)が社会を震撼させていました。こうした背景から臨床医を行政に参画させようという動きが活発になり,中毒関連で名前が知られていた私に,厚労省から声がかかったのです。サリンは有機リン系の毒物であり,私がかつて論文のテーマにしていた農薬中毒とつながりがあったことも理由だったようです。
――かつての中毒研究の経験がそこにつながってくるのですね。臨床現場から行政へのキャリアチェンジに,迷いはありましたか。
郡山 全くありませんでした。地下鉄サリン事件や和歌山毒物カレー事件のような大規模な事件を耳にするたびに,目の前の患者は助けられても複数の患者を同時に救うことはできない臨床家としての医療に,限界を痛感していました。自身の専門性や能力を踏まえた時,1人の医師として臨床で戦うよりも,より多くの患者を救うためのシステム作りを主戦場とする国の中枢に行ったほうが理にかなっていると,当時は考えたのです。さらに,厚労省在籍中の2001年にはアメリカ同時多発テロが発生し,日本国内でのテロ対策が急務となりました。日本はサリン事件の経験があるため化学テロの可能性も念頭に置いて対策を考える必要があり,厚労省で医療・中毒の専門家として働いていた私に再び声がかかりました。それがきっかけで,テロを含めた災害時に行政,医療などの関係機関がスムーズに医療情報を分析・伝達するためのシステムである「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル」の作成に中心的に携わりました。
その後,厚労省在籍時に救急救命士法の所管にかかわっていた縁もあり,国から「病院前救護の施策を進めるために力を貸してほしい」と臨床復帰後に再度要請を受け,一般財団法人救急振興財団が運営する救急救命研修所(通称:ELSTA)で救命士教育に携わることになったのです。そこから18年にわたり,救命士教育の現場に身を置くことになります。
救命士教育に覚えた違和感と,五感に根付いた観察能力の必要性
――救急医療のための教育を考えた時,医師の教育に携わる選択肢もあったと思います...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

郡山 一明(こおりやま・かずあき)氏 北九州八幡東病院 副院長
1988年産業医大卒。同大病院で神経内科研修後,92年同大大学院修了。入局した麻酔科で麻酔,救急医療を学ぶ。麻酔科指導医と救急科専門医を取得後に,厚生省(当時)で医療行政に従事し,テロ対策など危機管理の仕組み作りに携わった。2003年から18年にわたり救急救命九州研修所で救急救命士養成にかかわるとともに,国の病院前救護体制構築に尽力。その後,再び臨床医として救急医療の現場に復帰し,北九州総合病院救命救急センター長を経て,25年より現職。著書に『救急救命士によるファーストコンタクト[Web動画付]第3版──病院前救護の観察トレーニング』,『病院前救護学』(いずれも医学書院)。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
2026.01.13
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![救急救命士によるファーストコンタクト[Web動画付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6017/4848/1092/113689.jpg)