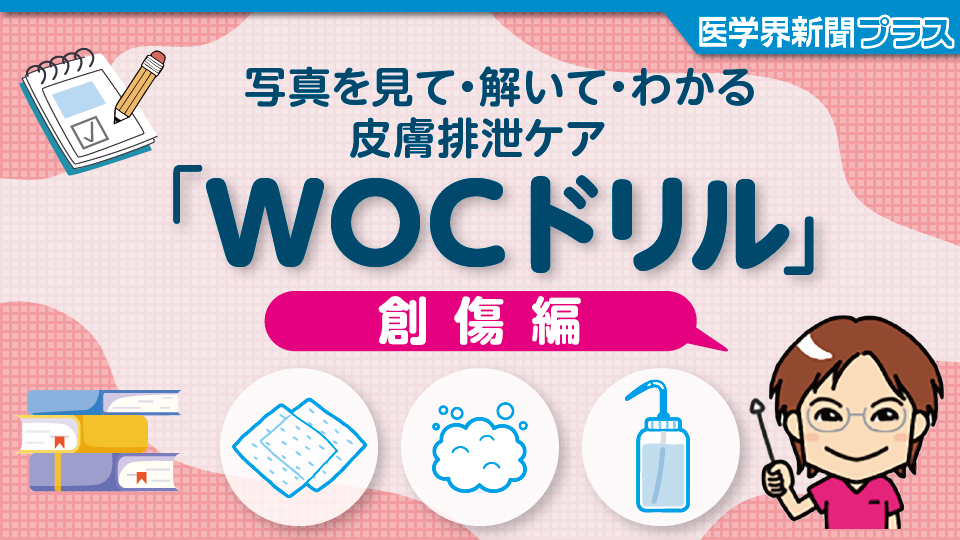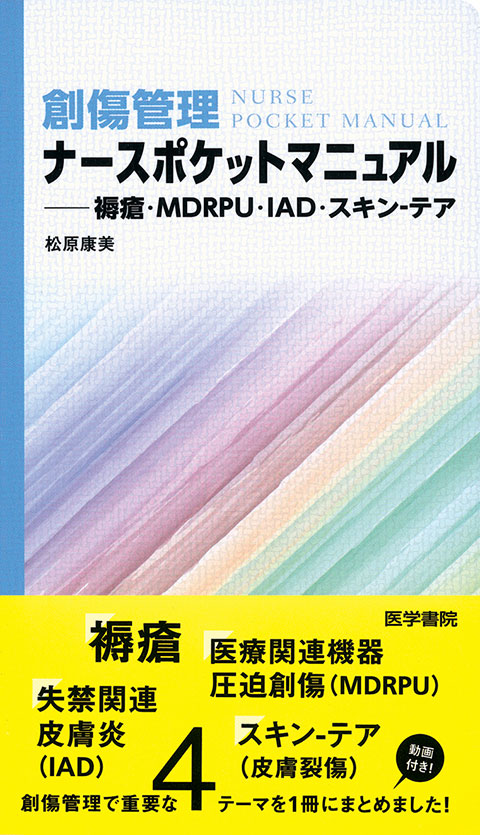地域の皮膚・排泄ケアの質向上を実現する
WOCナースのアウトリーチ活動を全国へ
対談・座談会 間宮 直子,池田 惠津子,松脇 孝太郎
2025.07.08 医学界新聞:第3575号より

皮膚・排泄ケア認定看護師,通称WOCナースが専門とするWound=創傷,Ostomy=ストーマ(人工肛門,人工膀胱),Continence=失禁のケアは,看護において高齢者のQOLに直結する重要な分野です。このたびWeb限定コンテンツ「医学界新聞プラス」では,WOC領域のケアを実際の症例写真とともに学べる連載『写真を見て・解いて・わかる皮膚・排泄ケア「WOCドリル」』がスタートしました。この連載の執筆者でありWOCナースとして大阪府吹田市で皮膚・排泄ケアのアウトリーチ活動を行う間宮氏と,同じく吹田市で介護老人福祉施設の管理者である池田氏,訪問看護ステーションの責任者を務める松脇氏が,地域における皮膚・排泄ケアの質向上の意義と,施設間連携・医療介護連携の可能性を探ります。
間宮 今後,超高齢者が医療機関以外の在宅や高齢者施設で生活することを考えると,地域における施設間の連携で当事者や家族のQOLを上げることも地域包括ケアの一端であると言えます。しかし「地域包括ケア」は言葉で言うほど簡単ではなく,想定通りに進んでいないところもあります。そのようななか,当院では病院長より新たな方針が打ち出されました。それは,高度な急性期病院でありつつ,医療・介護をトータルに支える地域密着型の病院機能も担う“二刀流の病院”をめざすというものです。このビジョン達成のために病院長から私に課せられたミッションは,後者の「地域」への貢献でした。そこで,同じ法人グループの中にある病院,高齢者施設,訪問看護ステーション同士での連携が,療養者のウェルビーイング向上につながり,効果的な地域包括ケアのひとつになるのではないかと考えました。この構想実現のモデルケースとなるべく,私自身はWOCナースとして皮膚・排泄ケア領域のアウトリーチ活動を行っています。そのなかで,在宅ケアを担う松脇さんや特別養護老人ホーム(以下,特養)を管理する池田さんには特にご協力をいただいております。
本日はアウトリーチ活動を中心にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
「チーム介護」の時代,皮膚・排泄は高齢者ケアの2大課題
間宮 高齢化の進展に伴い,以前にも増して皮膚脆弱性を伴うトラブルに遭遇するようになりました。病院内でもスタッフへの教育は行っているものの,皮膚の状態に応じたアセスメントが十分でないケースは多く見受けられます。また在宅や特養の現場に目を向けても高齢者のスキン-テア(皮膚裂傷)が多発しており,予防のための啓発活動が不可欠だと感じています。さらに皮膚トラブルに加えて失禁や人工肛門など排泄に関するケアの問題も増加しており,まさにWOCナースが専門とする皮膚と排泄の問題こそが,高齢者のケアにおける2大課題だと痛感しています。
松脇 訪問看護の現場でも,間宮さんが指摘したアセスメント面の弱さを感じることは多々あります。訪問は1人でお宅に伺うことが大半のため,目の前の問題に対してリアルタイムに別の医療職と相談し,長期的な見通しを立てた上で対応することが難しい場合が多いです。結果としてその時その時の一時的な対処でしのいでしまい,皮膚の状態が悪化し,病院受診や往診医につなげていくことが必要になります。
池田 私も特養における看護の質には課題を感じており,ここを向上させていくことが今後の日本の介護にとって極めて重要であるととらえています。というのも,チーム医療が推進された当初,看護師がキーパーソンと言われたのと同じように,現代は「チーム介護」の時代であり,その連携の中核的存在は看護師に他ならないと考えているからです。特養のような高齢者施設でも,看護師や介護職員,管理栄養士などさまざまな職種が入居者に対してかかわります。当然のことながら入居者を最も近くで,最も長い時間支援するのは介護職員です。彼らは食事の提供や入浴,排泄など生活全般にかかわるケアを担当するプロであっても,看護師のようなフィジカルアセスメントはできません。しかし施設の看護の質が高いと,看護の視点が自然と介護職員や他のスタッフに影響を及ぼすこともまた事実です。そのため生活の土台となる「健康」に専門職としてコミットできる看護師の質が高くなければ,高齢者の生活はなかなか守れないと実感する日々です。
間宮 お2人が話されたような現状を変えていくことが,WOCナースのアウトリーチ活動の目的の1つと言えます。地域の看護の質を底上げすれば,高齢者施設では介護職員の質が上がり,入居者のQOL向上につながる。在宅においてはおそらく夜間の救急が減り,家族の負担が減る。こうした変化は決して理想論ではなく,アウトリーチ活動によって皮膚・排泄ケアに関する情報格差を解消するだけでもかなり現実味を帯びると感じます。
WOCナースのアウトリーチ活動により現場に生じた変化
池田 間宮さんのアウトリーチ活動を受けて,当施設の看護師からは,「最新の治療法を学べる」「創傷被覆材の正しい選択や使用法がわかる」「創の状態評価について的確なアセスメントを教えてもらえる」「なぜそうなったのか,多角的な視点からの指標を得られる」といった声が多数寄せられており,これらが他の利用者のケアにも生かされ,看護師自身の成長につながっていると実感しています。また,介護職員への指導方法についても,間宮さんのかかわり方を見て学ぶ点が多いようです。
間宮 そう言っていただけるとうれしいです。私は,この法人グループ以外にも多くの高齢者施設や在宅医療を提供する機関へアウトリーチをしていますが,確かにWOCナースがいない他施設の看護師からも,「これまで改善しなかった褥瘡が良くなった」「保湿の必要性や弱い皮膚へのケア方法など,知識が広がった」という感想をもらうことが増え,活動の効果を実感しているところです。
池田 特に褥瘡に関しては,以前は「治らないもの」という認識が強かったものが,適切な介入で「治癒できるもの」に変化した成功体験は非常に大きいです。当施設では,持ち込みも含め,ここ数年で発生した褥瘡は全て治癒に至っています。このデータは,WOCナースのアウトリーチ活動の成果を示すエビデンスになると考えています。
松脇 訪問看護の場合,看護師が対象者にかかわれるのは医療保険・介護保険ともに概ね30~90分と限られており,その後のケアはご家族に委ねられます。そのため,褥瘡が一度良くなっても再発を繰り返すこともあり,ジレンマを感じることが多いのが正直なところです。そんな中で,間宮さんのようなスペシャリストに支えられているという感覚は非常...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

間宮 直子(まみや・なおこ)氏 大阪府済生会吹田病院 副看護部長
1997年大阪府済生会吹田病院に入職後,2011年から同院副看護部長に就任。04年に皮膚・排泄ケア認定看護師資格を取得。16年に創傷管理関連の特定行為研修修了。17年に滋慶医療科学大大学院医療安全管理学修士課程修了。所属学会は,日本創傷・オストミー・失禁管理学会(評議員),日本褥瘡学会(評議員・褥瘡認定師),日本フットケア・足病医学会(理事・学会認定師),日本認知症ケア学会(認知症ケア専門士) ほか。

池田 惠津子(いけだ・えつこ)氏 吹田特別養護老人ホーム高寿園 施設長 / 済生会吹田医療福祉センター 連携担当部長
2002年に大阪府済生会吹田病院に入職。08年から同院看護部長に就任し,13年からは副院長を兼任する。16年認定看護管理者。19年から現職。済生会大阪府支部理事。吹田市養護老人ホーム入所検討会議委員,吹田保健所高齢者施設等感染対策支援検討会委員を務める。

松脇 孝太郎(まつわき・こうたろう)氏 吹田訪問看護ステーションサテライト東淀川 サテライト長
2012年に大阪府済生会吹田福祉医療センター東淀川訪問看護ステーションに入職後,20年に訪問看護認定看護師資格を取得。23年から同ステーション所長に就任。24年12月組織改編により大阪府済生会吹田訪問看護ステーションサテライト東淀川サテライト長に就任。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
2026.01.13
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。